コラム「研究員のココロ」
病院経営と人材マネジメント
2006年07月24日 大野 勝利
1.病院の経営状況
病院を中心とする医療業界は、国民の福祉の向上と増進のため、また、医療提供者の供給不足と相まって、戦後長い間、国の政策的保護下におかれてきた。しかし、近年の国家財政の悪化、保険料収入の伸び悩み、急速な高齢化などにより、病院の唯一とも言える収入源である診療報酬の水準が厳しく抑えられてきている。
厚生労働省による医療施設(動態)調査・病院報告によると、平成16年10月現在、全国で9,077の病院が存在する。平成元年には1万を超える病院が存在していたことからすると1,000近く減少したことになる。さらに、存続している病院の経営状況を見た場合、厚生労働省が平成16年6月に実施した病院経営分析調査報告によると、総数ベースで68.7%の病院が赤字決算であることが確認できる。このような生き残りをかけた厳しい経営環境は将来もしばらくは続くものと考えられる。
特定の病院が、他病院との差別化を図り、競争力の高い経営体であり続けるためは、医療そのものの質の高さを確保することはもちろんである。一方、患者、職員、連携する他の医療機関、地域社会など、病院を取り巻く人や組織の満足度を高める働きかけや、医療行為を取り巻く人的サービスの向上、病院経営に対するコスト効率の改善など、一般企業と同様に経営的視点に立った活動を強め、継続性を持たせることが求められてきている。
2.病院組織の特色と人材マネジメント
一方、病院組織の特色と、関連する問題点を整理すると表1のような状況が浮かび上がる。
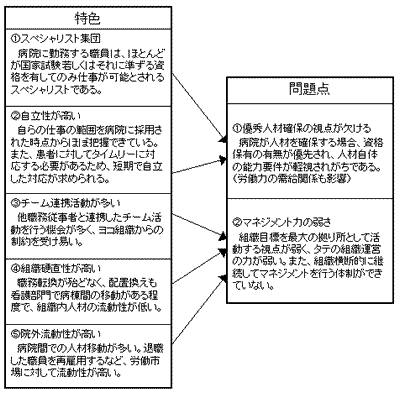
上記組織の特色に加えて、以下のような背景から、病院では人材価値向上に向けたマネジメント施策が強力に実施されてこなかった感がある。
- 経営者や病院に勤務する職員が、病院は原則として非営利企業であり、職員間の競争の原因となるような能力主義的な賃金施策は適さないものであると意識されてきたこと。
- 病医院の収益が国の政策上保護されてきており、職員各人の能力水準の向上がなければ経営がなりたたないという危機感が少なかったこと。
- 診療報酬、特に病院の主要な収益源となる入院に対する報酬は患者数(ベッド数)あたりの職員数によって定められている。職員各人の能力や頑張りにより直接的に収益を上げることのできるしくみとなっていないこと。
3.病院での人材マネジメント施策構築の重要性
病院は法令の定めるところにより、医療行為以外の収入が殆ど認められていない。マーケティングの分野でよく述べられている4P、商品(Product)・価格(Price)・流通(Place)・広報(Promotion)の観点で病院経営を見た場合、表2のように経営する立場にとって大きな制約がある。
| 商品(Product) | 医療行為が原則であり、それ以外は入院時の差額ベッド代からの収益など範囲が限られ、病院が独自に商品を開発することはできない。 |
| 価格 (Price) | 診療報酬として定められており、病院は、自ら提供する医療行為に対して価格を決定する権限を持たない。 |
| 流通 (Place) | 顧客は患者であり、地域密着型の経営にならざるを得ない。また、薬品、試薬などの医療材料の価格、流通形態も他産業と比較して単純化され、固定的であり、病院がコントロールできる裁量の範囲が狭い。 |
| 広報(Promotion) | 病院が広告できる範囲は法令により非常に狭く限定されており、自由なPRができない。 |
収入面の向上(商品&価格)は、医療の質と直結するものであり、他病院との差別化を行う上で最も重要で、かつ、大きな効果が期待できると考えられる。しかしながら、それを実現するためには医師を中心とした新たな人材の確保と、施設・設備の更新が必須であり、直ちにどの病院でも着手できる経営状況にあるとは言い難い。
それに対して、間接的にではあるが収入増が期待できる取り組みである流通の効率化、広報活動などは、病院独自の対応を、早期に模索することが可能である。また、支出を抑制するための諸活動も経営の健全性を高める効果が期待できる。
これらの差別化を行う主体となるものは“人”である。
確かに、病院には組織的な制約もあり、人の能力を短期間で向上させることは困難である。人材価値を向上させる取組みは、病院経営者が強い意思をもって、組織的・継続的に実施しなければ有効な効果は期待できない。しかしながら、それ故に、高い能力を有する人材の集団を抱える病院となった場合、他病院が簡単に追従できない、模倣し難い利点をもつこととなる。
病院経営にとって有効な人材マネジメントのしくみを構築し、職員の職務遂行能力の向上と、賃金を含む人的資源を組織的にコントロールすることは、病院経営の健全性を高めていくためには必須、かつ、急務であると考える。

