コラム「研究員のココロ」
今、アグリビジネスが熱い!
~異業種から農業参入への応援歌~
2006年05月15日 大井大輔
1.はじめに
昨年9月に規制緩和の一環として、株式会社による農業経営(農地リース方式)が全国で認められ、株式会社にとっては医療・教育に並ぶ未開の地であった農業への本格的な参入が可能となった。これ以前にも民間企業が農業に取り組むケースは見られたが、株式会社が本格的に農業経営をできるようになった点に今回の規制緩和の主眼がある。そこで、本稿では、民間企業による農業参入、特にこれまで「食」分野に携わっていない民間企業による農業参入について取り上げてみたい。
2.規制緩和による農業参入の促進
新聞紙面やテレビ番組で、ワタミ、カゴメやキユーピーといった大手民間企業による農業参入が大きく取り上げられている。もっとも、一口に民間企業の農業への参入といってもそのパターンには多様な形態があることから、まずは主な参入パターンを整理しておく(図表1)。また、単に民間企業といっても、先にあげた大手民間企業のようにこれまで加工食品の製造や外食等の「食」に携わってきた企業(以下、「食」関連企業)と、トヨタ自動車、JFEスチール、オムロン、ユニクロといった本業が「食」に関連しない企業(以下、異業種企業)の2つに大きく分けることができる。このような「食」との接点の有無により農業参入のパターンにも特徴が見られることから、それぞれの整理を試みた(図表2)。
「食」関連企業は、品質の良い原料を供給できる有力な農家(高品質な食材)を囲い込むために、(d)契約栽培(注1)を実施している。カゴメでは1899年から契約栽培を実施しており、契約栽培は早くから定着している形態と言える(文書による契約は1920年から実施)。一方、異業種企業の場合は、本業のプラント設計・建設技術を農業で活用するために、(c)施設栽培に参入するなどの形態が主流となる。1984年から野菜事業を立ち上げ、遊休地に水耕栽培施設を建設しているJFEスチールに代表される取組みである。
今回の規制緩和で注目されているものは、(a)農地リース方式 (b)農地取得である。これが従来の参入パターンと大きく異なる点は、株式会社による主体的な農業経営が本格的に行えるようになった点にある。契約栽培はあくまで主体は農家にあり、企業側では、経営にまで踏み込んだ管理ができない、自社の余剰人員を活用できない等の問題があった。しかし、株式会社が農地を取得できないまでも、農家から農地をリースして自社で農業経営ができるようになれば、自社の計画に従った農作物の作付けや余剰人員の活用といったことが可能となってメリットが生れるのである。これにより、農業を新規事業の一つとして位置付ける機運が企業側にもたらされたと言える。
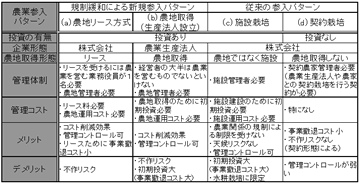
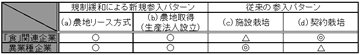
3.「食」関連企業・異業種企業による農業参入の特徴
「食」関連企業と異業種企業における農業参入パターンの違いは、図表2にあげた通りであるが、ここでは両企業におけるビジネスモデルの特徴を整理しておく(図表3)。一般に、「食」関連企業では、本業を強化すべく、事業の垂直統合としての農業への参入を実施している点に特徴がある。例えば、ワタミは本業である外食事業を強化するために、子会社ワタミファームを設立して農業に参入し、有機野菜の安定供給とコスト削減を実現した。このように、「農業経営」という川上のみならず、流通・小売といった川下である本業事業(外食)までも含んだビジネスモデルを再構築しているのである。現在、ワタミファームは、ワタミ以外のチャネル(食品スーパー)とも取引を開始しておりネット上で一般消費者向け有機野菜の直接販売も行っている。
一方、異業種企業は、本業で培ったノウハウを活用すべき新規市場として農業分野を位置付け、参入している点に特徴がある。先に挙げた、JFEスチールは、プラント設計・建設ノウハウ及び余剰資源(遊休地・人員)を活用すべく、1984年に野菜事業を立ち上げ、西宮市にある遊休地に水耕栽培施設を建設した。現在、子会社のJFEライフでは、無農薬洗浄野菜の水耕栽培事業を首都圏でも本格的に立ち上げている。
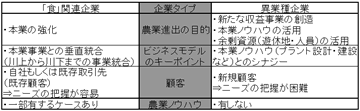
4.異業種企業が農業参入する際のポイント
「食」関連企業のみならず異業種大手企業も含めた様々な企業が農業に続々と参入していることから、農業は“蜜の味”のように思えるが、現実はそれほど甘くはない。例えば、近年では、オムロン(精密機器製造・販売)、JT(タバコ製造・販売)、ユニクロ(ファーストリテイリング:衣料品製造・販売)といった大手企業が鳴り物入りで農業に参入したが、オムロンとJTは参入から3年程度、ユニクロはわずか2年弱で撤退に追い込まれた。最も記憶に新しいユニクロは、本業のカジュアル衣料で成功を収めたSPA(注2)方式を農業分野に展開するモデルにより、農業に参入した。2002年には子会社エフアール・フーズで、生鮮野菜を販売する「SKIPストア」(インターネット通販及び直営店での販売)を開始したが、高品質で買いやすい価格の野菜を安定的に調達できず、農業から撤退することとなった経緯がある。また、オムロンも自社のコア技術である制御技術を活かして、工業的な農業経営の確立(農業の工業化)を目指して農業に参入したが、十分な収益を上げられずに撤退を余儀なくされている。
このように異業種からの参入は、「食」関連企業の農業参入に比べると、より大きな困難が伴う場合が多い。従って、農業への参入を検討されている企業は、本業ノウハウの活用に加えて、まず、『自社が農業に参入することが顧客視点で違和感がない(説明がつく)のか?』の問いに明確な答えを用意する必要がある。わかりやすく説得力のある農業参入のストーリーが必須となる。これらが見出せない場合、恐らく新規事業として農業に参入しても成功するのは難しいと考えた方が良い。もっとも、これらは農業に限らず、新分野での事業の立上げには必ず必要となる要素である。
新規事業として立ち上げるための納得のいくストーリーが練り上げられた上で、次に解決すべき課題は、農業経営の特殊性の克服である。農業は単位面積当りの収益性が低く、天候によるリスクが大きい上に、天候・農作物の成長に合わせて働かないといけないので、勤務形態が定期化できず勤怠管理が企業のそれと大きく異なるなどの特殊性を有している。農業への参入には、このような農業の持つ特殊性を十分に踏まえ、企業経営とどう統合していくのかを検討することが必要となる。以下では、これら異業種企業が農業へ参入する際に事前に検討しておくべきポイントを整理しておく。
(1)異業種から農業へ進出する際のストーリーの検討
先に述べた通り、異業種から農業に参入するには納得の得られるストーリー(=新規事業開発の妥当性)が必要である。例えば、上述のJFEスチールは農業参入に当り、本業のプラント設計・建設技術、衛生管理の手法等を活用した水耕栽培を検討し、本業のノウハウをしっかりと活用できている。しかし、自社の都合だけでは不十分で、顧客(消費者)に対して、『なぜJFEスチールが農業に参入するのか?』といった問いに対する明確な答えを持っておく必要がある。JFEスチールは、プラント事業を手掛けているからこそ、無農薬野菜を水耕栽培で提供することにより、顧客に対して「安心・安全・安定・健康」を届ける仕組みを作ることができるといった明確なコンセプトを示したのである。また、このコンセプト(取組み)が顧客から評価されて、2004年には「日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞」(日経MJ賞)を受賞している。
(2)ビジネスモデルの検討
当然であるが、単に農作物を栽培するだけでは異業種企業が存続するために必要な収益を得ることは困難である。ワタミやカゴメのような「食」関連企業が農業に参入して成功を収めている背景には、農業が本業を強化するためのものと位置付けられており、必ずしも農業単体で収益を得る必要がない点が挙げられる。逆に言えば、異業種企業が農業で収益を確保するには、「食」関連企業のように、「農業経営」という川上のみならず、流通・小売と言った川下まで含めて、「誰に」「何を」「どのように」して収益を上げるのかといった明確なビジネスモデルを検討する必要がある。この際、異業種ならではの斬新でユニークな切り口を生かしたビジネスモデルを期待したい。
また、必ずしも「農業経営」のみで収益性を確保できないわけではない。概して従来の「農業経営」では収益性が低いが、異業種ならではの新しい「農業経営」をすることによって収益を確保できることが期待される。単位面積当りの収益性が高く、かつ施設栽培に適した西洋の葉物(ハーブ類など)を機械部品の製造ラインのように徹底的な生産管理の下で栽培し出荷し収益を確保している異業種企業も見られるが、これなどは異業種(本業)で培ったノウハウを十全に活用している事例と言えよう。
(3)農業特有(生産)ノウハウの確保
農業がこれまで異業種企業が携わってきたビジネスと大きく異なることは既に述べた通りである。特に、生産面においては、異業種企業の有するノウハウだけでは対応できないことが多く、農業に携わっている専門家のアドバイスを受けることが有用となろう。中でも、自社で農地を持つ、もしくは農地をリースするといった形態で農業への参入を考えている場合は、これは重要なポイントとなる。同じ農作物でも地域によって、気候や土壌等が異なり、作付けのための作業内容も大きく異なるからである。
(4)品質・収穫量のばらつきの担保(品質グレード・収穫量による顧客の開拓)
顧客(売り先)を確保する重要性は、すべてのビジネスにおいて一様に言えることであるが、農業の難しさは顧客を確保しても、必ずしも顧客が要求する商品(農作物)を提供できる保証がない点にある。農作物は工業製品と比較して、数量や品質の面で、安定的に供給することが難しい。天候不順等によって、顧客が求める数量や品質を満たすことができない可能性が高いからである。つまり、収穫量や品質のばらつきにも対応できる売り先の確保が大きな課題となっている。従って、収穫量や品質のばらつきに対するリスクも踏まえ、複数年次契約などでの対応に加えて、幅広い顧客層を開拓しておく必要がある。すなわち、顧客が求める数量や品質の程度によって、顧客層をグルーピングし、それぞれのグループで顧客を開拓しておかなければならない。
5.異業種企業による農業参入に対する期待
周知の通り、日本の農業は、多くの課題を抱えている。農業の担い手の減少や後継者問題、食糧自給率の低下に加え、残留農薬等に見られる環境問題や食に対する安全・安心と言った新たな課題も生れている。これらの課題を解決する1つの方向性として、異業種からのノウハウの移転が重要であることは言うまでもない。これまでにあげた通り、民間企業では既に当たり前となっている顧客(消費者)の視点による商品開発・販売(=マーケティング戦略の検討)、流通構造短縮化(=直販化)、生産効率改善の徹底や受発注の調整などが農業分野に注入されつつある。今後も農業の垣根を越えた異業種からの積極的な参入が進み、これまで当たり前とされてきた業界の常識が取り壊されていくだろう。その結果、日本の農業が独自の進化を遂げ、次世代型農業に生まれ変わることを期待したい。
【注釈】

