コラム「研究員のココロ」
耐震強度偽装にメリットはあったのか
2006年02月06日 山野泰宏
構造計算書を偽造した、いわゆる耐震強度偽装事件が昨年11月に発覚し、世間を大きく騒がせている。自分の住むマンションの耐震強度に不安を感じている人も多いことだろう。過去には分譲マンションの手抜き工事が問題になったり、戸建の建売住宅などでも欠陥住宅などの問題が世間をにぎわせたことなどもあり、建設業界に対する世間の目はますます厳しくなっている。
本件は当局による捜査が進められているところであり、まだまだ事実関係が明らかになっていない部分も多いが、現在分かっている中でも理解しがたい点がいくつもある。筆者は以前に建設会社に籍を置いていたことがあり、また一級建築士という立場から、事件に対して感じていることを書き記してみる。
1.事件の特異な点
今回の事件において特異な点は、「設計士による設計図書の偽造」という点である。これまでに分譲マンションや事務所ビルなどの用途に限らず、施工段階での不正が顕在化した事例は数多くある。例えば、阪神淡路大震災において倒壊したビルにおいて、柱や梁の内部、コンクリートの間から、空き缶やごみなど本来そこにあるはずのないものが露出したことは記憶にあるだろう。いわゆる施工不良、手抜き工事であるが、こういった事例については、枚挙に暇がない。しかしどういう訳か、工事のもととなる設計図面については、不正がないものという前提に立っていた。この前提が崩されてしまったということが、これまでになかった特異な点である。
2.なぜ偽装が必要だったのか
新聞等でも指摘されている通り、分譲マンション工事は、躯体工事や設備工事など、細かい工事が多い割りに工事価格単価が低く、また技術的に難しい工事でもない。そのため中小建設会社や新規マンションディベロッパーの参入が容易であり、マンションブームを背景に、価格競争が激しくなっている。そういう厳しい環境の中で競争に勝つためには、どこかで通常よりも無理をしたコストダウンが必要だったということは想像に難くない。
3.構造計算書偽装のメリットはあるか
今回の事件で、施工を担当した建設会社は、構造計算を偽装した図面よりも更に鉄筋量を減らすなど、施工不良を行ったことも明らかとなっている。設計図書通り施工せず、工事段階で手抜きをするのであれば、設計図書を敢えて偽装するメリットはどこにあるのだろうか。この点が今回の事件において一番理解しがたい点である。
設計偽装は結局、違法建築物であることを図面という証拠で残してしまうというデメリットしかないのではないかと筆者は考える。現に本件も、建築確認申請のところで問題が顕在化し、結局建設会社の施工不良も指摘される事態となっている。リスクに対するリターンが小さすぎると思うが、なぜ設計偽装という手段を選択したのだろうか。施工不良単独ということも手段として選択可能であり、その場合、地震で建築物が倒壊するというような状況でない限り顕在化はしないのに、である。今後の捜査でこの点が明らかになることを期待したい。
設計偽装や施工不良は不法行為であり、決して許されるものではないが、今回どういう理由で施工不良に設計偽装という手段が組み合わされたのかを考えることが再発防止につながると考え、敢えてそれぞれのメリット・デメリットについて比較を行った(図表1)。この表からも分かるように、建築主・施工者にとって、設計偽装を選択するインセンティブはほとんどなく、設計者にとってもリスクに比べてリターンは大きくない。
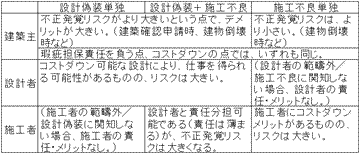
4.同様の不正は潜在的に存在するか
前述のように、施工不良との組合せの有無に関わらず、設計偽装は関係者にとってデメリットが大きい。よって今回同様の不正は皆無ではないにしろ、数としてはそれほど多くはないのではないかと考えられる。これまで同種の事件がほとんどなかったのも、デメリットに比べ、メリットが小さいためと言えるだろう。
5.今後の対策
建築確認申請の検査を厳格にしたところで、脱法行為にメリットがあれば、今後も別のやり方で設計偽装を行う事例は出てくると考えられる。今回の事件が発覚した当初は検査機関の不手際も指摘されたが、今回のような偽造を見抜くには、構造計算書の再計算が必要という指摘もあり、日本全体で行われる建築確認申請の数を考えると、検査のみに頼るのは不可能と思われる。よって今回のような事件の再発防止には、「設計偽装はデメリットしかない」ことを周知することで抑止力とするとともに、施工不良を徹底的にチェックすることが現実的ではないだろうか。そのためにも、前述の通り、今回の事件ではどこに設計偽装のメリットを感じたのかという点の詳細解明が不可欠である。
6.この事件を契機に
高度成長期の量的充足から、社会の成熟化につれ、人々の価値観も質的向上へと変化している。2003年に政府は「美しい国づくり大綱」を発表した。そこでは、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造が謳われている。2004年には、わが国初の景観に関する総合的な法律である景観法が制定された。
生活の質の向上を目指そうという時代の流れの中、モラルの低い一部の人たちが起こしたこととは言え、このように水を差すような事件は非常に残念なことである。自戒も含め、建築やまちづくりに携わる人々には、高いモラルが求められることを肝に銘じたい。
また、今回の事件により、建築に携わっているわけではない一般の方々にとっても、安全はただではない、自分の身は自分で守らねばならないということを強く意識する機会となったのではないだろうか。この事件をきっかけに、建築の専門家でなくとも、自分たちの生活に深く関わる建築物について、設備面の使い易さや見た目の雰囲気の良さだけでなく、目に見えない構造に至るまで、様々な角度から興味・関心を持つなどの意識改革を進め、厳しいチェックの目を養うことにより、二度とこういう事件を起こさせない、許さない世の中を作っていくことが重要ではないだろうか。

