クローズアップテーマ
4-11.ヘルシーカンパニーのススメ(2)
2007年10月30日
◆「ヘルシーカンパニー」の3つのメリット
ヘルシーカンパニーのメリットは企業・従業員別に下表のような点が指摘されている。一見良いことづくめではあるが、費用対効果の検証も必要だろう。本稿では定量的評価ができるヘルシーカンパニーの指標を検証する。
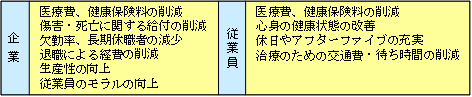
メリット1 医療費、健康保険料の抑制につながる
保健指導によって医療費抑制効果があったとの報告は多々あり、たとえばJFEスチールでは高脂血症の指導教室を実施し、年額約400万円の医療費節約効果(対象者約100人)があったとしており(注1)、三菱電機では2002年から実施している三菱ヘルスプランを通して、歯科関連の医療給付費を約2億円減少させるなど一定の効果を出している(注2)。また、ヤマハでは「健康講話」の実践を通じて1人当たりの平均医療費を低減させ(注3)、クレハ健康保険組合では訪問型の健康保険指導を通して医療費を削減しており(注4)、効果的な保健指導の実施によって医療費を削減した事例は枚挙に暇がない。
その他、ワールドでは従業員をセグメント化して保健師が効果的な施策を展開することで、健康保険料率をおよそ8年かけて86‰から47‰までほぼ半減させ、およそ10億円の経費削減効果をもたらしているという。
制度変更でボーナスからも保険料を取るようになったことが保険料率の低下に影響していることも影響しているが、保険料率60‰以下の健保は平成12年度の7健保から平成16年度には197健保へ増加している。保険料率が80‰以上の健保が652もある中で、保険料率を下げる実績を上げる優良健保との格差は覆いがたい。
メリット2 傷害・死亡に関する給付の抑制につながる
かつての労働災害から、長期欠勤、過労死や過労自殺がクローズアップされるようになっている。精神疾患による労災認定基準が緩和されたことで、損害賠償請求や刑事訴訟は増加傾向にある(注5)。
若手従業員が過労自殺した電通過労自殺事件では1億6,800万円という過去最高の損害賠償金支払いが命じられたが、電通では1人当たりの保健事業費が非常に高く(電通の保健事業費用は平成16年度で54,206円、全国平均の19,297円を大幅に上回る)、健康管理には相当のコストを割いている傾向が見受けられる。それにも関わらず、本件のために電通の受けたダメージは1億円や2億円程度の損失ではない。
その他、トヨタ自動車社員の過労による自殺やスギヤマ薬局の薬剤師の過労死(8,300万円の損害賠償)などここ数年で損害賠償請求に至った事例は増加傾向にある。従業員の健康管理への取り組みで企業が避けられるダメージは想像以上に大きい。
メリット3 長期欠勤、労働損失の抑制につながる
厚生労働省「平成17年度労働安全衛生基本調査」によると、過去1年間にメンタルヘルス上の理由により休業した労働者数の割合は0.2%にのぼるが、これは氷山の一角であろう。
平成17年度の従業員1人当たりの付加価値生産性(労働生産性)は約1,362万円(注6)に上るが、長期欠勤や退職により付加価値生産性を逸失することになる。欠勤1ヶ月につき100万円の逸失利益が生じる計算だが、実際の毀損はその程度ではとどまらない。
健康への取組みと収益との因果関係を正確に把握することは難しいものの、保健事業を効率的に実施することで投資分以上の医療費抑制を実現すれば、企業が従業員の健康増進に努める価値がある。ましてや企業イメージの毀損を避けられるなら、保健事業は効果的な投資であろう。
- (注1)
- 『効果的な保健対策-JFEスチールの例』「経済Trend」2006年11月より引用
- (注2)
- 『自立・自助の時代の医療~医療制度改革関連法の成立を踏まえて』「経済Trend」2006年11月より引用
- (注3)
- http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu/pdf/hs-b_0010.pdf 参照
- (注4)
- 法研『へるすあっぷ21』2007年7月
- (注5)
- 過労死の認定件数は2005年度で330件である。2002年から年間300件程度で推移している。
(参考:過労死・自死相談センターHP http://www.karoushi.jp/) - (注6)
- 付加価値額(99兆3,262億円)÷製造業従業員数(729万人)=1,362万円

