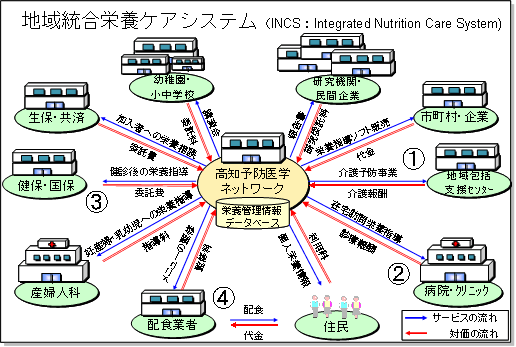クローズアップテーマ
4-14.保健指導等のアウトソーサー(3)
2007年11月20日 松原 伸幸
今回は栄養管理面での特定健診・保健指導のニュービジネス事例を紹介する。
厚生労働省が「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ」との標語で、生活習慣病予防(健康づくり)に取り組んでいるように、食事改善、栄養管理は重要な対策と位置づけている。医療の世界では、適切な栄養管理が疾患の治療を促進するというエビデンスに基づき、病院内に栄養サポートチーム(Nutrition Support Team)が次々と構築され、治療効果の向上や入院期間の短縮などの成果を挙げている。しかし、地域社会においては「未病」(不健康ではあるが病気を発症していない状態)の住民に対する一次予防、あるいは通院患者の継続的な栄養管理等について、専門的な栄養サポートを行うための地域保健・栄養システムが未整備であるという大きな課題がある。
高知大学、高知医療センターを中心に設立された有限責任中間法人高知予防医学ネットワークが核となり、統合ヘルスケアネットワーク(Integrated Healthcare Network)の考え方を取り入れた「地域統合栄養ケアシステム(Integrated Nutrition Care System)」の構築を目指している。
事業内容は次の通りである。
1.介護予防対象者に対する栄養ケアマネージメントサービス(低栄養改善支援)
2.退院後の在宅療養者に対する在宅訪問栄養食事指導
3.健康保険被保険者に対する健診後の保健・栄養指導
4.配食業者に対するメニュー監修
これらのサービスを提供するために、栄養サマリシステムと科学的根拠に基づいた栄養指導システムを構築している。この二つのシステムを使ってテーラーメイド型の個人の身体状況や食生活のパターンなどを重視した科学的根拠に基づいたアウトプット帳票が出力され、臨床栄養指導経験の浅い管理栄養士でも質を維持した栄養指導を行える体制を構築している。特に、3.健康保険被保険者に対する健診後の保健・栄養指導のサービス提供は、単に“食べるな”というだけの指導よりも、栄養管理面からの情報をもとにした食事を提供するアウトソーサーとして期待される。
高知予防医学ネットワークは、“積極的支援”等の3分類ごとに個別面接、集団栄養教室なども行っているが、注目すべきは低カロリー食の配食サービスである。単なる低カロリー食ではなく、対象者の状況に応じてバリエーションを加えたメニューの配食を想定している。
実効性の面から考えると低カロリー食の配食サービスは必須であるが、栄養管理の行き届いた食事の配食サービスは、中山間地域が多い地方ではニーズがあるもののコストの面で採算が難しく事業会社も少ないのが現状である。高知県内ではまさに過疎化が進む地域が多く、低カロリー食の配食サービスの事業化までは至っていない。現在は配送コストの削減に結びつける「地域ネットワークづくり」を模索している状況だ。
特定保健指導は、保健指導をできる事業者が不在の地域も多い。ましてや、指導内容を実現するためのサービス提供事業者が不在の地域が多い。医療機関や半公共セクターが提供の担い手とならざるを得ない局面が多いと考えられる。医療関係者、管理栄養士が低カロリー食を監修して、地域資源(地域の惣菜店、給食センター等)を活用して低カロリー食をしつらえ、介護ボランティアや自治体が実施する配食サービスと平行配食する仕組みなども考えられる。