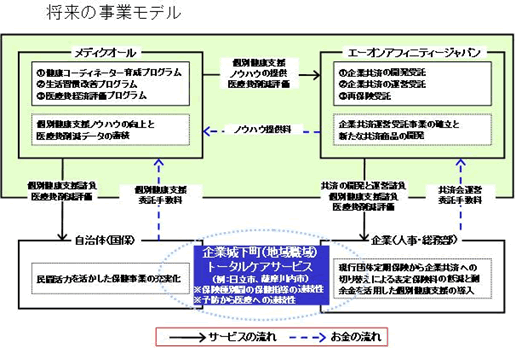クローズアップテーマ
4-2.保健指導等のアウトソーサー(1)
2007年08月13日 松原 伸幸
経済産業省は健康サービス分野における産業育成を目指して、優れたビジネスモデル提案の事業化を支援するサービス産業創出支援事業を展開している。保健アウトソーシングの新潮流を理解することを目的に、この事業の中から特定健診・保健指導のニュービジネス事例を紹介する。
従来から指摘されているように、市町村国保と企業健保が各人の基礎データを個別に管理しているため、企業の退職者が市町村国保へ移行した時にはデータが引継がれない。また、健診内容や保健指導方法が統一化されていないため、保検種別間で保健指導が分断されている。このような状況下、長期間の蓄積データから得られる疾病予防のためのデータを活用する事ができず、継続的な疾病予防サービスの提供が困難であった。この解決策として、市町村国保と企業健保の統一規格による管理手法により、退職者が引き続き同規格の疾病予防サービスを受けられる体制作りが望まれる。
今回紹介する株式会社メディクオールを代表団体とする「地域職域トータルケアサービスコンソーシアム」は、“市町村国保からの疾病予防サービスの受託事業”と“企業からの疾病予防サービスを組み込んだ企業自家共済運営受託事業”の組み合わせを企業城下町で展開し、「地域職域ワンストップ型トータルケアサービス」の提供を目指している。企業城下町なら、職域と地域の各々の対象者に重複する者が多いため、一貫して疾病予防サービスを提供しやすいところに目を向けたサービスモデルである。
また、疾病予防サービスの効果分析を行うための「医療費経済評価プログラム」を開発した。これは疫学統計学・医療経済学に基づいており、薬剤経済評価手法として標準化されたマルコフモデルを応用し、東京大学大学院と共同開発したものである。本事業では、企業従業員のデータに基づく疾病予防サービスの医療費削減効果を試算した。このデータを基に企業自家共済の開発・受託を大企業に対して進めている。
企業自家共済にしたのは、共済は相互扶助を目的とした運営のため、掛金は保健会社が運営する企業団体保険よりも安価に設定できるためである。加えて商品に対する認可を要しないため、幅広い共済商品を企業従業員に提供できる点でメリットがある。さらに余剰金は利益とせず、還付するか健康づくりに役立てる必要がある。要するに、この事業のビジネスモデルでは、共済の余剰金を原資として従業員の健康づくり指導を行うことで、新たな費用負担を発生させずに医療費削減を目指している。さらに、将来の医療費を抑制することでなお安い掛金を期待することも可能である。
他にも、仕組みづくりだけでなく仕組みを動かすための人材育成にも力を入れている。疾病予防から医療への連続性を持たせるため、疾病予防サービスで地元医師会や医療機関と連携し、症状が懸念される対象者のデータや生活習慣を医師へ引継ぐため、管理栄養士や保健師などの専門家を疾病予防サービスを担う「健康コーディネーター」として養成する講座を開発し、着々と健康コーディネーターを養成している。
生涯の健康づくりを一貫して効率的に推進しようとする自治体、企業健保にとっては参考になるサービスモデルである。
(出典)経済産業省「サービス産業を創る!2007」