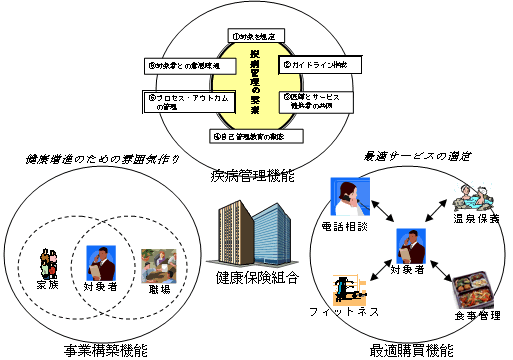クローズアップテーマ
4-16.今後求められる健康保険組合の役割とは
2007年11月26日
これまで法定健診、福利厚生等の保健事業を企業本体が担っていたたこともあり、健康保険組合の被保険者健康管理は補助的な役割であった。しかしながら、特定健診・特定保健指導等の義務化により健康保険組合の役割が重視されることになった。健康管理活動の見直しが迫られる過程で、健康保険組合の健康管理機能が改革を求められるようになる。
今までのわが国の健康管理活動は、被保険者(被扶養者)への保健事業を実施しても、その効果を積極的に検証評価することは行われてこなかった。欧米のDisease Management(疾病管理)※ではかねてより
(1)対象集団を明確にして、疾病管理の対象を規定する
(2)科学的根拠に基づく診療(EBM)ガイドラインを作る
(3)医師とサービス提供者の共同実践モデルを作る
(4)患者の自己管理教育(一次予防方法、行動変容プログラム等)を行う
(5)プロセスとアウトカムを測定し、評価し、管理する
(6)健康管理に対する定期的な報告を受け、対象者とコミュニケーションを取る
の6つの要素が掲げられており、評価し管理することの重要性を問うている。
わが国でも(1)対象規定、(2)自己管理教育、(6)コミュニケーションについては、たとえばコマツ健保組合が被保険者(被扶養者)をセグメントに分け、集中的に指導を行い、インターネット等を用いて綿密なコミュニケーションがとれる体制を整えている等、先進的な健保組合では取り組まれている事業である。また、(3)医師との共同実践モデルについては、メディカルフィットネスや食育など医師などの専門家を事業の中核に据えた取り組み事例が増えており、健保組合においても産業医や保健師等との連携が今後の事業成功のカギとなる。
このうち、特に(4)自己管理教育については、生活習慣病が他の疾患に比べて自己管理による病態の改善が望めることから、個人が病気の本質を理解して能動的に自己管理する必要がある。このような点から、被保険者が自己管理できるように補助し、行動変容を支援する取り組みが大切となる。コマツ健保組合等の取り組みを見ると、個人の自己管理だけに任せるのではなく、職場環境や配偶者・子供を含む家庭環境など本人が健康増進に取り組みやすい雰囲気を作り上げるための仕掛け作りの効果が高く、健保組合の取り組むべき事業であろう。
(5)EBMガイドライン、(6)アウトカム評価については、医療給付費と保健事業の関係性を分析する健保はあるものの、次の事業施策に生かしきれずに有効に機能していないようだ。
被保険者に継続的に健康管理に取り組んでもらうには、被保険者の生活行動を分析して、健診結果等でセグメント分けした集団群に対してピンポイントで実効性のあるメニューを用意しなければ高い効果は望めない。
健康保険組合は利用者のニーズや特性(職種・年齢・地域など)に関わらず、健診結果のみに合致するサービスを提供するため拒否反応を引き起こしている。個人ニーズに合致した最適なサービスを提供できる事業者を選定する調整機能が求められる。今後は、上記疾病管理機能に加え、保健事業をプランニングする事業構築機能、食事管理や運動プログラム等の幅広い各種サービスから効果の高いメニューを評価し絞り込む最適購買機能等が求められている(これらの機能も外部委託が可能)。
※ Disease management components include
http://www.dmaa.org/dm_definition.asp