コラム「研究員のココロ」
企業診断のお勧め
2008年06月23日 竹下隆
個人の人間ドック健康診断同様、企業にも総合的な診断が必要です。グループの整斉とした発展のために自社のみならずグループ関係会社の定期的な診断を是非ご検討ください。また、M&A対象企業のビジネスデューディリジェンス、あるいは企業の再生計画立案といったスポット的な課題にも企業診断の手法は活用可能です。
今回は、私共のクラスターが実施している企業診断の方法と考え方を紹介します。
企業診断モデル
下図が使用する企業診断モデルです。企業全体をもれなく把握するために、11の要素を設定しています。まず、それぞれの視点から、企業がどんな状態にあるのか、いかなる課題に直面しているのかをチェックし整理します。モデル図の各要素の中にその結果を要約し記述すれば企業全体の状態をひと目で俯瞰できます。
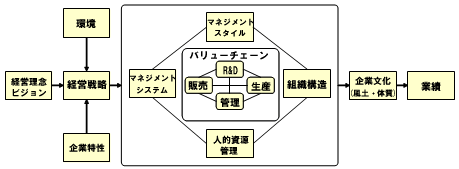
(注)
・経営戦略:企業戦略(事業構造戦略)、事業戦略(製品市場戦略、競争戦略)
・企業特性:事業特性、企業発展段階、存立基盤、成長ヒストリー、成功・失敗体験
・バリューチェーン:研究開発・販売・購買生産・管理の各機能
・マネジメントスタイル:リーダーシップ、意思決定、コントロール、コミュニケーションのスタイル
・マネジメントシステム:計画策定システム(経営計画、予算管理、目標管理)、業績把握システム
・組織構造:組織編成、階層、機能分化、責任権限、組織間連携
・人的資源管理:人事理念、人事制度と運用、要員構造、新陳代謝
・企業文化:共有化されている価値観、思考・行動様式
・業績:経営成績(P/L・CF)、財政状態(B/S)、シェア・新製品比率等の目標達成度
各要素にミスマッチはないかを診断
次に大目標であるビジョン到達にむけて各々が整合性をもって有機的に繋がっているかを検討します。
例えば、事業環境にマッチした戦略となっているか。戦略推進のためにバリューチェーンが競争に打ち勝つビジネスモデルとして構築されているか。企業文化は掲げたビジョンや計画の実現を妨げていないか。業績(経営成績、財政状態)面からみて現在の目標、戦略、マネジメントの枠組みは妥当か等々といった具合です。
また、各要素はこうでなければならないという普遍的な解はありません。大型案件単発受注事業と小口案件蓄積型事業とでは要求されるマネジメントスタイル、システム、組織構造、人的資源管理、企業文化の内容は大きく異なるはずです。前者は契約までに期間を要し、その間、変化に応じた臨機な対応が必要とされます。そうすると自由度を相当持たせたマネジメントが妥当ではないでしょうか。後者は、定められた活動を着実に実践していくことが大事であり、したがって日々のきめ細かいコントロールが肝要となります。このように、各要素はその企業が展開する事業の特性にマッチしたものでなければならないのです。特性の異なる複数の事業を持つ企業が事業部制、カンパニー制、分社と組織を区分していくのは、それぞれ異なったマネジメントを要求されるからに他なりません。
市場情報の確実性(大⇔小)や変化のスピード(速⇔遅)、収益獲得のスタイル(ストック型⇔フロー型)、重視すべき行動(how to do⇔what to do)、重要度の高い資源(物的資源⇔人的資源)、成果に要する時間(長期⇔短期)、投資規模(大⇔小)、要求される人材構造(均質集団⇔異種・異能集団)等の視点から自社の事業の特性を分析してみてください。そして、その特性にふさわしいマネジメントのあり方を検討し現在とのギャップを探るのです。
企業変革方向をデザイン
以上の検討からどの要素が問題なのか、ミスマッチとなっているのかが明らかになります。次にその要素の抱えている課題をどう解決するか、全体や事業特性との整合性を保つために何をどう変えるべきかを検討します。これが変革方向のデザインです。
但し、一つの要素を変えれば企業が変わると単純には考えないでください。各要素は相互に関連を持っています。例えば、企業文化を変えるためにはそれを創りあげてきた各要素(マネジメントスタイルやマネジメントシステム、人的資源管理等)にもメスを入れなくてはなりません。企業再生ともなると、ビジョンや目標、戦略からも見直すことになるので、多くの要素を整合性をとって変革することが必要となります。
デザイン後、変革方向と内容を診断モデル図の上に記述します。これで現状の姿と変革後の姿が対比できます。企業変革の方向として、この二つの図を組織に示し説明することにより、一層の理解と納得が得られるはずです。

