コラム「研究員のココロ」
経営トップよ“ビジョンを全社に浸透させよ!”<前編>
~『タテ(階層間)のビジョン浸透力』を強化する~
2007年11月05日 中川 隆哉
はじめに
筆者は、自らの活動分野を企業全体戦略におき、中期経営計画(中計)の策定をメインに仕事をさせていただいている。そのため、企業が自前で策定された中計をよく拝見させていただくが、「策定しっぱなし」、あるいは「実行しっぱなし」になっているケースが少なからず見受けられる。
筆者の属する経営革新クラスターでは、中計のPDCAを回すプロセスを通じた企業全体の総合的な実力として『経営戦略力』というコンセプトを提唱している。
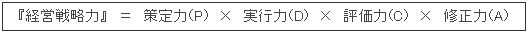
『経営戦略力』はPDCAプロセス全体の足し算ではなく掛け算であるため、上記のような「策定しっぱなし」、「実行しっぱなし」の企業の『経営戦略力』は必然的に低くなり、中計で掲げた目標は達成されることなく“絵に描いた餅”と化しているのが実態である。このように中計が画餅となる理由は数多くあるが、筆者はその最大の原因を、“経営トップの示すビジョンが全社に浸透していない”ことにあると認識している。
なぜ中計は“絵に描いた餅”に終わるのか
多くの企業は企業価値の増大を目標として、数年後にありたい姿(ビジョン)を明確化し、ビジョンと現実とのギャップをうめる戦略(中計)を策定し、その戦略にもとづいた日々の活動を行っている。したがって、ビジョンこそがすべての企業活動の源であり、ビジョンが『経営戦略力』の主体たる経営者・従業員の腹に落ちていないと、いかに精緻な中計のPDCAサイクルを設定したところで機能不全に陥るといえる。そして、残念ながら、筆者の知る範囲において、ビジョンが全社的に浸透しているケースは非常にまれである。こうして膨大な時間をかけて、経営トップの肝いりで策定された中計は、単なる分厚い紙くずとなるか、あるいは秘密文書保管庫の奥に眠ることとなっている。
『タテのビジョン浸透力』を考える
ビジョンを全社に浸透させる力を『ビジョン浸透力』と定義すると、
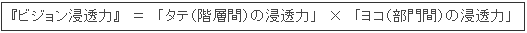
と分解することができると考えている。
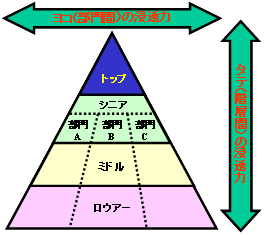
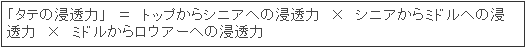
「タテの浸透力」は、各階層から直下の階層への浸透力の掛け算となるため、組織の下部へと進むにしたがい、その浸透度は薄れていくこととなる。
そして、現実問題としては、各階層間には“ハザマ”が存在し、うまくビジョンが階層間の“ハザマ”を乗り越えて伝わらないケースが多い。
『タテのビジョン浸透力』を強化する
では、階層間における“ハザマ”を克服し、「タテの浸透力」を強化するためにはどうしたらいいのだろうか。答えは非常にシンプルであり、階層間におけるビジョンの議論を徹底して行うということに尽きる。我々がクライアントの中計策定に携わらせていただくときには、まずは経営トップにビジョンを語ってもらい、それに対するシニアの質疑応答や意見交換を充分に実施して、ビジョンの熟成・共有化を行っている。そうしたプロセスの中で必ずトップからシニアに対して発せられる言葉が、「そんなことも分かっていなかったのか!」、「今まで何度も言っているじゃないか!」という類である。
経営トップは「伝えたつもり」でも実際には「伝わっていない」のであるが、「伝える」を「伝わる」に進化させ、ひいては「タテの浸透力」を強化するコツは、
- 「なぜこのビジョンなのか」を説明すること
- ビジョンを共有化する時間を確保すること
こうしたプロセスにより、階層間でビジョンを順次おろしていくことで組織下部まで浸透し、「タテの浸透力」が強化されるはずである。
次回は「ヨコの浸透力」について述べたい。
以上

