洞爺湖サミットが近づくにつれて、「排出量取引」あるいは「排出権取引」と言う単語を新聞・TVにて目にする機会が増えてきた。「排出権取引」はキャップ・アンド・トレード(注1)と言う制度であり、簡単に言えば政府が、企業に温室効果ガス排出上限枠を設定し、その排出枠を融通しあう事を認めて、上限目標の達成に柔軟性を与えている制度である。
キャップ・アンド・トレードと言う制度が、温室効果ガスの削減に有用な制度であるか否かについては、様々な意見がある。簡単にまとめれば、以下のような特徴を持ち、単純にキャップ・アンド・トレードを導入すれば全て上手く行くと言うものではない。
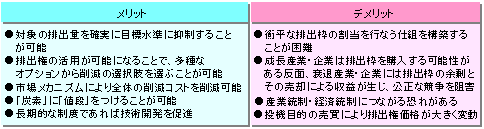
今回は、キャップ・アンド・トレード自体を良い悪いと言うのではなく、温室効果ガス削減目標の達成手段の一つとして見た場合に、「法的な義務を背景として、確実に目標水準に温室効果ガス排出量を抑制できる」と言う点に着目して、その「使い方」を考えてみたいと思う。
なお、本コラムの元になったコラムをクローズアップテーマ特別コラム「排出権取引(キャップ・アンド・トレード)のススメ」として公表しているので、ご興味のある方はご覧頂きたい。
1. 排出権取引(キャップ・アンド・トレード)の使い方
二酸化炭素排出量の多いエネルギー転換部門と産業部門において、二酸化炭素排出量を減らすとした場合、そのコストを誰が負担するべきなのかが大きな問題となる。特に鉄鋼業など国際的な競争に晒され、製造業全体の競争力に影響を及ぼすような業種について、二酸化炭素排出削減のコストをそのまま負担させる事は、日本の国際競争力を大きく毀損するおそれがあると言える。
キャップ・アンド・トレードには、排出枠の配分を通じて、コスト負担をさせる仕組み(排出枠の配分が多い会社はコスト負担が小さく、配分の少ない会社は追加的な対策が必要になり、コスト負担が大きくなる)が備わっている。その裏返しとして衡平(バランスの取れた)な排出枠の割当が難しい事が問題視される。しかし、そもそも衡平な排出枠の割当をする必要があるのだろうか。電気事業者のような、国内のみの「お客様」を相手にしている業界と鉄鋼業の様に世界と競争しつつ、製造業全体の競争力を支えている業種の間では、何をもってバランスが取れていると判断できるのだろうか。
「衡平な」割当は、競争環境・負担の再配分許容度・日本の国際競争力への影響度などを調整者である「政府」が多様な意見を尊重しつつ業界の位置付けを検討し、長期的には温室効果ガス排出量を大幅に削減するという目標との整合性を保ちつつ、各業界の排出枠を決定すれば良いのである。
具体的には、例えば電気事業者には、1990年度比50%削減程度の排出枠にする一方で、鉄鋼業は業界内のトップランナーを基準とするなどして、排出枠を設定し、1990年度比5%削減とする。他の産業部門の業種においても同様にして、トップランナーをベンチマークとした排出枠を設定し、国際競争力への影響を考慮した割当とする。
電気事業者は、排出枠の割当が上記のように少なくなった場合、石炭火力発電などの二酸化炭素を大量に排出する電源を使うには、排出係数を引き下げるために排出権が必要になるため、長期的には再生可能エネルギーやCCS技術へと移行していく必要がある。また、国内世論の動向によっては原子力発電の新規立地を進めることになる。その場合、多額のストランデッドコスト(注2)が発生する可能性がある。そのため、電気事業者への排出枠割当を少なくする場合は、新規の設備投資費用に加えてストランデッドコストをどのようにして回収していくかが重要な課題となる。
2. 誰がどのようにコストを負担すべきなのか?
キャップ・アンド・トレードにおいて、大きなコスト負担をすることになる電気事業者のコスト配分の考え方として、現在の非自由化分野における電気料金の決め方である総括原価方式(注3)に組み込む事で、需要家に広く薄く配分させる事を提案する(当然、自由化分野へもコスト負担させるべきであるが、主要な負担先としては非自由化分野を想定している)。
総括原価方式に地球温暖化対策のコストを反映させるという事は、電気事業者が一般家庭や事業所、小規模な工場など電源構成を自由に選ぶ事が出来ず、電気の消費量を大幅に削減する意識・インセンティブが弱い「地球温暖化防止の努力をすることが出来ない人」に代わって温室効果ガス削減努力をする事である。言い換えれば、最も対策が難しい民生部門における温室効果ガス削減を電気事業者が代わりに行う事を意味している。そして、総括原価方式に地球温暖化対策のコストを反映させる「根拠」が政府からの規制措置であるキャップ・アンド・トレードなのである。
3. 日本が目指す低炭素社会を示せ
現在、洞爺湖サミットに向けて首相官邸・経済産業省・環境省のそれぞれにおいて、キャップ・アンド・トレードに関する議論が行われている。これらの議論の中で大きく抜け落ちているのは、キャップ・アンド・トレードが良い悪いではなく、「温室効果ガスを2020年度には、1990年度比で○○%削減させる」という目標を持つか持たないか、持つのであればそれをトップダウンで決めるのか、積み上げで決めるかという事である。
日本は国際的な場で再三、「国別の削減目標はセクター別の積み上げ方式で決めるべきである」と主張している。しかし、EUはIPCCの分析を理由に2050年までには、全世界の温室効果ガス排出量を半減させる必要があるとしており、そのマイルストーンとして、2020年に先進国は25~40%の削減をすべきであると主張している。日本が結果として、積み上げ方式でEUに近い削減目標を打ち出せば評価は変わると思われるが、今の段階では日本の主張はEUから見ると「やれる範囲で頑張ります」と言う主張にしか映っていないと考えられる。IPCCの分析が正しいとすれば、世界において賛同を得られる考え方は、EUが示している2050年までには全世界において温室効果ガス排出量を半減させると言う主張であり、その通過点として2020年においても具体的な高い目標が必要になる事は当然である。
このような状況の中で、日本が積み上げ方式のみを主張し続けても、幅広い賛同を得られるとは考えられない。セクター別に積み上げる事は必要であるが、絶対量としての削減目標を決めて、その目標と積み上げ方式によるギャップがどの程度有り、そのギャップを克服する事ができるのか、を議論すべきである。
その議論の中でこそ、キャップ・アンド・トレードが、ギャップを克服するためのツールとしてどのように使う事ができるのかについて考える事ができる。今回、筆者が提案したような電気事業者に厳しく・産業部門に甘いような「使い方」もあれば、衡平さを重視した「使い方」もあり、それは政府や多様な利害関係者が議論を深めながら作り上げていくものである。いずれにしても日本の現状をふまえつつ、日本が目指す低炭素社会がどのようなものであり、2020年や2050年には「具体的に」どれほどの温室効果ガス排出量に抑制するのかを明確に語る事が重要である。
日本政府は、京都議定書に続く枠組みには、アメリカや中国など大量に温室効果ガスを排出している国々の参加を求めている。これらの国が参加できるように積み上げ方式を提案しているが、自らの削減努力を語らなければ、少なくとも中国やインドの賛同を得られるとは考えられない。中国やインドへ積み上げ方式での国別目標を求めるにしても、日本はより高い目標を示して、これから経済成長に伴って大量の温室効果ガスを排出しようとしている中国やインドへ、排出抑制の必要性を行動で示す事が重要ではないだろうか。
注1 キャップ・アンド・トレード:
二酸化炭素排出量の削減方法の一つ。各企業あるいは事業所単位で1年間に排出できる二酸化炭素量に上限値(キャップ)が設けられ、それを達成できない場合は罰金等の罰則が科せられる。補完的な仕組みとして、上限値まで二酸化炭素排出量を減らすことが出来ない企業は、他の企業から排出権を買って(トレード)自社の上限値を引き上げる事ができる。理論的には最小の費用で目的とする二酸化炭素削減量が達成できる。一方で、どのように決めても上限値を巡って企業・事業所間に不公平感があるなど制度としての課題も指摘されている。
注2 ストランデッドコスト:
電気事業において、電力自由化や政府や地域の電力規制が変更された場合に、それまでに実施した設備投資や契約と新しい電力価格との間で整合性が無くなり、それまでに投下した費用が回収不能になる場合がある。そのような回収不能になった費用をストランデッドコストと言い、政府等がルールを作るなどして、ストランデッドコストを回収する手だてが講じられない場合、電気事業者に多大な負債が残る事になる。
注3 総括原価方式:
供給計画・工事計画・業務計画・資金計画をベースに、そこに含まれる人件費+燃料費+修繕費+購入電力量+諸税+減価償却費+事業報酬+その他費用を合算した「総括原価」を算定する。この「総括原価」を需要家毎に使用する設備や送電ロス等を勘案して配分し、需要家(契約区分)毎の料金が決定される制度。
関連リンク
- クローズアップテーマ:地球温暖化【特別コラム】「排出権取引(キャップ・アンド・トレード)のススメ」

