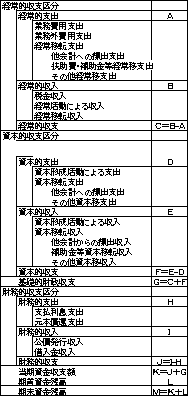コラム「研究員のココロ」
新地方公会計制度における「純資産変動計算書」とはなにか
2007年09月21日 井上研司
(1)新地方公会計の財務諸表
新地方公会計制度研究会報告書が公表されて「純資産変動計算書」という新しい財務諸表が導入されることになった。その作成や利用方法について各自治体でも関心を持たれていることと思われる。
地方公会計の財務諸表は、今回の報告書の公表によって貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の4表となった。民間の会計が、貸借対照表(以下、バランスシート)、損益計算書、資金収支計算書(以下、キャッシュフロー計算書)の財務3表よりなるから、行政コスト計算書を損益計算書と考えるなら、地方公会計のほうが一表多い(純資産変動計算書)ことになる。
ここでは、民間企業の財務諸表との比較の観点から純資産変動計算書とはなにかについて考えてみたい。一言で言うと、純資産変動計算書とは地方公会計におけるバランスシートの純資産の部を計算するものである。したがって、地方公会計におけるバランスシートの純資産の部の構成を見れば、純資産変動計算書の構造がわかる。
最初に各財務諸表の関連を以下での説明をふまえて概観してみたい。(以下での検討は新地方公会計制度研究会報告書の「基準モデル」に対するものである。また、地方公共団体の会計データの整備の状況に関しては、通常のシステムで扱われている程度のレベルを想定する。)
(2)4つの財務諸表の関係
民間の会計にも類似のものがあるバランスシート、キャッシュフロー計算書、行政コスト計算書(損益計算書)の3つの財務諸表と純資産変動計算書の関係を図1に整理した。公会計上の原データは現金主義で作成されているから、キャッシュフロー計算書(CF)は決算書の組み直しにより最初に現金主義の枠内で作成できる。しかし、キャッシュフロー計算書以外の資産変動計算書(NAS)を含む3つの財務諸表は発生主義で作成されるから決算書をまず発生主義に修正する必要がある。行政コスト計算書(CR)とバランスシート(BS)は、従来から作成が提案されてきた財務諸表であるが、ここで使用されている数値についてはすでに発生主義化されている。したがって、CRとBSが作成されていれば、そのデータを用いてNASの資産充当財源部分など大半は作成可能である。
NASは、決算書の収入(A)を収益(B)と財源の調達(C)に区分した上で、ここまでで作成されてきた発生主義のデータを組み直せばほぼ完成させることができる。最後にNASの「当期純資産変動額(当期末残高)」(F)とBSから計算される純資産の部の金額が一致すれば計算が正しかったことが確認される。図1の財務諸表中のアルファベットは、それぞれほかの財務諸表の対応する部分である。
(図1)新地方公会計制度における4つの財務諸表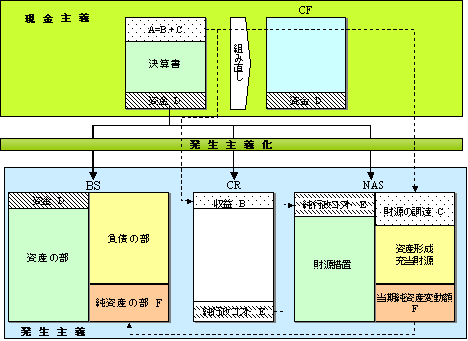
(注1)純資産変動計算書については「公会計改革」 桜内文城 講談社現代新書を参考にしている。
(注2) CF:キャッシュフロー計算書、BS:バランスシート、CR:行政コスト計算書、NAS:純資産変動計算書の略
(3)民間企業のバランスシートとの比較
当初の試みに戻って、バランスシート(BS)の純資産の部から純資産変動計算書(NAS)の中身についてみてみよう。バランスシートは、図2のように資産の部、負債の部、純資産の部の3つの部門より構成される。この構造は、民間であろうと地方公共団体であろうと変わりない。
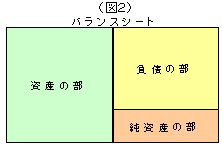
新地方公会計におけるバランスシートの純資産の部は、財源、資産形成充当財源、その他の純資産(開始時未分析残高など)よりなる。一方民間の会計では、純資産の部は資本金、資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等よりなる。
新地方公会計における根本的な考え方は、税収(財源のひとつ)を資本の拠出(注1)とみなすということであるから、この考え方からすると純資産の部に「財源」があがっていることも納得がいく。
資産形成充当財源であるが、これは道路などインフラ投資や庁舎等の建築、あるいは長期金融資産の保有等に充当された財源を処理する項目である。民間企業でも固定資産の現物出資を受けたり、出資金で固定資産を取得する場合は、同様の処理となるので、民間企業で言えば、資本金や資本剰余金に当たる。ただ、民間企業と異なり利益はないことを前提にするので、民間企業の利益剰余金に該当するものは原則ないと考えられる。(表1)
表1 民間企業の純資産の部との比較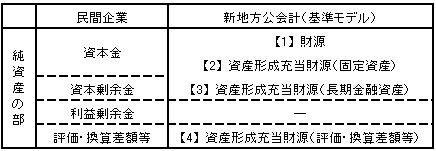
純資産変動計算書は地方公会計における純資産の部を計算するものであるが、これはどのように計算されるのであろうか。表1の内訳を見れば、財源と資産形成充当財源がどのように計算されるかが理解できればよいことがわかる。財源については次の項で扱うこととして、資産形成充当財源のひとつである固定資産(【2】)を例にとると、純資産の部の計算は次の式のように計算される。ここで計算された金額に期首の固定資産の金額を足したものは、バランスシート上の固定資産の金額である。言い換えると、固定資産の取得や減価償却はバランスシートの向かって左の固定資産と、向かって右の純資産の部に左右同じように増減されるということである。
(純資産変動計算書)
資産形成充当財源(固定資産) =
(固定資産の取得額+固定資産の所管換)―(減価償却費+減耗+除却等)
(バランスシート)
当期末の貸借対照表上の固定資産 =
前期末の貸借対照表上の固定資産 + 固定資産の取得額等 ― (減価償却費+減耗+除却等)
同様に、長期金融資産(【3】)についても、次のように計算される。
(純資産変動計算書)
資産形成充当財源(長期金融資産) = 長期金融資産の増加額 ― 長期金融資産の減少額
(バランスシート)
当期末の貸借対照表上の長期金融資産 =
前期末の貸借対照表上の長期金融資産 + 長期金融資産の増加額 ― 長期金融資産の減少額
(4)損益計算書と行政コスト計算書の比較
バランスシート(BS)からもわかる固定資産の金額を純資産変動計算書(NAS)にも収容する理由はどこにあるのであろうか。それは、地方公会計においては損益計算書が行政コスト計算書(CR)になっており、税収等財源を損益計算書に含めないからである。行政コスト計算書はコスト計算が目的であるから、民間企業の損益計算書の売上高にあたる部分には手数料や利用料などしか反映されていない(表2)。税収等財源をどのように扱うかについては、損益計算書に財源を含める方法やバランスシートに一旦負債として計上する方法も考えられるが、行政コスト計算書の業務収益において、民間企業の収益に該当する部分には収入の一部しか含まれない。ここに含まれなかった収入は、純資産変動計算書に「財源の増加」として収容され純資産の部の計算に含められる。「財源の増加」は、具体的には税収や、国庫支出金等の受入のうち資本移転収入等が該当するとされる。報告書での定義は、表3にあるとおりである。
表2 民間企業の損益計算書との比較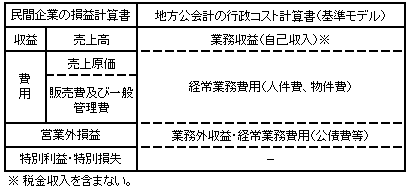
表3 収益、財源の調達の定義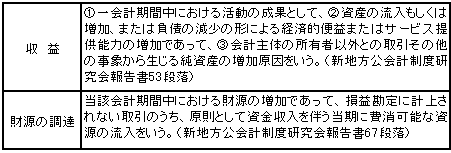
(5)キャッシュフロー計算書の比較
古典的会計の立場から言うとキャッシュフロー計算書(CF)は損益計算書から作られるという点で補助的な存在である。民間のキャッシュフロー計算書の作成方法には、二つの方法がある。ひとつは「間接法」であり、もうひとつが「直接法」である。いずれの方法によっても最後の行に計算されるのは現金等価物の金額である。間接法による場合、損益計算書の末尾に計算される利益(当期純利益、図3、PL下の網掛け部分)から出発してキャッシュフローに還元していくのに対して、直接法では資金の出入から直接キャッシュフロー計算書を作成するという点が異なる。民間企業では間接法で作成している例が大半であるとされる。(図4)。
(図3) 財務諸表の作成手順の比較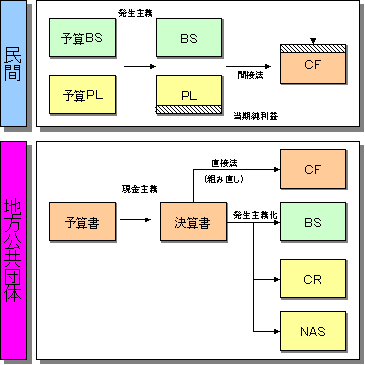
(注) CF:キャッシュフロー計算書、BS:バランスシート、PL:損益計算書、CR:行政コスト計算書、NAS:純資産変動計算書の略
一方、公会計システムは現金主義であるから、それはキャッシュフローそのものである。したがって、利益から還元する必要がなく、原データからの「組み直し」によって作成できる。この意味で、公会計のキャッシュフロー計算書は「直接法」により作成されるといえる(図3、地方公共団体)。さらに、キャッシュフロー計算書は、表示方法は違うものの予算書(決算書)そのものということができる。新公会計制度では、財源を資本(純資産)として扱い純資産変動計算書で処理しようと考えているが、財源が純資産変動計算書以外の財務諸表のほかに現れないかというと、キャッシュフロー計算書上に「経常的収入」のひとつとして「税金収入」が上がっている(図5)。したがって、税収等財源が純資産変動計算書以外の財務諸表からまったく漏れているわけではない。
(6)これからの公会計改革
民間企業の財務諸表との比較の観点から純資産変動計算書の他の財務諸表との関係について検討した。
地方の行財政改革のコンサルティングをする立場から言えば、最も公会計が意味あると考えられるのは、民間企業とのコスト比較においてである。この意味で少なくとも民間の会計と違和感なく容易に比較可能であることが公会計の制度を考える上で必要なのではないかと考えられる。これがここで民間企業の財務諸表と比較した理由である。
また、今回の新公会計制度は、「財務諸表の体系化に当たっては、… 原則として、国(財務省)の作成基準に準拠する 」とされている。国とは財務諸表の利用目的が異なるのではないかという見方もあるため、国の制度に引きずられることは地方の分権化に逆行する場合もあるのではないかと考えられる。
現在の地方公共団体の会計の最大の課題は、予算管理に偏重しているシステムを、コストマネジメントに活用できるシステムに変革することである。言い換えれば、予算システムにがんじがらめになったシステムをより柔軟なシステムに変更することでもある。今回の新公会計制度報告書によって純資産の部の計算が明確になったことは評価される。しかし、民間企業の会計システムが有用なのはその柔軟さにもあると考えられるので、制度の枠組みを厳密に決めることよりもまず、利用可能なものが広まることが大切なのではないか。
(以上)