コラム「研究員のココロ」
内なるブランド化による企業ステージアップ
2007年08月27日 竹内祐二
企業変革の2つのスタイル
企業が変革を遂げるスタイルには、外圧による変革と、内面からの変革の2つがある。前者は、株主や金融機関がガバナンスの主導権を握り、ときには経営者の思惑とは異なる姿に変革するもので、多くの場合リストラを伴う。このスタイルは、短期間で一定の成果が期待できるものの、社内にさまざまな傷跡を残すことになり、経営者としてはできるだけ避けたいのが本音であろう。
それに対して後者は、企業自らが危機を察知して未然防止の手を打ち、最悪窮地に陥ったとしても自力で脱する手だてを講じるスタイルである。このやり方は、企業変革の理想型であるが、すべての企業で実践できるとは限らない。トヨタのように“KAIZEN”活動が組織風土として定着している企業は別として、多くの企業では経営者が現状を直視することを避けたり、経営スキームの変更に難色を示したり、改革を推進できる人材が不足していたりするのが常であるからだ。
内面からの変革の新しいスタイル
外圧による強制的な変革は避けたいが、さりとて改革を推進する人材も豊富にいるわけでもない。こうした企業では、社員の潜在能力を引き出し、その力を推進力にして企業を変革させるスタイルが有効である。本稿では、このスタイルを“企業ステージアップ活動” による変革と呼ぶ。
まず、社員の潜在能力を引き出すには、社外の顧客、取引先、そして社員が自社をどのように見ているかを可視化することによって、現在の位置づけ(ポジション)を知らしめる。社員がおぼろげに描いている自社の位置づけ、すなわち、競合企業、同規模企業、同一地域の企業と比較してこれぐらいのレベルであろうという認識に対して、社内外からの評価を客観的な事実として示す。社員が認識と事実のギャップを知ることで、一人ひとりに自己反省と改善意欲が芽生えるのである。
次に、社員の潜在能力を改革の推進力とするためには、会社を現状よりも一段階高いステージにステップアップすることを全社で意思統一し、その姿を長期ビジョンとして明文化する。そのことによって、ステップアップに向けた課題が明らかになり、課題を解決しようとする力が生まれるのである。
企業ステージアップ活動への取り組み(1)
-会社のポジションを「ブランド浸透度」で測定する-
企業のブランド浸透には、顧客向けのエクスターナルブランディングと、社内向けのインターナルブランディングの2種類がある(図1参照)。

エクスターナルブランディングとは、テレビCMや新聞、雑誌などを通じて、企業認知度や商品イメージを向上させる活動で、多くの企業で一般的に行われているものである。インターナルブランディングとは、社員が重要なステークホルダーであるとの認識のもとに社員のロイヤルティを高める活動であるが、体系だった取り組みをしている企業は少ないようである。インターナルブランディングに熱心な企業のひとつにリッツ・カールトンがある。同社は、スタートアップと呼ばれる朝礼で20項目ある行動基準を毎日一つずつとりあげ、メンバー全員でその意味を考えるなど徹底した取り組みを行っている。同社は、社員を第2の顧客と位置づけ、継続的なインターナルブランディングによって、社員と顧客の双方から圧倒的なロイヤルティを獲得している。
ブランド浸透度は、現段階で顧客と社員から自社はどう見られているのか、顧客が持つイメージと社員が持つイメージに差があるのかなどの観点で測定する。測定の方法は主としてアンケート調査によるが、場合によってはデプスインタビューやグループインタビューなどを併用することもある。
企業ステージアップ活動への取り組み(2)-社内プロジェクトによる推進-
ステージアップ活動の推進体制としては、社内横断型のプロジェクトチームを組成すると効果的である。それは、ひとつには社内に全社活動であるという認識を持たせることができるからであり、もうひとつには社内から選抜したプロジェクトメンバーに高い視点から会社全体を見る機会を提供することで、人材育成につなげられるからである。また、人事部門や企画部門など特定部門が主導すると、社員の評価が正しく上がってこない恐れがある。
ステージアップ活動においては、ブランド浸透度の測定によって明らかになった課題に対処することはそれほど重要なことではない。それよりも、会社の現状のポジションを正しく認識したうえで、「ではどうあるべきか」「何を解決すべきか」の議論の方が重要である。長期ビジョンを設定する議論と、長期ビジョン達成に向けた課題を導くための議論のプロセスにこそ価値がある。
長期ビジョン設定の議論の過程で、戦略やビジネスモデルの組み替え、人事制度や管理会計制度といった経営システムの再設計などたくさんの検討テーマが発掘されるが、それらを一定期間内で議論し尽くすことは難しい。ステージアップ活動は、短期決戦型ではないので、これらの検討および課題解決は段階的に行うことが望ましい。
最初の段階では、経営陣とプロジェクトメンバーを中心にした5%のコア人材が、会社の現状と将来のあるべき姿についての共通認識を得ることに焦点を絞るべきである。5%の人材が共通認識を持てば企業は動き始め、次の段階でさらに20%の人材を巻き込めば企業は変わることができる(図2参照)。
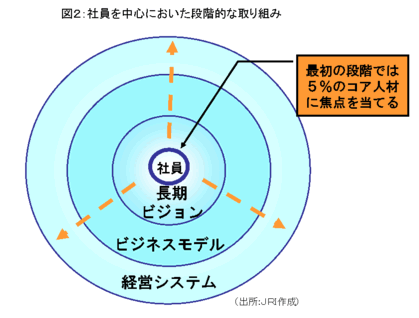
企業ステージアップ活動への取り組み(3)-期待効果-
ステージアップ活動の最大の効果は、社内に一体感が醸成されることである。社員は、経営者から長期的にめざす姿が示され、課題解決に向けた活動を目にすると、「会社が変わっている」という実感を持つ。社員と各部門が共通の目標に向かって仕事を進めると、互いに協力しようとする意識が生まれ、組織の壁も低くなる。
もう1つの効果は、プロジェクトメンバーをはじめとするステージアップ活動に主体的に関わってきた社員がいい意味で変わることである。これらの社員には、会社の現状を分析し、将来のあるべき姿を考える過程で、会社を牽引していかなくてはいけないという自覚が生まれる。もともと潜在能力のある社員は、いい刺激を与えると大きく成長することができる。
企業ステージアップ活動への取り組み(4)-なぜ社員が変わるのか-
ステージアップ活動は、社員の潜在能力を活用して内面から企業を変革する手法であり、社員の意識をどう変えるかが鍵となる。経営者の中には、社員の意識改革を図るには、「給料を上げれば・・・」とか「業績評価をきちんとすれば・・・」と考える人も見受けられる。
しかし、社員の意識を変えるのに給与の多寡は大きな問題ではない。弊社がこれまでに実施した意識調査では、社員の関心の度合いは、「処遇」よりも「社会貢献」や「組織の一体感」の方が高い、という結果が得られている。このことは、経営者が思うほど社員は未熟ではなく、場合によっては経営者よりも高い志を持っていることを示している。
成熟した価値観と高い志を持つ社員は、崇高な理念に共感を覚え、自分が社業を通じて社会に貢献しているという実感を大切にする。
ステージアップ活動は、社員一人ひとりに「あなたはどうありたいか」を問いかける。社員は、問いかけに対して自分なりの答えを出す過程で成長し、変わっていくのである。
企業ステージアップ活動への取り組み(5)-適用できる企業のタイプ-
ステージアップ活動は、全ての企業で成功するとは限らない。特に、経営者自身が変わろうとしない企業は、うまくいかないだけでなく、現状よりも社員のモラールダウンを引き起こす恐れがある。それは、社員が成長した目線で経営者を見て、変わろうとしない姿勢に失望するからである。ステージアップ活動は、経営者を含めた全社員が、さらに上のステージを目指そう、そのためには自分も成長しよう、という決意がなければ成功しない。
一方で、ステージアップ活動の効果が期待できるのは、(a)長年成長が鈍化して市場地位も業績も頭打ちの企業、(b)中堅企業の域を脱し大きく伸びていこうとする企業、さらには(c)合併などにより異文化の組織が同居する企業などである。
日本企業は、“人本主義”と呼ばれるように社員を大切にする経営を行ってきた。この考え方をさらに一歩進めて、社員と正面から向き合って“内なるブランド化”を進めることで、内面からの企業変革を成功させることができる。
(了)

