コラム「研究員のココロ」
経営品質活動はなぜ定着しないのか
2007年07月13日 三浦 利幸
1.経営品質活動とは
私の専門分野である「経営品質」と聞いてピンとくる人は、残念ながら現在の日本のビジネスマンの中では少数派だろう。
一般的に「経営品質向上プログラム」といわれる経営品質活動は、組織の理想的な姿に少しでも近づくことを目的に実施する経営革新である。標準的な手順としては、「日本経営品質賞アセスメント基準書」(以下、基準書という)をベースとして、セルフアセッサー(以下、アセッサーという)の研修を受けた人が、セルフアセスメント(以下、アセスメントという)という自社の経営品質診断を行って経営課題を見出し、その課題を解決するという流れで実施されるものである。基準書には良い経営を実現するために組織が実施すべき事項が8つのカテゴリー、さらに合計20のアセスメント項目に分類されて、質問文の形式で記載されており、これに基づいて自社の経営現状を記述した「経営品質活動書」(以下、活動書という)を作成する。アセスメントは活動書に記載された内容を基準書と照らし合わせて実施する。アセスメントでは組織の理想的な姿の達成を最終的な目的としてとらえ(これを価値基準という)、組織の理想に近づくための革新を行う力(成熟度)を評価するところが特徴である。
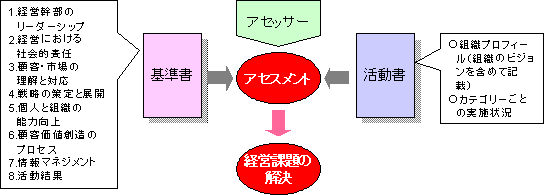
2.経営品質活動の停滞
その経営品質活動だが、経営トップ(一般的なイメージとしては取締役を指す)から現場の社員までの思考や行動の習慣などを評価し、改善していくようなものなので、短期間で成果を求めるべきものではなく、長期の活動としなければ意味が無い。しかし実は導入した企業でなかなか定着しないのが現状のようだ。なぜ経営品質活動は定着しないのだろうか?
筆者は、最大の原因はアセスメントの結論が経営トップにとってインパクトがない、ということだと、いくつかの企業の事例に基づいて推測している。
アセスメントの結果、「これは今まで気がつかなかったが重大な経営課題だ」と経営トップが認識するような経営改革の提言が出てくれば、当然経営トップはその課題解決に動くのは間違いなく、アセスメントを継続してやっていこうという気にもなるはずである。アセッサーに対しても、「よく提言してくれた」と評価が上がり、アセッサーのやる気も向上し、経営品質活動は盛り上がって定着するだろう。しかしそのように経営品質活動が盛り上がったという話は、あまり聞かない。
実際には、アセスメントから経営トップの期待に沿うような提言がなされず、「どんな凄い提言が出てくるか」と期待していた経営トップからすると、肩透かしを食らったような気分になるのだろう。これが繰り返されると、アセスメントしても仕方がないという気分になってしまう。
3.アセスメントが機能しない理由
アセスメントが経営トップの期待に沿えない理由はいくつか考えられるが、
(1)経営トップがアセスメントをする前から認識している課題しか出てこない
(2)組織の現状に対して的外れな課題しか出てこない
(3)どの会社にもあてはまるようなありきたりな課題しか出てこない
(4)重点が絞りきれておらず最重要課題が4つも5つもある
(5)アセスメントに対する経営トップの期待が過大であったり、的外れであったりする
などだろう。
(1)に関しては、アセッサーによる評価が経営トップと同じ意見に落ち着いたわけなので、ある意味妥当といえなくもないが、経営トップとしては経営品質のフレームワークを利用することにより自分が見落としている課題を発見してもらうことを期待しているわけで、その意味ではがっかりさせられるものだろう。アセスメントは、組織の目指す価値実現に向けて、全体最適の視点から、理想と現状のギャップの大きなところを見つけて、そのギャップの解消のための方策を提言するものである。といっても、全体最適の視点や、理想と現状のギャップを埋める方法を見つける洞察力などは、アセスメントの手法として十分にカバーされているわけではなく、単に「全体最適で考えましょう」、「理想と現状のギャップを埋めるための方法を見つけましょう」といっているだけにほとんど等しいので、センスのある人ならばうまく提言に結びつけることも可能であろうが、多くの人はなかなかそうはできない。
多くの人は自分の所属部門や役職の立場から離れられず、その枠を突き抜けた発想にはいき着けない。また理想と現状が違うことは分かっても、理想の状態へたどり着くための道筋が具体的にイメージできない。
アセスメントの手法では、複数のアセッサーが合議することで、よりレベルの高い提言に結び付けていくように考えられているが、根本的にセンスのない人がたくさん集まっても三人寄れば文殊の知恵とはいかないものである。一般的にアセッサーは部課長から係長・主任クラスより選任されているが、そのようなセンスのある人が十分に揃っている組織は少ないだろう。
それから上記(2)(3)(4)は、アセスメントの目的に対する理解が不十分であったり、スキルの修得が不十分であったりすることが原因という、アセスメントを開始する以前の問題なのだが、アセッサーとしてのトレーニングを受けていてもこうなってしまう人が少なくない。価値前提や全体最適で考えられる人が少ないように、アセスメントのスキルなどを正しく身につけられる人も、ある程度限られてしまうようだ。
最後に上記(5)に関して、アセスメントは経営課題を見出すための手法であるが、決して戦略を立案する手法でも、さらには組織の理想そのものや理想に近づくための戦略の良し悪しを評価する手法でもない。アセスメントから起死回生の戦略やビジネスモデルが出てこないかと期待しても、そのような提言は通常出てこない。例えば戦略に関していえば、戦略を立案するプロセスがアセスメントの評価対象なのであって、戦略そのものは評価や立案の対象外である。経営トップ自身もアセスメントの目的を正しく認識しなければならない。
4.誰がアセスメントすればよいのか?
部課長から係長・主任クラスには価値前提や全体最適で考えるセンスを持った人が少ない、しかしそれでも経営トップとして納得のいくアセスメントを行いたい、ということになると、方法は二つしかない。
ひとつは信頼できる外部機関に依頼する方法である。この場合、アセスメントのスキルは高く、その会社の文化に染まっていない客観性の高い目で診断できるので、経営トップが気づかなかった課題をいくつか指摘してもらうことが可能だろう。
もうひとつは経営トップが自らアセスメントを実施するという方法である。自らアセスメントを行えば、納得性に関してはかなり高まるだろう。取締役が10人、20人といるような大企業では難しいかもしれないが、取締役が数人の中堅・中小企業であれば、より実効性が高まるだろう。
経営トップがアセスメントのスキルを身につけるためのトレーニングを受ける時間がないことを心配されるかもしれない。しかし筆者の経験では、基準書やアセスメントの基本知識さえ覚えれば、多くのトレーニングを受けているセンスの無い人より、トレーニングはあまり受けていないがセンスのある人の方が、アセスメント能力が高いといえる。アセスメントの手法自体がセンスに頼る部分が大きいが、残念ながらセンスは少しぐらいトレーニングしてもなかなか伸ばすことはできない。経営トップは会社全体に経営責任を持っている立場なので、全体最適のセンスは少なくとも一般社員よりは普段から鍛えられているはずであり、またもともとそのようなセンスがあるから経営トップに就いているとも考えられる。価値前提に関しても、経営トップは会社が目指す姿を設定する立場にあるので、目指す姿のより明確なイメージがあり、そうなりたいという強い意志もあるはずである。経営トップはアセスメントのトレーニングを受けている時間がなかったとしても、下手に部課長クラスなどに任せるよりは、かなり適切なアセスメントができるだろう。
またアセスメントの前提として現状認識の統一を図るのが、活動書の冒頭に書く組織プロフィールの部分である。組織プロフィールは一般的には経営企画部門などが作成する場合が多いようだが、これも経営トップが自ら納得のいくものを作成するのが望ましいだろう。詳細データなどは関連部門に提供を依頼すればよい。
5.経営トップがアセスメントをしたら?
そもそもアセスメントは経営を全体としてとらえ、革新の方向性を見出していこうとする手法であるため、本来、経営トップがやらなければならないこととほぼイコールのはずである。従って経営トップが自らアセスメントを実施しても、まったくおかしくないはずだが、そのような例は、現実にはかなり少数派のようだ。しかし今までとは違った目で経営全体を見てみよう、というのが経営品質活動を導入する目的だとすれば、自らがその目を持つのが望ましいのは間違いない。アセスメントのための勉強は確かにある程度の時間をかける必要があるだろうが、経営品質協議会が認定するセルフアセッサーの資格を取るまで勉強する必要があるわけではない。
またアセスメントの実施方法にしても、基準書の項目1.1から順番にやり、20のアセスメント項目をきっちりと揃えて結論を出すような大袈裟なやり方でやらなくてもよい。普段の経営会議が即ちアセスメントになるはずだ。全体最適が常に頭にあれば、形式的にアセスメントの体裁をなしていなくても、それは立派な経営品質活動といえるだろう。各項目、少なくとも年に1回くらいは経営会議の議題とすべきだろうが、経営会議メンバー各個人が常に経営品質のフレームワークを意識しているのなら、都度重要と思われる項目だけを議題とすればよい。
そしてアセスメントには、アセスメントプロセスを通じて、アセッサーが自社の問題に対する気づきを得るという効果がある。しかし残念ながらアセスメントチームは通常1チーム6名くらい、最大でも10名では多すぎるというものなので、何千人もいる大企業では1%にも満たない人数である。気づきはアセスメントプロセスに参加することで得られるので、アセッサー以外の人がアセスメントの報告を聞いて同じような気づきを得ることを期待するのには無理がある。1%未満の人が気づきを得ても、通常組織全体への影響はほとんどないといっていいだろう。しかし気づきを得るのが経営トップであれば話は違ってくる。経営トップがアセスメントプロセスを経験し、自社の経営に対する気づきを得れば、その気づきを組織全体に波及していける可能性が十分にある。
6.経営品質は誰が向上させるのか?
ここまでアセスメントについて論じてきたが、しかしアセスメントはいくらやってもただの診断である。アセスメントをしただけでは、会社は何も変わらない。当たり前だが、アセスメントからの提言を各部門などで受けて、日常の業務、仕組み、考え方、対話やコミュニケーションなどを変えていって、初めて経営品質が向上する。さらには、アセスメントで提言されるまでもなく、各部門が基準書を理解して、自部門が何をしなければならないか自発的に判断して、行動するということが重要である。
各部門が自発的に行動するためには、自部門の役割を基準書と照らし合わせて理解している必要がある。各部門の役割、業務分担は、通常職務分掌規定などに定められているが、基準書で記述を求めている内容と職務分掌のつき合わせができていなければならない。
職務分掌は商品企画とか、販売とか、設計とか、経理とか、業務の行為を表現したものが多い。しかし基準書には、例えば「3.2 顧客からの意見や苦情への対応」に、「顧客から意見や苦情等を積極的に述べてもらうための方法はどのようなものですか」と書かれているように、業務の目的が記載されている。苦情対応は営業部の役割、ということは職務分掌ではっきりしていても、それを積極的に述べてもらう必要があるという認識がそもそもあるか、ということが重要である。基準書に書かれている要素が、自社においてはどの部門で対応すべきことなのか、職務分掌を元にして割り当てを明確にしなければならない。
さらには縦のつながりの中で、その方法を設定する責任があるのは営業部長なのか、営業所長なのか、個々の営業マンなのか、ということを明確にし、該当する者が「この方法は自分が責任を持って考えなければならないのだ」と意識することが必要である。
そして活動書のアセスメント項目に対する記述部分が、各部門から経営トップへの業務報告となる。特別なプロジェクトとして活動書を書こうとすると大変なことになるが、日常の業務報告だと思えば当たり前のことである。活動書の中には、部門の業務目標、目標達成に向けた取り組み内容(及びその方法を採用した背景や理由)、目標の達成結果、取り組みの改善に向けた活動などを書く必要があるが、これは各部門から経営トップに対する業務報告に求められるべき内容といえるだろう。一般的には各部門からの業務報告は、財務関連の数字が中心かもしれないが、これは基準書では「8.活動結果」でカバーしている。しかし経営会議で検討すべき内容は財務ばかりでよいわけではない。そのような財務の結果を生んだプロセスを検討する必要があるはずで、そのために基準書のカテゴリー1から7の内容と、カテゴリー8の財務以外の結果も業務報告に含むのが望ましいといえる。もちろん、頻繁に報告すべき内容と、年に1~2回で十分な内容があるだろうから、メリハリをつけるのは問題ない。
7.経営品質活動の進め方の提案
以上の要素をつないでいくと、経営品質活動は全体として次のように進めていくと上手くいくのではないかと考えられる
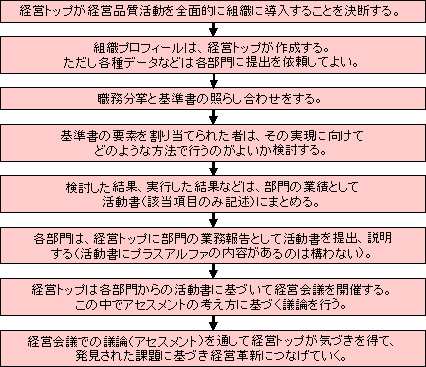
結局は新しい価値観なり、考え方なりを組織に導入する場合は、経営トップが先頭に立って実行し、社員の評価もその価値観や考え方に基づいてされなければ、根付いていかないだろう。

