コラム「研究員のココロ」
自治体病院への民間手法導入による経営改善の再考
2007年07月09日 大谷倫恵
1.はじめに
自治体病院の経営悪化について、最近、特に注目されている。経営母体である自治体そのものの財政状況の悪化に伴い、一般会計からの繰り入れがままならない状況もあり、病院本体の継続が非常に危うい状態にある。
各自治体、各病院ともに財政悪化による病院経営に手をこまねいているわけではない。病院の経営改善のためにさまざまな手法を採用し、再生しようと努力している。だが、現在までに画期的な改善に至った例は少なく、そのどれもが一長一短といった様相を呈している。本稿では、病院へのPFI導入を中心に、自治体病院の民間手法の導入による経営改善の可能性について考えてみたい。
2.自治体病院を取り巻く状況と病院へのPFIの導入
自治体病院は、医療法で、「公的医療機関」として定められており、地域住民へ医療を提供するために地方公共団体が開設した機関である。公的病院という性格から、離島、へき地などの医療を担うこと、また、高度医療や特殊医療などの不採算医療を積極的に実施することが求められている。
自治体病院の設立背景と存在意義はこれまで非常に明確であった。しかし、近年、医療保険財政が厳しさを増したこと、また医療制度改革などが実施されたことにより、病院単体での採算性の確保が非常に厳しい状況であることから、繰り入れによる病院運営の継続に警鐘が鳴らされている。
自治体病院の多くは「公営企業会計」で運営されており、一般会計とは別の会計基準が適用されている。2007年6月16日の朝日新聞によれば、普通会計を見ると赤字市町村は24にとどまるが、病院事業を含めた公営事業会計を連結すると164の市町村が赤字となるという(注1)。
各自治体は病院を維持・運営するために、一般会計などから病院の赤字分を補填し、不採算医療を含めた自治体病院の運営を支え、維持してきた。だが、自治体そのものの経営状態が非常に厳しい状況にあること、また、今年3月に財政再建団体に認定された夕張市などの例もあることなどから、自治体の経営状態の見直しとともに、自治体病院の維持・運営、経営手法、経営形態等についての検討が必要急務となっている。
自治体病院の経営に付随し、これまで、自治体財政の軽減の観点からさまざまな手法の導入が検討、実施されてきている。その1つが、英国で始まったPFI(Private Finance Initiative)の導入である。
PFIは、建設期間と維持管理・運営期間にわたって生じる資金を平準化して支払うことが可能なスキームである。従来型では、病院を新築・改築する際には、単年度会計で処理をしてきた。だが建築費が巨額であり財政の単年度支出を圧迫することから、新築・改築が必要な病院であっても、その実施時期、あるいは実施そのものについては、慎重にならざるをえなかった。また、老朽化が非常に進んでおり改築等が必要な病院であっても、単年度の膨大な費用の支出が不可能という理由で、改修等を実施できない病院も少なくなかった。
PFIの導入では、建築費を維持管理・運営事業を実施している期間に平準化して支払うことが可能となった。これまでなかなか病院の改築等に踏み切れなかった自治体も含めて、多くの自治体でPFIの導入が採用されている。PFIは、必要経費の事業期間の平準化というメリットだけではなく、性能発注を採用している。従来型で細かく決められていた仕様と同等レベルあるいはそれ以上のレベルを達成しつつ、従来型と同等の価格かそれ以下の価格での実施が可能となっている。
病院PFIから見た導入のメリットは建築コストの削減と医療周辺業務までを含めた一括発注による事業の実施といえる。
利用者側から見ると、老朽化の進んだ病院、なんとなく薄暗い雰囲気のする病院よりは、きれいな病院の方が気分の落ち込み具合も少ない。病気を抱える人にとって雰囲気は一つの重要な要素である。自治体にとって財政の負担軽減が図られ、かつ毎年度の支出が一定であるPFI導入によるメリット、利用者である患者への病院施設サービスの観点からもPFIの採用による施設の新築・改修は利点がある。
PFI導入のもう一つのメリットは、周辺業務の民間事業者への一括発注の観点である。医療を取り巻く業務には患者給食、検体検査、滅菌消毒、リネンサプライなどの「政令8業務」と呼ばれる業務がある。診療を支えるこれら業務は担える業者が法律で決められているものの、基準を満たしていれば民間事業者への発注が可能となる。このため、これまで個別に発注業務を行なっていた事務作業などの一括発注によりスケールメリットなどが見込める。
2007年6月時点で、病院へのPFI採用は11件、事業者が決定したものが6件(うちすでに開院されているものが3件)、現在、PFIの事業者選定に向けて実施されているものが5件となっている。すでに事業者が決定された6ケースのいずれにおいてもVFM(Value for Money)(注2)が出ており、従来型を採用するよりもPFIを導入することで財政負担の軽減となることが明確になっている。
【図表 PFIが導入された自治体病院とVFM】(2007年6月現在)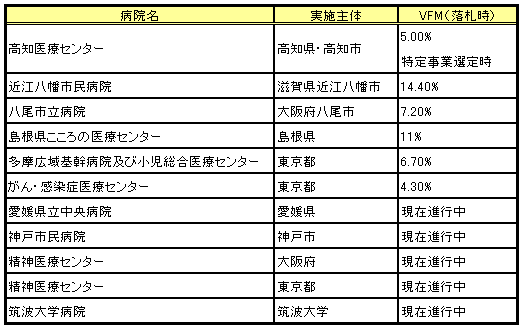
3.病院事業の経営改善の視点
病院の経営改善を考える上で重要な視点は、病院事業の根幹である医業収支部分の把握である。民間手法を取り入れた病院の経営改善手法にはPFIのほか、指定管理者制度、地方独立行政法人への移行が挙げられる。建設を含めた病院を取り巻く業務を見ると、各手法で担える部分は次の図の通りとなる。
【図表 病院への各民間手法導入における事業可能範囲】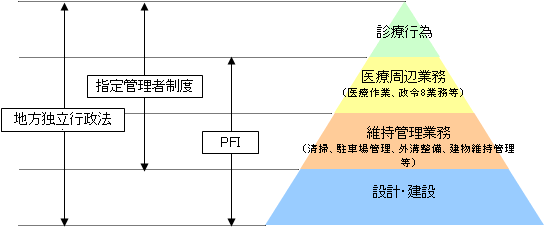
PFIは、医療法上、医業を支える部分までしか改善に寄与することができない。医業収益部分の根幹である診療行為の実施が不可能なため、周辺部分の改善はPFIの導入により可能であるが、根本的な経営改善は行政の病院経営の自助努力に任されることになる。
病院の経営改善を考えた場合、医業収益部分の改善を考える必要がある。現在、存続自体が危機的状況にある多くの病院では、医業収支部分の改善が必要な段階にある。
病院の診療行為を担える手法としては、指定管理者制度と独立行政法人化がある。指定管理者制度の場合、管理委託制度となるため、建設部分の実施を民間事業者へ一括発注することができない。横浜市をはじめとしてすでに多くの病院で実施されているが、病院の建物本体をそのまま指定管理者が利用するか、あるいは自治体が先行して病院建物を改築・新築した上で病院の運営を行なうという手法を採用することになる。
民間手法を導入したもう一つの手法として地方独立行政法人化をあげることができる。この手法では、建設から診療行為まですべてを一括で実施することが可能となる。現在、大阪府で5病院を地方独立行政法人化し、うち精神医療センターにPFIが導入され、現在、事業者選定にむけて進められている段階である。
4.病院の経営を考えた民間手法の導入検討のすすめ
自治体病院として存続するためには、まず、現在抱える問題の解決が必要となる。そのためには、現在の経営状態を分析し、今後の病院存続の意義と経営方針を明確にする必要がある。
民間手法のいずれのケースを採用しても医業部分の改善に着手する必要がある。そのためには、現在の病院における医業の構造、病院を取り巻く環境、病院そのものの運営にかかわる状況を把握し、不採算となっている部分の扱いを検討し改善していくことが求められている。
2007年6月初旬現在、地方独立行政法人の採用を決定・移行した病院は7病院となっている。
【図表 地方独立行政法人化が決定された自治体病院】(2007年6月現在)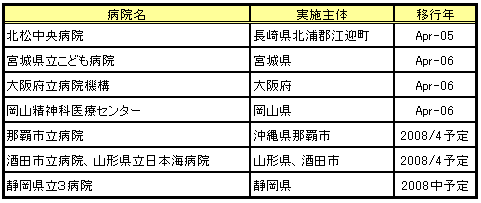
地方独立行政法人への移行のメリットは、病院の経営内容にまで踏み込んだ改善が可能となることにある。病院の周辺環境、医業環境などを踏まえ、中期計画を策定、また病院の理念を確立し、人事制度から病院の運営方針にいたるまで、病院を「経営」していくことが可能となる手法である。
現在、地方独立行政法人化への移行を踏まえた経営改善を検討している病院が多い。また、そのうちのいくつかの病院では、病院施設の老朽化も進んでおり、PFIの導入を踏まえた検討も視野に入れていると聞く。
地方独立行政法人への移行、PFIを採用など、病院の経営改善のために、さまざまな手法を講じて検討する中で、民間手法を導入したから病院経営が改善されるわけではないことに留意が必要である。医業を担う根幹部分において、どのような医療を提供していくのか、病院の理念、人材教育など、多方面にわたる検討が必要である。民間手法を採用したことで多くの問題が解決できるわけではない。病院経営の中枢である医業の部分に民間手法を反映させて病院運営をしていくかが肝要であり、経営改善につながると考える。

