「ちきゅうおんだんか」、「チキューオンダンカ」、「地球温暖化」・・・。2007年12月にインドネシア・バリ島にて開催された地球温暖化防止のための国際会議COP13(注1)に関連してニュース等にて「地球温暖化」という単語を耳にされた方は多いと思う。
主に化石燃料を燃焼させる事により発生する二酸化炭素等の温室効果ガスは熱を吸収する性質がある。地球温暖化とは、このガスが人為的活動により増えすぎたために、太陽からの熱のインプットと地球外への放熱のアウトプットのバランスが崩れ、地球が暖かくなっていく現象を指している。
2007年8月20日に岐阜県多治見市と埼玉県熊谷市で最高気温が40.9度に達し、74年ぶりに観測史上最高気温を更新するなど、身の回りでは地球温暖化の影響と思われる現象が起き始めており、自分たちの生活にも影響を及ぼすと「何となく」想像できる方は増えてきていると思われる。しかし、地球温暖化が自分たちの生活に対して、どのような具体的な影響を及ぼすか説明している文章が少ないため、地球温暖化を実感できない方も多いのかもしれない。
今回は年始めのコラムとして、少し柔らかめに「地球温暖化」が私達の生活にどのような影響を及ぼすのか、「地球温暖化を生き抜く賢い消費者に必要な10のこと」と題して、これだけは知っておきたいというハウツー形式で解説する。なお、コラムの目的上、断定的な表現にて説明をしているが、これらは全て個人的な見解であり、例示している行動を私および(株)日本総合研究所が積極的に推奨しているのではない事とこれらの説明を参考にされた結果、発生した損害について一切補償しないことをご了承頂きたい。
1. 『不都合な真実』を見る
2007年にノーベル平和賞を受賞したアル・ゴア氏の映画『不都合な真実』は単調な映画で若干眠くなるが、真面目に見ればその内容は十分に地球温暖化の現実を教えてくれる内容である。
ただし、映画を見終わった数分~数時間は「自分も何かをしなければ」という意識になるのだが、残念ながら、その後違うTV番組を見たり、一晩寝て起きると『不都合な真実』の内容をきれいさっぱり忘れているという別の『不都合な真実』が存在している。
したがって、地球温暖化に対する意識を高めるためには、『不都合な真実』のDVDを購入し、月に一回は家族揃って映画を真面目に鑑賞し、「自分も何かをしなければ」という意識を保ち続ける事が重要である。書籍の不都合な真実も良い本ではあるが、映像により表現することでアル・ゴア氏が伝えたいメッセージが、わかりやすく・しっかりと伝わってくることから、個人的にはDVDをお薦めする。
なお、書籍で地球温暖化を勉強したい方には、日本総研が総力を結集して執筆した「地球温暖化で伸びるビジネス(東洋経済新報社)」をお読み頂ければ幸いである(私は第10章・地球温暖化と「エネルギー」セクターを担当)。
2. 高台に住む/家を買う
地球温暖化による影響を早期に確認できる現象の一つが、海面上昇である。地域によってその影響は大きく異なるが、日本でも満潮時に屋形船が橋の下を通れなかったり、水辺の遊歩道が水没する現象が起きている。
インターネットには、海水面が上昇した際にどの地域が水没するかを調べる事が出来るサイトがあり(http://flood.firetree.net/?ll=33.8339,129.7265&z=12&m=7)、例えば海水面が7m上昇すると江東区、足立区、葛飾区、江戸川区の大半は水没してしまう事になる。7mという海水面の上昇はすぐには起きない(グリーンランドの氷がすべて融けると7m程度上昇する)、海水面の上昇に加えて満潮と台風が重なる事で洪水の被害が拡大する事も想定される。3番において台風が強力になる事を述べているが、複合的な要因により今後は沿岸地域では高潮や洪水のリスクが高まる事になる。
地球温暖化により洪水被害に遭わないためには7mの海面上昇にも耐える様な高台に住むべきであり、特に自宅を購入する場合はその立地には十分に配慮すべきである。
3. 損害保険に「しっかりと」加入する
現状では、地球温暖化により海面が上昇している主な理由は、海水が温まる事による水の膨張であり、その他の南極の氷や氷河が融ける事はこれに次ぐ理由となっている(南極や氷河の氷が全て融けると海水面は70m上昇するため、長期的にはこちらの方が問題は大きい)。このように海水の温度は地球温暖化により上昇しており、このことは強力な台風が生まれやすくなる事を意味している。
台風は太平洋上の暖かい海水で生まれ、日本に向かって北上してくる。この時、海水温が暖かくなると海水の蒸発量が増加して、台風がため込むエネルギーが増大する事と台風が生まれる様な暖かい海水の範囲が広がり、より日本に近い位置で台風が生まれる事で台風の被害が大きくなると考えられる。
この暖かい海水により台風がエネルギーをため込んでいく事象は2005年にアメリカ・ニューオリンズを襲ったハリケーン・カトリーナが代表例として有名である(『不都合な真実』においても撮影中に起きた事件として大きく取り上げられている)。
したがって、家屋や家財が台風の被害に遭う可能性も高まる事から、損害保険等の被害を補償するための対策をしっかりと講じておく事が重要である。損害保険を選ぶ際には補償内容にも注意が必要である。長期的な傾向として自然災害による保険金の支払額は増加傾向にあり、損害保険会社の経営圧迫要因となっている。そのため、同じような損害保険でも補償の内容が微妙に異なるケースも増えてくると思われ、自分の資産と補償の内容を照らし合わせて十分な内容であるか確認すべきである。
図表 ハリケーン・カトリーナ(フロリダ半島の幅と同程度の渦を形成)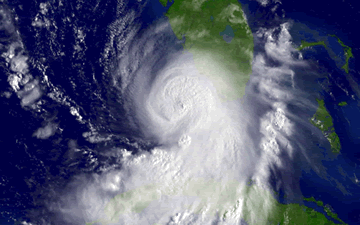
出典:U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration・
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
4. 再生可能エネルギーを使う
不都合な真実を見て、「自分も温室効果ガスを減らしたい!」と思った志の高い方には、待機電源を削減して、数グラム単位で二酸化炭素を削減する事も良いのだが、発電時に二酸化炭素を排出しない太陽光発電の様な再生可能エネルギーを使えば、家庭からの二酸化炭素の排出量を大幅に下げつつ、エネルギーを自由に使えることから、こちらの方がお勧めである。
例えばJCCCA(Japan Center for Climate Change Action:全国地球温暖化防止活動推進センター)のウェブサイトによると、日本における一世帯からの二酸化炭素排出量は5.5トン/年であり、そのうち電気は38.7%(2.1トン/年)を占めている。この電気からの排出量は太陽光発電を設置するなどして、再生可能エネルギーを利用する事でゼロにできる。更に自動車に乗らない家庭であれば、ガソリン・軽油分も排出していない事から、トータルでは1.8トン/年程度の排出量まで減らす事もできる。
マンションの様に自分では太陽光発電を設置できない家庭では、電力会社へ再生可能エネルギーを使える様にして欲しいと要望をし続ければ、欧米の様に一般家庭でも再生可能エネルギーを買える時代が来るかもしれないので、諦めずに電力会社を説得して頂きたい。
図表:家庭からの二酸化炭素排出量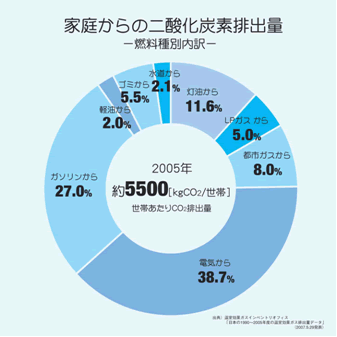
出典:温室効果ガスインベントリオフィス・JCCCAウェブサイト
5. 寒い地域に住む/家を買う
地球温暖化に伴って感染症・害虫の生息範囲は拡大してきている。関西を中心に多くの個体が見つかっている猛毒を持つセアカゴケグモや次第に生息地域を北上させているヒロヘリアオイラガは南方から侵入し、日本に定着しつつある害虫の代表例である。
一方、感染症では、多くの感染症を媒介するカの生息域拡大と気温の上昇によるウィルスの活性化という2つの側面がある。例えば日本脳炎は、現在では九州から東北までがウィルスの活動範囲とされている。しかし、地球温暖化によりカの生息域範囲が拡大し、ウィルス自体の活動が活発になる事で、感染者数の増加が懸念されている。
このように南方から侵入してきた感染症・害虫については、暖かくなる事で増加・定着あるいは感染者数の増加が懸念されている事から、より気温の低い地域に住む事でその被害を回避できる可能性が大きくなると考えられる。寒い地域の代表である北海道は、80年後には平均気温が4℃程度上昇するとのシミュレーションもあり、長期的には住みやすい地域になっていくかもしれない。
<図表:地球温暖化により増加・定着が懸念される害虫の例>
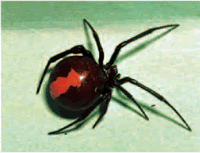 | 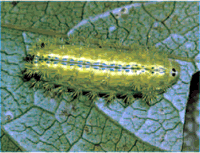 |
| セアカゴケグモ オーストラリア原産と考えられているクモで、コブラ毒に匹敵する毒をもっている。1995 年に高石市や四日市市で発見されたが、現在は大阪府や三重県以外に兵庫県、愛知県、京都府などでも発見されており、物資の移動に伴って分布が拡大した可能性が指摘されている。2005 年には群馬県でも数匹が発見され、駆除されたが、これは大阪府からの引越し荷物に紛れて運ばれたものと考えられている。低温に弱いといわれているが、温暖化で冬期の気温が上昇すると、より北方でも定着する可能性がある。 | ヒロヘリアオイラガ 幼虫の毒棘(どくきょく)に触れると激しい痛みを覚える。東南アジアや中国南部原産といわれ、1900 年代前半は鹿児島県などごく一部の地域で発生していただけだったが、次第に分布域が北上し、1970 ~1980 年代には近畿以南の各地、2000年代にかけては関東地方でも局地的に大発生するようになった。 |
出典:環境省 地球温暖化の感染症に係る影響に関する懇談会パンフレット
(写真提供:財団法人 日本環境衛生センター東日本支局環境生物部次長 武藤敦彦氏)
前編では生活や住居に関連した話題に言及した。引き続き「地球温暖化を生き抜く賢い消費者に必要な10のこと(後編)」では、仕事や投資などより範囲の広い分野に言及する。

