コラム「研究員のココロ」
医師が満足感と納得性を感じる年俸制度とは<後編>
2007年07月02日 加子栄一
Ⅱ.年俸制度・評価制度の設計
【1】年俸制度の設計
(1)年俸制の類型
年俸制には、4つの基本型と2つの変型があることを共通認識として確認した。
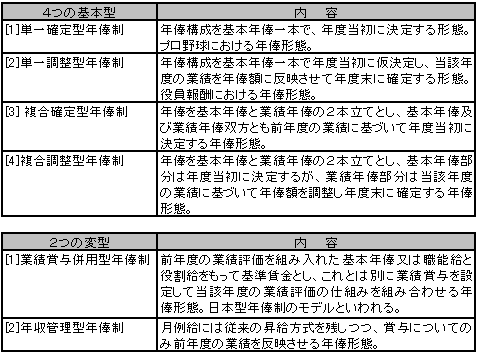
年俸制の各種類型を検討し、「4つの基本型」のうち[2](単一調整型年俸制)と[4](複合調整型年俸制)を選択し、設計することにした。
(2)年俸制2制度の概要について
【年俸制2制度の概要】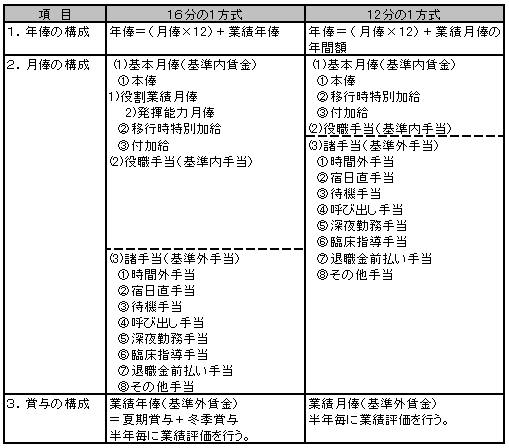
- 副部長以下に時間外手当がつくため、16分の1方式の業績年俸及び12分の1方式の業績月俸は基準外賃金として位置づけ、評価が反映する旨を明確にし、時間外算定基礎額からはずした(この取扱は労基署に確認済み)。
- 現行制度の諸手当は、必要性を吟味し、5つの手当を基本月俸に繰り入れた。
- 基本月俸部分は、賃金表を作成した。賃金は、安定性とメリハリ性の組み合わせが好ましいという意見を採り入れて、16分の1方式では、発揮能力月俸を安定性のある段階号俸表とした。12分の1方式では、本俸を同じく段階号俸表とした。一方、16分の1方式の役割業績給及び12分の1方式の業績月俸はメリハリのある洗い替え方式の賃金表とした。
- 新制度への移行をソフトにランディングさせるために、両方式に移行特別加給を設定した。
- 中途採用者の賃金の整合性を図るために付加給を設定した。
- 12分の1方式の業績月俸については、最終案に至るまで労基署への確認とメンバ-間の熱心な議論を行った。結論としては、業績月俸は業績評価が反映し、原則として6月及び12月に支給する。但し、本人の申し出により毎月の先払いができるものとした。
- 年俸制2制度の選択状況は、16分の1方式が25%、12分の1方式が75%であった。この数値は、筆者にとって予想外であり、変動要因が少ない安心感がある制度を医師は志向していることをうかがわせた。
(3)年俸更改制度の設定
経営陣と医師との処遇・評価に関する直接対話を促進するため年俸更改制度を採り入れた。経営陣と医師が年俸契約書を直接取り交わすもので、第1回目の更改時には、筆者も同席した。経営陣と直接話をして年俸額を決めるのは賃金に重みがついて好ましい、処遇・評価に関する話が経営陣と直接できるのは自分が期待されていることを実感できる、という肯定的な意見とともに、手間と時間がもったいない、本当に言い分を聞いてくれるのか、ガス抜きに過ぎないのでは、という否定的な意見も聞かれた。実際5人の医師が更改時にサインせず経営陣を驚かせた。筆者に善後策を講ずるよう要請があったため、サインしなかった医師と個別に面接を行った。サインを拒んだ理由は必ずしも同じではなかったが、根底に評価制度に関する不信感があった。新制度の導入にあたって、医局会において人事制度の説明会を開催するとともに科別の勉強会も行った。これらの施策も必ずしも功を奏してはおらず、更にキメ細かなフォロ-の必要性を感じさせた。個別面接時に評価制度の更に詳しい内容と1年間の猶予期間を設定した旨、評価者に対する訓練の実施、等を説明した結果、2回目の更改で全員がサインを行った。
【検 証】
制度移行時の更改契約にサインをしない医師が出たのは予想外であった。評価制度の本格実施を1年間遅らせたのは正解であったが、医師の合意形成のためにはよりキメ細かな対応が必要である。
【2】評価制度の設計
(1)評価制度全体像の検討
評価制度のあるべき姿を実現するためには、まず評価制度の全体像をはっきりさせることが肝要である。ポイントは、次の5点である。
- 中期経営計画から医師各人の目標までが連鎖するような仕組みとする。
- 中期経営計画に示されたバランス・スコアカ-ドの内容が医師個人の評価項目に反映するようにする。
- 年度計画→部門計画→部署計画→個人目標という流れが実感できるようなツ-ルを作成し、使用する(ツ-ルは最小限とする)。
- 絶対評価のための基準設定及び評価結果のフィ-ドバックを行うために目標管理の3面接(目標・中間・育成)を採り入れる。
- 評価の気付きを高めるために自己評価というプロセスを採り入れる。
【評価制度の全体図の例示】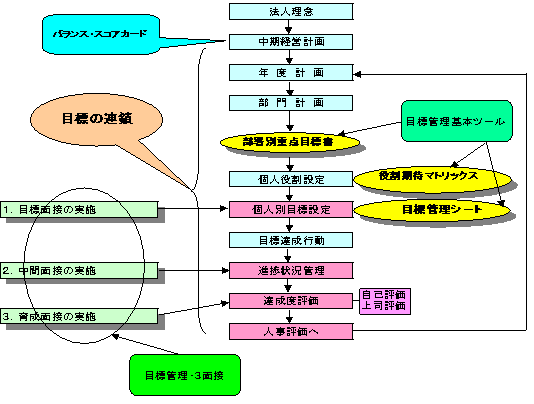
(2)評価要素・内容の具体化
評価要素・内容にバランス・スコアカ-ドの4視点(患者・利用者の視点、学習と成長[人材と変革]の視点、業務プロセスの視点、財務の視点)を採り入れ、かつ階層別に相応しいコンピテンシ-的発想を盛り込むと次に示すような内容となる。
【階層別評価要素・内容の例示】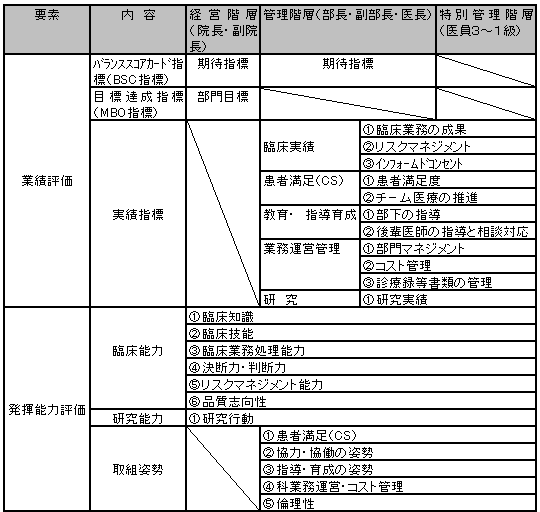
(3)評価基準の明確化
評価基準を明らかにすることも必要である。評価基準は3つあり、その内容を階層別に展開すると次のようになる。
【評価基準の階層別展開の事例】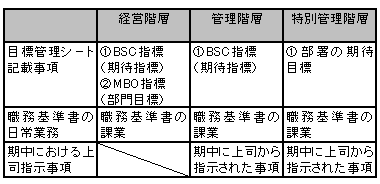
(4)評価者訓練の実施
制度は構築に一汗(ひとあせ)、運用に二汗(ふたあせ)と言われるように運営・定着化に手間をかけないと制度改定のねらいは達成できない。
そのため、評価制度を運用するキ-マンである評価者に対して、事例を使った評価者訓練を行った。事例は、日本総研が用意し、人事評価マニュアルの説明→事例による個人演習→グル-プ討議→回答例の確認→質疑応答、という手順で行った。
人事評価マニュアルを説明する時は、人ごとのように聞いている評価者が多かったが、事例演習(個人・グル-プ)では真剣に取り組むようになり、特にグル-プ討議では議論が活発に行われていた。アンケ-トでは、次のような意見があった。
- 被評価者の事実行動を評価項目に結びつけるプロセスが難しかった。
- 5段階(SABCD)のいずれを選ぶか、個人の甘辛が大きく出るのではないか。
- 四六時中被評価者を観察しているわけではないので見落としがあるような気がする。
- 評価などと、高を括っていたが結構論理的で奥が深いと認識した。
- 評価者を十分教育しないといけない。こういった訓練は継続すべきである。
- 評価結果をフィ-ドバックするのは難しい。よほど納得性のあることを言わないとだめだ。面と向かって注意を受けたことがないメンバ-ならなおさらだ。
評価制度を実施することは、病院方針なので受け入れるが運用に自信が持てない、という評価者が大部分である。これは、筆者の経験からすると、予想通りの結果であり、そのために医師以外の職員より1年遅れで実施することにしている。その1年間を、全員の合意形成と評価結果検証にフルに使わなくてはいけない。
Ⅲ.医師を満足させる年俸制度とは
医師にとって賃金が年俸制度であることは当たり前であり、しかも年功的に昇給する制度では満足感と納得性を与えることはできない。ではどうすれば良いか。筆者は、年俸制度をトータルな制度に変えることだと考える。
医師は先述したが、子供の頃からエリ-トであり、受験勉強に勝ち続け、それこそ数え切れない程の賞賛・承認を獲得してきた。この賞賛・承認はいわゆる満足要因であり、勉学に対する動機付けは高いレベルを維持し続けてきた。しかし、医学部に入学し、医師になった途端、賞賛・承認というフィ-ドバックの機会が失われているのではないか。
筆者が考える医師年俸制度とは、年俸制という賃金制度を等級制度を中心にして評価制度及び育成制度と有機的に関連させるトータルな制度である。人事制度は複雑に見えるが、等級基準(等級制度)・処遇(賃金・賞与・退職金)・評価(評価制度)・育成(OJT・OffJT)という4つの柱に集約される。この4つの柱を、等級基準を中心に据えて処遇・評価・育成を相互に関連させ有機的に結びつけない限り制度構築の効果は期待できない。
4つの中でも特に評価制度の構築・運用が鍵であり、医師にふさわしい評価基準(BSC指標とコンピテンシー項目)、評価結果をフィードバックすることによる達成感・承認・責任・成長といった満足要因の醸成、更改契約という経営陣との直接対話による特別な存在であるという自覚の醸成、等で医師の承認欲求は満たされ更に立派な医師になるという自己実現欲求に繋がっていくのではないかと考える。
【年俸制度をトータルな制度にした場合のイメージ図】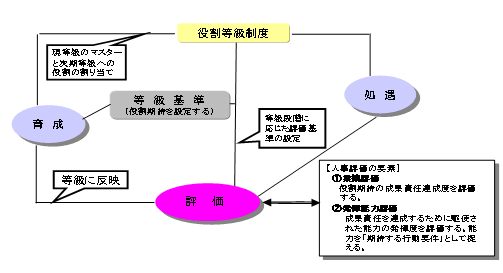
以 上

