コラム「研究員のココロ」
規模拡大した「ニッポンのプロ農家」が「生きる道」
~規模拡大とビジネスモデル~
2007年07月02日 大澤信一
FTAやWTO交渉の進展とともに、日本農業の構造改革、とりわけその国際競争力強化が我が国全体の国益という見地から注目されている。我が国はどのような、農業構造改革案を採択すべきなのか。ここではこの問題を取り上げてみたい。
結論を先に述べれば、日本の農業改革には、「規模拡大による経営効率化」と「新しいビジネスモデルの構築」という改革に向けた、車の両輪が必要である。しかし現在の農業政策は規模拡大という点については、大きく改革の舵が切られたと言ってよいが、新しいビジネスモデル構築という点では、いまだ明確な政策提案がなされていない。新しいビジネスモデルの提案こそ、現在の農政改革の喫緊の課題ということが出来よう。
1)品目横断的経営所得安定対策という規模拡大政策
本コラムの読者には馴染みがないかもしれないが、日本農業は本2007年4月より農業経営の規模拡大に向けて大きな政策転換を進めている。「品目横断的経営所得安定対策」の本格導入が其れである。この政策は、米麦といういわゆる土地利用型農業について、その農業支援の主要部分を、本州以南では4ha以上、北海道では10ha以上の大型農家に集中的に直接支払いするという政策である。これにより、現在、大小規模が混在する約300万戸の農家を2010年を目処に約40万の大規模農業経営体に絞り込むことを意図している(図表1)。
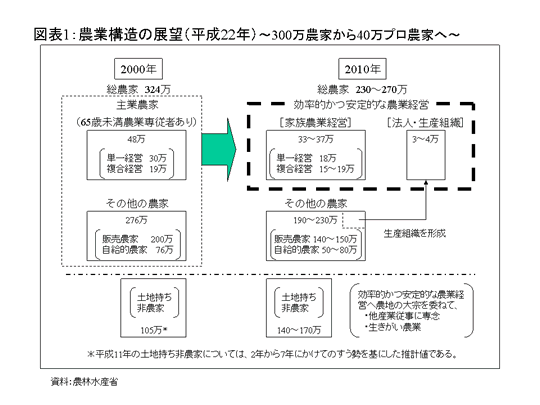
従来の日本農業が、零細な分散圃場をあちこちに抱え、農業機械を移動させながら効率の悪い農作業を続けてきたことを考えれば、少なくとも一定面積以上のまとまった農地を一気に機械耕作することでより効率的な農業経営が可能になる。規模拡大という点からは大きな方向転換、前進であるといってよい。
2)拡大した「日本の」大規模農家が生きる道
さて、問題はこの規模拡大した大規模農業経営体がどのような農業経営で食べて行くか?という点である。図表2には、今後我が国が、FTA交渉などで丁々発止と遣り合っていくことが予想される関係諸国の平均的な経営規模が示してある。これによれば、農家一戸あたりの平均農地面積では、わが国が1.8ha(北海道17.5ha)であるのに対し、米国178.9ha(日本の99倍)、EU平均が15.8ha(同9倍)、わが国とのFTA交渉が開始された豪州に至っては3,240.9ha(同1801倍)である(農林省、2001年~2005年の各国値比較)。またこの図表には記載がないが、中国など発展途上国では、我が国に比較して格段に安価な労働力という強力な競争優位性がある。規模拡大による経営合理化、効率化による農業再生政策には、北海道を除けば大きな限界があるといってよい。本州以南で4ha以上、北海道で10ha以上の大型農家という、「日本の」大規模農家がどのような農業のビジネスモデルで生きてゆくか、この点の提案がなければ農業構造改革は「絵に描いた餅」ということになる。
図表2 各国農業の平均経営面積比較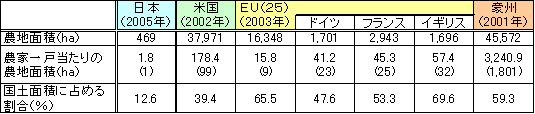
(資料)農林水産省「耕地及び作付け面積統計」「2005年農林業センサス」
米国 USDA “UNITED STATES-2002 Census of Agriculture”
EU “Agriculture in the European Union Statistical and Economic Information 2004” 豪州 “AUSTRALIA 2001 Agricultural Census”
- (注1)
- 括弧内は日本に対する倍率である。
- (注2)
- 日本の農地面積には、採草・放牧地等を含まない。
- (注3)
- 日本の農家は「販売農家」である。
- (注4)
- 日本の「国土面積に占める割合」は、北方領土を除いた国土面積に対する割合である。
3)農業でも「ジャパニーズ・ウエイ」(日本の行き方)の確立を
結局、現在の農業改革の延長線上に想定されている、「日本の」大規模プロ農家は、国際的に見れば、自分よりはるかに大きな先進諸国の超大規模農業経営や、とんでもなく安価な労働力を使える発展途上国農業と厳しい競争を繰り広げなければならない。日本農業には、他の先進諸国や発展途上国農業にはない独自の強い競争力を備えることが期待されているといってよい。
言い換えれば、農業でも「ジャパニーズ・ウエイ」(日本の行き方)の確立が不可欠ということになる。20世紀の後半に、製造業の分野でトヨタやホンダやソニーなどが見せてくれたような、借り物でない、ニッポンの独自の行き方が求められているということになるのだ。
このような見方から、現在の日本農業を見回すと、そこには一筋の光明がさしていることに気がつく。それは繁盛直売所である。ここでは携帯電話によるPOSシステムや、縦横に整備された高速道路網など、現在の日本社会を象徴する社会環境を巧みに利用して、周囲の大型量販店に並ぶ安価な輸入農産物に伍して大健闘している。そこでの人気商品は、農産物だけでなく、地域の食文化を色濃く反映した漬物や惣菜、弁当であったり、あるいは併設の地元食材を使ったレストランのメニューであったりする。その非価格競争力は強力である。
この繁盛直売所の「繁盛の秘訣」、「エッセンス」をより大規模に、専業農家も仲間に入れて発展させることこそ「日本の」大規模プロ農家の「生きる道」ではないか。これが筆者の提案である。ご関心をもたれた読者は拙著「セミプロ農業が日本を救う」(東洋経済新報社)をご参考いただきたい。

