コラム「研究員のココロ」
企業合併における人事制度構築
2007年06月11日 角 直紀
最近、企業合併や買収に伴う人事制度構築を依頼されることが多くなりました。企業の合併・買収という場は、好むと好まざるにかかわらず、一企業の組織としての特性やそこに働く社員のスタンスといった、普段、組織の大前提とされ、中々見ることのできない本質的なところを見せてくれる機会でもあります。そういった中で、企業合併において、どのように人事制度等の統合に臨むべきか、コンサルタントとして、考えるところを書いてみたいと思います。
1.よくある制度統合作業
合併においては、両社の各層が様々な統合委員会と作業部会を作り、作業に入ることになります。よく見受けられるのが、制度統合のみを目的として、両社事務局がバタバタと作業を行いながら、とりあえず足して二で割ったり、政治力で片寄せしようとせめぎあったりと、いうようなケースです。
本来は、人事制度は重要なので、しっかり検討すべきであることは、関係者にも当然、分かっています。しかし、いったん作業が始まってしまうと、人事担当者は、統合に伴う膨大な事務作業に忙殺されるのが通常であり、スケジュールが進んでいく中で、新会社の人事制度をどうするかという意思決定も旅費交通費の取り扱いをどうするかと同じようなプロセスの中で議論されてしまうことになりがちです。
2.未来志向の合併へ
合併・買収後においては、新会社の経営の方向性を見据えて、どのようなメッセージを社員に対して発して行くかは重要です。
社員は、合併に伴う不安が先に立つと、過去志向になりがちです。そこで、会社側も、社員に不安を感じさせないようにということを主眼において、徒に現状維持や現状保証を前面に押し出してしまうようなケースもよく見受けられることです。
しかし、そもそも合併は生き残る為であったはずです。どちらが勝つとか負けるとかではなく、今までの処遇がどうであったからとかではなく、まずは、合併後の新会社の運営や経営の方向性を見据えた未来志向の制度設計が求められます。それが固まってから、はじめてこれまでの処遇レベルをどうするかという問題になるはずです。
更に、経営の立場からは、旧会社が抱えていた、これまでの問題を見直す絶好の機会と捉えるべきことができます。旧会社同士のつばぜりあいの中で見せかけを良くしようと問題を隠したりするのは論外ですし、合併をスムーズに進めることばかり考えて、本質的な問題を先送りするのも、結果として合併の効果を下げてしまいかねません。
3.求められる強力なリーダーシップ
合併統合に当たっては、そもそも会社とは何なのか?ある組織で当然であるとされていることは他の組織でも当然なのか?などと、これまでの働いてきた基盤が問い直されることになります。このことから、社員はこれまでのやり方が否定されるのではないかと、漠然とした不安を抱えます。組織としてのアイデンティティとそこに働く個人としてのアイデンティティが揺さぶりを掛けられるのです。
合併をリードする立場にある者は、そういった社員の心情に配慮しつつ、あるべき方向を示し、導いていくというコミュニケーションを取っていくことが求められます。すなわち、大きな変革の絵を描いて、社員を導いていくという強力なリーダーシップが求められるのです。
「気持ちは対等」などという言葉も良く聞かれますが、合併においてはリーダーシップが不明確になる場合があります。こういった話は、分科会レベルの話から、役員レベルの話まであります。足の引っ張り合いになっては良い結果は生まれません。そういった場合には、両社にリーダーを立てながら進めていくといった配役上の配慮も必要になります。
具体的に制度等を詰めていく過程でも、微妙に(あるいはあからさまに)身内ひいきの言動が出てくることもあります。作業部会レベルではあるべき論をしっかり議論してきたのに、トップに近い層になって、政治的な動きに巻き込まれてしまうという展開もあります。
そういった恐れがある場合には、意思決定プロセスのシナリオをしっかり描いておく必要があります。例えば、将来にコミットしている新リーダーの決断や、我々のような第三者の客観的な判断をプロセスの中に取り入れていきながら、職制の流れで話がずれていかないように組み立てを考えていく必要があります。
4.組織文化まで掘り下げた方向付け
合併に当たっては、様々な調整事項があり、担当者はそれに忙殺され勝ちです。しかし、人事制度だけは新会社の方向性を決める重要事項ですので、やっつけ仕事で行うべきではありません。半年から1年程度の制度凍結期間を設けるような場合もあります。確かに、中途半端なものを作るよりはその方がベターです。
なお、大規模な合併においては、統合のために取り敢えずの人事制度を作り、その後、あまり間を置かずに新会社としての人事制度を策定するような方法も考えられます。しかし、社員の混乱や雰囲気の問題、掛かる手間を踏まえると、その方法がベストかどうかは検討が必要です。
では、どのような検討を行えば、しっかりとした検討を行ったことになるのでしょうか。
その為には、制度だけでなく、その前提となるポリシーや文化のレベルまで掘り下げて行く必要があると考えます。E・シャイン教授が「企業文化」(白桃書房社)という書物において、次のようなことを述べています。
「ジョイント・ベンチャー(企業合併・・・筆者注)は、成熟した文化同士が出会うことである・・・。会社の哲学やスタイル、・・・組織の内部構造など、「文化的」と考えられる面についてはまずチェックされることがない。だが、・・・文化的ミスマッチは財務、製品、市場のミスマッチと同じくらい危険である。」
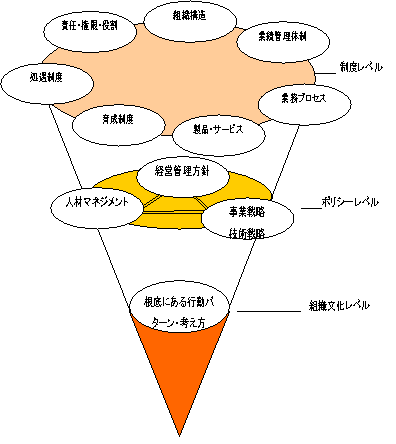
E.H.シャイン「企業文化」のコンセプトに基づきJRIが作成
つまり、企業合併というのは、二つの組織文化がぶつかり合う事態であり、そこでは、それぞれが前提としているモノの捉え方、考え方を改めて捉えなおすことが求められるのです。ここで、成り行きに任せるのか、意図的に方向付けて行くのかは、合併の経緯にもよります。ただ、いずれにせよ、テーマを掘り下げ、社員が(場合によってはマーケットが)どう受け止めるのか、それも踏まえて、どこまで新会社としての「改革」「再生」といった運動を展開するか、その為には、経営としてどういうメッセージを出すべきかまで十分に検討した上で意思決定して、新会社の人事制度のポリシーを固めるべきなのです。
5.合併作業の「ゴール」とは
価値観の違いや新会社としての方向性などを脇に置いたまま、表面的な制度の差異を埋めることだけを目的として策定された新会社の人事制度は、妥協の産物であり、トゲを抜かれたものとなります。内容も、当たり障りないものになっているので、あまり反対する社員もいません。本当にこれで良いのでしょうか。
最終的に問われるのは、合併の当事者として、合併のゴールをどう捉えるかです。「合併作業を滞りなく進めること」と「合併して、その成果を出して行くこと」は違うのです。
人事の担当者にとって、取り敢えずのゴールは、合併後にも社員にしっかりと給与が支払われることです。しかし、経営にとってのゴールは違うところにあります。
後者に関しては、たとえ失敗しても、その結果は急に出るものではないので、現場に近ければ近いほど、目の前の作業に眼が向いてしまうことはやむをえないと思います。しかし、それで良いのかという問題なのです。
人材マネジメントという言葉が様々な場面で語られるようになってきました。人事管理を人事制度の内容だけで語るのではなく、もっとトータルで考えていこうということです。つまり、ツールとしての人事制度を導入し、運用することを通じて、組織の人材をどのように導いていこうとしているのかが人材マネジメントの視点です。
合併を成功させるには、トップから担当者に至るまで、この人材マネジメントの視点を忘れてはならないのです。

