コラム「研究員のココロ」
大学全入時代の業務改革
~コンセンサスをどう取るか~
2007年05月28日 豊田憲和
1.はじめに
近年、大学においては業務改革に取り組むことがもはや当然のこととなってきている。この背景には、少子化時代を向かえ、各大学が生き残りをかけた経営改革にいやがおうでも取り組まなければならなくなったといった事情がある。しかし、思ったとおりにコンセンサスが取れず、業務改革が進まないという大学は多い。その理由としては、自らの大学の状況に適さない手法でコンセンサスを取ろうとしていることが考えられる。
本稿では、各大学の状況により、どのようにコンセンサスを取ることが有効と考えられるかについて、アグリーメント・マトリックス(注1)という観点から考察する。
2.コンセンサスを形成する手法
下記図表は、アグリーメント・マトリックスという考え方であり、組織を、a.目的に関するコンセンサス、即ち変革の目的や意義、優先事項など、変革によって何を得たいのかに関する従業員の合意状況と、b.実現手法に関するコンセンサス、即ち目的を実現するための手法・進め方に関する従業員の合意状況で4つのポジションに分類し、各組織において、変革を実現する際、どのような手法がコンセンサスを得やすいかを示したものである。
図表(アグリーメント・マトリックス)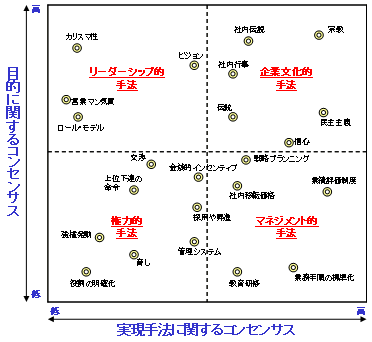
(出所)Diamond Harvard Business Review, March 2007より筆者が作成
目的と実現方法のいずれにおいても合意状況が低い場合、すなわちマトリックス左下の区分に組織が位置する場合、コンセンサスを取るための手法として考えられるのは、「強権発動」や「脅し」といった、強制力の強い権力的手法となる。
実現手法に関する合意状況が高く、目的に関する合意状況が低い場合、すなわちマトリックス右下の区分に組織が位置する場合には、従業員は、達成したい目的はばらばらだが、その実現手法に対しては一定の共通認識を有していることとなる。このため、コンセンサスを取るための手法としては、「業績評価制度」の導入や「教育研修」等の、マネジメント的手法が適している。
左上のマトリックスに区分される場合は、目的については従業員の中で一定の共通認識は見られるものの、その実現手法はばらばらであるといった状況である。この場合は、強力なリーダーの「カリスマ性」や「ビジョン」といった、リーダーシップ的手法によるコンセンサスの取り方が適している。
右上のマトリックスに区分される場合は、目的と実現手法のいずれにおいても合意状況が高いことを意味する。このような組織の場合、変革に際しては、「宗教」や「伝統」、「民主主義」的なアプローチのような、企業文化的手法が適していると考えられる。
なお、マトリックスの区分は、どのポジションに属しているから特に優れているということではなく、あくまでも組織の状況と、その状況に合ったコンセンサス形成手法をプロットしたに過ぎないことに注意が必要である。
3.大学でのコンセンサス形成手法と適用上の留意点
上記のマトリックス区分に従った手法を用いたコンセンサス形成は、大学組織においても有効である。
例えば東京大学は、「東京大学アクション・プラン2005-2008」の下、業務運営の改善及び効率化、人事の適正化、事務等の効率化・合理化に取り組んでおり、一定の成果を上げている。東京大学においては、小宮山学長の存在を前面に出しての改善活動奨励、本部事務局を「部局のパートナー」と位置づけるビジョン的な手法等、リーダーシップ的手法を中心とした業務改革を行っていると考えられる。同大学の場合、日本を代表する国立大学という自負のもと、多くの職員が「まずは本学が率先して改革を行う」という強い目的意識を共有しており、マトリックスの左上の象限にベクトルが向いていると考えられるため、このような手法が適しているものと考えられる。
東京大学に限らず、わが国を代表する大学としての自負とそのブランドの下で、業務改革の取組みを行っている大学などでは、同様の手法の適用は有効と考えられる。
また、例えば東洋大学や甲南大学の場合、システムを導入するにあたり、業務分析の結果により業務を考えるのではなく、システムに業務を合わせるという、まさに「逆転の発想」とも言うべき業務標準化の手法により改革を行っている(注2)。両大学の場合は、早くから業務のシステム化に取り組んできており、実現手法に対する合意状況が一定程度高い状況、即ちマトリックス右下の区分に組織が位置していたため、このようなドラスティックな改革手法が実行できたものと考えられる。
しかし、上記のような大学の例は実はまれであり、多くの大学の現状は、マトリックスの左下の区分に分類される。
まず、目的の視点から考えた場合、学生教育のため、学術研究のため、学生のキャンパスライフや就職のため、教職員のためと、多くの達成すべき目的が混在しているのが大学であり、高い合意状況を形成しづらい環境にある。
また、国公立大学や伝統的な大規模私立大学の場合、部局制による縦割り組織の影響は大きく、部局間で業務遂行方法に対する見解が異なることが少なからず発生している。例えば、全学での効率化を狙って、教職員によるダイレクト入力とペーパレス化による情報化推進計画を進める際に、部局ごとの職員の平均的なITリテラシーのレベル差や組織的規模の違いによる想定導入効果の差から、容易に合意に至らないことがある。このように、部局間の利害得失の違いなどから、実現手法に関する合意状況も低いことが多い。
従って、上記マトリックスに則して考えるのであれば、多くの大学においては、コンセンサス形成の手法として、当面は権力的手法が合致しているということになる。上述した各大学の事例が、多くの大学においてはなかなか適用しづらいのはそのためである。
それでは、権力的手法の中でも、どの手法が有効と考えられるのだろうか。
上記のマトリックスのポジショニングは絶対的なものではなく、組織が存続していく中で、適宜変化していくものである。ある時点では権力的手法の中の「役割の明確化」が最も有効であったとしても、それがいつまでもベストであるとは限らない。したがって、いくつかの手法を合わせて用いることが有効であろう。とはいえ、左下のマトリックスに区分される組織が、区分を大きく超えた手法を用いる場合は、有効性の観点から十分な吟味が必要である。
加えて、権力的手法を取るに際して、いくつか留意すべき点がある。トップダウンによる権力的手法が比較的容易に適用可能な営利企業と異なり、部局によるセルフマネジメントが定着し、現場の発言力が強い、大学組織においては、「強権発動」、「上意下達の命令」、「採用や昇進」、「金銭的インセンティブ」といった手法に実効性を持たせるため、指揮命令系統の強化やトップの権限の明確化など、思い切った制度の改革等が必須となる。具体的には、採用・配置・評価等の権限を集中化して強化する、既存の年功序列的な人事制度にメスを入れる等の対応策が必要であろう。
また、「役割の明確化」では、新たに定義した役割での成果の状況を継続的にウォッチし、役割の内容や範囲の妥当性を定期的に検証することが重要となる。なぜなら、「役割の明確化」をすることは、場合によっては役割外への取組意欲を下げることにつながりかねず、結果として、新たな業務や役割を担うという業務改革本来の狙いが達成できず、その効果を十分に得ることが難しくなる恐れがあるからである。
4.終わりに
本稿では、アグリーメント・マトリックスという切り口で、変革の際、各大学の状況に応じて、どのような手法でコンセンサスを取ることが有効かについて考察した。
結論としては、多くの大学の現状からは、まずは権力的手法を取ることが現実的であると言えよう。ただし、その際、権力的手法に実効性を持たせる上で留意すべき点を考慮した上で、いくつかの手法を合わせて活用することを視野に入れるべきである。
自学の状況を把握した上で、現状取るべき手法は何であり、長期的にはどのような手法を取っていくべきかを考えることが、より効果的な業務改革を実現する上で重要となる。
- (注1)
- Clayton, C. M , Matthew Marx, and Howard, S. H., The Tools of Cooperation and Change: Diamond Harvard Business Review, March 2007(有賀裕子訳「アグリーメント・マトリックス」).
- (注2)
- 日本アイ・ビー・エム株式会社HP お客様導入事例より
- 参考文献
- Clayton, C. M , Matthew Marx, and Howard, S. H., The Tools of Cooperation and Change: Diamond Harvard Business Review, March 2007(有賀裕子訳「アグリーメント・マトリックス」)

