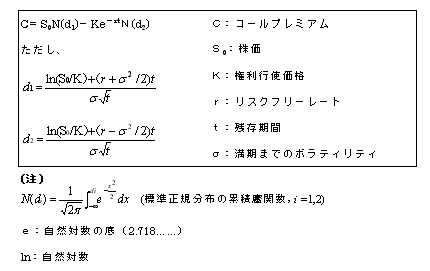コラム「研究員のココロ」
ストック・オプション再考察
2007年04月27日 三枝裕和
1.現状
今回は財務会計上の費用化やM&A対策としての導入など、最近非常に話題になっているストック・オプション(新株予約権)について改めてその意義を再考察してみようと思う。
ストック・オプションの財務会計上における費用化(※1)については、会社法の施行日(平成18年5月1日)以後に付与されるストック・オプション、自社株式オプションおよび交付される自社の株式について適用するとされており、すでに開示が始まっている。
今のところ、アメリカのバックデーティング(※2)のように特に大きな問題があったという話は聞かないが、ストック・オプションの費用化という議論は、費用認識の根拠、どの時点で費用を認識すべきか、負債・資本いずれの部門に計上すべきかといった論点(純資産の部という折衷案によりこの議論はどこかにいってしまったが)についてあまり深く議論がなされておらず、今回の基準は国際的な費用化の流れへの同調といった部分が強い。また、実際に費用として計上すべき権利付与時点での公正価値の算定手法については明言されておらず、例として挙げられているブラック・ショールズ・モデル(※3)についても、株価変動の激しい新興上場企業には費用が高く見積もられる可能性があるなど、利益大幅減のリスクや企業間の比較可能性といった点でも問題を残している。そういった点を考えると、以前よりもストック・オプション制度を利用しづらくなった点は否めない。
なかには費用化によるリスクを嫌い、早々にストック・オプション制度そのものを廃止してしまった企業もあるが、ストック・オプション制度には企業をよりよい方向へ導くためのエッセンスがたくさん詰まっており、経営戦略といった面からも有用な手段である。そこで今回はストック・オプション費用化による影響を踏まえたうえで、もう一度企業がストック・オプション制度を用いる場合の利点について考えてみたい。
2.ストック・オプション会計基準が企業に与える影響
実際にストック・オプション費用化が義務付けられるとどのような問題が生じるのだろうか。基準では明言を避け、合理的な価格を見積もるためのモデルによる算定という表現を使用しており、例としてブラック・ショールズ・モデルや二項モデルが挙げられている。いずれも金融工学の知識を必要とし、これらの評価モデルを会計に組み込むことで、企業・評価機関(監査法人・税務署等)双方に負荷が増えることとなった。この費用算定に関わる事務処理、内部評価といった問題は内部統制の問題にも深く関わっており、費用処理についての適正性検証は今後大きな問題となる可能性もある。
実際、アメリカで既に実務で多く導入されているブラック・ショールズ・モデルでは、
- 権利行使までの予想残存期間の測定
- 今後の株価の変動の予測
といった不確定な要因により、公正価値が大きく変動してしまうため、企業にとっては算定の結果次第では利益が大幅に減少するリスクを抱えることにもなる。特に株価の変動が激しい新興上場企業などでは公正価値を高く見積もられてしまい、利益に与える影響も大きくなってしまう。また権利行使付与時点の違いによっても大きく公正価値が変わる可能性がある。こうした算定手法のあいまいさから、今回の基準は企業に恣意的な操作を行える余地を多く残すこととなり、企業にも評価機関にも難しい課題を残す結果となった。
3.ストック・オプションの戦略的活用
しかし、今回の基準制定や最近の経済の流れを受け、ストック・オプションには新たな戦略的活用手段も生まれている。それらを含めるとストック・オプションの利点は概ね次のようなものになる。
- 役員・従業員へのインセンティブプラン
- 有能な人材の確保・定着
- 後継者への相続税対策
- エージェンシーコストの代替効果
- 金融機関や取引先等への付与による資金調達の促進やM&A防衛策としての適用
- 持株比率低下防止
- 費用の損金参入による税額軽減
- 報酬に代替することで、当面の人件費を抑え、内部留保を増やすことができる。
確かに、今回のストック・オプションの費用化によって、期間利益にマイナスの影響が出ることは避けられないため、企業によってはこれまでのように便利に使えるものではなくなったが、キャッシュの発生を伴わず、報酬を先送りにできるという点や、役員・従業員と株主の企業に対する価値観のベクトルを同じにするという点での利点は少しも失われていない。
むしろ、今後企業が気をつけるべきは、ストック・オプションの乱発を止め、企業を取り巻くステークホルダーに見える形で、ストック・オプションの付与について公開し、財務諸表に与える影響やストック・オプションが会社にもたらす効果について、しっかりと説明をすることであろう。これまで外部の人からは容易にうかがい知ることができなかったストック・オプションの実態について、まがりなりにも開示できるようになったことで、企業としての説明責任も果たしやすくなった。それにより各種ステークホルダーの不満を封じ込め、ストック・オプションを企業戦略に組み込むことができる。
4.まとめ
ストック・オプションはもちろん良い部分のみを企業にもたらすものではなく、
- 株式公開後にコア人材が辞めてしまう。
- 株価が伸びず、ストック・オプションを行使できなかった場合に士気が下がる。
- 乱発による株式の希薄化を嫌い、資金調達が円滑に行えなくなる可能性がある。
- 株価上昇を約束し、株主への説明責任が必要
といったデメリットも確かにあり、そういった点についても、付与時点で十分に配慮する必要がある。また、これらの問題点については、各ステークホルダーへの明確な説明や人材確保のための施策を並行して実施することで解決を図ることができると考えられる。
しかしながら、ストック・オプションは3で挙げたように、正しく使えば、企業に与える価値は計り知れない。今回の基準導入にあたり、企業はストック・オプションの発行を決定する前に、発行するストック・オプションの公正価値を試算し、今後の利益に与える影響をシミュレートする必要がある。今回の基準制定をひとつの契機として、各企業はストック・オプションの公正価値とストック・オプションの付与による企業への経済効果予測を比較した上で、適格なストック・オプションの付与を行えるようこれまで以上に留意する必要があるだろう。
※1:ストック・オプション費用化の仕組み:Aが財務諸表上で計上すべきストック・オプションの費用、企業はこのAの値を付与日の時点で予測して計上しなければならない。
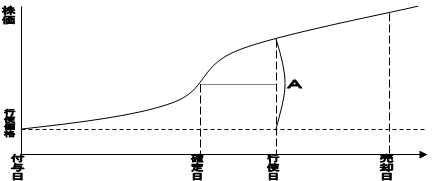
※2:アメリカでは被付与者により利益が出るようにストック・オプションの付与日を、株価の底値にあとで修正していたことが発覚し、そのため、多くの企業が過去の財務諸表を修正させられる事態となっている。
※3:ブラック・ショールズ・モデルとは以下の式により、ストック・オプションの価値を算定するものである。