プロフェッショナルの洞察
イノベーション推進のための手がかり 03 普通の技術者がイノベーションを起こす日本の強み
2006年10月01日 佐久田昌治
 日本企業は1980年代以降、研究開発を促進し、新しい技術をつくり上げて、会社の事業を大きく発展させてきた。まさに企業におけるイノベーションであるが、日本総研ではこうした企業のイノベーションについて151の事例を分析した。
日本企業は1980年代以降、研究開発を促進し、新しい技術をつくり上げて、会社の事業を大きく発展させてきた。まさに企業におけるイノベーションであるが、日本総研ではこうした企業のイノベーションについて151の事例を分析した。この分析で浮かび上がった驚くべき事実は、実際の技術開発、イノベーションを担ったのは、一握りのエリートではなく普通の技術者が多いということだ。逆にエリート大学の卒業生はほとんどいないという事実が分かった。さらに面白いのは、これらのイノベーションは、会社を挙げて取り組んだ研究よりも、第一線の研究からはずれた人が10年、20年、コツコツ取り組んで実を結んだ例の方が多いということだ。技術の進歩とともに、そうした課題に対して情熱と執念をもって取り組んだ技術者、科学者が実を結んでいるのである。
一方、海外においてはそうした例はほとんどない。イギリス、ドイツ、アメリカでも、新しい技術を開発するのはエリートと決まっており、エリートでないとでイノベーションを生み出す研究に携わることも少ない。中国や韓国、台湾も基本的には企業文化の大衆化はない。このため、海外諸国ではいかにエリートをつくるかに一生懸命、国を挙げて取り組んでいるのだ。
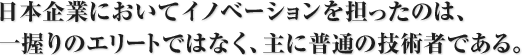
 最近、「あなたの会社は世界でトップといえる技術をもっていますか?」という質問を企業に投げかけた結果、7~8割からYESという回答を得た。しかも、その技術は90年代に生まれたものが多かった。
最近、「あなたの会社は世界でトップといえる技術をもっていますか?」という質問を企業に投げかけた結果、7~8割からYESという回答を得た。しかも、その技術は90年代に生まれたものが多かった。90年代といえば日本経済が停滞していた時期であり、リストラなどが盛んに行われた時代である。しかし、そこでも日本企業は着実にイノベーションを進めてきていたのだ。そして、今、その結果が花開いている。また前述の通り、エリート、非エリートといった区分けをすることなく取り組んできたことも功を奏した。
たとえば花王は20年間増収増益を続けている企業であるが、同社は社員の1/4を研究者が占めている。研究に対して非常にオープンで、事業家を含めて誰もが研究に参画することができ、豊富な実績を築き上げてきた。これだけ多くの階層の人が研究開発をするだけでなく、事業家までもが取り組んでいる例は少ないだろう。
医薬分野ではエーザイがアルツハイマー治療薬「アリセプト」を開発した。これを行った杉本八郎氏は、もともと研究補助員として同社に入社した。こうしたことは欧米の企業では考えられないことだ。
このように、日本独特のイノベーション開発の強みを、いかに伸ばすかが今後の課題であり、欧米やアジア諸国との差別化のポイントとなる。この点を改めて徹底的に研究し、再認識することがこれからの日本の科学技術振興にとって不可欠となる。
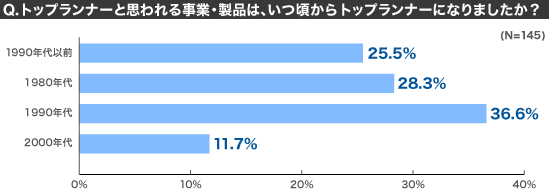
研究産業協会H16レポートから
※わが国の製造業、建設業、サービス業の研究開発担当役員に対するアンケート調査。回答数は184社。
これまで3回に渡って見てきたが、日本におけるイノベーションを推進し、国際的な競争力を強化するための施策を要約すると次のとおりである。第一に、大学院の博士課程での給与支給を検討するなどして、大学院生の数や質を向上させ、基礎研究力を強化すること。第二に、大学の研究と地域産業を結びつけることで地域独自のイノベーションを創出すること。そして第三に、エリートに限らず多様な研究者がイノベーションに取り組むという、日本特有のスタイルを今後も守り、推進していくこと。こうした取り組みをバランスよく進めることが、これからの日本の科学技術振興を支える根幹となるだろう。
関連リンク
- 01 企業の研究開発力に支えられている日本
- プロフェッショナルの洞察 一覧へ
02 イノベーションの歴史
03 普通の技術者がイノベーションを起こす日本の強み

