コラム「研究員のココロ」
環境価値創成と知的財産権<第2回>
2007年04月16日 吉田 賢一
◆環境と法との関係
それでは環境の価値化は、どのように社会的に捉えられてきているのだろうか。ここでは社会の規範である法律の観点から見てみよう。
1993年に地球環境を視野に入れた環境基本法が制定されて以来、新たな環境法の制定や既存法の一部改正などによる規制強化など法整備は着々と進んでいる。基本法をベースに個別法が連なる形で体系が整えられつつあり、その下に環境管理法が位置づけられる。環境管理法とは規制や行政計画のフレームを中心に、環境の保全を目的とした総合的法体系を意味する。そこに従来から存在してきた環境規制法や、「循環型社会形成基本法」に連なる容器包装や建設廃材、食品、自動車などを対象とする各種個別リサイクル法、エネルギーや温暖化に関わる「地球温暖化対策推進法」「新エネ促進法(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法)」「改正省エネルギー法」、そして有害物質の管理を主とした「ダイオキシン類対策特別措置法」「PRTR法(環境汚染物排出・移動登録制度)」などや、自然環境保全に関する「改正水質汚濁防止法」「環境アセスメント法」などが位置づけられる。こうした環境関連の法制度の整備によって、いわば公害対策を中心に構築されてきた環境分野がテーマごとにカテゴライズされ、体系的な環境政策の枠組みによって、むしろ新しい環境ビジネスを生み出す苗床ともなっている。産業構造審議会・環境部会・産業と環境小委員会・地域循環ビジネス専門委員会の中間報告「循環ビジネス戦略=循環型社会を築くビジネス支援のあり方=」(2004年2月)によれば、「我が国においては、世界有数のリサイクル法制が整備されている。これらのリサイクル法制は製造事業者、利用事業者、販売事業者、消費者、地方自治体等の役割分担や費用負担のルールを定め、具体的な再商品化の実施を目指している。これらはある意味で循環ビジネスが主体的な創出を目的としたものと言え」るとされている。同時に、「環境管理法」には、これまでになかった「環境教育法」と「環境情報開示法」を位置づけることで、法体系には属さないISO14000シリーズや環境報告書、環境会計のシステムといった「民間環境管理法」との連関性が高まり、改めてトータルとしての「環境法体系」が整えられることとなったのである。そのうち、「環境教育法」が「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」であり、「環境情報開示法」が「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」(環境配慮促進法)である。
なお、最新の判例を集める「別冊ジュリスト判例百選」(有斐閣)では、「大気汚染、水質汚濁、騒音・振動(工場騒音、建設・工事騒、道路・鉄道・航空機騒音、放送騒音、一般騒音)、悪臭、地盤沈下、廃棄物・廃棄物処理施設、日照・通風妨害、風害・光害、眺望・景観、自然保護、埋立・海岸保全、文化財・アメニティ、原子力、その他環境破壊、訴訟救助・カルテ提出命令、公害紛争処理法、刑事事件」が取り扱われており、従来の「多量・集中・短期・単独・確実」な公害問題への事後対応・救済」が主たるコンテンツとなっている。
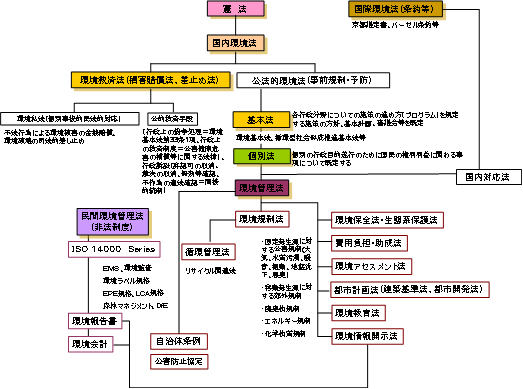
出典:小沢鋭仁・吉田賢一・江間泰穂「環境ファイナンス」(2005年), p.51.
◆経済法務の隆盛~知的財産をめぐる動き
ここで閑話休題。環境から離れて、企業活動や大学経営を概観すると、昨今では「知財戦略」といった言葉が氾濫していることに気づく。また、青色発光ダイオードをめぐる企業と発明者との係争など特許権の帰属やロイヤリティ収入のあり方をめぐっての争点には事欠かない状況にある。知的財産を取り巻く環境は絶えず変化しており、政府が展開する知的財産戦略のスピードもさらに勢いを増している。
2002年の2月に小泉総理が施政方針演説において知的財産の重要性に言及して以来、「知的財産基本法」の成立、知的財産戦略本部の設置、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」の策定、同推進計画の改訂版である「知的財産推進計画2004」の策定、2006年6月8日には3度目の改訂となる「知的財産推進計画2006」の策定がなされるなど、政府一丸となって、ダイナミックな施策が展開されている。(特許行政年次報告書2005年版、p.16)2002年7月3日には、知的財産戦略会議において「知的財産戦略大綱」が発表された。これに基づき「知的財産基本法」が2002年11月27日に成立し、知的財産権を有効に活用し、豊かな文化の創造・国際競争力の強化を通じた、活力ある経済社会の実現を目指すこととなっている。さらに、「知的財産戦略本部」では、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」を策定し、2005年度までに集中的・計画的に施策を遂行しているといった状況にある。同時に、バブル崩壊後、経済の低迷が続く中で、我が国においても、知的財産権を国家的な規模で創造、保護、活用して日本経済の再生を目指すことが必要であるとの認識が醸成されてきている。そこで、1990年代後半から知的財産権について注目が集まり、知的財産権の保護を重視する観点から、裁判所に対しても様々な指摘なされ2005年4月には特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所が設置されている。
次回、第3回に続く

