コラム「研究員のココロ」
企業のコア・コンピタンスとしての「経営戦略力」を鍛える<第1回>
2007年04月16日 谷口知史
1.はじめに
■本稿の趣旨について
筆者は、昨年本欄において、企業のコア・コンピタンスとしての「経営戦略力」というコンセプトを提示し、以下の論点の整理を企図した(「企業のコア・コンピタンスとしての『経営戦略力』を考える」9月4日・9月11日・9月15日掲載)。
- 何故「経営戦略力」が重要なのか(Why)
- 「経営戦略力」の向上によって何を目指すのか(What)
- 「経営戦略力」の向上のためにはどうするべきか(How)
その後、弊社(クラスター)主催トップマネジメントセミナー、クライアントとの共同勉強会およびコンサルティングの現場等を通じて、多くの方々と「経営戦略力」というコンセプトについて議論を重ねる機会を得た。その結果、企業のトップマネジメントの方々を中心として、広く「経営戦略力」というコンセプトに対するご賛同・ご理解を頂くと同時に、上記の各論点に関するご質問・ご意見等を数多く頂いた。
本稿は、そうしたご質問・ご意見等に対する筆者(およびクラスター・メンバー)の見解を中心に、前回稿の続編としての位置づけで「経営戦略力」というコンセプトに関する論点整理のブラッシュアップを図ることを目的としている(そのため、一部内容は前回稿のレビューを含む)。併せて、本稿を経営戦略コンサルタントからの問題提起の一環として捉えて頂ければ幸いである。
2.「経営戦略力」というコンセプトに対するトップマネジメントの問題意識
■「経営戦略力」というコンセプトについて
筆者は、「経営戦略力」を「経営戦略を策定し、実行し、その結果を評価し、必要に応じて修正する一連のプロセスを通じた、企業全体の総合的な実力」と定義している。また、「経営戦略力」は「経営戦略レベルにおけるマネジメント・サイクル(PDCAサイクル)が機能している企業かどうか」という視点で評価できるものと考えている。
(図表1)は、「経営戦略力」から生ずる企業間格差について、基本的なイメージをシンプルに数値化したものである。「経営戦略力」は、「経営戦略の策定・実行・評価・修正のプロセス全体の累積(総和ベースではなく相乗ベース)」で示されるため、企業の総合力を測るモノサシとして捉えることができる。
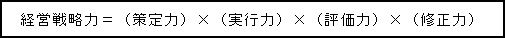
(図表1)において、「経営戦略の策定・実行・評価・修正」の各プロセスの達成水準が異なる企業モデルを3タイプ設定している。モデル企業3社を「経営戦略力」で評価した場合には、
A社(各プロセスの達成水準100)=100(優良企業レベル)
B社(各プロセスの達成水準 90)= 66(普通企業レベル)
C社(各プロセスの達成水準 80)= 41(不良企業レベル)
という結果となる。
上記のとおり、各プロセス単位での企業間格差は必ずしも大きくはないが、全プロセスを相乗した結果としての「経営戦略力」は大きく異なる。
この様に考えて、筆者は「優れた企業のコア・コンピタンス(他社にない独自の強み)」として「経営戦略力」というコンセプトを提示している。
図表1 経営戦略レベルのPDCAサイクルの機能度による企業間格差(基本イメージ)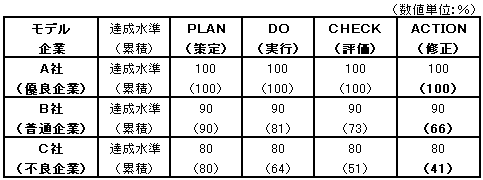
上記の基本的な考え方を共有した上で、企業のトップマネジメントの方々を対象に、自社の「経営戦略力」の自己評価を依頼したところ、筆者が予想していた以上に自己評価を行うことの難しさを認識した。その際に、多くのトップマネジメントの方々から頂いたコメントを要約すれば次のようになる。
そうした事由を受けて、本稿では、「経営戦略力の向上のためにはどうするべきか(How)」に重点を置きながら、「経営戦略力を鍛える」ための具体的な方向性について重ねて考えてみたい。
- 何故「経営戦略力」が重要なのか(Why)という点については自分なりに明確化できる。
- 「経営戦略力」の向上によって何を目指すのか(What)という点についても自分なりに明確化できる。
- 「経営戦略力」の向上のためにはどうするべきか(How)という点については自分自身が必ずしも明確化できていない。そのために、自己評価することが難しい。
次回、第2回に続く

