コラム「研究員のココロ」
部下育成の心理学
~学習する組織の本質~
2007年04月16日 各務晶久
人を育てる上で「褒める」ことは不可欠であり,その重要性は古今を問わず広く認識されている。近年の教育現場では「褒め伸ばし」という言葉が注目され,流行のコーチングでも褒めて育てるというスタンスをとることが多いようである。また,古くは,山本五十六が「やってみせ,言って聞かせて,させてみて,褒めてやらねば人は動かじ」と看破している。人間ばかりではない。馬の調教や犬の訓練でさえ褒めることに最大の比重を置いているそうである。しかし,いくら褒めることの重要性が理解できても,実践は容易ではない。真に部下を動機付け,成長を促すためには,「褒める事柄」をどう選ぶかに加え,その原因(成功要因)に注意を払う必要がある。成功や失敗から常に学び続ける「学習する組織」へ変革するためには,部下のモチベーションを高める心理的メカニズムを理解しなければならない。
部下の成長を促す上できわめて重要となるのが,仕事の成功や失敗の原因をどこに求めるか(帰属させるか)である。社会心理学者のワイナーら(1972)は,成功と失敗に関する帰属モデル(表1)と動機付けの関係を説明している。帰属モデルとは,ある行動から引き起こされる結果の原因を「統制の所在」と「安定性」の二次元で分類したものである。「統制の所在」は,原因を内的とみなすか外的とみなすか,つまり,自分でコントロール可能か否かである。一方,「安定性」は変動しやすいか否かである。これらの分類に従えば,1.自分がコントロールでき,且つ安定している原因は「能力」であり,2.自分がコントロールできるが不安定な(常に一定レベルを保つのは難しい)原因は「努力」である。一方,3.自分でコントロールできないが,安定している原因は「課題の難度」(仕事の難しさ)であり,4.自分でコントロールできない上に不安定な原因は「運」となる。
表1:成功・失敗に関するワイナー(Weiner,B)のモデル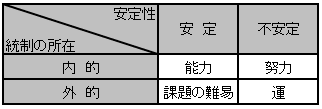
仕事の成功や失敗をどこに帰属させるか(1.能力,2.努力,3.課題の難度,4.
運)によって,心理的影響は大きく異なる。「統制の所在」は自尊感情に,「安定性」は次課題の成功や失敗の期待に,それぞれ影響を及ぼし,達成行動への動機付けを決めるとしている。ワイナーのモデルでは,成功の原因を安定的で内的なもの(能力)に帰属すると,次の行動に対する期待が最も高くなり,次の機会に対する動機づけは最高になると考えられている。また,失敗の原因を,不安定で内的なもの(努力)に帰属すると,次の課題に対して動機づけを高めるとされている。つまり,仕事の成功を「能力」に帰属させると,「有能感」や「再現性の期待」を同時に高めることができるが,仕事が簡単だった(課題の難度)とか,偶然(運)という原因に帰属させると,「有能感」や「再現性の期待」の双方を満足させることはできない。つまり,モチベーションは高まらない。一方,仕事の失敗を「努力」に帰属させると,「有能感」を傷つけず,「失敗再現の恐れ」を低減することができる。仕事が難しかった(課題の難度)とか,偶然(運)という原因に帰属させると,「有能感」を傷つけないが,自身でコントロールできない原因であるため,「失敗再現の恐れ」を低減することはできない。つまり,次の課題に対するモチベーションが高まらない,という結果になる。
これらのことは,日常の部下とのコミュニケーションの実践において,極めて重要な示唆を与えてくれる。多くの日本人は部下をあからさまに褒めないし,部下の失敗も分析的に批判しない。たまに褒める場合には,「今回は偶然にも状況が追い風だったため提案が成功したが,異なる状況でも対応できるよう気を引き締めておくこと」というように,本人の「能力」よりも「外部」に原因を帰属させた褒め方をすることが多い。部下の慢心を招かないようにという配慮,謙虚さを美徳とする日本人らしい感覚からだろう。これでは「有能感」や「再現性の期待」は高まらず,動機付けに有効な褒め方とはいえない。本人が安定的に発揮している能力を成功要因として褒めるべきである。提案力や分析力,企画書作成のセンスやプレゼン能力,アプローチスタイルなど表出化した能力のため成果に結びついたことを認めてやるのである。一方,失敗については,「たまたま運が悪かっただけだから,次回頑張れ」というように「外部」の原因に帰属させるか,「分析力が足りない」「根性が足りない」などと「能力」(時には人格部分)に原因を帰属させる場合も見受けらよう。前者は「失敗再現の恐れ」を低減できず,後者は「有能感」を傷つけるため,モチベーションを減じてしまう。本人の「努力」部分である仕事のプロセスを,共感的に反省することが不可欠である。ただし,上司から問題点を高圧的に指摘することは絶対に避けなければならない。部下の口から「何が問題だったか」「一体どうすれば良かったのか」を語らせ,内省を促すのである。「正しい答え」は実務者である部下が一番知っているのである。
要するに,仕事の成功を褒めるときには,本人の能力を褒め,失敗の反省を促す際には本人の投入した努力の量と質について内省を促すことが重要なのである。にもかかわらず,日ごろのマネジメントは正反対のアプローチという上司が意外と多いのである。学習する組織への変革の第一歩は,仕事の成功と失敗の原因帰属を正しく行うことからはじめなければならないのである。
【参考文献】
バーナード ワイナー(著),宮本 美沙子・林 保(翻訳)「ヒューマン・モチベーション―動機づけの心理学」金子書房,1989年

