コラム「研究員のココロ」
環境価値創成と知的財産権<第1回>
2007年04月09日 吉田 賢一
◆「環境」が意味するものの変化
かつての環境問題は「多量・集中・短期・単独・確実」な公害問題への事後対応・救済であったが、今日では「少量・広域・長期・複合・不確実」な地球規模の環境問題へのリスク対応・予防的政策展開に変化している。その大きな転換点が、温室効果ガスの排出量の削減についての法的拘束力のある約束等を定めた2005年2月16日の「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の発効であった。このことにより、世界の地球温暖化対策は新たな一歩を踏み出したのである。しかしながら、我が国は、温室効果ガスの排出量を第一約束期間に基準年と比べて6%削減させるという条約上の縛りがありつつも、実際の排出量は増加となっており、更なる取組の強化が求められている。そこで、地球レベルから身近な地域レベルに及ぶ環境問題の複合性から、国による取組のみでなく、むしろ人間の生活行動から発生する環境負荷等の実態を考えるならば、身近な地域での取組をより主体的に位置づけることが必要となっているのである。
◆「環境」の定義
それではこうしたグローカルな「環境」とは一体何なのだろうか。改めてその正確な定義を求めようとすると、実はどこにも明示されていないことに気づく。
私たちがまず手にするのは「環境基本法」であろう。そこでは、「公害」が取り上げられており、「環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう」(環境基本法第2条3項)としている。いわば私たちの日常生活を「自然」として捉えたものが「環境」であり、それは当たり前のことであるからこそ、そこへの負荷を与えた結果としての「公害」を惹き起こすことを防止する観点を基本に据えている。それは、同法の前身である公害対策基本法の性格を受け継いでいることの証左でもある。
一方、「環境権」という言葉も昨今よく耳にするが、一般的には「現在世代と将来世代の良い環境を享受する権利(環境権=憲法より導出される基本的人権ないし法原則)」と「それを保障する各主体の義務と責務」を合わせたものを「環境権」とすることが多い。いわば環境に対して働きかけを行う私たちの権利と義務である。ところが、我が国では実定法上の明文規定を欠き、環境基本法は環境権の規定を設けていない。しかしながら、基本的人権の面では、憲法第13条、25条を根拠として学説上承認されつつあり、各地方自治体でも、直接規定ではない形で、環境権を環境基本条例等の前文や条項として規定を置くところもある。講学上のみならず実質的にも実定化している概念であるといえよう。
なお、経済学的には、外部不経済、独占と費用逓減の問題、不完全競争及び情報の不完全性・非対称性といった観点から、「環境」は典型的な公共財であり、それらを保全するための公的介入の必要性が指摘されている。
◆新しい「環境」の価値
ところで、規模の大小にかかわらず、人間の活動の中で、もっとも地球環境に影響を及ぼす「経済」に従事する企業は、具体的な環境取組と、それを生かした事業展開を行うことが重要となっている。従来、環境と経済活動は両立しえないと捉えられてきた。確かにモノを作るために山を切り崩し、野を切り拓き製品を加工し、そして温暖化ガスを排出するトラックで輸送し消費地へ届けるといった一連の行為は、環境に負荷を与えざるを得ない。第一次産業、第二次産業、そして第三次産業であれ、こうした環境に働きかけた結果によってビジネスと市場が成り立っている。しかしながら、古代ギリシアの時代からの「よりよく生きる」という人間の恒久的なテーマを考えたとき、地球環境と共生することは、まさに人間が環境に配慮しながら、理性によってバランス感覚をもって節度ある生活を送ることに他ならない。そのとき、「カネ」は中立的な存在であることに留意が必要である。投資や資本調達の形で企業の体力を強めていく力を、環境に配慮し環境と共生、共創する企業にこそ向けることで、「カネ」が本来持つダイナミズムが発揮されることとなる。昨今では、社会的責任投資(Social Responsibility Investment; SRI)などにより、経済のみでなく、環境や社会性の側面からパフォーマンスや潜在性の高い企業へ投資する金融商品が登場している。このことは、企業活動が環境負荷を与えざるをえないことを客観的に、そして謙虚に受けとめ、環境負荷を与えている実態とそれに対する具体的な取組が必要となっていることを示している。環境会計や環境報告書等といった、汎用性の高い指標を持つ共通評価軸でもって情報を開示している企業こそが、資本市場の「カネ」の持つダイナミズムを享受できるのである。しかし、大企業ならば人的資源やコスト負担力から環境の取組が可能となるものの、中小企業では、たとえ潜在性があるとしても現時点の体力では十分な環境取組ができないといった現実もある。そこで、排出権取引やファンド商品といった多様な形で、「環境ファイナンス」の素質を持つ商品や、中小企業の環境取組を容易にする簡便な環境管理システムを整えることが必要となる。
ここで重要なことは、これまでの地球環境、自然環境、都市環境、社会・生活環境など私たちと取り巻く周辺要素であった「直接的対象あるいは客体としての環境」ではなく、人間の社会経済活動を周囲の自然環境と融合させることで生じる成果物に対して、新たな経済的市場的価値を生み出す行為や、様々なアクター(ステークホルダー)が関わることによる価値の創造行為(リサイクル活動、戦略的環境アセスメント、SRIなど)による「間接的対象あるいは人間の相互作用の副次的結果としての環境」の存在を認識することである。むろん環境の価値とは、かけがえのない自然や私たちの生活の形を保全することにこそ、その本義がある。しかし、これからは保全のみでなく保全するために用いる技術や製品開発、そして保全することで得られる利得(必ずしも経済的なそれではなく、安全・安心といった非貨幣的な価値性も含む)という観点から、いわば環境を価値化し、それを市場で交換することによって新たな経済的活力が生まれる可能性を示唆することができるのである。これを筆者は「環境価値創成」と定義している。
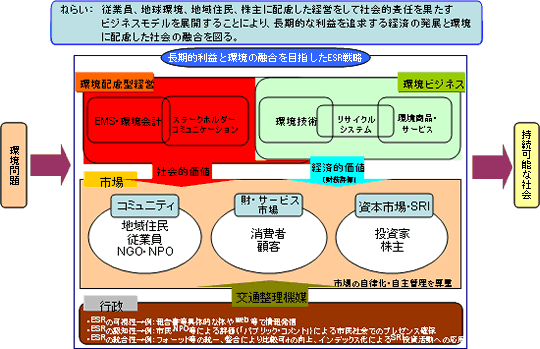
出典:筆者作成.
◆環境の価値化がもたらすパラダイム転換
環境の価値化を考えるにあたって、新たにESR(Environmental Stakeholders Relations)という概念を紹介したい。CSRが企業を主体にした概念であるのに対し、ESRとは、企業を地域社会の構成員(アクター)の一つとして相対的に位置づけ、その活動が及ぼすインパクトを「環境」をキーワードに社会的側面と経済的側面から捉えていこうとする概念である。「環境」の社会的側面とは、企業活動が及ぼす周辺環境の負荷を正しく認識し、地域を構成する他のアクターとの協働をもって、市場の自主性にもとづく自主管理により総体としての環境負荷の低減を進めていく、新しい公共管理の方向性を意味している。
一方、「環境」の経済的側面とは、企業の環境配慮型経営を進めることにより、コストとして捉えられていた環境を、社会的に評価・認証するシステム等の構築により付加価値として捉え直し、これまでの公害問題等に見られたような二律背反であった「環境」と「経済」の融合を展望する方向性を意味している。これにより、我が国で伸び悩んでいるSRI等の環境へ配慮した投資活動や、環境融資など環境を媒介として新しい価値を市場で創造する本来の資本的活動を活発化することを展望しうるのである。
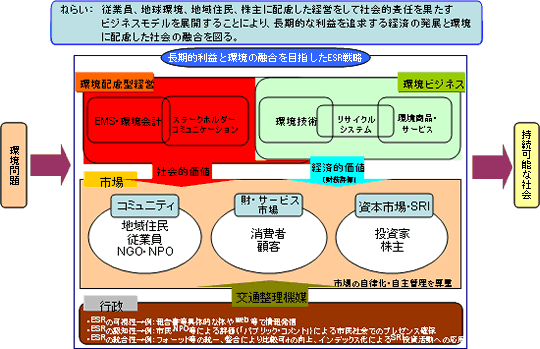
出典:経済産業省環境調和産業推進室,
「平成17年度環境ビジネス創出支援の評価に関する調査事業に関する調査報告書」
(2006年3月), p.78.
次回、第2回へ続く

