コラム「研究員のココロ」
「人材求心力」の時代
2007年03月19日 藤井 薫
1990年から人事コンサルティングを生業としている。早いもので17年になる。
人事という分野の性質上、たいていの場合、企業ニーズやマネジメント手法は社会や人心の変化を映して緩やかに移り変わっていく。それでも、時にはいわゆる成果主義の導入のように大きな流れが目に見えることがある。フィールドの実感として、ここにきてまた新たなうねりが起きているように思う。
90年代の成果主義はバブル崩壊後の経済環境に加え、団塊世代が最も賃金が高い上級管理職適齢期に到達した労務構成を背景として、業績に応じた人件費ファンド管理と個人処遇格差拡大を強調した「賃金論」の色合いが濃いものだったが、今では企業業績は徐々に好転し、団塊世代のリタイヤや労働人口の減少など状況は大きく様変わりしている。
いま企業の人材マネジメント上の最大関心事は「人を惹きつけること」に移りつつある。
誰を、誰に。そして、どのように
「人を惹きつけること」といっても、誰を誰に惹きつけるのかを明確にしておかなくてはならない。
「誰に」はもちろん「わが社に」ということだが、どこの会社にも当てはまるような何の変哲もない人事理念や人事処遇体系を掲げている会社がほとんどではないだろうか。もっとも、人事理念や人事処遇体系はよそと変わっていればよいというものでもないし、人事面のみで人を惹きつけられるものではないことは十分承知しているのだが、一般に、あまりにも色がなさ過ぎる。世間並みの処遇体系・処遇水準の整備は人材求心力確保の基本条件ではあっても、けっしてそれ以上のものではない。やはり、強く惹きつけるにはそれなりの特徴が必要だ。
「誰を」という問いには、さまざまな答えがありうる。ひとつ言えることは、全員に好かれることは理想かもしれないが、おそらくそれは不可能なことであり、その必要もないということだろう。そこで、この問いへの答えとして次のふたつの軸を提起したい。
(1)わが社「らしさ」への共感・共振の強さ
(2)ポテンシャル、パフォーマンスの高さ
人材マネジメントポリシーマトリクス
ふたつの軸の組み合わせによって「誰を」を定義する。「どのように」という人材マネジメント上の基本方針はそれぞれの象限によって異なる。
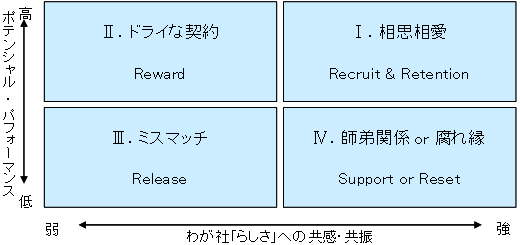
Ⅰ.相思相愛
ポテンシャル・パフォーマンスも高いし、わが社に強く惹かれている人材。
理想的な相手であり、捕まえなくてはいけないし逃がしてはいけない。従業員全員がこの相思相愛関係であれば苦労はないが、現実はそうはいかない。ただ、どんな企業であれ、従業員の何割かはこうでなければ組織の屋台骨は支えられない。
ポテンシャル・パフォーマンスを上げるための施策も重要だが、ある面それ以上に「らしさ」への共感・共振を強める施策が重要だ。この点を誤るとこの第1象限の人材はいずれ第2象限へ移行・変質してしまう。
Ⅱ.ドライな契約
ポテンシャル・パフォーマンスは高いが、勤め先は別段わが社でなくてもかまわないといった人材。
会社側が「やることだけやってくれれば」というスタンスの場合、当然のことながら働く側も「貰えるものさえ貰えれば」という意識が強くなる。ドライな契約によるGive & Takeの利害関係であり、金の切れ目が縁の切れ目になる。
このドライな契約関係は必ずしも問題だというわけではなく、高度専門職やパートタイマーを多く抱える事業ではこの第2象限の特性を意識した施策が必要になる。高度専門職と定型業務を担当するパートタイマー、まったく違うようだが両者とも社外通用力があるという意味で類似性がある。
処遇水準が重要な要素であり、基本的に成果主義はこの象限にはフィットする。
Ⅲ.ミスマッチ
ポテンシャル・パフォーマンス、「らしさ」への共感・共振ともに低いグループであり、積極的に放出とは言わないまでも、社業・社風への適合性を見定めたうえで転進奨励?!といったところだろうか。
Ⅳ.師弟関係 or 腐れ縁
第4象限には2種類の人材が混在する。
ひとつは育成途上にある比較的経験が浅いグループ。ポテンシャル・パフォーマンスを上げるための教育・支援が主要施策であり、成果主義はなじまない。
もうひとつは比較的経験が長いグループ。このグループには「かつて活躍した」人たちが含まれることも多く、年功的体系下では相当の高処遇を受けていることも珍しくない。程度問題ではあるが、この状態を放置していると、「らしさ」が発するメッセージをゆがめ、「らしさ」への信頼を低下させることになりかねない。手をつけにくい領域ではあるが、場合によっては職務や処遇の思い切ったリセットが必要だ。
「らしさ」をつかむ
ジョハリの窓ではないが、分かっているようで意外と自分のことは分からない。「らしさ」を把握するためには、他人の眼も必要だ。わたし(わが社)はなにものか?自分に似合うものもあれば、そうでないものもある。少なくとも人事分野の場合、「らしさ」と大きく矛盾する仕組みや施策は所詮運用しきれない。
人材求心力の時代を乗り切るために、まずは「らしさ」に眼を向けることからはじめたらどうだろう。
以上

