コラム「研究員のココロ」
特定健診等の義務化にあたっての推進課題
2007年03月19日 山田敦弘
1.特定健診等の義務化の概要
平成20年4月1日より特定健診等の義務化が実施される。特定健診等の義務化は、平成18年6月の国会にて成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」にもとづいて、健康診断や保健指導等の実施強化を健康保険組合などの医療保険者に求めるものである。健診項目については、メタボリック症候群の予防にターゲットをあてたものが実施される。また、その対象については、40歳以上の被保険者及びその被扶養者までを範囲とする。これにより、これまでの労働安全衛生法に基づき従業員だけに義務を課していた健診等の対象範囲が、被扶養者にまで広がることになる。さらに、取り組みについての評価がシビアに実施されることになる。取り組み状況に加え、成果についても評価されることになっている。また、平成25年度の成果の評価により、医療保険者として後期高齢者医療制度への拠出金が最大10%も加算・減算されることになっている。
2.推進にあたっての課題
特定健診等の義務化は、対象者の範囲の拡大や評価方法などにおいて、従来の取り組みにからドラスティックな変化をもたらすため、様々な問題が発生するのではないかと懸念されている。ここでは、大きく3つの課題を取り上げる。
課題1:被扶養者の健診受診率をあげること
特定健診等の義務化では、被保険者だけではなく、被扶養者への実施もその対象範囲としている。現状において、被保険者の受診率は8割を超えているが、被扶養者は1割未満となっており、被扶養者への実施が容易ではないことがうかがえる。その理由として、まず、被扶養者は事業所に出向くことがなく且つ居住地が分散していることがあげられえる。そのため、事業所毎に健診機会を設けても、それに合わせて受診に来てもらえない場合も少なくない。また、被保険者は会社への帰属意識が高く、会社側から受診の案内が届けば極力対応するように行動する。しかし、被扶養者は、もともと会社への帰属意識も高くないため、よほど背中を押されない限りは受診の案内が届いても対応しないことが少なくない。
課題2:保健指導には手間とお金がかかること
特定健診等の義務化では、健診結果に基づき受診者を階層化し、それぞれに合った保健指導を実施することになっている。ある医療保険者によると、厚生労働省が示している「標準的な健診・保健指導プログラム(暫定版)」に基づきシミュレーションを実施したところ、積極的支援をするべきに該当する人は全体の3割近く又はそれを上回ることが想定された。積極的支援は、「標準的な健診・保健指導プログラム」の3ヶ月以上の継続的な支援では支援ポイントが180以上と定められている。ここで言う180ポイントとは、例えば合計30分間の個別支援(個人面談)と合計60分間のグループ支援(集団研修等)の両方を1人の対象者に実施することになる。これを全体の3割に対して実施することはかなり費用が嵩むことが想定される。
<支援ポイント>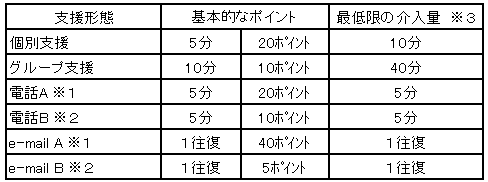
※2:行動計画の実施状況の確認と励ましや出来ていることには賞賛をする支援
※3:それぞれポイントの上限もある。
(平成19年2月14日「市町村国保における特定健診・保健指導実施にむけた関係者研修会」資料より抜粋)
課題3:取り組み量=期待した成果ではないこと
特定健診等の義務化では、取り組みとその成果を定量的にみるために、細かく点数化がされる。この点数によって医療保険者の取り組みが評価され、後期高齢者医療制度への拠出金の加算・減算が決まることになる。最大10%の減算を目指し、健診や保健指導を手厚く実施したとしても、労働・生活環境や個性に違い等があり必ずしも成果が表れるとは限らない。むしろ健診や保健指導を強化した費用が、減算に見合わない場合も出てくることが想定される。
3.取り組みにあたっての考え方
特定健診等の義務化は、医療保険者が主体となって取り組むような形にはなっているが、受診や保健指導の実施率を上げるためには、企業側の協力は欠かせない。今まで仕事に充てていた時間を、これらの活動に充てることになるからである。そのためにも、従業員の健康を維持すること、また健康に対する意識を変えることが、企業にとってどのようなメリットになるのかということを、ここであらためて見直すことが望まれる。見直した結果、例えば企業の業務効率の向上等と関連が強いといわれている抑うつなどのメンタル面での検査なども加える必要があるかもしれない。また、業種によっては、睡眠障害の検査をする必要もあるかもしれない。特定健診等の義務化を医療保険者の義務としてだけとらえるのではなく、企業としてのパフォーマンスを上げるために従業員や家族の健康について何をするべきかを考える時期に来ていると思われる。

