プロフェッショナルの洞察
イノベーション推進のための手がかり 01 企業の研究開発力に支えられている日本
2006年08月01日 佐久田昌治
 アメリカで認可されている特許数をみると、かなりの部分を日本の企業が占めている。毎年トップとなるIBMに次いで常連として並ぶのは、キヤノン、NEC、東芝、松下……といった日本企業であり、日本の開発力の強さが伺える。
アメリカで認可されている特許数をみると、かなりの部分を日本の企業が占めている。毎年トップとなるIBMに次いで常連として並ぶのは、キヤノン、NEC、東芝、松下……といった日本企業であり、日本の開発力の強さが伺える。しかし、その一方で、日本の国立研究所や大学を見ると、層の厚さ、研究開発の量、論文のどれをとっても、日本の国力にふさわしい貢献をしているとは思えない。「科学技術立国」などと言ってはいるものの、本来、基礎技術を支えるべき国の研究所や大学の貢献は信じられないほど小さいのが現実だ。
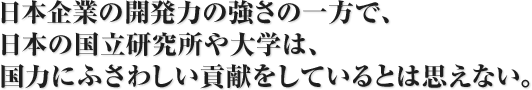
以前、科学技術庁の依頼を受けて、技術領域別に各国が得意とする分野を調査したことがある。その結果を見ると、日本の技術力の強さ、弱さが端的に見えてくる。当時の調査では、「既存技術領域」、「先端技術領域」、「科学技術領域」の3つに分けていたが、日本が優勢なのは企業が担う「既存技術領域」であり、それ以外では劣勢というのが現実だった。
具体的に見ていくと、自然エネルギーは日本があまり取り組んでこなかったこともあって弱い。医療、コンピュータ、ソフトウェア、ネットワークではそこそこ強いが、ナノテクや交通システムでは遅れをとっている。また今後の分野として期待されているゲノム科学や脳・神経、バイオインフォマティクスなども弱いというのが実情である。
つまり、60年代から80年代にかけての高度成長時代に力をつけた分野は今日においても強いが、その後は、日本企業としても次の方向性をつかみきれていないことが見えてくる。次のテーマを見極めることは高いリスクを伴い、これを民間企業に強いるのは無理な話である。これこそ国が積極的に取り組むべきことであろう。
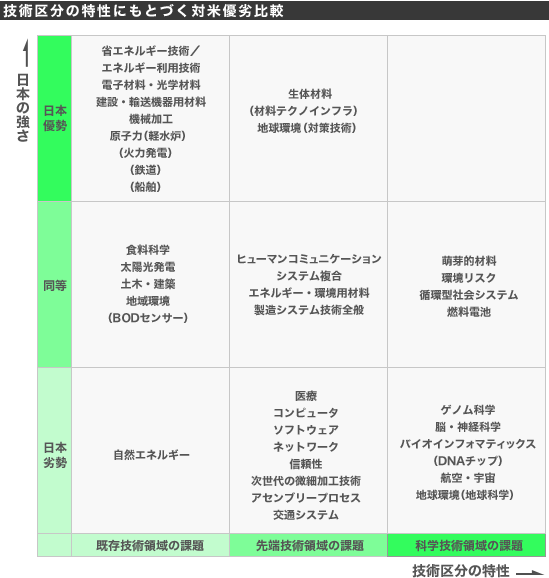
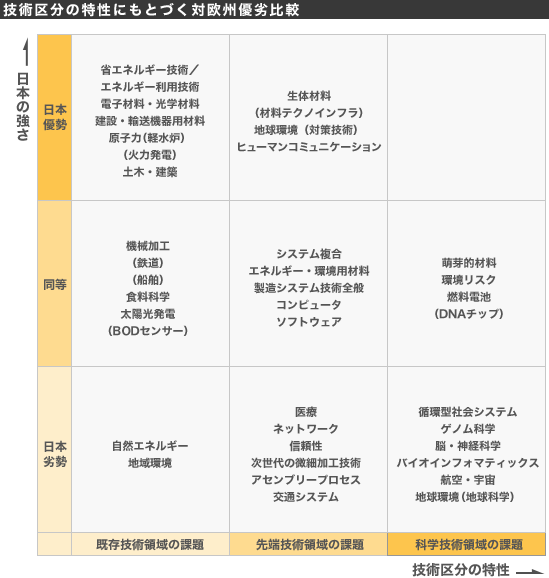
 先端的な科学技術の力を強化するためには、「大学院の強化」が急務である。しかし、今、ここに大きな問題が起こっている。それは日本のトップクラスの大学で博士課程に進む人がいなくなってきているのだ。その原因はハッキリしている。博士課程に進学しても無給であるため、生活ができないのだ。一部で奨学金をもらう人もいるが、25~30歳という時期を無給で過ごすというのはあまりにも酷な話だ。
先端的な科学技術の力を強化するためには、「大学院の強化」が急務である。しかし、今、ここに大きな問題が起こっている。それは日本のトップクラスの大学で博士課程に進む人がいなくなってきているのだ。その原因はハッキリしている。博士課程に進学しても無給であるため、生活ができないのだ。一部で奨学金をもらう人もいるが、25~30歳という時期を無給で過ごすというのはあまりにも酷な話だ。研究プロジェクトの重要な部分で学生のサポートは必要であるにもかかわらず、わが国においては、博士号取得者(ポスドク)には給与を支払ってもいいが、学生にはダメというのが決まりになっている。またポスドクの処遇も厳しいのが実情で、任期も短い上に、待遇についての将来の見通しもハッキリしないことが多い。これでは優秀な若い人材にとってリスクが高過ぎるのではないか。
一方、欧米では、博士課程の学生に給与を支払っており、たとえばMITの場合、大手企業に入るのと同程度の金額が出るという。これならば学生にとって博士課程進学を企業就職と同等に検討することができるだろう。
日本でもこのやり方を導入するのは容易なことだ。博士課程にきちんと給与を出すとともに、ポスドクに対してもすべてを任期制にするのではなく、優秀な人は正規雇用するという手もあるだろう。これなら国の方針を根本的に変えることなく、運用面での簡単な変更で実現できるはずだ。科学だけでなく、人文科学、社会科学を含めて大学の博士課程でこうした対応することで、日本の研究環境は大きく変わるはずである。
次回は、科学技術によって起こったイノベーションの歴史を振り返ってみる。
関連リンク
- 01 企業の研究開発力に支えられている日本
02 イノベーションの歴史
03 普通の技術者がイノベーションを起こす日本の強み

