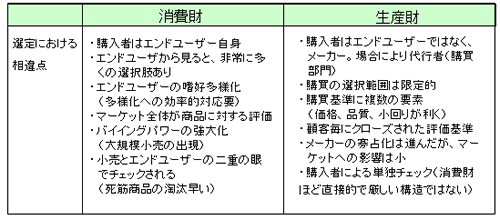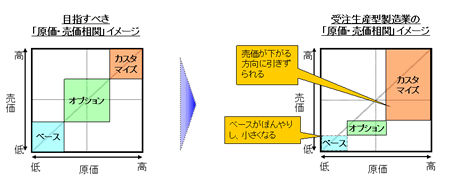コラム「研究員のココロ」
受注生産型製造業のビジネスモデル革新
2006年12月11日 大畑邦夫
■はじめに
コンサルティングを通じて、これまで数多くの生産財メーカーや卸売業の改革をご支援して参りましたが、その中で強く感じるのは、生産財ビジネスが消費財に比べ非常に遅れているということです。生産財はビジネス全体として非効率な面が多く、旧態依然とした取引慣行の下、多種多様な顧客(産業使用者)の要望に振り回され、結果的に「忙しいだけで儲からない」構造を引きずった企業が極めて多くなっています。ところが一方では、生産財メーカーの一部は極めて高い収益を上げており、大きな企業間格差が生じています。
今回は2週にわたって、我々戦略イノベーションクラスターで継続的に研究を進めている生産財ビジネスについて、中でもとりわけビジネスモデル構築の難しい受注生産型製造業の特徴やその抱える課題を整理し、ビジネスモデル革新の必要性と如何にしてこれを実践するかについて、ご紹介しようと思います。
■生産財ビジネスの特殊性
生産財ビジネスは極めて大きな特殊性を持っており、消費財とは全く異なるマーケティングやビジネスモデルが必要になってきます。では、その特殊性はどこから来るのでしょうか?私は基本的に以下のように整理しています。
- 顧客との距離が遠い
製品組込系への製品供給の場合、消費者の評価は製品全体に対して行われることが多く、部品レベルまでなかなか降りてくることはありません。顧客ニーズの収集も消費財メーカー経由になることが多く、クレーム以外の情報収集が十分に行えないケースが多くなっています。
また、生産ライン系への製品供給の場合、特に汎用品的な色彩が強いほど、一般的に製品供給のチャネル階層が深く、実ユーザーが見えなくなる傾向があるように見受けられます。 - 個客の顔を見すぎる
例えばキーパーツを生産ラインに供給しているメーカーの場合、受注生産的な要素が強く、直販体制を取っていることが多くなっています。受注生産的な要素が強くなれば強くなるほど、個別顧客の要求に囚われがちになります。顧客ではなく「個客」を追い、ニーズではなく「顔」を見るわけです。
一般的に営業担当者は、この顧客要望に応えることこそがCS(Customer Satisfaction)の達成につながると考えがちで、開発も製造もこの意見になかなか異を唱えることができない傾向があります。 - 製品の評価基準が顧客毎にクローズしている
マーケティング理論では、生産財の購買は複数部署の担当者の合意に基づき行われるため、消費財に比べて合理的・論理的であるとされています。この理論はある意味正論ですが、ビジネスの実態を表していない部分が多いと感じています。
私は、生産財に関しては製品の評価基準が顧客毎にクローズしているため、多様性があると考えています。一見合理的に見える企業の購買行動にも、非合理的な部分が垣間見えます。この多様性や非合理性が、生産財企業にさまざまな生き残り方を許すことになったと考えています。
以上のように、生産財ビジネスに関わる多くの企業は、
- 直接的な顧客(産業使用者)の評価基準の閉鎖性と多様性に基づく緩やかさ
- エンドユーザーのニーズを把握しづらい本質的な難しさ
- 顧客ニーズを標準化しづらい難しさ
の中で、自社のドメインやビジネスモデルを十分に明確にできていないと考えています。
■受注生産型製造業の難しさ
完全受注生産型の製造業は極めて少数と思われますが、生産財に携わる多くのメーカーが受注生産的な要素(一部の製品カテゴリーなど)を持っていると考えています。キーパーツを生産ラインに供給するメーカーなどに受注生産の傾向が強くなります。
経験的に受注生産的な要素の強いメーカーでは、次のような問題を抱えていることが多くなっていると言えます。
●営業
- 顧客ニーズをそのまま具現化することがCSにつながると考えてしまう傾向が強い。
- 顧客の詳細なニーズを設計部門に正確に伝えられず、手戻りやクレーム発生につながる。
- 納期遵守に向けた各工程のスケジュール管理が十分に行えず、納期遅れが発生したり、LT短縮のため、コスト増加が発生する。
- 標準原価の考え方を明確に規定できないため、見積もり段階の予定コストの精度が低く、採算性の悪化につながる。
●開発・設計
- 過度な顧客の要求仕様をチェックできないため、コストアップにつながる可能性がある。
- 仕様の確認ミスや漏れが出て、手戻りやクレームが発生する。
- 短期間で業務を行わねばならず、ミスが発生する。
- 設計変更が頻発する。
- 前該の類似設計情報をうまく共有できていないために、流用設計がうまく行えなかったり、間違った流用によって採算性を悪化させることがある。
- 業務多忙により、設計業務の標準化に取り組むことができない。
●購買・生産
- 短いLTで業務遂行を求められるため、業務が混乱し、ミスや手戻りが発生する。これにより、コストが増加する。
- 設計変更により、手戻りが発生する。
- 見込みで動かねばならない場合があり、ロスが発生する可能性がある。
次の図は製造業すべてにあてはまる基本となる考え方で極めて重要なものです。この図は、ベース、オプション、カスタマイズの三つから製品は構成されることを表しています。縦軸が売価、横軸が原価を表していますが、この売価と原価のバランスが取れないと採算が取れないことになります。左側の図は、三つの要素それぞれで売価と原価のバランスが取れている理想的な姿を表しています。
受注生産型製造業の場合、顧客ニーズに過剰に適応してしまうことが多く、右側の図のように自らの製品や技術のベース・オプション部分が不明確になり、カスタマイズ部分が増え採算性が悪化するケースが多くなりがちです。
最後に少しこれまでの整理をさせていただきます。
生産財ビジネスにおける営業の位置づけは、本来消費財のそれとは大きく異なり、極めて特殊なものと言えます。取扱商品が汎用品的なものであればあるほど、顧客ニーズの把握が難しくなり、キーパーツで受注生産的であればあるほど、顧客に振り回され、自分を見失うことが多くなります。
消費財であれば、マーケットの情報は営業担当者が集めてこなくても、さまざまなルートから入手可能ですが、生産財ビジネスにおけるマーケット情報は営業担当者以外収集することは困難です。しかし多くの場合、営業は売ることに注力しなければならず、情報収集はなおざりにされる傾向が強くなっています。業績評価の基準も売上偏重を後押しします。また、そもそもどのような情報をどのように収集するかも指示されていませんし、マーケットニーズを見極める能力を高める訓練も受けていないのが実態です。
取扱商品によって営業の位置づけは異なりますが、多くの生産財企業-特に受注生産型製造業においては、営業と開発・技術との業務連携の悪さが新製品が出ないとか、採算性が低いといった企業課題の根源であり、この部分の機能連携強化が一歩抜きん出るための肝になると考えます。
※私ども戦略イノベーションクラスターでは、受注生産型製造業向けのトップマネジメントセミナーを2007年1月17日(水)に開催させていただきます。ご興味がおありの方は、ご参加を検討いただければ幸いです。