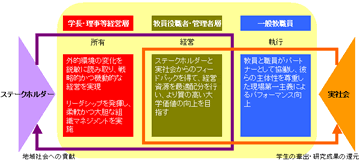コラム「研究員のココロ」
リスクマネジメント時代の大学経営<上>
2005年12月05日 吉田 賢一
1.大学を取り巻く経営環境の現在
少子化による人口構造の変化、生活者意識の変化、産業構造の変動によるサービスのソフト化、グローバル化の進展、あらゆる分野での諸技術の高度化、ITによる社会構造のユビキタス化、そして地方分権化による地域時代の到来及び行財政改革による私的セクターの拡大といった様々な環境変化の位相が輻輳している。それは、大学経営に限らずあらゆる組織体の運営に影響を与えるようになっている。そして従前からの系譜である大学改革の淵源ともなっている。一方で、大学業界に限ってみれば、国立大学の法人化により新たな競争原理が持ち込まれ、より一層の組織体としての大学の一体性、柔軟性、状況適合性が求められるようになっている。
このように、大学を取り巻く環境は大きく変動しつつあり、これまで護送船団方式で維持された大学の世界に、国立大学法人化をはじめとした競争原理がもたらされ、すでにCOEプログラム(トップ30)や競争的資金、特色ある大学教育支援プログラムをめぐって、激しい動きが各大学に起きつつある。海外からも同様の圧力が生じつつあり、海外のマンモス大学の進出の可能性や留学生の「ジャパンパッシング」現象が顕著となり、経営環境の変動は、国内だけの問題として捉えられなくなってきている。また、日本経済の低迷により、政策的文脈から経済構造の変動がもたらされたことで、新産業創出に向けた動きが顕在化するにつれ、産業界が求める人材像においても語学のみならずITや専門職的なキャリアデベロップメントなどが明確に示されるようになっている。さらに、少子高齢化の傾向も、大学全入時代の到来として顕在化し、従来の18歳人口の自然増を当てにした右肩上がりの収入構造の維持は許されなくなってきている。
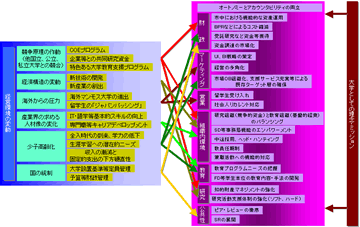
それはとりもなおさず、これまで潜在的にしか認識されて来なかった大学経営にとってのリスクが顕在化していることに他ならず、企業と同様に学外の環境を「経営環境」として捉え、場当たり的な戦術論に拘泥するのではなく、より中長期的なパースペクティブを持った戦略的なマネジメント体制の構築が求められているのである。
こうしたいわば「攻め」の経営には「油断」や「隙」、すなわち組織内外に潜む「リスク」を見過ごさないように、大局的な視点から見つめる「アラート(哨戒)」の機能と、絶え間なく組織全体をチェックする「パトロール(警ら)」機能が必要となる。
しかしながら、私たちにご相談に来られる大学関係の方々の多くは、そうした「攻め」の経営に対し、大きな不安を抱かれ思い切った一歩を踏み出せないといった状況にある。それは、そもそも「リスク」が何か、そしてそれにどう向き合うか、といった点において具体的なノウハウがないことに起因するものといえる。
そもそも大学は研究と教育というその生来的な機能からして、普遍の価値観をベースに一定の時間を費やすことで成果が導出され、その結果、大学組織は極めて固定的に形成されてきたという特質がある。このことは経営者の能力を云々する以前に組織が持つ論理として、外的環境の変化がもたらす悪影響を排除するという意味で、「守り」の組織体制とならざるを得なかったといえるのである。「学問の府」としての大学の社会性や公共性が主張される所以である。
しかし、大学を取り巻く環境は従前に増して着実に、そして急速に変化しており、研究と教育という大学本来の機能に立ち返りつつも、新しい時代環境に適したパラダイムに根ざす大学機能の確立がまさに求められつつあるといえるのである。
そこで、大学改革が叫ばれる今日、組織にとって避けられない「リスクマネジメント」について若干の考察を行い、これまで単発的な経営課題への取組がなされてきた我が国大学にとって、リスクを適切に管理するとの視点から、統合的かつ客観的に省察する必要性を指摘したいと考えている。
2.大学にとってのリスクマネジメントとは何か
リスクマネジメントとは、「ある組織体の内外に及ぶ様々な活動におけるリスクをできるだけ早期に認識し、その構造を把握、分析及び評価することをもって組織に及ぼす影響を最小限にとどめ、コストパフォーマンスの側面から適切な統制管理を行う手法の諸体系」と定義することができる。
ここでいうリスクとは、一般的には「危機」や「危険」と訳され、「危機管理」と言われることもある。しかし、リスクには、トラブル・事件が発生する「可能性」とその「トラブル・事件の事象そのもの」、そしてトラブル・事件が発生した「環境条件や構造的要因」を含むこととなるきわめて構造的な概念でもある。
企業においては事業活動を通じた企業価値を損なうことなく維持していくために、組織内外のあらゆる障害を適切に予測、回避していくことが重要となる。
一方で、大学をはじめとする公的機関においても、未曾有の大災害といった外部から及ぶ予測外の事態といったリスクは当然考えられるが、昨今においては、経済・社会・環境のトリプルボトムラインの観点から「CSR」(Corporate Social Responsibility; 企業の社会的責任)が叫ばれているが、これは企業に限らず公的機関においても、ステークホルダー(Stakeholders; 利害関係者)に対する適切な関係性を保つことが求められるようになってきていることを意味している。ましてや地方分権化の潮流に即して地域社会とのつながりが重視されている今日、社会性の強い大学にとっては、組織内から積極的にステークホルダーなど組織外へ働きかけ、いわばリスクを未然に防ぐリスク・コミュニケーションの必要性が高まっているといえるのである。
そこで重要となるのが「ガバナンス(Governance)」の視点である。新しい大学の「ガバナンス」では、より機能的なチェック・アンド・バランスをシステム化し、大学経営の透明性・効率性を高め、ステークホルダーである学生の父兄、地域市民・企業、寄付者等篤志家、行政等との信頼関係を強固なものとし、有機的な連携関係を構築することが求められるといえよう。