3.お客様の声・意見を「いかす」仕組み作り
PDCAのサイクルとしてお客様の満足度向上に取組むとき、各種の調査は、一連のサイクルのCheck機能として働かなければ意味がありません。言い換えると、問題点がより鮮明になったり、改善・改革の進捗が確認できるなど、何らかのアクションに結びつくものであることが求められるのです。そのためには、「聞くべき人に」「聞くべきことが」「しかるべき方法で」聞けるような仕組みが構築できているか、を改めて点検する必要があるでしょう。
(1)誰に聞くか →「聞くべき人」に聞く
第一に、「本当に意見を聞きたい人」の意見がきける仕組みになっているか、がポイントです。お客様の評価についてのおおまかな現状や問題点を把握するには、お客様を無作為に選んで、ご意見を聞いておくのも一つの考え方です。
しかし、一方で、地域での競争が激化する中、各金融機関では「今後、特にこういったお客様の、こんなニーズにお応えしたい。こういうお客様と関係を深めたい」という方針をお持ちです。各金融機関にとって、誰の満足度を高めたいかといえば、このお客様の満足度であるはずです。従って、しっかりと把握しておくべきは「これから関係を作りたい、深めたいお客様群」のご意見であり、評価に他なりません。
幅広い方のご意見をおうかがいすることを否定しているのではありません。例えば、幅広い方の意見は一通り把握しつつ、重要視するお客様の層に関しては、数に厚みを持たせる、負担にならない範囲で質問を追加する等、やり方は色々考えられるでしょう。
(2)何を聞くか →アクションに結びつけられるように踏み込んで聞く
お客様から貴重なご意見を頂戴するからには、何らかの改革・改善のアクションに結びつけたいものです。そのためには、おうかがいする内容も「聞いた結果、具体的に手が打てる」ようなものにしておかなければなりません。
例えば、一口に「窓口の対応が悪い」といっても、「挨拶するときの笑顔が足りない」のか、「説明の内容がわかりにくい」のか、「何か聞いたときに窓口の人がすぐに答えられず、わかる人をつれてくるまで待たされる」のか、わかりません。このあたりを具体的にしておかないと、次の手の打ちようがありません。また、いくつかの施策の結果、仮に満足度が向上したとしても、どの取組みがお客様に評価されているのか、がわからないと、それぞれの施策を継続すべきかの判断もつきません。
「この点は特に問題なので力を入れて改善したい」「ここはうちの強みなので、より一層のばしてお客様の満足度を高めたい」といった点に関しては、一歩踏み込んで、お客様の評価・ご意見がうかがえるようにしておく必要があります。
(3)どのように聞くか →アンケートに頼り過ぎない
「満足度調査」というと、すぐに書面のアンケート調査を思い浮かべてしまいますが、アンケート調査がお客様の声を拾い上げる唯一の手段ではありませんし、アンケート調査で聞けることには限界もあります。
例えば、法人のお客様へのアンケート調査の結果、「もっと情報提供をしてほしい」という意見が多かったとして、ここからどのような施策が考えられるでしょうか。せいぜい渉外担当者に「もっとしっかり勉強して、お客様の相談にのるように」という号令をかける程度で終ってしまいそうです。この場合、普段からお客様と接している渉外担当者の方が、直接お客様(法人の経営者の方)にヒアリングするといった方法も考えられます。お客様との直接の対話を通じて、個々のお客様が、どのような背景(お客様が直面している事業での課題等)のもとに、どのような情報を欲しているかを把握することができれば、例えば「この業種のこういうお客様には、こういう支援や情報が必要ではないか」というように、各金融機関が一丸となってとるべき施策(の仮説)についても随分、議論しやすくなるでしょう。
お客様から直接ご意見をおうかがいできる情報の窓口は、日頃お客様と接する渉外担当者、コールセンターなど、アンケート調査の他にもたくさんあります。それぞれの特徴を活かし連携することで、全体として知りたいことがわかるような仕組みになっているか、を確認してみましょう。
以上の視点で、これまでに実施した調査を再確認すると、(過去の調査を同じやり方で継続するのではなく)対象や内容を見直した新たな枠組みのもとで調査を実施することが必要になるかもしれません。
例えば、昨年度に実施した調査を、現在のおおまかな問題点を浮き彫りにするための「フェーズ1」の調査(公表された調査内容を見ていると、このタイプが多かったような印象を受けます)として位置付け、今後は「フェーズ1」で浮き彫りになった問題や課題への取組みの進捗を「フェーズ2」の調査で確認・検証していく、といった進め方が考えられるでしょう(図「調査の位置付け」)。
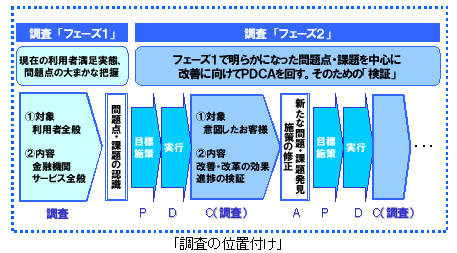
4.むすびにかえて
最後に、一つ心に留めていただきたいのは、お客様のご意見をうかがった時点でそのお客様の期待値は高まっている、という点です。いわばお客様から「ボールを投げられた」状態にあるのです。いただいた意見を受け止め、これにきちんと対応しなければ、「なんだ、意見だけ聞いておいて、何も変わらないじゃないか」と、かえって不満を作り出すことにもなりかねません。さらに怖いのは「意見を言っても応えてくれないから、もう何も言わないよ」とお客様が口を閉ざしてしまう(そして何も言わずに他の金融機関に去っていく)ことです。そうならないためにも、今一度、お客様のご意見をどのように受け止め、いかに満足度を高めていくか、について考え抜く必要があるのではないでしょうか。
意図したお客様の満足を勝ち取り、地域での存在感を高めるための戦いは、まだ幕があいたばかりなのです。

