コラム「研究員のココロ」
構造改革下の公共図書館
~公民協働の構造へ~
2005年11月28日 永見真利子
1.公共図書館の運営体制の変容
ドラマの主人公や登場人物が公共図書館で働く姿を見かけます。現在放映中のあるドラマでは、主人公の妹が近所の公共図書館にパート勤めをしている設定です。ドラマはドラマであって、あくまで現実とは異なるとはいえ、「公共図書館でパート勤めをする」ということが一般的に浸透してきたことの表れなのではないでしょうか。
(社)日本図書館協会の統計によると、2004年の公共図書館職員のうち、正規の公務員は全国平均で半数強(図1参照)、残りの半数弱は非正規公務員である非常勤や臨時雇用(パートやアルバイト)の職員です。ここで、非常勤・臨時雇用職員は年間勤務時間を1500時間以上(月20日勤務と想定した場合、一日6.25時間以上の勤務)を1人としてカウントしていることを考慮すると、実際に公共図書館で働いている非常勤・臨時雇用職員数は正規公務員数を上回っていることも考えられます。このデータから、わが国の公共図書館は非常勤や臨時雇用職員なくして成り立たない状況になっている、と言っても過言ではないでしょう。同時に、正規・非常勤・臨時という様々な雇用形態の職員を抱えながら、専門的な職能の確保と、一定の業務水準を中長期にわたり維持するために頭を悩ます公共図書館館長が多数おられることが容易に想像されます。また、非正規公務員による役務提供のもうひとつの方策として、運営部分の業務委託があり、これを選択する図書館も2002年時点で全国17.5%(※1)にのぼるというデータもあります。かつて正規公務員のみで運営されていた公共図書館は、時流の中で運営体制が徐々に変容し、ここにきて新たな潮流としてPFIや指定管理者制度が台頭してきました。これまでの役務提供のあり方による運営体制の変容から、運営サービスそのものを調達するという「構造改革」の波が公共図書館に押し寄せてきているのです。
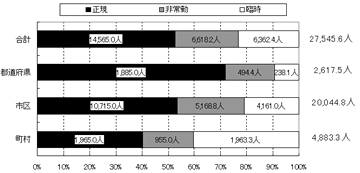
※非常勤・臨時職員は、年間実働時間1500時間を1人として換算
2.公共図書館の財政事情
さて、昨今、全国の自治体の財政が厳しい状況にあることは周知の事実ですが、この影響は当然ながら社会教育の分野にも及んでいます。公共図書館でいえば、先に触れた非常勤・臨時職員の雇用や業務委託もその一例ですし、PFIや指定管理者制度の導入もその一端といえます。また、公共図書館の財産ともいえる書籍等の購入費用(以下、「資料費」といいます。)の縮減傾向にも財政事情が表れています。(社)日本図書館協会の統計によると、全国の公共図書館数は年々増加し、平均すれば1自治体に1館程度の設置が進んでいますが(※2)、資料費予算の全国総計額は1998年をピークに減少傾向にあります(図2参照)。これを、1館当たりの資料費予算で見ると、ピークの1996年に比べ2004年には4分の3程度にまで削減されています(但し、物価変動は見込んでいません。)。公共図書館が一定水準のサービスを提供するには、少なくとも恒常的に資料費を確保してこそ成り立つと考えますが、厳しい財政事情からはそれもままならない状況です。
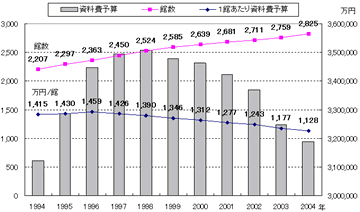
加えて、施設そのものの老朽化や狭隘化、バリアフリー・ユニバーサルデザインへの未対応などの問題が顕在化しています。しかし資料費さえも削減されているのですから、改修や建替などに取り組むことはさらに困難な状況です。その実情は、公共図書館で働く方々が一番実感されていることと思います。
3.公共図書館の構造改革への挑戦
2000年にPFI法が成立した際に、図書館界では公共図書館へのPFI法の影響は少ないという機運が一部にありました。しかし、三重県桑名市ではわが国で初めての公共図書館へのPFI導入に向け、2001年6月にPFI法に則り実施方針を公表し、2004年10月には全国に先駆けて開館に至り、先月には開館1周年を迎えたところです(※3)。筆者は、この桑名市立中央図書館のPFI導入に際し、市のアドバイザーとして携わりました。桑名市立中央図書館のPFI導入の概要は、建設費を民間資金により調達し、事業期間中(30年)の図書館運営の主幹業務を市職員が担い、それ以外の運営及び維持管理業務サービスを民間企業である特別目的会社(SPC)から調達し、市は建設、運営及び維持管理業務についてのサービス対価をSPCに支払うスキームです。また、提供されるサービスに民間のノウハウをより活かすために、資料購入をもSPCが行う仕組みとしている点が特徴的です(但し、資料の選定方針は市が決定しますし、選定の決定権限も市が持っています。)。これらの仕組みにより、建設費の市の財政負担を長期間にわたり平準化させ、かつ、恒常的に資料費予算を確保しながら、事業全体のコスト削減(バリュー・フォー・マネー:VFM)を達成し、継続的かつ安定的な図書館サービスを市民に提供する構造となっています。また、PFIの特徴のひとつであるモニタリングとインセンティブ/ペナルティの仕組み(※4)により、図書館界で近年必要性が強く叫ばれている図書館パフォーマンスの評価を実践する場にもなっています(※5)。
公共図書館へのPFI導入は未だ黎明期にあり運用上の課題も少なくありません。しかし、「サービスの外部調達」という「構造改革」への挑戦は桑名市の例に留まらず、少なくとも全国で4館(開館予定順に、杉戸町、稲城市、府中市、長崎市。)の開館が予定されており、この他にも公共図書館へのPFI導入の検討を進めている自治体が多数あります。また、公共図書館の「構造改革」のもうひとつの波である指定管理者制度の導入事例も出現しはじめています。
筆者が桑名市立中央図書館へのPFI導入に携わる中で、一番に注力した点は「市民にとってよりよい図書館サービスを提供するためには、どうすればよいか」ということです。この当たり前のことに立ち返れば、市民にとって最も重要なことはサービスの実施主体よりも、サービスそのものが市民にとって満足いくものであるかどうか、であることは明らかです。
これからも公共図書館のサービスを市民に提供するのは公共自治体であることに変わりはありませんが、コスト削減を達成しつつ、民間の持つノウハウを活かしながら安定的にサービスを調達するという「公民協働の構造」が、これからの公共図書館経営の重要な柱のひとつとなることでしょう。
【脚注】
- ※1
- 文部科学省 公立図書館等の現状に関する調査(2003年1月)
- ※2
- 全国の図書館総数を自治体数で平均すれば、1自治体当たり1館程度が設置されています。但し、(社)日本図書館協会のまとめる自治体当たりの図書館数を示す「図書館設置率」は54.5%(2004年4月時点)に留まります。市区部は97.9%とほぼ全てに設置されていますが、町は48.3%、村は17.6%に過ぎません。
- ※3
- 当館の現在までの入館者数は開館半年で約36万人、その後半年で約34万人と、以前に比して約3倍の入館者数を数えています。詳しい事業内容は、桑名市HPに掲載されています。また、「NPMに基づく先進的アウトソーシング事例」(内閣府委託調査:財団法人関西情報・産業活性化センター)や内閣府PFI推進室 先進事例の紹介を参照ください。
- ※4
- PFI導入により、SPCの提供するサービスが市の提示する要求水準(パフォーマンス)に達しているかを、市は監視(測定・評価)し、パフォーマンスの達成度に応じて市はサービス対価の増減を行います。桑名市の例では、市の規定する利用者数より実績数が多い場合にはSPCにインセンティブ・フィーを支払い、パフォーマンスが一定以下の場合にはペナルティとしてサービス対価が減額される仕組みとなっています。
- ※5
- 配属職員数等を規定した仕様発注による通常の業務委託では、パフォーマンスの到達状況に応じた業務管理ができませんでしたが、PFIでは性能発注による発注方式をとるため、必然的にパフォーマンスの到達によるサービスの評価を行うことになります。

