コラム「研究員のココロ」
キャリアの自律性向上に焦点を当てた人事施策<後編>
2005年11月28日 君島 一雄
5.社員の自律的なキャリア開発をどのようにして支援するか
では、どうすればよいのだろうか。まずは、社員が自らの専門能力を高めること、つまり、担当業務分野での知識・スキルをさらに広げたり深めたりすることや、今後、自分が進みたい方向に向けてみずから主体的に能力開発するよう促すために会社側が社員に対して「気づき」の機会を与える必要がある。具体的には、社内でどのようなキャリアを開発する機会があるのか、どうすれば希望するキャリアを手に入れることができるのか、そのためにはどのような努力をすればよいのかなどについての情報を提供することである。つまり、社員みずからが自分自身の意志を確認し、自らのキャリア開発を自己責任により行っていくための道筋をわかりやすくすることである。そうすることにより、社員が自分が希望するキャリアを手に入れるために自律的・主体的にみずらの能力開発に取り組むよう促すことができる。
もう一つは、社内での研修(キャリアデザイン研修など)の機会を通じて生涯発達心理学の理論にもとづいた年代毎の発達課題などについて教育することである。エリクソンの漸成説によれば、発達課題は年代毎に「アイデンティティの確立」⇒「親密性」⇒「世代性」の順で変わってくるとされている。社員がこうした年代毎の発達課題があるということを理解するだけでも、「自分がどのような成長をしていけばよいのか」について気づくためのヒントが得られるはずである。
以上述べてきた専門能力分野の視点及び年代毎の発達課題の視点に共通していえることは、自分が何がクリアできていて何がクリアできていないかを知ることが重要であるということである。こうした「気づき」の機会を研修などの場で与えることは大変重要であるが、同時に、こうして気づいたことを現実の仕事の中で実際の業務とリンクさせながら、つまり、日常業務の中で課題に挑戦し、それを克服することを通じて学習を促進させていくことも同様に重要である。こうした学習を支援するための会社側の取り組みとしては、職場における日常的な支援(目標管理制度の適切な運用、組織的なメンタリング)を行うことをまず挙げることができる。さらに、社員がみずから自発的に大きな課題に挑戦することができる機会を提供することも必要となる。これは、本人が節目の経験を自ら主体的に行うための機会を提供することであり、具体的には、FA(フリーエージェント)制度や社内公募制度などの仕組みが該当する。
しかし、これらの仕組みはすでに多くの大手企業が導入済みであるにも関わらず、実際にはなかなかうまく機能していないということもよく聞く。こうした仕組みを導入することも大事だが、それ以上に会社と社員の関係の成熟度に応じて自社における最適の仕組みを導入することの方が重要であると考えられる。以下において、会社と社員の関係の成熟度に応じたキャリア開発支援策のあり方(試論)について述べることとする。
6.会社と社員の関係の成熟度の段階毎のキャリア開発のあり方
下図に会社と社員の関係の成熟度の段階毎のキャリア開発のあり方を示す。
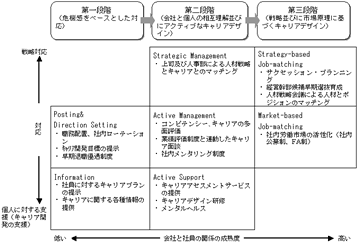
まず、この図に描かれている第一段階に達する前の状態について述べてみることとする。この段階では、会社が社員を子供として扱っている状態にあり、結果として社員が会社に依存しきっている状態である。これまで会社の経営が極めて厳しくなってリストラ(人員整理)を考えるざるを得なくなった場合、リストラの対象となりやすかったのは、高賃金に見合っただけの成果をなかなか上げらない中高年(その中でも評価の低い社員)であった。しかも皮肉なことに、会社中心で生きてきた(すなわち、会社に依存してきた度合いの高い人)ほど、「自分は会社のために尽くしてきた」という意識を持ちやすい。しかしながら、そういう人は往々にして本人が思っているよりも会社からは貢献度を評価されず、リストラの対象となる可能性が高いのである。幸いにして各企業が実施してきた人員整理(希望退職、退職の勧奨、指名解雇)の施策は過去のものとなってきたが、いったん作られた流れ、すなわち、「会社は終身雇用を必ずしも保証はしない」という労使間の暗黙の合意を元に戻そうということにはならないであろう。
特に、第一段階以前の会社と社員の関係で起きやすい不幸な状態(例えば、会社の業績が極度に落ち込んで人員整理の必要が起きた場合、辞めなければならなくなった社員が経済面でも精神面でも大きな打撃を受けやすい状態)を未然に防ぐ意味で、会社と社員の間の強すぎる依存状態を見直す必要がある。それに該当するのが、図の第一段階で実施する施策である。この段階では、戦略対応の部分でいうなら、自社の経営戦略や今後の人材開発目標を踏まえながら、さらに、年代毎のキャリア発達課題を踏まえながら、社員にキャリア開発目標を提示し長期的な能力開発の方向性を提示する。ここで大事なことは、個々人にどのようなキャリアを開発すべきかを具体的な提示するのではなく、与えられた業務以外の分野で、自分としてやりがいを感じることができると同時に、みずからの市場価値を主張できる段階までのキャリア開発を社内においていかにして実現できるか、そのガイドラインを提示することである。一方で、自分の将来を社内でのキャリア開発を肯定的に考えられない人に対しては、早期退職優遇制度などの施策を同時に実施するといったことも必要となる。さらに、対個人というという面では、キャリアについての有益な情報提供とかキャリアカウンセリングなどの情報提供なども有効である。
第二段階にもなると、会社と社員との関係が成熟してくるので、さらに深みのある対応を行っていく必要がある。業績評価と連動したキャリア面談や会社の人事戦略と個人のキャリア開発とのマッチングなどを挙げることができる。つまり、中長期的なキャリア開発と年度ごとのパフォーマンスマネジメントとを組み合わせるのである。
第三段階では、キャリア開発に当たっての会社と個人の相互の関係を会社の戦略と連動させたマネジメントを行うことが可能である。この段階になってくると、社員の仕事に対する価値観や意欲(例:どこまで仕事にのめり込むか、どこまで自分らしさを大切にするか、仕事と家庭生活のバランスをどうとるかとなど)に応じて、それぞれ適切な施策を講ずることができるようになる。例えば、社員を会社の業績への貢献度とこれからのコア人材としての期待度の観点で区分すると、大きくは、(1)経営幹部候補 (2)平均的な社員 (3)問題を抱えている社員の3つに分けられるが、それぞれに対する適切な対応方法を検討してみると、下記のように言える。
(1)の経営幹部候補(あるいはそれに順ずる社員)に対しては、早期選抜育成制度を事業戦略と連動させて行うことが特に重要である。つまり、人材開発と事業戦略との推進とを併行して行うのである。
次に、(2)の平均的な社員に対しては、基本的には本人の「気づき」を促すことに焦点を当てること(例えば、キャリアデザイン研修で自分の棚卸をするセッションを用意すること)が必要である。さらに、みずから主体的に「ひと皮むける体験」を行おうとする人(あるいはその準備が出来ている人)に対しては、FA制や社内公募制などのチャンスを用意しておくことが有効である。そして当然ながら、(1)と(2)の境界は固定的なものとせず、すなわちいったん貼ったレッテルを状況の変化に応じていつでもはがせるようにしておく必要がある。(例えば、早期選抜組の場合でも、責任や仕事の負荷があまりに過大で本人も耐え難いようになるならば、いつでも元のコースに戻れるようにしておく必要がある。)
最後に(3)の問題を抱えている社員に対しては、メンタルヘルスなどの施策が必要になる。キャリアカウンセリングを行うにしても、今抱えている仕事上の問題点や人間関係などの悩みを解決するためのカウンセリングが中心となる。(なお、(3)の問題を抱えている社員は、図の第三段階到達以前において多く見られることが想定されるので、(3)の人材に対応する人事施策は、図では第二段階のActive-Supportの中に位置づけられている。)
7.気づきの支援が一番のポイント
図の第二段階に達している企業はまだ一部で、多くの企業が、まだ第一段階にあると思われる。また、第三段階での施策(FA制度、社内公募制度など)を導入している会社は多いものの、それが効果的に活用されている企業はごくわずかではなかろうか。
これまで繰り返し述べたように、これからは社員のキャリア開発を社員個人の自覚の問題とするのでなく、会社が本来持っている人材育成機能を組織的・効果的に活用する視点が重要であるといえよう。
その際に大事なのが社員に気づきを与える仕組みで、組織の中でキャリア開発を進めていくための枠組みを整えた上で会社が主導して社員のキャリアデザイン研修を実施し、社員が自らのキャリアを真剣に考えるための機会を提供すると共に、研修受講後の社員のキャリア開発を組織ぐるみで進めていくための人事施策が必要になるのである。

