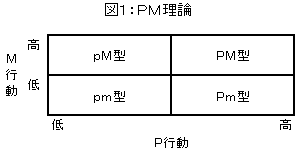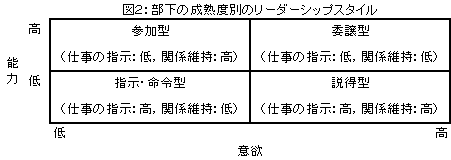コラム「研究員のココロ」
名著に学ぶ!リーダーシップ論再考
2006年10月30日 各務晶久
1.部下のマネジメントが難しい時代
「部下に何とか仕事をしてもらう」というのは多くの管理職にとって避けられない課題である。自律的に行動し、意気高く働く部下だけで構成される組織の長なら、このような悩みとは無縁である。しかし、日々の仕事で精一杯という未熟な部下、協働意識や貢献意欲に欠ける部下も残念ながら一定数存在する。彼らのモチベーションをどのようにすればうまく引き出せるのか、どのように仕事を割り当て、どのように業務をマネジメントすればよいか、管理職は日々頭を悩ませているのが現実である。
今や「石の上にも三年」「技を目で見て盗め」などと言っていたのでは間違いなく部下はついてこない。その上、変化対応型の組織として、プロジェクトチームやクロスファンクショナルチームなどのマトリクス組織が増えているが、これらの組織では上下関係が曖昧で、ポジションパワーで言うことを聞かせるのも困難である。技術進歩の激しい現代では、最新技術は部下の方が上という場合も多く、「長年の経験とカン」で押し通しても面従腹背は避けられない。団塊の世代が大量退職を迎える所謂2007年問題が現実のものとなり、管理職は待ったなしに若返る。部下のマネジメントはかつてないほど重要で難しい問題になっている。
2.名著を紐解く
このような時代だからこそ「名著に学べ!」である。目新しいフレームワークに目を奪われがちになるが、今やスタンダードになった「名著」を紐解くとまさに知恵の宝庫である。経営学の入門書を何冊か書店で手にとって見ると、必ず“リーダーシップ”に関するスタンダードな理論がいくつか解説されている。今や定番となったこれらの理論が今こそ輝きを放ち、スポットライトを浴びるのである。上司と部下のマンツーマンコミュニケーションにおいて発揮すべきリーダーシップやそのための技術・知恵が満載なのである。
3.リーダーシップをめぐる誤解
リーダーシップをめぐる誤解の主なものは次の二点であろう。
- リーダーシップはカリスマ性やパーソナリティーであり、訓練しても身につかない。
- リーダーシップとは “集団に対する影響力”であり、トップマネジメント層のためのものである。
このような誤解から、リーダーシップ理論に無関心なビジネスパーソンは少なくない。しかし、スタンダードなリーダーシップ論を注意深く紐解くと、非常に重要な次の二つの事実が浮かび上がる。
- リーダーシップはスキルであり、訓練によって身に付けられる。
- 集団に対してだけでなく、一対一のコミュニケーションでも発揮すべきものである。
では、一対一のコミュニケーションにおいて必要なリーダーシップとその技術とはどのようなものであろうか。
4.頑強な二軸、仕事(課題)軸と人間軸
PM理論(三隅二不二)を中心としたパラダイムでは、リーダーシップ行動とその効果に関して、非常にシンプルな結論が頑強に得られている。
- リーダーシップ行動は、仕事(課題)に直結した行動と、人間として部下への思いやりや集団としてのまとまりの維持に直結した行動によって記述される。
- 仕事(課題)軸、人間軸の二つの軸でともに高い行動を示すリーダーシップ行動のスタイルが、最も普遍的に有効なスタイルである。(注)
PM理論では、仕事軸をP(パフォーマンス)、人間軸をM(メンテナンス)と定義している。QCDS(品質、納期、コスト、安全)などにおいて、高い目標を掲げたり、緻密にフォローしたり、プレッシャーをかけたりという監督行動をP行動、部下の意見に耳を傾けたり、気まずい雰囲気を解きほぐしたりする行動をM行動と呼んだのである。
あらゆる産業のさまざまなポジションでリーダー行動を分析した結果、リーダーにはこの二軸に関する行動が繰り返し確認されてきた。大事なのはP行動とM行動の双方ともに高いPM型が最も有効なスタイルであること、PとMは掛け算であり、足し算ではないことである。つまり、どちらかがゼロなら効果はゼロ、短期的には効果を上げそうだが長続きしない。日本のリーダーシップ研究の第一人者である神戸大学の金井教授は、このスタンダードな基本の二軸は、最新の変革型のリーダーシップ理論においてさえ、その基盤に見え隠れすると論じている。リーダーシップを論じる上で、それほど頑強且つ不動の二軸なのである。
5.実務への応用が容易な状況アプローチ
仕事(課題)軸と人間軸の双方が必要といっても、状況によってそれぞれの行動の重要性は変わるはずである。その点を部下の成熟度で説明したのが、P.ハーシーとK.H.ブランチャードの状況リーダーシップ(Situational Leadership)である。部下の成熟度を「意欲」と「能力」に分け有効なリーダーシップスタイルを定義したものである。(1)もっとも未熟な部下は指示・命令型、(2)能力が低いまま意欲の高まってきた部下には説得型(指示もするし、人間関係も大事にする)、(3)逆に能力は高いのに意欲は低い部下には参加型(指示は低いが人間関係を大事にする)、(4)最も成熟した部下(能力も意欲も高い)には委譲型で接するのが良いというものである。
部下のタイプ別に仕事(課題)軸と人間軸の二軸を使い分けるこの理論は、シンプルではあるが極めて実践的である。我々がクライアントに実施したさまざまなリーダーシップ開発プログラムでも、状況適応リーダーシップ理論をバックボーンにしたプログラムが、もっとも受講者にメッセージが伝わりやすく、その後のマネジメントスタイルの変革に与える影響は大きかった。
6.おわりに
部下に気を使う弱腰な上司ほど、人間関係の維持に関心を払い、参加型のマネジメントを志向する。自身の上司がかつて専制的だった場合の反動でそうなる場合も多い。口やかましく事細かな指示をせず、意思決定に参加させるこのスタイルは、民主的で唯一の方法だと誤解しがちである。しかし、その仕事を担当させたばかりの部下や新入社員に具体的な指示を与えず、問題意識や改善方法について尋ね、意思決定への積極的な参画を促しても、部下は要求に応えられずストレスを感じる。逆に相手が誰であろうが、細かな指示を与え続ける上司も改めるべきである。仕事に習熟した部下にとって細かな指示はくどい以外の何ものでもなく、意欲を減退させるだけである。
画一的なスタイルではうまくいかない。自身の癖を知り、部下の成熟度に合わせたリーダーシップスタイルの使い分けが肝心なのである。