コラム「研究員のココロ」
人口減少時代の「勝ち組」自治体と「負け組」自治体
~2007年問題を千載一遇のチャンスに~
2005年11月14日 矢野勝彦
人口減少は全国の非都市部、地方に行くほど激しい。【人口減少地図】で示す通り、まるでその暗い将来を暗示するかのように軒並み黒く塗り潰された地方は特に深刻だ。
人口減少の何が問題か。その答えは、地域に負のスパイラル現象を引き起こすことだ。つまり人口減少は地域の経済活動を縮小させる。今や地方は補助金や交付金が期待できないし、公共工事も減少しているので、否応無く生活サービスやコミュニティ機能のレベルは低下せざるを得ない。それにより人口がますます流出するという悪循環に陥るのだ。
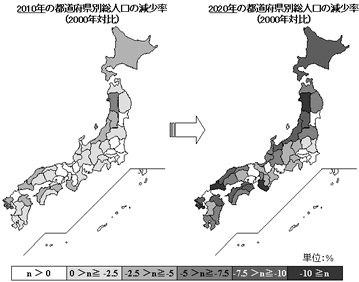
ネオ・シニア層誘致による3つの効果
逼迫する財政状況下で、これまでにない大きな難問に直面している自治体は何をなすべきか。ヒントは身近なところにある。折りしもわが国には都市部を中心とした団塊の世代の大量退職という「2007年問題」が控えている。このネオ・シニア層はアクティブでリッチなうえに、熟練した技能、ノウハウ、人脈を持った“金の卵”ならぬ“銀の卵”と言える。このネオ・シニア層を地域に呼び込むこと(=「人財」誘致)は、地域に莫大なメリットをもたらす。具体的に3点指摘しておこう。
(1)地域への経済波及効果
今年3月に北海道が行った調査によれば、60歳の高齢者夫婦1世帯が移住することによる地域への経済波及効果は約2億円である(消費支出と平均余命等を勘案し、平成12年北海道地域産業連関表を使用して算出)。ネオ・シニア層は移住した先で、健康、医療、生活支援など様々な商品やサービスを消費する。それが、新しい商品やサービスの開発に繋がり、余暇関連サービス、地域交通サービスなどの21世紀型の新しい産業を創出する。
特に生活を支援する生活サービス産業群は、労働集約型でかつ地域に密着しているので、経済効果が地域内に還元されるし、雇用の創出効果が大きい。その効果は、60歳の高齢者夫婦1世帯にかかる老人医療費や介護費用等の公的負担約5000万円を遥かに上回る。
(2)地域の産業構造転換
経済・社会が成熟したことの必然の帰結として産業構造は変化し、サービス産業の経済化が進む。地域もこのトレンドを受け、これまでの工場誘致や輸出産業に固執するのではなく、生活サービス産業を戦略産業として育成する必要がある。経済のグローバル化の結果として、製造業の空洞化に見られるように、先進国では労働集約的な第1次・第2次産業を持続させることは難しくなるので、高付加価値で雇用創出効果の大きいサービスを産業として育成することが重要になるからだ。「人財」誘致による生活サービス産業の創出はその流れを加速させ、観光・集客交流、生活・福祉、医療、不動産や金融、保険に至るまで幅広い分野に波及する。
(3)地域の生活の質(Quality of Life)の向上
新しい生活支援の商品・サービス群は、生活インフラの整備・拡充に直結するので、移住者だけでなく、もともとそこに暮らす地域住民にとってもその満足度が高まる。「住みよさランキング」などの指標となっている安心感(医療・福祉の充実)、利便性(小売店・金融機関の拡充)、快適性(住宅等の生活インフラ整備)、富裕度(地方財政力の向上)、住居水準(持ち家率や面積)などのレベルが上がり、地域全体の魅力度の向上に繋がることになる。
この3点は、相互に連関しながら、人口減少による地域経済の縮小がさらなる人口流出を促すという負のスパイラルを正のスパイラルに逆転させる。地域の魅力度が高まることで、人口がますます流入するという好循環だ。
動き出した全国の自治体
団塊の大量離職という2007年問題は、地域再生を実現させるきっかけになる。この千載一遇のチャンスをものにしようと全国各地が動き出している。
たとえば北海道伊達市では、約4年も前から市役所が旗振り役となって、高齢者向けの新しい生活サービス産業の創出で、若者にとっても働きがいのある町づくりを進めてきた。公有地の活用等で民間企業が低料金の老人ホームを運営する「安心ハウス」を建設。車や運転手を効率的に活用して生活者ニーズにきめ細かく対応する「ライフモビリティサービス」は2回の実証実験を終え事業化に着手する。比較的気候が温暖であることも手伝い、リタイア後に移り住む人が増え、住宅地地価上昇率が03年度、04年度と全国トップに躍り出た。
兵庫県八千代町は、典型的な中山間地域だが、ここには国土交通省にも選定された「観光カリスマ」がいる。町役場に勤める観光カリスマを中心に、都市住民向けの滞在型市民農園を企画。きめ細かな交流プログラムを実施することで、都市住民と地域住民の交流を促し、定住化に結び付けている。
これら伊達市や八千代町のように自ら努力する市町村と連携し、広域的な取組みを支援する都道府県もある。
例えば青森県では、04年度重点施策として、名川町をモデル地区に「あおもり達者村」事業を展開。県の基幹産業である農業を前面に打ち出し、首都圏の中高年層をターゲットに第二のふるさとづくり活動を本格化している。
宮崎県では、温暖な気候や豊かな自然、充実したスポーツ施設という既存資源を最大限に活かして“健康”をキーワードに交流人口の増大と人財の誘致を図る。
また、佐賀県では、温泉、焼き物、自然などの地域資源を家族単位で体感・体験できる「ファミリーツーリズム」という考え方を提唱し、団塊の世代だけでなく、その子供、孫の3世代の取り込みを狙った戦略を採る。
北海道がパートナー市町村とともに取り組んでいる「北の大地への移住促進事業」はさらに一歩踏み込んでいる。2007年をターゲットに「マーケティング(首都圏等への1万人アンケート調査)→実証実験(1カ月の長期滞在)→都市部へのプロモーション→受入体制の整備」を民間顔負けの手順で段階的に進める。この事業を貫くキーワードは移住ビジネスだ。いつまでも公共の施策として位置づけるのではなく、移住ビジネスという新しい民間ビジネスモデルを構築、実践することで持続可能性を担保する。
これらの都市部から遠距離にある自治体と少し趣を異にするのが二地域居住地域だ。首都圏に対する信州や伊豆、房総、近畿圏に対する紀州などは、都市生活者がもう一つの生活拠点を構える二地域居住地域である。二地域居住人口は既に約100万人。その潜在需要は移住の約10倍とされている。二地域居住は将来的に人財誘致につながりやすい。だからと言って努力が不要な訳ではない。
今年、長野県内で地価が上昇に転じたのは軽井沢町だけだ。抗がん能力を高めるとされる森林療法による集客交流を推進する長野県飯山市、特産品販売等によるPR活動を近畿圏で積極展開している京都府綾部市などのような努力がなければ需要を掘り起こすことはできない。
「人財誘致」に向けての3つのポイント
2007年までに残された時間は少ない。先行する自治体の取組みを俯瞰すれば、それぞれの自治体が置かれている立場は違っても、「人財」誘致に向けてクリアすべき共通ポイントが浮かび上がる。
第1のポイントは、官民のコラボレーションである。どの地域も自治体と民間組織が協働体制を構築している。程度の差こそあれ、ニーズ調査や実証実験等を通じてマクロな事業環境を分析するのが自治体、その上でミクロな事業モデルを検討し、実践するのが民間だ。官民連携型であれ、純民間型であれ、確固としたビジネスモデルを構築し、事業としての自律性と持続可能性を確保することが重要だ。
都市部の人財発地側の事業モデルは大手旅行会社を中心に出来上がっているが、各種地域密着サービスのコーディネート機能を中核とする人財受地側の事業モデルはまだまだ開発途上だ。ここに民間の知恵と工夫が生かされる。
第2のポイントは、地域間の競争と連携である。単独市町村から見れば、隣り合う市町村はライバルで競争関係にある。しかし、市町村単体での人財誘致には自ずと限界がある。市町村を互いに切磋琢磨させ、足らない資源を補完させ、広域的なサービスの質と魅力度の向上につなげるのが都道府県の役割だ。人財誘致へのファーストステップともなる観光分野では、すでに青森県、岩手県、秋田県が組んだ北東北三県観光立県推進協議会や九州全県が一丸となった九州観光推進機構が発足するなど、さらなる広域連携による地域ブランド力の向上が図られている。
そして第3のポイントは、人である。先行地域、そこには1人になっても事業をやり遂げる志の高いキーマンが必ずいる。役人でも民間人でも構わない。もし、地域にいなければ外から連れて来れば良い。地域住民が気づいていない埋もれた資源を再発見するには外部から客観視する眼も必要だ。この人財誘致は、職ありきの従来型UIJターンとは一味も二味も違う新しい試みであり、事業の組み立て方も地域によって異なるから統一的なマニュアルは存在しない。しかし、熱意ある人の周りには人が集まる。人は金は持ってこなくても、知恵やノウハウを持ってくる。
最後に、デクヴェルト(decouverte)という言葉を紹介したい。フランス語で自己発見を意味する。欧州の観光学で言うSocio-cultural awareness。つまり、受入れて交流して初めて自分達の優れた資源に気づく。アイルランドの人々が、海外からの交流によって自国資源に目覚め、アイデンティティを高めていった例がつとに有名だ。
どの地域にも必ず優れた資源がある。外部との交流によって優れた資源を見出し、地域ならではのサービスを組み立て、人財誘致につなぐ。置かれた環境を言い訳に、この努力を怠る自治体には、負け組としての未来が待っている。
(本稿は「週刊エコノミスト」2005年11月15日号(毎日新聞社)に掲載されたレポートから一部転用しました。)

