コラム「研究員のココロ」
自治体病院はどうすれば良いのか
2006年09月25日 松原 伸幸
1.はじめに
公的病院を取り巻く環境が激変している。
小泉改革が進めた「小さな政府」の流れの中で、医療構造改革でも医療分野に対する国の予算は削減され、公的病院の縮小・統廃合・民営化が進められている。
国立病院・診療所や労災病院は独立行政法人化され、大学病院も大学自体が国立大学法人化されており、社会保険病院も今後は民営化の議論の中で整理されていく。残るは地域医療を担ってきた自治体病院である。
自治体病院は地域の実情に応じ、不採算地区の医療、救急医療を含む地域の医療水準の向上を目的として設立、運営がなされてきた。しかし、「官から民へ」「国から地方へ」の掛け声による地方交付税の削減、診療報酬制度の変更等により自治体病院の経営環境は厳しいものとなっている。効率を優先する自治体の経営改革が進む中、医療費適正化、地方財政改革という点からも自治体病院の経営への圧力が増しており、「民間で提供できるサービスは民間に委ねる」という考え方はある意味正しい。とはいえ、行政の領域がどこまでなのかの議論もないままの政策では行政、市民とも混乱するばかりである。特に医療分野のように市民の生活、命に直結するものは、行き当たりばったりの政策ではなく筋の通った政策に則って実施されるべきである。
自治体病院の再生・民営化は、公営企業(公営交通・水道等)の再生・民営化の試金石でもある。以下に、簡単ではあるが論点の整理をしてみたい。
2.自治体病院の現状
ナショナル・ミニマムの観点から、すべての自治体が必要とされる一定水準の行政サービスを提供できるように、税源の均衡化を図る仕組みとして交付税制度が確立されている。各自治体の病院事業に対する一般会計からの繰出金(病院事業繰出金)については、その所要額を毎年度、地方財政計画に計上し、その一部について交付税(普通交付税および特別交付税)によって財政措置が講じられている。しかも、指定者管理者制度を導入した場合あるいは地方独立行政法人を設立した場合においても、同等の交付税措置が講じられている。これは、公設民営化やPFIあるいは独法化をしたからといっても、結局は税金で維持しなければ経営は成り立たないということである。(表1参照)
自治体病院の赤字額は、昭和60~63年頃には全国で2,300~2,800億円程度の繰入金を出せば、どこの病院も経常収支が均衡していた。しかしバブル景気の平成時代に3,000億円を突破すると、その後のバブル崩壊後も繰入金を増加しても計上収支が赤字の状態が続き、平成12年度~16年度の直近5年間では、毎年5,500億円程度の繰入金を入れても、1,000億円程度の赤字がでている。この数字からも判るとおり、国・自治体としては、これ以上の繰入金の増額は難しい財政状況であり、5,500億円程度が上限値ということである。このままの状態で自治体病院を放置していては、累計赤字が増加するだけという厳しい状況を物語っている。(表2参照)
9月2日付け東京新聞に志木市の長沼市長のコメントが載っている。
「国の補助はなく、県の補助も夜間・休日診療一回につき4万円。しかし、実際の経費は10万円以上かかり、人口6万人台の自治体が病院を維持するには限界」
ただし、自治体病院と言っても、次の4つに大別できる。
- がん・難病治療等の高度専門医療を提供する病院(一部の県立病院)
- 医療過疎等の民間医療機関の供給が不足している地域病院
- 小児医療、救急医療等の地域に不足している診療科を提供する病院
- その他の病院
②はシビル・ミニマムの点から自治体が提供すべきである。①の高度専門医療機関や③のいわゆる不採算医療は、自治体で維持すべきか、民間医療機関への補助金支給等も含めて対応できないかを検討すべきである。④は民間医療機関と完全に競合しており、民業圧迫となっていないか、行政の事業範囲かを再検討する必要がある。
財政問題以外にも、医師、看護師の不足に直面している。特に地方においては、メディアで取り上げられているように、一部の診療科が休診となっていたり、入院施設があるにもかかわらず宿直の医師が確保できないために入院を受け入れられないなど、地域の医療サービスの維持ができなくなっている。しかし、本当に医師は不足しているのであろうか。平成10年に厚生労働省が出した医師の需要供給予測(出典:「医療需要の見直し等に関する意見書」)では、平成10年度には需給関係が逆転し、必要医師数を上回る供給がされているはずであった。これを踏まえ、当時の内閣は医師超過とならないように各医育機関の定員を10%減らすことを閣議決定した。ところが、実際には医師不足で地域医療が崩壊し始め、この夏には厚労省が医師不足の地域の医育機関で増員を認めている。
とはいえ、年間5,000名の医師が増加している状況で、何故自治体病院の医師不足が解消しないのかは様々な意見がある。都市部への医師の集中、学閥支配による人材流通の硬直化、働き盛りである30歳後半~40歳台の医師の個人開業志向など、諸条件が絡み合った結果として今に至ったのである。しかし、有力な民間医療機関は臨床医研修に注力し、自ら医師を育てて確保する対策を講じてきた結果、医師不足とはなっていない。良い指導医がいて研修体制ができていれば医師は集まるのである。
例えば、千葉県旭市(人口約4万人)にある国保旭中央病院(平成17年7月1日より市立病院)は、30人以上の大学教授のほか多くの病院長を輩出している。開院以来47年間にわたって病院長を勤めた故諸橋院長の「医師は全てを患者さんに捧げるべきで、24時間勤務が当たり前である」との信念を引き継いで、医師は全員が敷地内かその近傍に居住しており、他の病院より激務にもかかわらず医師不足は深刻ではない。しかも、病院全体の医業損益は黒字状態で、他会計繰入金はなく独立採算事業である(在宅介護支援センター、配色サービスの委託事業は除く)。
高給の提示だけで医師が確保できるのではなく、“医業に対するビジョン”がなければ良い医師は集まらない。
「自治体病院だから赤字でもしょうがない」という意識で経営されている病院では、いつまでたっても医師不足で、赤字が拡大していくことになる。
3.おわりに
自治体病院の経営改善の取組みは、全国の自治体が都道府県、市町村を問わず実施して、地域の解決策を探している。首長、議員だけでなく、住民も現実を直視した上で、地域の医療サービスとして“行政がどこまで関与するのか”をしっかりと議論する必要がある。この問題に対する解決策は「民営化すれば解決する」というような唯一の解答は存在せず、地域の環境、特性によって様々な方策が導き出されるはずである。基本的に民営化できるのであれば民営化すべきである。自治体にとってはオフバランス化による将来債務の削減によって、地域の福祉政策や健康政策に予算を振り向ける事ができるようになる。あるいは民営化できなくても、MBO(Management Buy Out:経営陣による企業買収)に近い形で医療従事者に病院経営を実施してもらうスタンスが重要である。自分達のこととして問題を捉えて、第三者も含めて最適解を導き出していくべきであろう。
日本総研が事務局となって10月5日(木)に「第一回自治体病院 再生・民営化検討研究会」を開催する。自治体病院の再生・民営化の道筋を立てる事を目的に立ち上げたが、当初予想を上回る参加申込みがあった。11月、12月にも開催予定であり、是非参加して各病院の目指す道を見つけていただきたい。
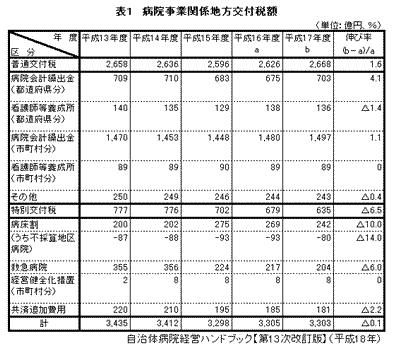
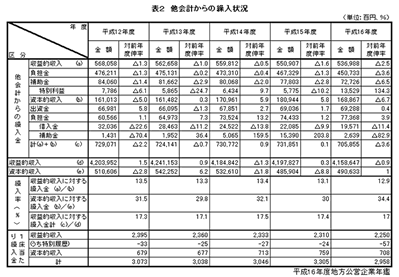
参考文献
- 自治体病院経営研究会(2006)『自治体病院経営ハンドブック〔第13次改定版(平
成18年)〕』(ぎょうせい) - 武弘道(2005)『こうしたら病院はよくなった!』(中央経済社)
- 総務省(2006)『平成16年度地方公営企業年鑑』
- ぎょうせい『月刊ガバナンス 9月号 No.65/2006』
- 医学書院『病院 Vol.64 No.9 2005』

