コラム「研究員のココロ」
従業員は費用か資産か?
~ファイナンス理論を応用した人的資産リスクマネジメント~
2006年06月19日 平康 慶浩
1.人を雇うと費用が発生する?
人を雇うということは会社にとって当たり前のことです。社員を雇う、派遣社員を雇う、アルバイトを雇う、などなど・・・。よほどの知的財産に基づくビジネスか、アウトソーシングを徹底していない限り、会社は社員(厳密には従業員)で成り立っています。
さて、この社員ですが、会計処理上は費用科目に分類されます。月給、あるいは賞与を支払うことで社員は会社に所属しますが、月給も賞与も会計上は費用だからです。
本稿では、この常識ともいえる「人件費の費用計上」をもう一度考えてみたいと思います。
その理由は、それぞれの会社における人件費の意味を考え直すことで、短期、長期に関わらず、企業価値の維持、拡大をさらに手助けするためです。(例えば成長している会社で社員を一気に増やしたりします。一方、衰退しつつある会社で一時的に社員を解雇する場合があります。いずれも短期的な視点での雇用調整であり、人を雇うことに対するリスクにまで踏み込んだ発想が不足している可能性があります。)
しかし、実際に会計上費用計上されている人件費をいきなり考え直すといってもわかりづらいかもしれません。
ではこういいなおしてみるといかがでしょう?
人件費は確かに費用ではあるけれど、人を雇うということは月々の費用としてだけ考えることのできるものではない、と。
例えば月給20万円の正社員を雇うとします。賞与は年間4ヶ月とすると、この人にかかる年間の人件費は320万円です。
では会社にとって、この人を雇うという意思決定は、320万円の買い物をするのと同じ意味でしょうか?
多くの会社での採用稟議では、これがあたかも320万円の買い物であるかのように扱われているようです。新卒採用についてはまだじっくり検討されますが、中途採用については特に、採用する人の年収がそのまま費用であるかのように考えられます。
これは本当に適切な考え方なのでしょうか?
2.リース資産としての人件費の計算
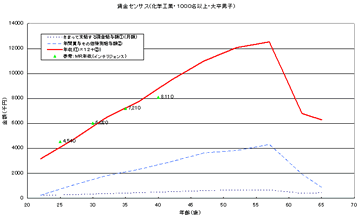
本稿では一例として、製薬業界におけるMR(医薬専門の営業職)についての分析を行います。
まず上記の図は、賃金センサスをもとに化学工業/社員1000名以上/大卒男子についての平均年収の年齢別変遷を示したものです。内訳は月例給与と賞与からなっています。なお、データの信頼性を補完するために、(株)インテリジェンスの求人情報からピックアップした、MR(医薬関連の営業社員)標準年収を年齢毎にプロットしています。
22歳の大卒時点で年収が300万円台であっても、50歳代後半には1200万円まで年収は増加しています。なお、これは賃金センサス上に製薬業界という分類がなかったための暫定措置ですが、一般にMRという職種ではさらに人件費が高いことが一般的です。
ですから上記は少なくともこれくらいの人件費が発生する、という基礎数値としてお考えください。
さて、このグラフから考えられることは、例えば週刊誌などで行っているように、人件費の総額を計算することです。上記の例ではこれは3億7千万円ほどになります。しかし、人を雇う場合の費用はその年度の年収分しか発生しません。将来一人づつ平均して1200万円払うとしても、今はそこまで考えなくてすみます。また一定の歴史を持つ会社であれば、すでに1200万円を支払っている社員がいるので、次の世代の社員が順々にその報酬額にシフトしていくことになります。そのため人員構成が若干変わったとしても、総額人件費は大きく変わらない人材の循環状況が作られているかもしれません(例えば全ての年次に社員が一人づついれば、一人新入社員が入る毎に一人定年退職するので、総額人件費は変わらないとする考え方です。これが定期昇給の基本的な理論背景になります。もちろんいまどきそんな会社はほとんどありませんが。)
本稿ではここで、「現在価値」という概念を用います。
現在価値とは、将来払う/手に入る金額が、今、どのような価値を持っているのか、ということをあらわしたものです。例えば今手元に10万円あるのと、1年後に10万円もらえるのとでは、多くの場合、今の10万円の方が価値があります。1年後の10万円は今の10万円よりも価値が低いわけです。では、1年後の10万円は今の価値にすればいくらか、といえば、これは逆に今10万円借りたら1年後にいくら返さなければいけないか、ということで計算することができます。
現在価値を計算する場合、10年国債の金利や長期プライムレートの金利等を用いて計算することが多いのですが、今回はこの金利水準を1.8%として考えます。
さて、金利水準が1.8%であるとするならば、10万円を借りたら1年後に1800円を利息として払うことになります。逆に1年後に10万円返すと考えれば、今98231円を借りることができます。この「98231円」が10万円の現在価値です。
では図1に示した人件費の現在価値は?
計算方法は割愛しますが、3億7千万相当の人件費合計の現在価値はおよそ2億5千万円ほどになります。58歳のときに支払う 1000万円相当の年収は、現在価値に割り戻すと520万円ほどになるのです。
もし今この社員を採用するときに、一括で2億5千万円を渡し、年収以外を自分で運用するようにすすめたとしましょう。すると、この社員は年利1.8%で運用している限り、図1のグラフとまったく同じ年収をそれぞれの年に受け取ることができます。
さて、上記の分析から皆さんは何を感じ取られたでしょう?
入社時点で2億5千万くれたら、自分ならもっとうまく運用するのに?もちろんそう思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし会社の側から考えると、この人件費というものが、実はとんでもないものであることがお分かりいただけますでしょうか?
図1を前提にするならば、この会社では2億5千万の「資産」を、年利1.8%の分割払いで購入していることと同じなのです。
言い換えると、人件費は毎年発生している費用ではなく、すでに発生している巨額の費用を毎年利息をつけて按分しているに過ぎない、と考えることができます。
故に、人件費とは単純な費用ではなく、人という資産をリース購入した費用の割賦費用である、と言い換えることができます。
良く論じられる「人件費リスク」というものは実は「人的資産リスク」なわけです。これが本稿の第一のポイントです。
| ポイント1: 人件費とは人的資産のリース費用である。故に人件費リスクや雇用リスクというものは、「人的資産リスク」と言い換えることができる。 |
3.今の採用と退職の方法では人的資産リスクを回避できない!
このように考えたとき、1章での採用稟議の考え方が誤っていることがご理解いただけると思います。たとえ300万円少々の年収で社員を雇うとしても、それは数億円(業界によって幅はありますが)の資産をリース購入することと同じことなわけです。新卒社員だとこれは少なくとも人事部長以上の決裁が必要かもしれませんが、例えば事業部門の営業社員を中途で採用する場合など、極端な場合、課長クラスに採用権限が付与されている場合もあります。これは、課長クラスに少なくとも1億円以上の資産購入の決裁権限を与えていることと同じ意味になるはずなのですが、なかなかそのように理解されている会社は少ないようです。
では採用権限が資産購入よりも簡単に与えられる理由を考えて見ましょう。
これは二つの手段が会社に与えられているからだと考えられます。ひとつは解雇/退職であり、もうひとつは年収調整です。
何らかの理由で社員を雇い続けることができなくなった場合で正当な理由がある場合、会社は社員に退職してもらうことができます。退職金のある会社の場合は一時的費用が発生しますが、定年退職までの間に支払う可能性のある給与額と比較すれば少額な場合がほとんどです。ただ、退職による雇用調整は労働者保護の観点から難しい場合も多いのが実態です。
そこで次に、さまざまな手法での人件費カットが考えられます。いわゆる「成果主義人事制度」もこの考え方の延長にあるものですが、会社、部門あるいは個人の業績にあわせて年収を変動させることで、会社側のリスクを調整することができます。成果主義人事制度でも間に合わない場合、一律の賃金カットが行われる場合もあります。
このように会社は短期雇用調整と年収調整という二つの方法で、人件費のリスクを調整することができるわけです。
しかし実際にはこれらの方法だけで、人的試算リスクを調整することができるでしょうか?
人的資産リスクとはすなわち、会社にとっての収益変動のリスクであると言い換えることができます。例えばこれを売上高で測ってみましょう。
1995年から2004年の製薬業界115社を例に分析したところ、毎年の売上高変動率は12.22%であるという結果がでました。これは売上高変動率の標準偏差として算出したものですから、およそ68%の確率で売上高は前年の±12.22%の範囲に含まれるということになります。
この変動率(以後ボラティリティという表現を使います)で4年間の売上高変動の確率を見たところ、4年目になると初年度を100%とすると174.4%~52.4%の幅で変動する可能性が高いことがわかります。
ここで売上高が初年度の100%を切る可能性は50.88%になります。そしてこの50.88%について下回る金額の率は5.53%というように計算できます。
(このあたりの計算方法は書き出すと長くなるので、紙面上割愛させていただきます。要は製薬業界では4年間で、ほぼ半分の確率で売上が約5%下がる可能性があるという風にご理解ください。)
このことから、製薬業界においては売上高を基準にする場合、5.53%の長期費用リスクが存在するということがいえます。そして例えばMRという売上高に直結する職種においては、この長期費用リスクがそのまま人的資産リスクとして顕在化する可能性があります。
4.「便益」概念で人的資産リスクを回避する
この例では人的資産リスクを売上高のボラティリティで説明しましたが、これ以外にも商品開発サイクルや人材の付加価値などで計算することもできます。例えば製薬業界では新薬上市時(註1)の売上高変動サイクルが7年であり、上市初年度と4年目の製品売上高比率が1:6程度になるという分析結果があります(2005年実施 平康)。
いずれにせよ、これらの分析から、会社にとって、人的資産というものが大きなリスク要因であるということが言えるわけです。
ではこのリスク要因を回避するために会社が実施すべき対応にはどのようなものが考えられるでしょう。
ここで人的資産リスクの内容を、もう少し具体的に考えて見ましょう。
例えば年収1000万円の社員がいるとします。この人がもし毎年1000万円以下の利益貢献しかしてくれないのであれば、この人は会社にとってお荷物社員ということになります。しかし例えば5000万円以上の利益貢献をしてくれていれば、この人は会社に毎年4000万円の利益をもたらしてくれる素晴らしい社員ということになります。
よって人的資産リスクは、その人件費の多寡よりも、「貢献してくれる利益-人件費」で測る方が適切だといえます。
また、今年貢献してくれなくとも、在職している期間を総合してプラスであり、かつその変動の幅が収益のボラティリティを下回るものである場合には十分に意味のあるものです。
これを「便益」という単語であらわします。
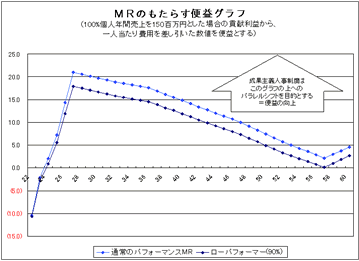
この図は業界で標準的なMRについての便益をグラフ化したものです。またMRの中でも通常のパフォーマンスを発揮する人と、それよりも若干パフォーマンスが低い人(90%相当)とがいる可能性を考慮して、グラフにしています。
このグラフが常に0以上の位置にある場合、会社にとっての便益が高くなりますし、その水準が高ければ高いほど収益に貢献してくれることになります。逆にこのグラフが下に下がれば会社の便益が下がることになります。
これが本稿の第二のポイントです。
| ポイント2: 従業員の生み出す効用を企業収益、あるいは職種に強く関わる財務指標で把握する。そこから各年度の従業員にかかる総費用を減じたものを人的資産の「便益」として定義する。 |
さて、いわゆる成果主義人事制度をはじめとする人事制度改革は、多くの場合このグラフを上に移動させる効果を期待して実施します。以下にその方法と効果を列記してみます。
- 業績にあわせた報酬変動
- :業績にあわせて費用を変動させるので、便益そのものを向上する可能性がある。
- 各種指導的評価制度(コンピテンシー、目標管理など)
- :業績を上向ける効果を期待する。その結果同程度の費用でも便益が向上する。
- 教育研修制度、キャリアパス構築
- :業績を上向けるとともに、ローパフォーマー発生リスクを低減させることを期待。
- 退職金制度、早期退職制度
- :費用リスクを低減させる。
5.人的資産リスクのポートフォリオマネジメント
成果主義人事制度をはじめとする人事制度改革は、企業にとっての便益を高める、あるいはリスクを低減する効果を期待して実施するものであるということがわかります。
もちろんその結果として、モチベーション=人の心に与える影響や、組織風土の変革といった要素を見過ごすわけにはいきませんが、経営の観点からは従業員トータルでの便益向上が目的となります。
各種人事制度改革の経営上の意義、あるいは改革の定量的効果を測るためには、人件費というものが単年度の費用リスクではなく、長期間保有する資産としてのリスクをもつという考え方をします。そしてこのリスクを低減することが今後の企業価値向上のために必須となるのです。
しかし人事制度改革だけで本質的な人的資産リスクの低減は、実は困難です。
前述の製薬業界の例で言うならば、4年間で5.53%のリスクが生じるわけですが、38年間で見ると、このリスクは極めて大きな数値になります。これをすべて業績に基づく賃金制度や教育研修体系の整備で回避することが可能でしょうか。
そこで人的資産リスクを本質的に回避するための手法として、「人的資産ポートフォリオ」の構築をお勧めします。
これは会社のビジネスに必要な人材をいわゆる「正社員」のみで検討するのでなく、有期雇用社員やパートタイム社員等で構成することです。
もちろん多くの成功している企業において、有期雇用社員やパートタイム社員の有効活用をすすめておられます。故に、「人的資産ポートフォリオ」の概念だけであれば、決して目新しいものではありません。
しかし本稿のポイントはポートフォリオを企画業務とルーチン業務、雇用期間の長短といった縦横の軸で区分せず、企業にとっての「便益」を軸にして、雇用形態毎、職種毎の従業員との相関を分析し、さらに共分散による定量的分析を行うことにあります。
これが本稿の3つ目のポイントであり、結論でもあります。
| ポイント3(結論): 従業員を人的資産として定義する(ポイント1)とともに、従業員が生み出す収益への影響を便益として定義する(ポイント2)ことで、定量的に雇用と報酬額のポートフォリオを構築する。 これが「人的資産ポートフォリオ」である。 |
そのためには、ビジネスモデルに基づく便益の分析が必須となります。
一人ひとりの社員による付加価値創出が重要なビジネスと、社員の代替可能性が高いビジネスとでは人材雇用ポートフォリオも大きく異なってきます。
人材による付加価値の創出、ノウハウの再生産などが求められるビジネスにおいては、コア職種においていわゆる「正社員」雇用に意義があります。採用時の選別とその後の教育により、社員それぞれの現在価値を高めていくことが競争力の源泉になります(註2)。
一方で、一定のビジネスモデルを倍数展開するなどの業態においては「正社員」雇用は高いリスクを持ちます。このようなビジネスには、例えばチェーン展開をしている小売業などが当てはまります。しかしそのような会社で、正社員と有期雇用社員の割合などについて明確に定めている企業はそれほど多くはありません。どちらかといえば、アルバイトなどについては各店舗の店長裁量で採用退職を管理しているところがほとんどです。このような方法では、資産としての人材についてリスクマネジメントはとうていできません。
6.人的資産のポートフォリオマネジメントが生み出す効果
ここまでの議論で、人件費をリース資産の割賦費用と見るということ(ポイント1)、従業員がもたらしてくれる企業収益への貢献を便益概念で把握すること(ポイント2)、これらの考え方に基づく雇用と報酬のポートフォリオを定量的に構築すること(ポイント3)などを説明してきました。
これらの考え方の最大の目的は、企業としての収益を最大化する、という点にあります。
そしてこの目的は、企業の存在意義と直結するものです。
例えばこの方法を適用することで、以下のような分析を定量的に実施できます。
- 管理職と一般社員の人員構成比と、それぞれの適正報酬額の算出
- 店社員とアルバイトの構成比、それにともなう社員、アルバイトそれぞれのキャリアパス構築
- サプライチェーンを構成する各職種毎の人員構成比と適正報酬額の算出
- 営業職の外部業務委託比率と、委託単価の算出
「当社では人材が最大の資産です。」
「当社では従業員を人財として厚遇しております。」
しかし、経営の根幹となる会計処理上は、従業員を資産としてみるように区分されていません。
そして、短期雇用調整や年収調整は、その人材/人財をあたかも原材料費として扱うような、近視眼的な発想でしかないものです。
本稿のアプローチによって、経営の現場で、従業員が本当に資産として大切に扱われることになり、そのことでそれぞれの企業業績が更に向上することを願ってやみません。
- 註1:
上市とは研究開発段階を完了した薬剤が製品として市場に出回ることで、「じょうし」と読みます。製薬業界では一般的な用語として使われています。 - 註2:
従業員教育という取り組みについても「人的資産」として従業員を定義することでアプローチを大きく改善することができます。教育とは人的資産への再投資であり、便益を高めることが目的となるものです。故に便益に直結する再投資をタイムリーに実施することが従業員教育の根幹となります。この考え方と、人的資産ポートフォリオにおける報酬水準の定義により、従業員のキャリアパスについても大きく改善することが可能です。
分析協力:クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社 イノベックス事業本部
了

