コラム「研究員のココロ」
自治体の仕事を考え直す時代:「人材ポートフォリオ」の導入を
2006年05月29日 山本辰久
1.再考すべき自治体の業務内容
数年前の正月、元同僚である地方公務員の知人から届いた年賀状に、一言書き添えてあった。「公務員冬の時代です。」厳しい財政状況のため、新規事業が削減され、限られた予算の中で職務を果たさねばならず、個人の士気にも影響が及びかねない様子がありありと伝わってきた。
かつては自分も働いた場を表現する言葉として、当人の気持ちを思うと非常に複雑な気持ちではあった。とは言え、今後、自治体の財政状況が画期的に好転することは、残念だがあまり考えられない。転職した身ではしょせん他人事の発言と言われるかもしれないが、「冬」だと感じてしまう価値観を変え、前向きに働ける新たな視点を見つけることが大事ではないだろうか。
これまで自治体の担当者は、使った予算額や出来上がったモノを見て仕事の達成感を得て来た。特に、その仕事がトップから政策的に重要視されていればいるほど、申し分無いものであった。しかしそれは、市民の視点から見たとき、真に正しい価値観と言えるものだったのだろうか。最近になって、事業の成果や顧客満足度により仕事の達成度を測定する「行政評価」の考え方が広がっていることは、評価の難しい行政に新しい価値観のヒントを与えたと言う点で、一歩前進だと感じている。
そして、この種の問題を根本的に解決するには、さらに人事政策面からの「治療」も必要であるとの確信を、最近新たにしている。
昨年度当社では、人事制度改革に積極的に取り組まれている自治体の方々や、民間企業の組織論を専門とする研究者のご参加を得て、「自治体における人的資本活用研究会」を運営させて頂いた。その場では、「財政制約と人材育成のバランスを取ることが難しい」、「非正規職員が正規職員より高度な業務をしている例もある」等、課題の多い現場の生の声をお聞きすることが出来た。
行政改革の大きな流れの中で、各自治体は経費削減あるいは新規採用の抑制に取り組んで来た。しかし、現行の枠組みの中では限界が見えており、さらなる改革のステップに進むには、「自治体の仕事とは何か」、また「求められる職員像とは何か」について、抜本的な再検討の余地が有るということだ。団塊世代職員の大量退職は、その状況をさらに深刻なものにするだろう。
2.「自治体版人材ポートフォリオ」の活用
今後の自治体人事改革の一つの視点として、自治体の所管する各業務の特性をもとに、それに合った人材をポートフォリオの形で明確化し、適材適所の配置を図るという「人材ポートフォリオ」の活用を提案したい。
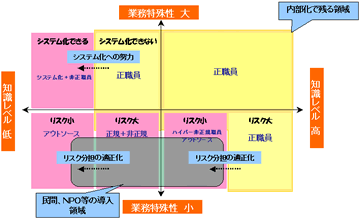
人材ポートフォリオについては、元来民間企業に即した分類が示されている(注1)が、ここでは自治体業務を、求められる「知識レベル」と「業務の特殊性(各自治体固有の特殊性)」の2つの評価軸の大小により類型化することとする。
それぞれの特性によって、外部化の可能性の高いもの、内部に残すことが望ましいものなどを分析した後、さらに人材の適正配置を進めるために、(ITCなどを活用した)システム化による知識レベル制約の軽減、契約上の工夫等による問題発生時のリスク分担の適正化など、補完的な仕組みを併用するものである。これらにより、人材の有効な活用を図りつつ、民間企業やNPO等の活躍の領域を拡大することも出来る。
以上のような、人材ポートフォリオ作成の過程を通じて、自治体業務の棚卸しと在庫の再整理が可能になり、より望ましい人材配置の姿が明らかになるのである。
ところで、実際の現場での適用にあたっては、多岐にわたる自治体の業務を、具体に類型化していくことが必要となる。類型化のためのマニュアルの決定版は存在しないため、担当課を加えて十分に検討することになるが、ここでは、これまでのような言い訳を通じさせてはいけない。例えば、「知識レベル」に関して、「豊富な行政知識が必要」という表現が、これまでも外部化を阻む理由として何かと安易に使われて来たが、果たしてそれぞれの業務について本当にそういい切れるのか、厳しく判断することになる。また、「『おらが村』ならではの個性」も「業務特殊性」として主張されそうな点だが、幸か不幸か、我が国の行政制度や自治体政策には全国共通・横並びのものが多いということが、しばしば忘れられている。ノウハウを他の自治体と共通化出来る業務は、案外多いはずだ。
また、必ずしも全ての業務について網羅的で緻密な類型化を行う必要はなく、2つの評価軸に沿って、各業務の大まかな特性を確認するだけでも意味はある。例えば、「優先的に内部に残す方向で、まずは職員の関連スキルを磨くべき業務」、あるいは「将来の外部化を目指して、当面は効率化を進めるべき業務」といった形で方向性を整理し、一連の業務改革・人事制度改革にじっくり取り組む、というアプローチもあることを指摘しておく。
3.市民・職員双方へのメリットを期待
最後に、行政における人材ポートフォリオ活用の大きな目的は、限られた人材が最大限に能力を発揮できる業務を担当し、当の職員だけでなく、対価を払ってサービスを享受する市民を含む全ての関係者が、よりハッピーになれる仕組みを作っていくこと、と位置づけるべきである。
単なるリストラ論議で終わるのではなく、地域の貴重な人材資源である自治体職員が高いモチベーションを維持する原動力となることにより、市民の利益にもつながることが重要、ということである。
その結果、市民にとっての行政サービスへの満足度が高まるとともに、職員の方からも「役所も少し遅い春を迎えました。」というコメントが聞けるように!

