Sohatsu Eyes
都立病院PFI:落札者決定
2006年02月12日 工藤 真紀
去る1月31日、東京都の病院PFI事業にて落札者が決定した。まずはこの壮大な事業を進めてこられた発注者である東京都関係者の方々、すべての応募者の方々に心より敬意を表したい。アドバイザーという当事者より一歩引いた立場からしても、長年の検討がまずは結実したという感慨がある。
本事業の事業者選定の特徴は、応募者がマネジメント力に優れた「サービスプロバイダー」であることを重視するというコンセプト主導の設計が全般的になされた点と、病院PFIとしては初めて一般競争入札による事業者選定を行わなければならなかったという2点に集約されると考えている。
その特徴にともなう技術的工夫をこの場で全てご紹介するわけにはいかないので、ここでは1点だけ触れさせていただく。すなわち、今回の審査結果(東京都HP参照)を見ていただく際には、今回の事業者選定の以下のような特徴に留意いただきたいということである。
今回の発注者には業務の質を向上させてほしいという想いが強くあり、評価体系が価格のみの勝負ではないことを示す必要があった。価格点90点に対して性能点が210点という配点で性能点の比重が高くはあったが、質が大きな要素であることをより明確に示すため、性能点は評価項目ごとに順位付けを行い、1位に満点、最下位である3位に0点、2位にその中間点を配点するという方法をとり、性能点の配点そのままの差がつく可能性のある体系とした。これにより、性能点で大きな点差がつく評価体系となった。
これを可能にしたのは、性能評価を行った応募者は、全て本事業の事業者として「適格な応募者」であることをあらかじめ実質的に審査されていたという前提があったことによる。具体的には、5月の資格審査にて経営担当チームを対象とした面接を含めた実質的な能力審査を行なった他、12月に提出された入札書類の審査については性能点の評価に先立ち、全ての業務について要求水準を満たした業務が実施可能であることを「基礎審査項目」として実質的に審査を行った。
今回は結果として応募者間で大きな点差がついたが、あえて性能点で大きな点差をつけるという審査の技術的な特徴によるものであり、能力の絶対差を示すものではない。性能評価に先立つ実質審査を通過して残った3グループは全て、「サービスプロバイダー」として優れた能力があり、本事業の事業者として適格な応募者であると評価されたということをご理解いただければ幸いである。実際3グループの提案はいずれも、過去に例がないほど素晴らしく優れたものであったと個人的には感じている。
東京都という大舞台で繰り広げられた本事業は、多くの方の知恵と苦労が詰まっている。病院PFIに関心を持つ自治体が増えている中、本事業の経験を後続に生かしていけるよう努めたい。
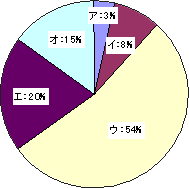 左図:自治体の病院PFIに対する関心
左図:自治体の病院PFIに対する関心ア:既に実施済みである。
イ:実施を検討している。
ウ:実施を検討してはいないが関心はある。
エ:関心がない
オ:その他
(2005年 日本総合研究所 調べ)
関連資料:公立病院における民間活用手法に関するアンケート調査結果概要
http://www.jri.co.jp/thinktank/sohatsu/pfi_ppp/report/051025.pdf
※eyesは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

