コラム「研究員のココロ」
知的資産経営のすすめ
~ 断片的な情報から、体系化された知的資産の活用へ ~
2005年10月03日 井関貴資
1.知的資産経営とは
21世紀は「知識」の時代だと、盛んにメディアでは喧伝されている。実際に、「社内での知識共有(Knowledge Management)や、知識を活用することが、企業が成長するためには必要な要件である」とか、「単なる「情報」の束を「知恵」と化することが強い企業である」といった言説が後を絶たない。少なくとも企業経営において、有形のものである資本金や製品、設備などの「カネ、モノ」という「目に見える(Tangible)」資産だけで企業の価値を把握することができるという幻想は、企業戦略における特許などの知的財産権の重視やブランド戦略の隆盛などを鑑みると、既に消滅していると考えられる。
その背景には、90年代においてインターネットが全世界的に普及したことによって、既存の高度工業化社会がパラダイム・シフトを起こし、また情報化・メディアの多様化の加速度的進展が、これまで重要視されてきた資産の重要性を相対的に低下させたことが挙げられるであろう。すなわち、「カネ、モノ」を持つことよりも、むしろ「必要な情報をいかにメディアなどを駆使して即時的に得ることができるか」が企業の競争力の源として考えられるようになってきた。
しかしながら、これだけ情報の非対称性が進展すると、単なるバラバラの情報を手に入れるだけでは、このグローバルな環境下で企業が競争的な優位に立つことは困難である。今や特別の専門家だけが知りうる情報は少なく、大抵の情報は容易に誰でも入手可能な環境下に我々は置かれている。
そこで、注目される概念として出てきたのが、「知的資産経営」である。その概念は、以下のような特徴を有する。
|
これらに注目して、「目に見える価値」だけでなく、「目に見えない(Intangible)価値」をも即座に把握し、それらを収益に結びつけることが、企業が競争力を高めるためには必須であるという考えが、「知的資産経営」のコンセプトである。
2.知的資産の分類
前述した知的資産は、どのように分類できるのであろうか。以下の図で、企業における各種資源をブレイクダウンしたものと、その具体的な例を挙げた。
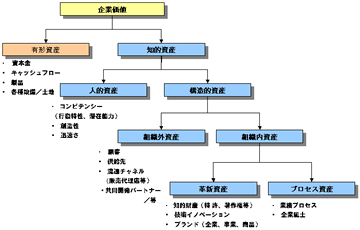
(パトリック・サリヴァン著)を参考にして、筆者が再整理及び改変)
企業における資産とは、これまでは有形資産における価値(図左部)のみが強調されてきたが、実際は「知的資産」(図右部)の比重が極めて高く、これが株価・企業価値、更には企業の競争優位性を測る上で重要な部分を占めていることが、この図を見ると把握できるであろう。
「モノ・カネ」とともに、経営の3要素と言われてきた「ヒト」、つまり「人的資産」に関しても、単なる労働力ととらえるのではなく、独特のコンピテンシー(行動特性、潜在的能力)を持つ資産ととらえることにより、知識社会における人的資産の有効的な活用が可能になるであろう。
また、「構造的資産」として、「組織外資産」と「組織内資産」に分類した。まず組織内資産には、その企業が独自に築き上げてきた「プロセス資産」が存在する。具体的には、その企業にしか保有されていない業務プロセス(例を挙げれば、トヨタのカンバン方式など固有のノウハウ)や独自の企業風土などは、知的資産として軽視できない資産である。さらに、「革新資産」とは、その企業が保有する知的財産権(特許、著作権、企業機密など)、および技術などのイノベーション、および各種ブランド資産(企業ブランド、事業ブランド、商品ブランドなど)が存在し、企業の優位性を示す指標として重要である。
さらに、企業同士のM&Aや業務提携が増加している現在では、自社以外の資産を積極的に評価することも肝要である。資産の模倣が買収などの戦略により、容易かつポピュラーになっているため、単に自社が持ちうるコア資産だけでなく、企業と密接に関連した関連主体(顧客、サプライヤー、販売代理店、アライアンス・パートナーなど)も、「組織外資産」として考慮することは、企業が競争優位を保つ視点から鑑みても肝要であろう。
3.知的資産に関する政府や企業の取組み
知的資産という言葉は使われていないものの、無形資産の重要性に注目した研究は、我が国でも経済産業省を初めとして、多くの機関でなされてきた。具体的には、古くは昭和49年に通商産業省内に設置された企業経営力委員会で、財務諸表による分析のみでは考慮され得ない、組織構造、研究開発、リーダーシップ、マーケティング等の定性的要因を「経営力」として評価しようという研究が先駆けて行われた。
しかし、「知的資産」というコンセプトに関する研究が脚光を浴び始めたのは、北欧を初めとする欧州からであった。1990年代前半に、スウェーデンの保険会社であるスカンディア社は、知的資産に関する研究プロジェクトを立ち上げ、企業の年次報告書(アニュアル・レポート)に世界初とされている「知的資本報告書」を補足資料として発表した。そこでの知的資産の分類や指標が、世界的なモデルとなることとなった。
その後、欧州ではデンマーク・オランダなどでも知的資産に対する研究プロジェクトが政府主導で推進され、我が国でも21世紀に入り注目が高まってきた。
日産自動車や資生堂などの海外の動向に敏感な企業では、知的財産や企業ブランド、ステークホルダー等を知的資産として認識・評価し、企業経営に積極的に活かしている。また、日立製作所や武田薬品工業等、我が国におけるリーディング・カンパニーも、知的資産経営のコンセプトを導入し、それぞれの資産を評価・算定し、企業価値を高めるための取組みを行っている。
将来的には、前述のような大企業だけでなく、社内における資産が限られている中小企業こそ、知的資産経営の考え方を導入すべきであると考える。
4.知的資産経営の実現のための方法論
知的資産経営の実現に向けて、まず自社の資源の棚卸しを行う必要がある。最初のステップとして、自社のコアとなる資産がどこにあるかを適切に評価し、また足りない資産は何かを明らかにすることが求められる。
特に、十分な社内資産を持たない中小企業は、組織外資産に着目して、それらを取り入れる可能性について積極的に吟味する必要がある。
自社のコア資産の抽出、および各種資産の強みと弱みについて、格付け手法等により評価した後に、それに即した「企業ビジョン」を構築する。
その後、「ミッション・ステートメント」すなわち企業が果たすべき役割・機能を明らかに公言したものを策定し、それを具体的な「イニシアティブ・プラン(優先されるべき行動プラン)」にまで落とし込む。それらは、「KPI(Key Performance Indicator:鍵となる達成指標)」により、定期的に評価され、見直されなければならない。知的資産経営を導入するためのステップとやるべき事、その際の留意点を纏めたものが以下の図になる。
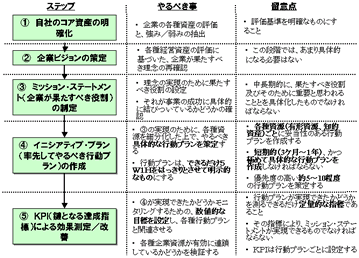
上記の知的資産経営を企業に導入するステップは、あくまで汎用的な方法論である。導入段階において最も苦労するのは、知的資産を定量的かつ的確に評価することが困難なことである。この問題に関しては、世界的にも様々な研究が成されているが、決定的な手法は開発されていないのが現状である。
しかしながら、各種資産価値を適切に測定・評価し、それらを効率的に運用するためのグランド・デザインを描くことは、長期的には各企業の競争力向上に必ずや資することであろう。それは、21世紀における「知識創造型社会」を生き抜くための必須条件とも言えよう。知的資産経営の実現のために留意すべき点は、以下であると考える。
|
【参考文献】
- 「知的経営の真髄~知的資本を市場価値に転化させる手法~」(パトリック・サリヴァン著、東洋経済出版社、2002年)
- 「産業構造審議会 新成長政策部会 経営・知的資産小委員会 中間報告書(案)」(経済産業省、2005年6月10日)

