コラム「研究員のココロ」
人、まち、ものが一体となった地域ブランドの形成
2005年09月12日 金子 和夫
地方自治体や商工団体で、地域ブランド論議が活発であるが、地域ブランドとは何か、よくわからないという意見を聞く。ここでは、地域ブランドの成功ポイントについて検討してみたい。
1.地域ブランドとは何か
ブランドとは、商品やサービスを他の生産者のものから区別するために、商品につけられる生産地や生産者の名である。商品名にブランド名をつけることで、市場における差別化の効果が生まれる。商品の基本的な価値に、さまざまな情報価値を加えて、従来の品質重視の商品づくりから、ブランド重視の商品づくりへ展開して、商品のブランドを確立することができる。
生産者にとっては、商標権などによる商品特徴の保護、他生産者との差別化、市場におけるポジションの明確化、競争相手に対する優位性の確保、値引き販売の回避が可能となる。また、長期的にロイヤルティの高い顧客を確保でき、売上高の安定をもたらし、利益率の向上を図ることができる。
ますますきびしくなる産地間競争、国際競争の中で、それぞれの産地が生き残っていく上で進められる製品差別化戦略と表裏一体となって展開されるのが、地域ブランド戦略である。
2.商品・サービスと地域イメージの一体化を図る
地域ブランドには、「地域発の商品・サービスの高付加価値化・集約化」を軸とした地域ブランドの取り組みと、「地域のイメージの活用・展開を軸とした地域ブランド化」の取り組みの2つがある。このあたりが、よくわからないといわれる所以である。
地域ブランドを成功させるためには、商品・サービスの高付加価値化だけでなく、地域イメージのブランド化をセットで展開することが必要である。
前者は、地場伝統野菜のように、農家の有志が地場伝統野菜振興グループを形成し、栽培技術の普及に努め、独自の味を追求し、特徴ある伝統野菜を生産し、「安心・安全・美味しい」を前面に打ち出し、ブランド化を図るものである。
後者は、歴史的な町並み地区において、歴史と文化、産業などをストーリー性を持って展開し、買物や飲食だけでなく、観光など、参加体験型の観光を展開するものである。
各地で取り組まれている地域ブランドは、前者の商品・サービスの高付加価値化としての地域ブランドが多いが、個別商品・サービスの高付加価値化だけでは、消費者に訴求することが困難であるため、後者のような地域イメージの形成と活用を含めて展開することが必要である。
つまり、地域ブランドは、「地域発の商品・サービスのブランド化」と、「地域イメージのブランド化」を結びつけて好循環を生み出すことが求められる。
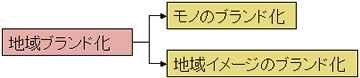
3.地域ブランドづくりの成功6か条
地域ブランドの取り組みは始まったばかりである。これから取り組もうとする団体は以下の点に注意していただきたい。
(1)地域の特性や資源について、十分検討する
地域ブランドづくりには、地域に対する理解と愛着が必要である。地域にはどのような資源があるか、「ワークショップ」や「まち歩き」でじっくり調査してほしい。
長野県小布施町では、江戸時代に地元に滞在した画家葛飾北斎の作品を地域の資源として、文化の香り豊かな栗菓子の里を形成することに成功した。
(2)消費者ニーズに対応した商品開発に取り組む
ともすれば、生産者発想の商品開発になりがちで、どこのだれに売るのか、理解に苦しむ商品がよくある。消費者の声を直接聞いたり、バイヤーやクリエーターのアドバイスを受けるなど、消費者ニーズに対応した商品開発を心がけてほしい。
高知県馬路村では、杉の間伐材を活用したインテリア雑貨の開発に際して、首都圏で高感度消費者、クリエーター、バイヤーのグループインタビュー調査を実施して、商品開発の方向性を整理した。
(3)地域ブランドの送り手とビジョンを打ち出す
商品開発が先行して、いろんな商品が集まるのはよいが、地域の誰が何を伝えようとしているのか、わからないケースがある。地域ブランドのリーダーは誰か、どんな夢、ビジョンを伝えようとしているのか、しっかりと議論してほしい。
O市では、地域ブランドに取り組み、ハイテク分野から和菓子まで様々な地域ブランド商品を認定したが、地域のイメージ、送り手、ビジョンが拡散してしまった。
(4)商品に物語やデザインなどの付加価値をつける
品質や技術が優れているといった商品の基本的な価値だけでなく、地域や商品にまつわる物語や、すぐれたデザインなど、消費者にアピールする情報価値を考えることが重要だ。
岩手県遠野市では、「民話のふるさと」や「遠野物語」などのイメージを活用した地域ブランドに取り組んでいる。
(5)商品づくりと流通チャネルの検討を同時に進める
販売先の目処もなく、商品開発をしているケースが目立つ。むしろ、どこで誰に販売したいのかを明確にして、小売業と共同で開発するくらいの取り組みが望ましい。
新潟県五泉市では、ニット産地であるが、独自ブランド商品の開発と、東京・神戸のアンテナショップ開設を同時に推進した。
(6)ビジネス・モデル化を図る
地域ブランドは、単なる商品づくりではない。原材料に対する生産者のこだわり、町並みの整備、生産者と消費者を結ぶ流通チャネルなどを一体的なビジネス・モデルとして構築することが必要だ。
高知県馬路村農協は、ゆず製品で有名であるが、村内産のゆずに限定し、自社工場で商品化、電話・FAX・インターネットで消費者に直販している。
以上、地域ブランドについて、取り組みポイントを紹介した。地域ブランドは、自らの地域の資源を再発見して、地域の誇りと愛着を回復する取り組みであることから、小さな商店街や山村こそ、取り組んでほしいテーマである。
なお、次の論文も参考としていただきたい。
地域ブランドでまちおこし「-地域ブランドの効果的なマネジメント-」
(掲載:地域活性化センター『地域づくり』9月号<2002年>)

