コラム「研究員のココロ」
公共サービス提供におけるパートナーシップ
~ 財団法人北海道市町村振興協会 委託調査「これからの公共サービス提供のあり方研究」の成果と、それを踏まえた考察 ~ (後編)
2005年09月05日 矢ヶ崎紀子
前回は、財団法人北海道市町村振興協会からの委託調査「これからの公共サービス提供のあり方に関する調査研究」の目標、および、そのメインテーマであるパートナーシップとは何か、についてご紹介させていただきました。前回のポイントは、これまでの公共サービス提供の手法(縦糸)に、パートナーシップという手法(横糸)を加えることによって、足腰の強い地域経営(地域特有のタペストリー)が織り上げられていくということです。今回は、パートナーシップを進める手順、リスクとコスト等についてご紹介します。
パートナーシップを進める手順
「これからの公共サービス提供のあり方に関する調査研究」報告書(報告書名は「パートナーシップの実践」)のなかでは、パートナーシップの進め方として、以下の手順を提案しています(図表1)。もちろん、必ず以下の図のような順番で行うべきということではなく、一部は同時並行に行っていくことが現実的な場合もあります。パートナーシップはそれ自体が学習するプロセスですので、きちんと制度設計をしてから実施するよりも、試行錯誤の実験を繰り返しながら、徐々に成功体験を積み重ね、仕組みのブラッシュアップをしていくほうが、その地域に合ったよい仕組みができあがると思われます。
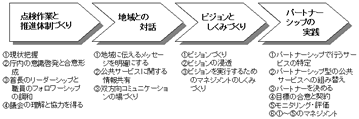
上記の手順の詳細な内容と留意点については、報告書本体の記述を参考にして下さい。ここでは、いくつものポイントの中から、特に重要な点を2つ紹介します。
- ポイント1
- 行政の役割の相対化:
- 行政を、公共サービスの提供の主体の一つとして、意識的に位置付ける
ただし、行政は、意識的に一歩下がるものの、単なる黒子になり下がって、“丸投げパートナーシップ”をすることは避けるべきです。行政は、他の主体を圧倒する質量の資源(人、モノ、カネ、情報、ノウハウ等)と権限を持っており、このため、行政には、他の主体が公共サービス提供に関与することを支援する役割を担ったり、長期的な視野に立って地域経営の方向性を検討したり等、地域においてパートナーシップという仕組みが健全に機能するための目配りをするという高度な仕事が要求されます。また、行政には、情報開示を積極的に行い主体間の情報の非対称性を軽減する努力や、NPO等市民団体や地縁組織等の資源の量に大きな差異がある主体と付き合う際の距離感覚に留意すること等も求められるのです。(図表2および図表3を参照ください。)
個人的な見解ですが、こうした高度な仕事をこなす行政職員の給与は削減の対象としてはいけないと思っています。(もっとも、今以上にたっぷり払えということもでありません。) しかし、知的レベルの高い仕事はその成果が目に見えない場合が多いことから、当初は、その仕事の高度さと重要性を理事者や幹部がよく認識し、行政職員が知的で創造的な仕事に専心できるような環境を作り上げていくことが重要なのかもしれません。
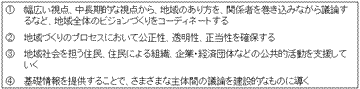
~行政職員に求められる資質~
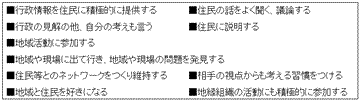
- ポイント2
- 住民の理解を得る
私もこういった批判は事実を言い当てている側面があると思います。しかし、的を得ているか、時宜を得ているか、というと、必ずしもそうではありません。今は、過去の責任追及を行っているような悠長な時間はないのです。私は、パートナーシップに誠実に取り組もうとしている地方自治体の職員にそういった質問を投げかける人に、逆に質問をしたい衝動にかられます。「では、お金さえあれば、よい公共サービスが提供できるのですか? それは、当事者意識のない第三者が、必要以上に高規格に提供する“豪華”なものになったりしないのですか?」
今は、過去のことはきちんと反省し、そこから改善点を見出すことで精算を行い、地域経営における“ヨコ糸”の強化を行うことが急務なのです。“ヨコ糸”の強化とは、サービスの受け手であった住民や企業等の意識、そして、なにより、公共サービス提供を独占してきた行政内部の意識を改革していくことから着手しなければならず、言わば、OSの開発し直しから着手しなければならないのですから、時間がかかります。OSの部分をしっかりさせておかないと、あやふやなビジョンや意識の上では、PFIだろうが指定管理者制度だろうが、いくら立派そうなアプリケーションをのせても、結局はそのアプリケーションの特性を十分に引き出すことはできません。現在の地方自治体の財政状況等を勘案すると、北海道白老町、東京都三鷹市、長野県栄村、静岡県掛川市等のパートナーシップの先進自治体と言われる地域において10~20年かけて達成してきたことを、おそらく、今後3~5年程度で形にしていかなくてはならないでしょう。埼玉県志木市や北海道ニセコ町等では、こうした意識から、パートナーシップ体質の地域経営への転換のために短期間で大鉈が振るわれているのです。
そこで、こうした状況をきちんと住民に説明し、双方向のコミュニケーションを積み重ねるなかで、最初は少数でも理解してくれるリーダー層を発掘し、彼らの活動を支援していくことです。行政職員から言われても納得しない人でも、住民同士の話し合いのなかで納得してくれる人もいます。
「パートナーシップの実践」報告書では、公共サービスのパートナーとなるために地域の多様な主体が育ち合う環境を、当面は行政が意図的につくっていくべきであると提案しています。例えば、イベントの実行委員会方式等を活用してパートナーシップを学ぶ機会(パートナーとなる入り口)のメニューを多くもつこと、行政と住民・企業等が対等な立場で公共サービスの実践について学ぶ機会を常設すること、そして、介護や公園管理等の住民・企業等にとって身近なテーマから取り組むことなどです。
パートナーシップという手法のリスクとコスト
万能な手法はないのですから、パートナーシップという手法にも、ある程度のリスクは伴います。まずもって、住民にパートナーシップの導入について理解してもらうというリスクがあります。ここをおざなりにしたまま、行政と一部の住民との間で閉鎖的なパートナーシップが進められてしまうと、地域社会のなかに相互不信が起こり、ソーシャル・キャピタルの醸成にマイナスの影響を与えます。しかし、公共施設を建てるなどの新しくインフラを整備することに比べれば、比較的リスクは少ないと考えられます。また、パートナーシップのプロセス自体に、PDCAサイクルを組み込んでおくことによって、失敗の最小化と方向修正のマイナーチェンジを加えながら、改善の螺旋階段を上っていける可能性が高いのです。
パートナーシップは、リスクよりも、それが軌道に乗るまでのコストが問題です。公共サービスの担い手となるパートナーとして育つまでに住民、住民組織、企業等がかける時間、費用、手間隙等のコストもありますが、最も大きな問題は、行政がパートナー育成やパートナーシップの仕組みづくり等のためにかける様々なコスト、それも、すぐには成果が出ないタイプのコスト、を許容できるかということです。パートナーシップの推進担当となった行政職員からは、よく、「いつまでやればいいんだろう。やってもやっても、報われないような気がする」といった声を聞くことがあります。一方で、先進自治体の職員からは、「我慢の時期は長かったけれど、ある時点からドライブがかかるように、多くの住民の意識が前向きになってきた手応えを感じた」というコメントもあります。この間を、どのように乗り切るのか。
そして、議会の理解も得ていかなければなりません。パートナーシップによる公共サービス提供の実例が増えてくると、議員のなかには、自分達の頭ごなしに行政と住民が直接物事を決めているという“危機感”を抱く人が出てきます。これまで、自分の選挙区内の道路の修繕ひとつとっても、有権者からの苦情・陳情を行政の担当部局に伝えて地元に利益をもたらしてきたという意識の強い議員にとって、パートナーシップという手法は、一見すると自分の役割を奪う脅威のように思えることがあります。もっとも、パートナーシップを取り入れた地域経営下では、行政組織と同様に、議員および議会には、これまで以上に高度で重要な(ある意味“本来的な”)役割があるのですが、議員にそれに気付いてもらうには、誰かが根気よく説明をしないといけません。これもコストです。
そこで、こうしたコストを、地域経営を足腰の強いものにするための“投資”だと考えるリーダーシップが必要になります。また、パートナーシップ体質の地域づくりが実現するという明日を信じて頑張っていくための、ビジョンも必要となるでしょう。
パートナーシップのススメ
こうした大変さはありますが、行政=公共サービス提供(公益の追求)、住民・企業等=サービスの受け手(私益の追求)、といった単純な役割分担の図式では健全な地域経営が限界に来ていることを深刻に受け止め、ぜひ、一つでも多くの自治体がパートナーシップを導入し、縦糸と横糸の双方が強靭な地域社会づくりを実現していってほしいと思います。
これからの公共サービス提供のあり方研究会に参加したメンバーのなかには、既に、「パートナーシップの実践」報告書の原稿作成の段階から、同時並行的に自分達の自治体のなかでパートナーシップ導入に着手していった、チャレンジ精神あふれる自治体が複数ありました。そうした自治体の担当職員との話し合いの中から、パートナーシップはどんな小さな自治体でもチャレンジしていける手法であることを実感しています。いえ、あるいは、小さな自治体ほど、パートナーシップの着手から成果を実感できるまでの期間が短いのかもしれません。
最後に、本研究会の副座長である河西教授の言を紹介します。地域経営におけるパートナーシップの本質をわかりやすく表現している言葉だと思います。
<戦国の名将の一人である毛利元就に関して「3本の矢」という有名な逸話があります。この逸話はフィクションのようですが、現代の地域社会にとって意味ある示唆を与えてくれています。3本の矢は、それぞれ行政、産業、住民。行政、産業、住民のセクター、単独では非力かもしれませんが、3つのセクターが協力し、団結すれば、地域社会を取り巻く厳しい環境の中で、地域社会へ提供する公共サービスを支えられる。そんな地域経営の戦略が、この逸話から導き出されます。3本の矢を束ねて、折れにくくすること。それが今回の研究会のテーマである、パートナーシップです。…(後半省略)。>
(「パートナーシップの実践」の「おわりに」より抜粋)

