コラム「研究員のココロ」
地方分権論に旧くて新しい「租税競争」の視点を
2005年06月06日 吉野 薫
そういえば、ひところ話題が盛り上がった「東京都銀行税」の話は、その後どうなったんでしたっけ。同じく石原東京都知事が提唱した「ホテル税」も、片山鳥取県知事が噛み付いた結果、なかったことになったのでしょうか…? そのほか、大阪府の「銀行税」や横浜市の「馬券税」、はたまた東京都杉並区の「ゴミ袋税」、東京都豊島区の「放置自転車税」、山梨県河口湖町(当時)の「遊漁税」などなど。すっかり忘れ去られた感があります。
“課税自主権”といった言葉が一般のマスコミを賑わせた時代がありました。それはちょうど、平成12年4月に地方分権一括法が施行された頃。地方の課税自主権の一部拡大が法的にも裏付けを得て、“いよいよ地方の時代”としてこうした独自税制が世間の耳目を集めたのでした。
そして現在。いわゆる三位一体の改革が進められています。地方税のあり方も当然論議に挙がるべきだと思われるのですが、かつてのような“課税自主権”フィーバーは起こっていません。それどころか、そんな話題があったことに隔世の感すら感じるような状況です。“三位”のうち一つの柱である「税源移譲」を語るに当たって、地方公共団体が発揮すべき税制の自主性についても検討が及ぶべきではないでしょうか。
このコラムでは、課税自主権の拡大に伴う問題として、租税競争(tax competition)と呼ばれる現象について紹介します。個々の地方公共団体がそれぞれに努力すれば日本全体が活性化する、といった安易なシナリオの設定に警鐘を鳴らしておきたいと考えています。
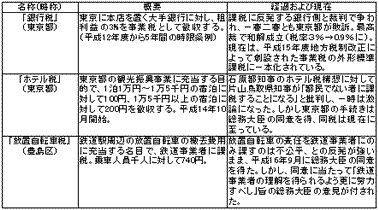
地方公共団体による「課税自主権」とは
一口に課税自主権といっても、いくつかの次元があります。このことを最初に整理しておきましょう。
- ・税目の自主性
- →「何から税金を徴収するか」という点に関する自主性。「ホテル税」や「放置自転車税」(法定外目的税)の創設はこれに当たる。また、旧来から「核燃料税」「砂利採取税」などの税金(法定外普通税)を設けている地方公共団体もある。
- ・課税標準の自主性
- →「何を基準に税額を算定するか」という点に関する自主性。いわゆる「銀行税」は、税額算定の基準を銀行の所得ではなく粗利益に設定する措置であり、この自主権の行使に当たる。
- ・税率の自主性
- →「税率をどう設定するか」に関する自主性。現在、地方税率は法律で定められた「標準税率」に従っており、一定の要件内で地方公共団体が標準税率より高い税率を設定することができる。
これらのうち、我が国における「課税自主権」論では前二者が中心的な話題となってきました。少なくとも当面は、税率の自主性を拡大する方向は志向されないようです。
三位一体改革の議論と課税自主権の拡大
さて、国から地方への税源移譲と、地方の課税自主権の拡大に関しては、賛否それぞれの立場からの評価があります。それらの論拠を筆者なりに大別してみました。この分類は、地方税の問題に留まらず、三位一体改革の総体を検討するうえでも有用な視点だと考えています。
(A)「地方が独自財源を得て創意工夫を発揮すれば、甘えやムダが排され、効率的な行政運営ができる」
(B)「国の一律的な管理をやめ、地方がキメ細かい行政サービスを提供すべきであり、その財源を地方自身が確保すべきだ」
(C)「基幹的な税源には地域間格差があるので、財源移譲に当たっては格差是正のための仕組みが必要である」
(A)は地方公共団体と国とのインセンティブ付与に係る論点であるため、これを筆者は「垂直的効率性」と呼称します 。1
また、(B)は国と地方との役割分担について、(C)は地方間の格差についての論点であり、それぞれ「垂直的公平性」「水平的公平性」と名づけています。
もうひとつの論点=水平的効率性
こうした議論の中で軽視されがちだった論点として、「水平的効率性」の問題に言及しなければなりません。これは地方公共団体間の「租税競争(tax competition)」に伴う非効率性の問題です。
租税競争とは、理論経済学の世界では古くから論じられている現象です。その理論モデルには色々なバリエーションがありますが、基本的な論旨は次のようなものです。
・複数の地域政府が課税自主権を発揮(典型的には税率を操作)することで、投資や労働力(生産要素)の導入を図る
・他の地域政府に生産要素を奪われないように、各地域政府はより低い税率をつけるような戦略を取る
・この結果、均衡として低い税率の世界が実現し、本来徴収できるはずの税金が入手できなくなる
このように地域間競争が生起する結果、社会的に望ましくない非効率な状態に陥る、というのが租税競争の基本的な問題意識なのです 。2
日本で租税競争が起こる可能性はあるか?
残念なことに、これまで租税競争の問題はほとんど省みられることがありませんでした。その最も大きな理由は先述のとおり、日本においては地方公共団体の税率に対する自主性は限定的であり、今後においても税率設定の自由化は地方分権の方向性として目指されていない、という点にあります。
しかしながら、上記で概説した理論モデルでは、多くの場合「租税」と「補助金」とを同一に扱っていることを指摘しておきたいと思います。すなわち、補助金を“マイナスの税金”と考えられなくもありません。この考えに従うと、たとえば地方公共団体による以下のような政策はまさに租税競争のモデルが予言する戦略なのではありませんか……
・企業の誘致を図るために、固定資産税の減免や新規雇用に対する補助金を企業に提供する。
・若年ファミリーの定住を促すために、少子化対策に係る補助金・助成金を創設する。
たとえば企業の所有する固定資産は社会全体にとって価値ある税源だといえるでしょう。ここから税金を取らない、という判断は、一地方公共団体だけの問題なのでしょうか。租税競争が警告する非効率性は現実的な問題である、と筆者が主張するゆえんがここにあります。
結語として=租税競争の問題を軽んずるべからず
租税競争が現実的な問題としてクローズアップされるようになったのは1990年代以降の欧州でした。経済統合を進めるうえでの各国の税制設計のあり方を考える必要が生じ、OECD租税委員会による「有害な租税競争プロジェクト」等を通じて議論が進められてきて現在に至っています。同プロジェクトで示された解決策は十全なものではない、という批判も聞かれます。しかし、租税競争の適切なルール作りに向けて、各国の利害対立を乗り越えて、政策担当者や経済学者が真摯に議論した、という点では評価すべき出来事だったと筆者は考えます。
一方で我が国における地方政府間の租税競争。ここまで述べてきたとおり、あまり省みられることがなかった問題意識ではありますが、三位一体改革を柱とする地方制度設計に当たっては軽視できない点であることを主張しておきたいです。地方がそれぞれに頑張れば社会全体が良くなる、といった単純な図式で捉えるべきではありません。地方交付税の裏付けが手厚かった時代ならまだしも、今後は地方政府の誤った頑張りが本当に地方行政の首を絞める結果を招きかねない時代が訪れることでしょう。最後に、次の二点を提言して本稿の結語とします。
・地方税制と各種補助金政策(企業誘致に係る税の減免等)はこれまで全く別個の施策として捉えられてきた。しかし地方分権のあり方を考える上では、それらを一体的に捉えるべきである。そのうえで、「適切な地域間競争」のルール作りを検討しなければならない。
・租税競争の枠組みで捉えると、地方公共団体の政策の帰結は当該団体内のみに留まるものではない。したがって、地方公共団体の政策責任者(首長や議員)を選挙できる範囲と政策の影響が及ぶ範囲とが一致していない。地方分権に際しては、こうした齟齬を克服するような政治的プロセスも検討される必要がある。
1:なお、この論点はしばしば地方政府の“モラルハザード”と表現されることがある。だたし、“モラルハザード”は社会制度設計に関して展開されるゲーム理論の特定分野(Principal-Agent Model)の用語であり、その使用には留意が必要である。
2:租税競争が非効率を生み出さないモデルを提唱する論考も多数存在するが、ここではモデルのバリエーションではなくこの問題意識自体を紹介することに主眼を置いている。

