コラム「研究員のココロ」
「営業力の診断」
2006年03月13日 芦田 弘
1.古くて新しい問題
「販売拡大の限界を感じている」「営業部門の改革を行ってもうまくいかない」「売上が伸びないのは、営業に何か問題があるからではないか」など営業に関する悩みの相談は後を絶ちません。一般的に、営業を必要としない企業は殆んどないので、こうした声が多くなるのも当然ですが、「営業の問題」は、いつの時代になっても、相も変らず聞こえてくる永遠の経営課題です。
営業に関する問題は、なぜ一筋縄では解決できないのでしょうか。原因のひとつは、営業の業務特性に因るところが大きいと考えられます。事務や生産の業務と比較すると分かりやすいのですが、営業には a.インプットとアウトプットの関係がはっきりしない b.一人ひとりの生産性の個人差が非常に大きい、という特徴があります。売上という最終成果は、さまざまな要因が複雑にからみあって創出されるため、常に営業には「曖昧さ」が付きまといます(a)。また、トップセールスと下位セールスとでは、成果の差が10倍以上開くこともありますが、事務や生産では有り得えません。すなわち、営業は「極めて属人性の高い業務」なのです(b)。もうひとつの原因は、営業の問題をとらえる次元や切り口が、経験や立場等によって大きく異なるため、社内で問題の共通認識を図りにくいことです。すなわち、セールストークや商談方法等のハウツーを問題視する人もいれば、情報共有化や行動管理等の仕組みの不備を指摘する人もいる一方で、特定の営業員を名指しで批判したり、組織体制や人事制度、さらにはマーケティング戦略にまで議論が及ぶことさえあるからです。
2.営業力の診断視点
1.で述べた「営業の業務特性」および「営業問題の共通認識のむずかしさ」を踏まえると、営業力の診断(課題抽出と対策立案)には多面的視点が求められます。しかし、視点を増やしすぎれば複雑になり当事者の理解を得にくくなるだけです。また逆に特定の視点に絞りすぎると問題の本質を見失いかねません。
そこで、少し唐突だと思われるかもしれませんが、果樹をイメージして、診断視点を4つに整理してみました。営業力の構成要素を果樹に例えると、根っ子に相当するのは「組織風土・人材」、幹は「商品力・チャネル力」、枝は「マネジメントおよび業務の仕組み」、葉は「個別ノウハウ」であると私は考えています。この「4視点」がそれぞれ健全でなければ、りっぱな果実(最終成果)は実らないはずです。この例えでいえば、根腐れは起こしていないか、幹は空洞化していないか、枝は生え揃っているか、葉は青々と茂っているか、が営業力の診断チェックポイントになります。
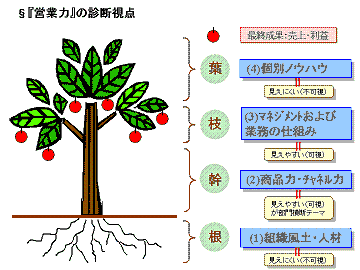
(1)組織風土・人材 【根っ子:根腐れは起こしていないか】
ある卸売会社で営業力強化のコンサルティングをやらせていただいたケースですが、ここで感じたのは組織風土の問題でした。創業メンバーである社長と役員は、自らの努力で会社をここまで築き上げてきた実力・自信があるが故に「俺の若いころは今の3倍は働いたし、お客様にいかに喜んでもらうか知恵を絞りに絞ったものだ。」と言って、今の営業員のやることなすことに物足りなさを感じていました。その結果、何をやっても否定されたり、怒られたりするので、営業員のモチベーションは低下し、退職者が続出しました。
営業員に一番求められる資質は「目標達成意欲」だと言われています。私も、その通りだと思っています。したがって、営業員のモチベーション低下は致命的です。
それでは、お客様に一番嫌われる営業員はどんな人材でしょうか。アンケートを採ると最上位に挙がるのは「商品知識のない営業員」です。お客様の方がネット等を検索して営業員以上の情報を持っていることが珍しくない時代では当然とも言えます。豊富な知識を持つお客様に満足感を与えるには、高度な専門知識とコミュニケーションスキルが必要になります。この点は営業人材力に依るところが大きいというのが、多くのコンサルティング経験から得た私の実感です。
(2)商品力・チャネル力 【幹:幹は空洞化していないか】
ある生産財メーカーでの営業力強化コンサルティングの事例です。「うちの営業は本当にどうしようもない。やるべきことをやっていない。すべてがいい加減で信用できない。」これは、私が実際に聞いた管理部門と技術部門の生の声でした。しかし、現状を分析すると、この会社の製品は、耐久性があり修理しやすいという長所がある反面、用途の絞り込みが不十分で価格競争力もないことが判明しました。競合他社は、成長用途分野に絞り込んだ小型製品を低価格で販売していました。商品力がない製品でも売り込んでこそ営業だというのは時代錯誤の考え方だと思います。今は、買い手の方がはるかに情報を持っているので、まやかしは通用しません。この事例で私が感じたのは、営業は叩かれ易い部門であるということです。商品力を度外視して、売上が上がらないのは営業がだらしないからだという勘違いです。事務や技術では管理書類等は社内ルールをきちんと守って作成されていました。顧客や競合先といった管理不能対象と直面して外回りをしている営業に内部同様の事務処理レベルを求め、不備を一方的に非難するこの会社の姿勢には少々疑問を感じました。
また、事業特性に合致した販売チャネルの構築を怠りながら、売上不振を自社営業員のせいにする企業の事例も見てきました。
(3)マネジメントおよび業務の仕組み 【枝:枝は生え揃っているか】
根っこと幹だけでは果実は育ちません。枝に相当するのはマネジメントおよび業務の仕組みです。営業活動プロセスや顧客情報を分かりやすくかつ互いに目に見えるようにする(可視化・情報共有化)・PDCAのマネジメントサイクルをまわせるようにする(目標管理)・組織的営業ができる仕組みを構築する(部門間連携)等が定番の課題です。これらは、営業革新のテーマとして一番多く取り上げられていると思います。
(4)個別ノウハウ 【葉:葉は青々と茂っているか】
(3)のマネジメントおよび業務の仕組みを再構築して導入した場合、実施段階でベテラン営業員の抵抗に合うというのもよく聞く話しです。ベテランほど、慣れ親しんだやり方を今さら変えられないという保守的心理が働くためです。そして、その深層には、営業は理屈じゃないという意識があるようです。そもそも曖昧さが付きまとう業務なので、その判断を一概に否定できません。測定不能な人間関係や千差万別な取引状況の中で、最終成果(売上)の有無が確定するので、むしろ、本質をついているとも言えます。教科書的な仕組みを作ってマニュアルを整備するだけで、売上が向上するほど営業は単純ではありません。最後に求められるのは、営業員自身のパーソナリティを踏まえた上で、お客様のパーソナリティや心の流れ等にも適合して状況を判断し行動する個別ノウハウだと思います。これは、言語化・形態化できない暗黙知と呼ばれるものだと考えます(言語化できるかもしれませんが膨大な内容になり実用性はないと思います)。こうした多種多様な葉(個別ノウハウ)が生い茂った果樹ほど、りっぱな果実を多く生み出すと考えられます。
3.おわりに
営業は、事業全体あるいは商売そのものの縮図です。営業を見れば、その会社の構造や体質がほぼわかるとも言われます。お客様から、貴社の弱点を見透かされないためにも、一度この4つの視点から自己診断されることをお勧めします。

