Business & Economic Review 2006年11月号
【OPINION】
成長戦略は人口問題でも有力策-海外流出リスク回避に向けて
2006年10月25日 藤井英彦
要約
- 減少したわが国総人口
(イ)2005年12月、総務省は「平成12年及び17年国勢調査結果による補間補正人口(暫定値)」を公表し、わが国人口が戦後初めて減少に転じたと発表した。すなわち、2005年の人口は1億2,775万7,000人となり、前年比4万3,975人減った。
もっとも、これは平成17年国勢調査要計表による人口公表に伴って2000年11月から2005年9月までの人口推計を遡及して計算した暫定値である。そのため、今後、平成17年国勢調査の確定人口公表によって計数が変わる可能性があり、人口が減少したという認識自体が修正を迫られる余地はある。しかし、わが国の人口が、第二次大戦前後の特殊な時期を除いてみれば、明治以来の増加傾向から減少期に転じる歴史的岐路に差し掛かっているという状況に変わりはない。
(ロ)わが国の人口減少は、まずもって少子高齢化の進行に起因する。少子化によって出生数が減少する一方、死亡数が増加したからである。出生数から死亡数を差し引いた、いわゆる自然要因による人口の変化をみると、1970年代半ば以降、過去30年にわたり趨勢的に増勢が鈍化し、2005年の年間増加数は8,754人増と1万人を切った(図表1)。70年代前半の130万人台と比べ、隔世の感がある。
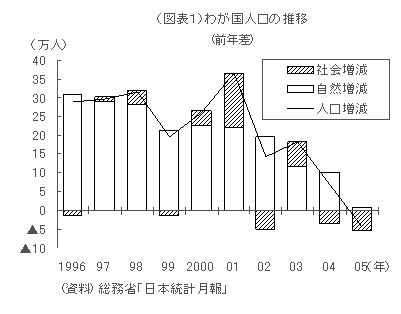
今後を展望しても、出生数の減少と死亡数の増勢が中期的に続く見通しである。国 立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(2002年1月推計)」によると、2005年には出生数が114万人で死亡数が112万人、差し引き2万人のプラスであるもの の、10年後の2015年には出生数の99万人に対して死亡数が138万人へ増え、差し引き39万人のマイナスになる。さらに、20年後の2025年には出生数が86万人と一段と減る 一方、死亡数は159万人とさらに増え、差し引きマイナス幅は72万人と2015年の39万人からほぼ倍増する見込みである。
(ハ)しかし、2005年についてみれば、自然要因はわずかながらもプラスに寄与した。一方、国境を超えた人の移動、いわゆる出入国による社会要因は5万2,729人のマイナスであった(図表1)。この点に着目すると、昨年わが国総人口が減少に転じた主因は、少なくとも限界的にみる限り、社会要因ということになる。もっとも、近年、東アジア各国やブラジルを中心にわが国に入国する外国人の数が、年を追って増えており、社会要因が人口減少の主因という捉え方には違和感がある。
そこで、日本人と外国人に分けて、社会要因の動向について整理してみた。旅行者など、短期滞在者は居住要件を満たさないため、外国人については外国人登録者数とした。これは、一般に90日を超えて滞在する外国人は入国の日から90日以内に居住地の市区町村で外国人登録を行うことが法令により義務付けられているためである。一方、日本人については、海外在留邦人、すなわち、海外に3カ月以上滞在している長期滞在者と海外永住者をみた。
前年比増減数をみると、まず外国人登録者数では、99年後半に、例えば研究分野では従来必要とされていた3年以上の経験の条件を弾力化したり、研修生について提出書類を簡素化するなどの見直しが行われ、その翌年の2000年には前年比13万人と大幅に増加した(図表2)。しかし、2001年以降、年を追って増勢が鈍化し、2005年には4万人弱と2000年の3分の1まで減っている。一方、海外在留邦人数は、2000年以降、長期滞在者を中心に着実に増勢が加速した。2005年には5万人強に達し、外国人登録者数の伸びを上回るに至っている。このようにみると、2005年のわが国総人口の減少は、外国人の国内流入が細る一方、日本人の海外流出傾向が強まった結果と位置付けられる。
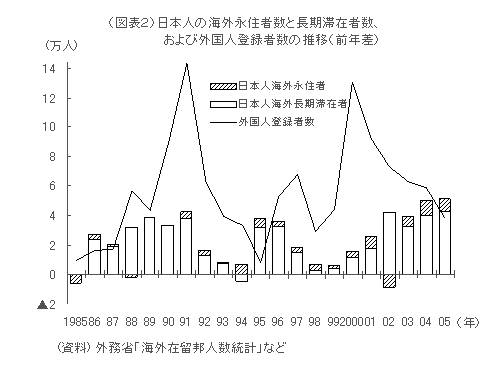
(ニ)それでは、今後、わが国人口はどのような推移をたどると展望されるか。まず自然要因、すなわち、出生数の減少と死亡数の増加による人口減少は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(2002年1月推計)」による限り、今後、緩やかに進行していくと見込まれる。それに対して、仮に2005年のような社会要因による人口減少が今後も続いたり、さらに減少傾向が加速する場合、わが国は予想外に早く深刻な人口減少に直面することになる。
それでは、社会要因の行方をどのようにみればよいか。まず、日本人や外国人の出入国動向は、入国管理手続きの簡素化や見直しによる制度的要因に加えて、内外景気の動向にも左右され、従来の推移をみても定まった傾向は看取されないという見方もあろう。加えて、2001年の9.11事件によって海外出張など国際移動が抑制され、2002年の社会要因による人口変動が前年の15万人増から一転して5万人減となり、2003年には新型肺炎SARSが発生するなど、近年、不測のショックが相次ぐなか、社会要因による人口変動の行方に方向性を見出すことは難しいともいえよう。一方、近年、職場を求めて外国人の国内流入傾向が強まっている、あるいは、これからわが国の人口減少は次第に深刻さを増していくため、今後、外国人労働者への依存が強まり、社会要因は人口増加に作用する可能性が大きいとする見方もありうる。
(ホ)しかし、そうした見方は次のような現状と必ずしも整合的でない。まず、経済・社会のグローバル化が急速に進むなか、世界各国では、近年、人口移動による社会要因が出生数や死亡数による自然要因と並ぶ人口増減の主因の一つとなってきたことである。例えば、OECD主要各国を対象に、2000年から国毎にデータが取れる直近の年として最長2005年までの年平均人口増減率をみると、社会要因が自然要因を上回る国が少なくない(図表3)。データが採れた25カ国を対象に自然要因と社会要因の寄与の大きさを比べると、自然要因が社会要因を上回った国は9カ国に過ぎず、逆に社会要因が自然要因を上回った国が16カ国に上る。
さらに、自然要因による人口増減率と社会要因による人口増減率との関係をみると、正の相関が看取される。すなわち、人口の自然増加数が多い国ほど外国からの人口流入が多い。無論、出生数や死亡数と、国境を超えた人の移動との間に直接的な関係はないし、明確な因果関係があるわけでもない。もっとも、出生数が多く自然要因によって人口が増えている国、とりわけ、人口増加、あるいはそれに伴う労働力の増加を梃子に経済が力強く成長している国であるほど、企業をはじめ海外からの市場参入の動きが活発化する一方、逆に人口が減り、それに伴って経済が低迷している国では国内市場から海外に退出する動きが広がるという展開は、経済や社会のグローバル化に伴う一つの典型的現象として捉えられよう。あるいは、両者を因果関係ではなく、雇用情勢や成長力の中長期的展望の違いとみることができるかもしれない。例えば、その表れ方を図式化してみると、経済の活性化に成功した国では、海外から国内市場参入の動きが拡がるとともに、自然要因による人口増加も強まるのに対して、経済成長力が相対的に脆弱な国では、海外から国内市場に参入しようとする動きが次第に後退するうえ、自然要因による人口増加も伸び悩む、というプロセスを想定してもあながち牽強付会に過ぎるとはいえまい。
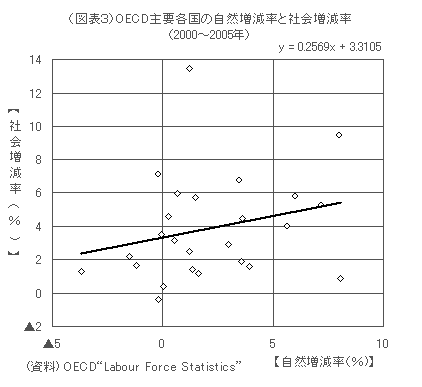
(ヘ)しかし、OECD主要25カ国とわが国を単純に対比することはできない。移民政 策、すなわち、移民を積極的に受け入れるか、それとも移民の流入を厳しく制限するかのスタンスは国によってまちまちである。加えて、法人税や固定資産税を軽減した り、設備投資や雇用増加に補助金を支給するなど、海外資本の誘致に向けたインセンティブも国や地域によって大きく異なる。また、グローバル化の人口動態に対する影 響をみるという観点からみると、企業サイドでは賃金水準が相対的に低い途上国や中進国を選好する一方、労働者サイドでは賃金水準が高い先進国を選好するため、途上 国や中進国と先進国では状況が全く異なる可能性が大きいなど、そうした複雑な事情が各国の人口増減の違いに作用しているからである。
そこで本稿では、比較のベースをなるべく揃えるために、先進国のうち経済規模が大きい主要各国のなかから、わが国と同様、近年、人口減少に転じたドイツに注目し、このところの推移を整理してみた。なお、日独以外の主要先進各国は、出生率の高い米仏をはじめとして総じて人口が増加しているうえ、今後を展望しても中期的に人口が減少する事態に陥る可能性は小さく、わが国との対比は必ずしも適切でない。 - 人口減少に転じたドイツ
(イ)ドイツの人口は、2002年に8,253万6,700人でピークを打った後、2003年以降、減少傾向に転じており、減勢が年を追って拡大している(図表4)。すなわち、2003年の前年比▲5,000人から2004年に前年比▲3万800人へ、さらに2005年には前年比▲6万2,800人にマイナス幅が拡大した。
こうした人口の推移を、出生数から死亡数を差し引いた自然要因と国内外での人口移動に伴う社会要因とに分けてみると、近年の人口減少は自然要因よりもむしろ、社会要因が主因となっている。このため、人口が近年減少傾向に転じた点のみならず、人口減少の主因が社会要因である点など、ドイツはわが国と共通する点が少なくない。自然要因、社会要因別に人口の変動をみると次の通りである。
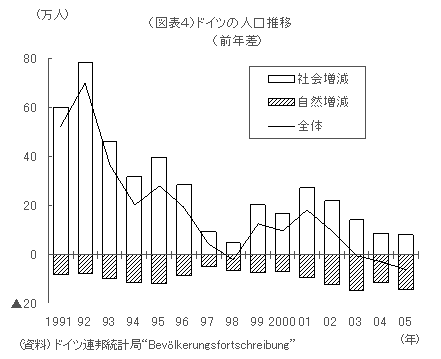
(ロ)まず自然要因による人口増減数は、出生数の減少に伴って72年以降ほぼ一貫し てマイナスで推移してきた。近年では11万人から14万人のマイナスであり、大きな変化はみられない。それに対して、社会要因による人口増減数は近年大幅に増勢が落ち ている。例えば、2000年以降最も大きく人口が増加した2001年と2005年を比べると、前年比増減数は2001年の18万人増に対して2005年には6万人減であり、合算すると24 万人のギャップが両年間に生じている。そのうち、社会要因による人口増加は2001年の27万人から2005年には8万人へと増勢が19万人減っており、2001年と2005年のギャ ップの大半が社会要因に帰せられる。そこで以下では、もう一歩踏み込んで自然要因と社会要因の推移をみた。
(1)自然要因
(イ)まず、自然要因について出生数と死亡数の推移をやや長期的な視点からみると、死亡数が人口減少を食い止める方向に作用してきた(図表5)。すなわち、死亡数は1969年の98万8,092人をピークに緩やかながら趨勢的に減少傾向をたどり、2005年には83万227人となっている。背景には、医療サービスの充実に伴って平均余命が延び、死亡数の増加が回避されたという事情が指摘されよう。それに対して、出生数は長年にわたり人口減少に作用してきた。すなわち、出生数は64年の135万7,304人をピークに70年代前半まで急ピッチで減少した。72年には90万1,657人と死亡数を下回るに至り、その後、今日まで出生数が死亡数を下回っており、自然要因での人口減少が続いている。
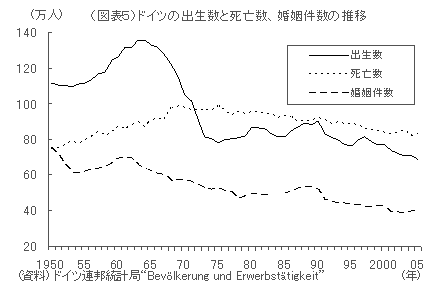
なお、70年代半ば以降の推移をやや詳しくみると、出生数は一進一退を繰り返しな がら若干増加し、90年には90万5,675人となった後、それをピークに再び減少傾向をたどり、2005年には68万5,795人まで落ち込んでいる。こうした出生数の変動、すな わち、60年代半ばの出生数のピークとその後の急減、あるいは70年代半ば以降の増加や90年代の減少についてみると、その要因として婚姻件数の変動が指摘される。もっとも、そのインパクトは70年代半ばを境に大きく減退した。合計特殊出生率の推移にみられる通り、70年代半ばを境に前後の局面を比較すると、合計特殊出生率は60年代 の2.4前後の水準から70年代半ば以降1.4前後へ大きく低下している。
(ロ)これらをわが国の現状を踏まえながら要すれば、次の点が指摘されよう。まず自然要因は出生と死亡に伴う動向であるため、安定した推移をたどることである。そのため、いったん出生数が死亡数を下回り始めると、合計特殊出生率の上昇に成功しない限り、長期にわたって人口減少圧力から逃れることは出来ない。ちなみに、わが国では、70年代半ば以降、出生数がほぼ一貫して減少傾向をたどるなか、2005年には死亡数と出生数がほぼ同水準となり、自然要因による人口減少の本格化が目前に迫っている。
一方、医療・介護サービスの拡充を通じて平均余命が延びると、死亡数が抑制され、それが人口減少に歯止めとして作用するものの、ドイツの場合、そうした効果が今後も持続する展開は期待薄なことである。平均余命のさらなる延長には限界があるためであり、今後はむしろ、死亡数が増加し、その分、人口減少に拍車が掛かる公算が大きい。ちなみに、国際連合の2004年版将来推計人口によると、ドイツの人口1,000人当たりの死亡者数は、2000~2005年の10.3人から20年後の2020~2025年には12.3人に増加し、30年前の1970~75年水準まで戻ると見込まれている。一方、わが国でもドイツと同様に今後死亡数が緩やかに増加する見込みである。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(2002年1月推計)」によると、死亡数は2005年の112万人から10年後の2015年に138万人、20年後の2025年には159万人へ年間2万人強のペースで増加する。
(2)社会要因
(イ)次に国境を跨いだ人口移動についてみると、ドイツはトルコ系を中心に外国人労働者が多数流入した国として有名である。これは、第二次大戦後、多くの西欧各国と同様に高度成長に伴って国内の人手不足問題が深刻化したうえ、少子化の進行によって外国人労働力への依存が増大したためである。60年代後半には外国人の入国者数が100万人規模まで拡大し、出国者数を差し引いたネット入国者数は50万人代半ばに達した。しかし、73年の第一次石油危機以降、ドイツ経済が停滞色を強め、外国人労働に対するスタンスが厳しさを増すなか、外国人の入国者数は大きく減少し、75~76年には30万人台、83年には20万人台まで落ち込んだ。
それに対して、ドイツ人の出入国者数は70年代半ばまでほぼ拮抗して推移し、年間のネット入国者数は数千人にとどまっていたものの、70年代後半以降、外国人の動きと逆に、入国者数が次第に増加した。80年代半ば一時的に低迷したものの、80年代後半には再び増勢が戻り、その結果、出国者数を差し引いたネット入国者数で比較すると、外国人とほぼ比肩するまでドイツ人入国者が増加した。年によって変動しているものの、総じてみれば、外国人のみならず、ドイツ人の入国動向も社会要因による人口増減を左右する大きな要素となっている。そこで、90年代入り後の出入国者数の動向を外国人とドイツ人に分けてたどると、次の通りである。
(ロ)外国人についてまず入国者数をみると、90年代初め、両独統合を契機に人口流入ブームが盛り上がり、92年には121万人に達した後、趨勢的に減少した。こうした外国人入国者数の伸び悩みは雇用環境の悪化が主因であり、例えば近年では、失業率が2001年の6.9%をボトムに2004年の9.2%まで年を追って上昇するなか、入国者数は2001年の69万人から2005年には58万人に落ち込んでいる(図表6)。
一方、出国者数は93年の78万人を除くと、90年代には総じて60万人前後で推移してきたのに対して、2001年以降50万人前後へ減少した。それらの結果、出国者数を差し引いたネットの外国人入国者数は92年の60万人を除くと、総じて10万人から20万人で推移しており、大きな変動はみられない。なお97~98年には、それぞれネットベースで2万人、3万人の外国人流出となっているが、これも、雇用環境の悪化が主因であり、両年とも失業率が9%前後まで上昇していた。
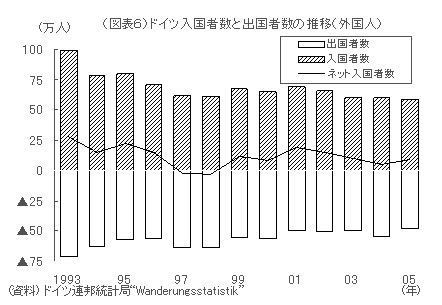
(ハ)次にドイツ人について、まず入国者数をみると、94年の31万人をピークにほぼ 年を追って減少し、2005年には13万人となった(図表7)。一方、出国者数は80年代後半以降総じて11万人前後で推移してきたものの、2003年から増え始め、2004年に15 万人と過去最多となり、2005年には前年比5,852人減ったものの、依然14万人となった。それらの結果、出国者数を差し引いたネットのドイツ人入国者数は、90年の31万 人をピークに減り続け、2005年にはついに▲2万人の流出超となった。これも、外国人と同様、ドイツ国内の厳しい雇用情勢のもと、国外に新天地を求める動きとされる。 もっとも、老後、地中海沿岸など過ごしやすいエリアでの生活を求めて移住する動きも根強い点に着目し、必ずしもドイツの雇用情勢に起因するとは限らないという指 摘もあろう。そこで、直近でドイツ人のネット入国者数がピークとなった2001年と詳細な最新データがとれる2004年を比べると、2001年にはすべての年齢層で増加してい たのに対して、2004年には25~39歳の年齢層でマイナスとなっている。いわば若年層から中年層に至る労働力の中核部分で人口が国外に流出し、基幹労働力を喪失する深 刻な事態が発生している。
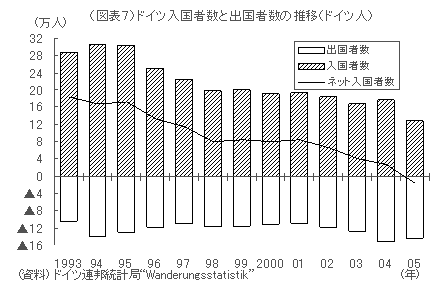
さらに、厳しいドイツ国内雇用情勢を反映した動きであるとしても、ドイツでは地 域別格差が大きく、仮に旧東独地域が人口減少の中心であれば、両独統合ブームの反動と位置付けるべきであり、必ずしもドイツ全体の人口問題と捉えるべきでないとい う見方もあろう。また、そうであれば、相対的にスキルの低い労働力を中心とした国外流出であり、年齢層からみれば基幹労働力であるとしても、問題はさほど深刻でな いという見方が成り立つかもしれない。
そこで、旧西独地域と旧東独地域に分けてドイツ人のネット入国者数を直近のピークとなった2001年と2004年で比べると、旧西独地域では17万人から8万人へと人口流入が9万人減る一方、旧東独地域では逆に▲8万人から▲6万人へ人口流出が2万人減っており、旧西独地域での動きが主因となっている。さらに州別にみると、ドイツ南部に位置し、近年、成長センターとしてドイツ経済を牽引してきたバーデン・ヴュルテンベルク州とバイエルン州2州で人口流入に急ブレーキが掛かった結果である。 - 今後の課題
(イ)近年のドイツの人口減少は、少子化に伴う自然減が70年代から長らく定着するなか、90年代半ば以降、ドイツ人の国内流入傾向が次第に弱まり、2005年には国外流出に転じた結果であり、経済停滞に伴う雇用情勢の悪化が根因と捉えられよう。翻ってわが国では、外国人入国者数の伸び悩みと日本人の海外長期滞在者の増加によって2005年に総人口が減少に転じた。
さらにこれまで自然減には陥らなかったものの、今後出生数が死亡数を下回り、自然要因による減少傾向が次第に強まると見込まれており、少子化対策は喫緊の課題である。一方、わが国の外国人労働力の活用度合いは諸外国を大きく下回る。例えば、主要各国における2003年の労働力人口に占める外国人労働力のシェアをみると、アメリカの14.8%を筆頭に、ドイツ9.0%、フランス5.2%、イギリス
5.1%であるのに対して、わが国は0.3%に過ぎず、各国とのギャップは大きい。そのため、今後、少子化の進行によって自然要因による人口減少ペースが加速すると見込まれるなか、わが国は外国人労働力をより積極的に活用すべきとする見方は国内のみならず、本年7月にOECDが発表した対日経済審査報告書をはじめとして海外でも根強い。
(ロ)しかし、それらだけでは必ずしも十分とはいえないだろう。どんなに出生数が増えても、国外流出がそれを上回って増えれば人口減少に歯止めは掛からないし、ドイツで看取されたように、国外に飛躍的成長を遂げる魅力的な経済があり、国内経済が相対的に成長力に劣り、停滞を余儀なくされると、そうした国や地域への人口移動が強まる筋合いだからである。少なくともわが国の場合、その懸念はすでに顕在化しており、今後、一段と強まる兆しすら窺われる。
加えて、近年の主要各国の成長要因をサプライサイドから整理すると、経済成長の主力エンジンは、労働投入量よりもむしろ、資本ストックや全要素生産性である(図表8)。2000~2005年の年平均経済成長率に対する寄与度をみると、例えばわが国は1.4%の成長率に対して、全要素生産性が1.4ポイント、設備ストックが1.1ポイント寄与した。移民と高い出生率で人口が増加している米仏をみても、アメリカは2.7%の成長率に対して、全要素生産性と設備ストックがそれぞれ1.1ポイント寄与する一方、労働投入量は0.5ポイントの寄与に過ぎず、フランスでも、2.1%の成長率に対して、全要素生産性が1.1ポイント、設備ストックが0.6ポイント寄与する一方、労働投入量は0.4ポイントの寄与にとどまった。2003年から人口が減少したドイツでも、1.4%の成長率に対して、全要素生産性が0.8ポイント、設備ストックが0.6ポイント寄与している。
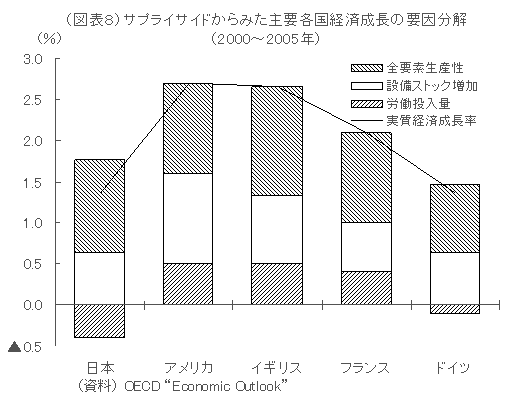
(ハ)このようにみると、人口減少の問題を打開するには単に少子化対策や外国人労 働力の活用にとどまらず、国内経済・産業の成長戦略の成否が焦点であるといえよう。サプライサイドから整理すれば、設備ストックを一段と拡充しながら、どのように全 要素生産性を引き上げていくかがポイントになる。そうした観点からみると、とりわけ、a.研究開発投資の戦略的推進、b.外資の積極的活用、c.ヒトづくりの一段の強化、 が喫緊の課題である。
(1)研究開発投資の戦略的推進
(イ)全要素生産性を持続的に引き上げるには、経済・産業の高度化を進め、高付加価値化を実現できるか否かが鍵を握る。具体的には、既存産業の競争力強化と同時に、新たな産業や事業の創出が重要である。そうした認識が広く浸透するなか、先進国と途上国とを問わず、世界規模で新たな産業や事業の創出を目指して研究開発投資に取り組む動きが近年ますます強まっている。
わが国でも、96~2000年度の第一期、2001~2005年度の第二期に引き続き、2006年度から10年度までの5年間が第三期と位置付けられ、科学技術基本計画が強力に推進されている。厳しい財政状況のなか、例外的に予算増が認められ、第三期の研究開発関連予算は第二期の24兆円を上回る25兆円規模とされた。
さらに、成果を着実に挙げていくために、研究開発の効率的実施に向けた取り組みが一段と強化されている。例えば、ライフサイエンスや情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料など重点分野を明示したうえで、個別プロジェクト毎に課題や目標を明確に提示して方向性を明確に示す一方、進捗度合いや成果をチェックし、そうした個別プロジェクト毎の評価結果を研究目標の変更や予算の増減に反映させるなど、戦略的な推進体制の強化が図られている。
(ロ)こうした長年にわたる官民の取り組みはすでに成果を挙げてきている。すなわち、外国からの受取額から外国への支払いを差し引いた特許等使用料収支は赤字基調が定着していたものの、90年代に入って次第にマイナス幅が縮小した後、2003年に1,493億円の黒字に転じ、2004年に2,232億円、2005年には3,288億円へ年を追って黒字幅が拡大している。さらに、鉄鋼や非鉄金属などの素材分野から工作機械や半導体製造装置などの製造機械分野、情報端末や液晶テレビなどの消費財まであらゆる分野で、研究開発を原動力に製品の高付加価値化が推進され、それがわが国経済の一段の競争力強化と本格的な景気回復の礎となってきた。
わが国の研究開発に対する積極的姿勢は、諸外国を上回る投資規模の大きさに端的に表れている(図表9)。2004年時点で投資規模を主要各国間で対比してみると、名目GDP比でみて、アメリカの2.7%、ドイツの2.5%、フランスの2.2%、イギリスの1.9%に対して、わが国は3.1%であり、各国をはるかに凌駕している。もっとも、これを主体別に分けてみると、わが国の場合、政府セクターのウエイトの小ささが際立つ。すなわち、政府セクターは、米独英3カ国で3割、フランスでは4割を占めるなか、わが国は2割弱にとどまる。これは、わが国の場合、企業主導による研究開発体制が長年にわたって定着してきたという経緯に起因する。さらにいえば、戦後のキャッチアップ過程を中心として、効率的に研究開発を行うには、事業化に密着した推進体制、すなわち、企業セクターによる研究開発が最適であったという事情が指摘されよう。
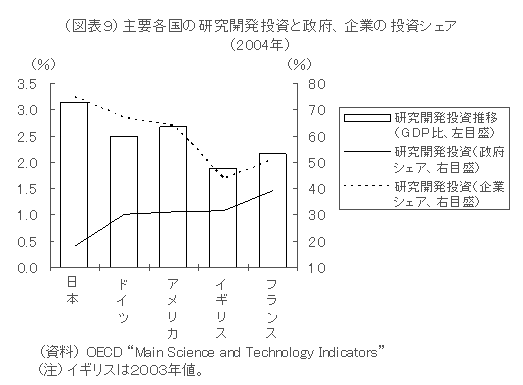
(ハ)確かに既存製品の高度化や既存技術をベースとした応用製品の開発であれば、 要素技術や様々なノウハウを蓄積しているだけに、当該分野をコアコンピタンスとする企業が研究開発を行うことがもっとも効率的である。しかし、インターネットやナ ノテクノロジーなど、これまで存在しなかった新たな社会や市場を創造する画期的な技術革新は既存製品や既存技術と不連続なケースが多く、そうした研究開発プロジェ クトを民間ベースだけで成功に導くことは容易でない。実績が示す通り、わが国企業の研究開発能力は極めて高いものの、今日、各国では官民を上げた取り組みが一段と 強化され、研究開発における企業リスクの軽減が図られているからである。
このようにみると、わが国でも、基礎研究分野を中心として政府セクターに一段と積極的役割が期待される。加えて、研究開発を事業化に結実させ経済的成果を挙げるためには、第三期科学技術基本計画が指向する戦略的推進体制の強化や外国人研究者の活用、さらに実績のある研究者のみならず、若手をはじめ研究実績の乏しい研究者にもチャンスを与えて研究をサポートする競争的研究資金制度の一層の拡充など、各国を上回る強力な研究体制の構築が必須である。
(2)外資の積極的活用
(イ)研究開発活動によって新たな発見が行われたり、パイロットモデルの制作に漕ぎ着けるだけでは、経済・産業の高度化は実現されない。高付加価値体質への転換を進め、成長力や競争力を実際に向上させるには、研究成果を盛り込んだ新たな設備投資によって既存設備のリプレースを進め、経済の供給力を強化しなくてはならない。
そうした観点から、このところのわが国民間設備投資をみると、企業の業績向上や国内回帰の動きを反映して近年、底堅い推移が続いており、設備ストックの増強が進んでいる。しかし、それは国内企業による投資が大半を占めており、外国企業による投資は極めて限定的なものに過ぎない。この点を、名目GDP比でみた2000~2005年平均の外国企業の国内向け直接投資規模で主要各国と対比してみると、わが国への外国企業の投資の少なさが突出している。すなわち、わが国が0.15%にとどまっているのに対して、各国では、イギリスの3.60%を筆頭に、フランスは2.95%、ドイツが1.15%、アメリカの0.99%と、いずれもGDPの1%から4%弱に達している(図表10)。いわば、各国では外国資本が民間設備投資を支える重要な柱となっているのに対して、わが国では国内資本だけに依存する片肺飛行が続いている。
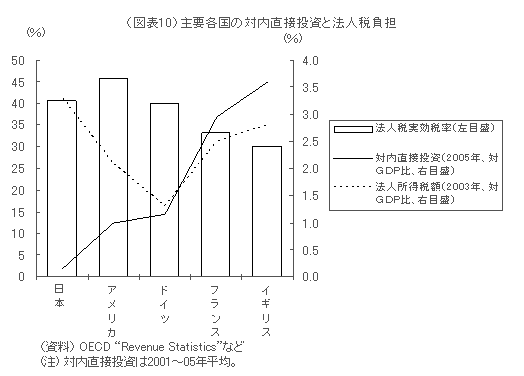
(ロ)加えて、わが国への対内直接投資は、近年、再び低迷色を強めており、2005年 には名目GDP比0.07%まで落ち込んだ。わが国経済は、ペースは緩やかであるものの、いざなぎ景気を超え戦後最長を展望するまで景気拡大を続けているだけに、外国資本 の流入を阻む要因は国内の需要動向ではなく、むしろそれ以外の要因といえよう。そうした要因として、長期的関係や系列をはじめとする閉鎖的な取引慣行あるいは日本 語という非関税障壁が指摘されるケースが少なくない。
しかし、こうした見方には説得力が乏しい。まず90年代に入り、グローバル化が急速に進行するなか、大企業のみならず、中堅・中小企業でも新規開拓によって取引先を拡大し、取引関係の開放に向けた取り組みが強まっており、閉鎖的取引慣行は大きく崩れている。一方、わが国の隣国韓国が2000年入り後受け入れた直接投資がGDP比で年平均0.9%とわが国を大きく上回り、米独とほぼ比肩する規模に達している点を踏まえてみれば、言葉による非関税障壁という見方も説明力を失おう。
(ハ)むしろ今日では、わが国の事業コストの高さが重要性を増している可能性がある。こうした観点から法人税負担をみると、実効税率では必ずしも高くないものの、実際の負担規模は主要各国のなかで最大となっている。すなわち、まず実効税率をみると、最大はアメリカの45.95%、次いでわが国の40.69%とドイツの39.9%、さらにフランスが33.33%で、イギリスが主要5カ国中最も小さく30.0%となっている。しかし、法人所得税負担の名目GDPに対する比率で対比してみると、最大がわが国の3.3%であるのに対して、以下順にイギリス2.8%、フランス2.5%、アメリカ2.1%、ドイツ1.3%となっており、わが国企業の法人税負担の重さが際立つ。加えて、アメリカの実効税率はわが国を上回る一方、ドイツはわが国と同水準でありながら、実際の税負担は大きく異なる。
これは、研究開発や雇用増加に対してインセンティブとして法人税負担を軽減するなど、国内市場への内外企業誘致に向けて積極的な取り組みが推進されてきた結果である。企業負担軽減に向けた動きは、先進各国にとどまらず、世界各国に拡がっており、シンガポールやマレーシアをはじめ、東アジア各国でも積極的に進められている。そうした制度間競争は、各国を上回って負担が軽い国で企業誘致が進み、負担を軽くしても負担水準が平均的な多くの国々ではインセンティブ効果は期待薄となる一方、負担が相対的に重い国では逆に企業誘致が阻害されるという深刻な国別格差を増幅させる懸念が大きい。このようにみると、わが国経済に依然残存する高コスト体質の是正と併せ、公的負担の軽減など、事業コストの引き下げに向けた取り組みは焦眉の急である。
(3)ヒトづくりの一段の強化
(イ)経済・産業の高度化を実現するには、ヒトづくりのさらなる強化も欠かせない。既存の技術から懸け離れた画期的な研究開発を生み出し、新たな製品を市場に送り出し、さらに新事業を円滑に成長・発展させて経済・産業の高付加価値化を実現するには、一連のプロセスに漏れなく有能な人材を配置する必要がある。そのため、各国では近年一段と人材調達を目指した動き、とりわけ、教育の強化や留学生の積極的受け入れ、さらに研究者や技術者の積極的招致への取り組みが強まっている。これらについて主要各国と対比してみると、次の通りである。
(ロ)まず教育について、小学校から高等学校までの初等中等教育と、大学や大学院などの高等教育に分けて政府の財政支出規模を名目GDP比でみると、わが国はどちらの分野についても各国中最も小さい(図表11)。すなわち、初等中等教育分野では、主要先進4カ国をみるとフランスの4.1%を筆頭に最小のドイツが3.1%であるなど、各国で算数や理科嫌いを無くし、基礎学力の強化が指向されるなか、わが国は2.7%にとどまる。3.7%のOECD各国平均との格差は1ポイントに達している。一方、高等教育分野では、専門家の養成強化を目指してOECD各国では平均1.3%に達しており、主要先進4カ国でも最大のアメリカ1.4%から最小のフランスでも1.0%とほぼ各国平均前後の水準であるのに対して、わが国は0.5%にとどまる。ちなみに、GDP比でみて政府の教育支出規模がわが国を下回る国はOECD諸国のなかに皆無である。
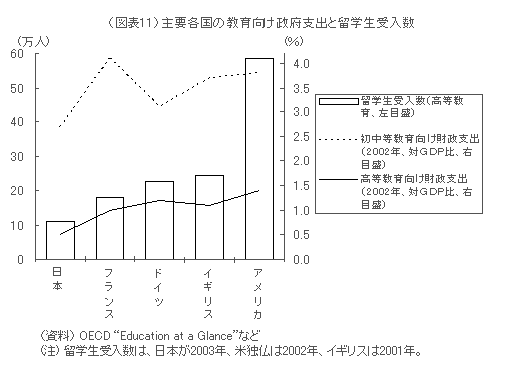
(ハ)次いで、留学生の受け入れについてみると、90年代に入り、グローバル化が本 格化するなか、国外からも有能な人材を確保し、競争力の中長期的強化を図ろうとする戦略的取り組みが各国で強まった。主要各国について90年から2001年への受け入れ 数の推移をみると、アメリカが41万人から17万人増加して58万人で最大、次いでイギリスが8万人から24万人、ドイツが11万人から21万人、フランスは14万人から16万人 に増加した。それに対して、わが国では、83年以来、留学生10万人計画のもと積極的に留学生受け入れが推進されてきたものの、受け入れ数は2003年でも依然として11万 人にとどまり、主要各国を大きく下回る。
(ニ)さらに、即戦力として活躍が期待される研究者でも、留学生の受け入れと同様、海外から有能な人材を積極的に取り入れ、活用しようとする動きが各国で強まっている。例えば、フランスのCNRS(国立科学研究センター)では1万人の研究者のうち、外国人が2割を占める一方、ドイツのマックスプランク協会では外国人が270名の研究幹部長職の4人に一人、5,700名の若手科学者の半数以上を占める模様である。
ここでは、データの制約から、外国人研究者を世界で最も積極的に活用している国とされるアメリカを例に取ってわが国と対比してみると次の通りである。まずわが国でも、外国人研究者を活用しようとする動きが90年代以降次第に強まり、2004年の外国人研究者数は1万701人となった。もっとも、わが国の研究者数は全体で83万人に上るため、外国人研究者が占めるシェアは1.3%に過ぎない。それに対して、アメリカの外国人研究者の活用度合いはわが国を大きく上回る。外国人研究者の活躍をみる
観点から博士号取得者に着目すると、外国人の取得者数は2003年時点で30万人に上り、アメリカの全博士号取得者に占めるシェアは34.6%と3分の1に及ぶ。分野別にみると、とりわけ理工科系で高く、例えばコンピューターサイエンスで57.4%、エンジニアリングでは50.6%など、過半を占める分野も少なくない。
人材の強化や外資の活用、研究開発の推進など、成長戦略は各国が最優先で追求する政策課題である。そのため、国内の改革断行にとどまらず、海外に目配りし、各国を上回る事業環境を構築しない限り、成長戦略の成功は覚束無い。人口減少が目前に迫るわが国にとって、その成否は死活的に重要である。新政権のリーダーシップ発揮が切望される。

