Business & Economic Review 2006年09月号
【OPINION】
地方の停滞を打破する分権改革を
2006年08月25日 藤井英彦
- はじめに
2006年5月11日、地方六団体から「分権型社会のビジョン(中間報告)」と題する地方財政の自立に向けた七つの提言と工程表が発表された。続いて、5月26日には総務大臣主催の地方分権21世紀ビジョン懇談会が最終報告案を公表した。いずれも中期
的スタンスで地方分権改革を着実かつ強力に推進していこうとする取り組みであり、分権改革に向けた動きが国と地方双方で再び盛り上がっている。
地方六団体と地方分権21世紀ビジョン懇談会のペーパーを対比してみると、新地方分権推進法と新分権一括法など、個別には表記や仕組みに違いがある。しかし総じてみれば、地方財政の健全化と地方再生が地方分権の最終目的と位置付けると同時に、それらの実現に地方分権が不可欠であるとする点で、両者に大きな差異はない。
推進メニューを地方分権21世紀ビジョン懇談会のペーパーをもとに整理すると、まず第1の柱が既往政策のさらなる推進であり、a.地方交付税の見直しと税源移譲、補助金改革からなる三位一体改革、b.行革推進とそれによる歳出削減、c.2000年度から2004年度まで施行された地方分権一括法をリニューアルした新地方分権一括法の制定、に整理される。もう一つの柱が今回新たに盛り込まれた改革スキームであり、主なものとして、a.再生型破綻法制の整備、b.地方債の完全自由化、c.道州制、の三つが挙げられる。破綻法制の整備や地方債の自由化は市場メカニズムを活用した財政規律の強化が主眼である一方、道州制は、今日国が保持する権限の大幅な移譲に応えられる受け皿となる、強力な地方政府の構築を目指したものである。
しかし、こうした陣立てだけで地方財政の健全化と地域経済の再生という地方分権の目標が達成できるのか。仮に達成が難しいとすれば、どのような方策や政策の修正が必要か。本稿では、こうした視点をベースに、面積と並び新型地方交付税制度の算定基準とされる人口、あるいは主要な経済要素の一つである雇用といった切り口からアプローチしてみた。 - わが国の現状と将来展望
(イ)まず、地方分権21世紀ビジョン懇談会のペーパーによると、今後の地方分権改革の推進は中期的スパンで行われるスケジュールとなっている。例えば、三位一体改革や再生型破綻法制の整備、地方分権一括法案の国会提出は3年を目処とする一方、道州制や地方債の完全自由化では10年後の実現が目標とされる。そうしたスケジューリングの根底には、本ペーパーの文言、とりわけ、「今日の日本は、世界でもっとも急激な少子高齢化と人口減少に直面し、その意味で世界の課題先進国である」とする表現に即してみる限り、そうした事態が本格化するまでに分権改革を断行し、地方財政の健全化と地域経済の活性化を実現する必要があるという認識があると読める。ちなみに、国立社会保障・人口問題研究所の2002年1月推計日本の将来推計人口の中位推計によれば、わが国総人口は2007年以降減少に向かうが、前年比減少数は2010年から▲10万人台に乗り、2015年から▲30万人台に拡大すると見込まれている。こうした予測に基づけば、本格的な人口減少局面は5~10年先であり、分権改革を遂行する猶予は残っているという見方も成り立とう。
しかし、地方圏では、すでに深刻な人口減少問題が顕在化している。わが国人口の
推移を、a.東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県からなる東京圏、b.愛知、岐阜、三重の3県からなる名古屋圏、c.大阪、兵庫、京都、奈良の4府県からなる大阪圏、d.それら以外の地方圏、の四つに大別してみると、東京圏が95年以降趨勢的に増勢を加速させてきたのと対照的に、地方圏は次第に増勢が鈍化して2002年にマイナスへ転じ、2005年には▲10.5万人と前年比マイナス幅が10万人台を超えた(図表1)。なお、その他のエリアについてみると、名古屋圏では着実な人口増加が続いており、1994年以降、前年比4万人前後の増加ペースが続いている。一方、大阪圏では近年人口増加に陰りが見え始めており、2002年には▲0.4万人、2004年には▲0.8万人の減少となっている。
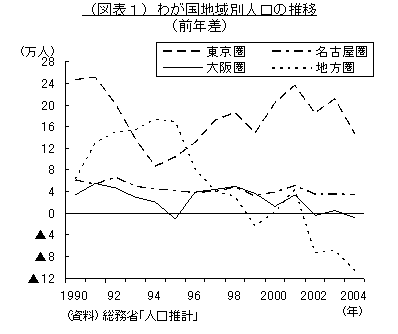
(ロ)それでは、わが国人口動態上、地域別格差が拡大している要因は何か。出生率は、地域別格差が依然小さくないものの、いずれの都道府県でも総じて趨勢的に低下しているため、とりわけ東京圏と地方圏の間で看取される対照的な動きの説明として不十分である。そこで、転入者数から転出者数を差し引いた転入超過数の推移を地域別にたどってみた(図表2)。
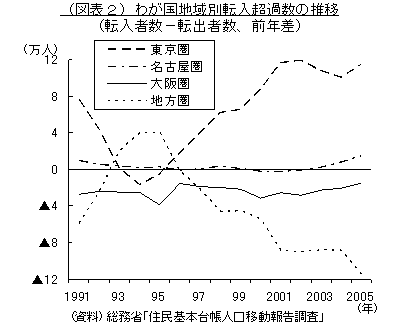
これによると、東京圏と地方圏の動きが対照的である点が、人口の推移をみるよりも一層鮮明である。すなわち、東京圏では94年の▲1.7万人、95年の▲0.5万人から96年に1.8万人のプラスに転じた後、年を追って増勢が加速し、2005年には11.5万人の増加となった。それに対して、地方圏では、95年の4.1万人増から96年に▲0.2万人のマイナスに転じた後、東京圏と正反対に年を追って減勢が加速し、2005年にはほぼ東京圏のプラスに見合う▲11.7万人の減少となっている。
その他のエリアについてみると、名古屋圏では長らく転入者数と転出者数がほぼバ
ランスした状態が続いてきたなか、転入超過数が2004年の0.8万人から05年に1.5万人へプラス幅が拡大している。一方、大阪圏は、総じてみれば2~3万人規模の転出超過が続いていものの、近年、若干ずつ転出超過数が減っている。すなわち、大阪圏の転入超過数は、2000年の▲3.2万人をボトムとして2005年には▲1.5万人となり、2000年から5年間でマイナス幅が1.7万人縮小した。
(ハ)以上を重ね合わせてみると、地方圏における近年の人口減少の深刻化は、出生率の低下が進むなか、地方圏から都市圏への人口流出傾向が加速した結果と整理することができよう。それでは、地方圏からの人口流出が加速した要因は何か。マクロ経済の視点からみれば、2002年1月を底に景気は回復局面に転じている。さらに地域毎にみても、バラツキがあるとはいえ、内閣府の地域経済動向をはじめとして総じて最悪期を脱し改善傾向をたどっているという認識が支配的である。ちなみに、完全失業率の推移を地域別にみると、エリアによって時期は若干前後するものの、北海道から九州まですべての地方で2002年をピークとして低下傾向が続いている。
こうした認識や失業率の推移と相矛盾する地方圏の人口減少や人口流出の現象をどのようにみればよいか。そこで、より雇用実態に即した動きをみる観点から、失業率という加工指標ではなく、就業者数と失業者数の推移に着目し、失業率が最悪であった2002年と直近の2005年との変化を地域別に対比してみた(図表3)。これによると、いずれの地域も完全失業率が1%ポイント前後低下し、失業者が減少している点では共通しているものの、就業者数の動向については、次の通り地域別に大きな差異がみられる。
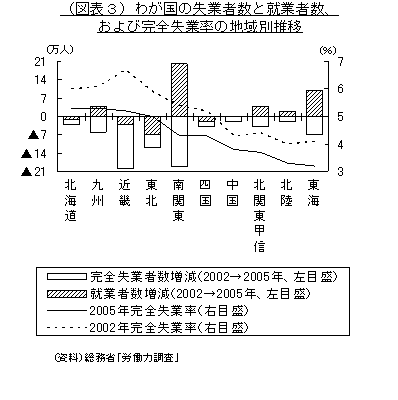
まず、失業者数の減少を上回って就業者が増加した地域、すなわち、景気回復に伴う労働需要の増大によって、失業者が就職するだけでなく、全体として新たに雇用が生み出された地域は南関東と東海の2エリアのみであり、それら以外の地域はすべて失業者の減少に見合った就業者数の増加さえ実現されていない。さらに、そうした地域のなかで若干でも就業者数が増えた地方は九州と北関東甲信、北陸の3エリアに過ぎず、それ以外の地域は、東北を筆頭に、就業者が減少するか横這いである。加えて、北海道、九州、近畿、東北の4地方の完全失業率は2005年時点でも依然全国平均を上回っており、失業者数の減少幅が相対的に小さい。
このようにみると、近年の失業率低下は、マクロ的にみて、失業者の受け皿を上回る新規雇用の創出という典型的な景気回復プロセスを通じて達成した地域は南関東と東海の2エリアにとどまり、それら以外の大半の地域では、新規雇用の創出よりむしろ単に失業者の減少によって実現されたものと位置付けられよう。失業者が減少したという点に着目すれば、最悪期を脱したという認識に間違いはない。しかし、失業の減少は、雇用が増えなくても、高齢者層が年金生活に入ったり主婦層が家庭に回帰するなど、求職活動を放棄する人が増えても看取されうる。労働者が増えない、さらに減少する現象は地域経済の停滞や不振を示唆する深刻な事態であり、景気回復が実感されないという一部の指摘は地域別にみれば正鵠を得た認識である可能性が大きい。
(ニ)加えて、近年の地方圏の人口減少は従来の想定を上回って進行している。ちなみに、国立社会保障・人口問題研究所が2002年3月に公表した都道府県別将来推計人口(図表4)に基づく2000年から2005年までの年平均増減数と、総務省都道府県別人口推計の実績値である2000年から直近2004年までの年平均増減数を対比すると、次の通りである。まず、東京圏は14.2万人増の想定から19.5万人増へ5.3万人上振れ、名古屋圏が2.3万人増の想定から4.0万人増へ1.7万人上振れた。それに対して、大阪圏は1.2万人増の想定から0.7万人増へ0.5万人下振れ、地方圏は▲2.1万人の想定から▲5.1万人へ3万人下振れ、減少スピードが加速している。2005年の地方圏からの転出者数が一段と増加した点を踏まえると、地方圏の人口減少は2005年に一層ペースアップした公算が大きい。
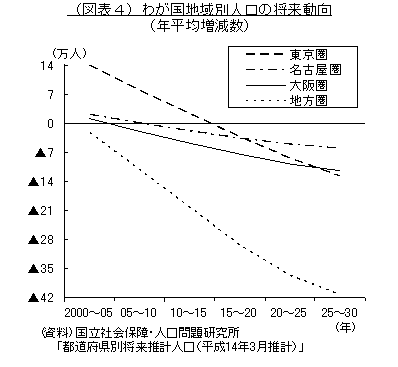
こうした地方圏での人口減少や人口流出、労働需要の停滞は、地方財政の健全化と並び、地域経済の自立と活性化を最終目標と位置付ける地方分権改革、さらに特区施策や地方再生対策なども含め、今日まで推進されてきた地域振興策だけでは、深刻な地域経済の低迷を打破するには力不足であることを物語っているといえよう。さらに、近年、三位一体改革をはじめとして地方分権改革が本格化するなか、逆に、人口減少や人口流出が加速化し、問題が一段と深刻化している現状に照らせば、中期的に腰の据わった骨太の対策を着実に推進していくだけでなく、早急に実効性の高い施策を打ち出し、強力に実施していくことは焦眉の急である。
強力な地域振興策の可及的速やかな展開が喫緊の課題とされるのは、地方経済がすでに深刻な停滞に直面しているうえ、今後、地方圏の人口減少スピードが一層加速する結果、地域経済が一段と厳しい低迷に陥る懸念が大きいからである。例えば、再び国立社会保障・人口問題研究所が2002年3月に公表した都道府県別将来推計人口をみると都市圏に比べて、地方圏の人口減少ペースは際立って速い(前掲図表4)。すなわち、東京、名古屋、大阪の3大都市圏では、今後、人口が減少局面に突入していくものの、年平均増減数は今から10年後の2015~2020年でも東京圏が▲3.1万人、名古屋圏が▲3.5万人、大阪圏が▲7.4万人にとどまる。それに対して、地方圏の年平均増減数は2005~10年の▲11.1万人から10~15年▲20.2万人、15~20年▲29.3万人と、5年毎に10万人単位で減少ペースが加速する。すでに2005年の地方圏からの人口流出数が11.5万人に達している点を加味すると、現行地域振興策の抜本的見直しが行われない場合、都道府県別将来推計人口の推計をさらに上回って地方圏の人口が減少する懸念は否定できない。 - 仏独米3カ国の動向
(イ)70年代以降、日独の台頭によって次第に産業空洞化の危機に直面したアメリカや、国内経済の低迷に陥った英仏では、地域経済振興に向けた様々な取り組みが積み重ねられてきた。主な取り組みを整理すると、規制緩和や小さな政府によって官民の役割を見直し、民間活力の発揚を目指した行政改革や自由化、あるいは税制改革による公的負担の軽減など、政策メニューは幅広い分野に及ぶ。
とりわけ地域経済振興についてみると、中央政府よりもむしろ地方政府が中心的な役割を担う推進スタイルが支配的である。中央政府が主体となる経済振興では単一あるいは少数の推進モデルとなりやすく、一国経済全体として底上げ効果は期待できるものの、各地域が、ヒト・モノ・カネ・情報といった経済資源を国内外から吸引する独自の魅力を生み出すことは難しい。それに対して、地域が推進主体になると、エリアの独自性をより強く追求することが容易になる。加えて、企業や大学と連携したり、近隣地域や隣接する外国自治体と協力して推進力を強化したり、一括交付金など、自由度の大きい資金を中央政府から獲得することで、地域事情に即した柔軟で機動的、戦略的な地域再生プロジェクトが推し進められるケースが多い。
こうした観点から、わが国でも、それぞれの地域に関する問題については国から自立して独自に政策展開を行う地方政府の構築が指向されている。地方分権21世紀ビジョン懇談会の報告書で提唱されている道州制も、こうしたコンテクストのなかで理解
されよう。もっとも、改めてわが国の道州制をめぐる議論をみると、財政制約などの観点から現行の都道府県を超える広域圏域を単位とする地方政府が必要であるとする認識がベースとなっている。例えば、地方制度調査会が2006年2月に公表した「道州制のあり方に関する答申」をみると、a.9道州、b.11道州、c.13道州、の3プランが具体的に提示されており、それによると、北海道を除き、さらに東京都を組み込むか否かの点で議論の余地が残されているものの、それら以外の府県はいずれも、東北や九州などといった地方圏に統合されて新たな道州制が誕生すると想定されている。
確かにわが国の現状に即してみれば、経済規模と地域活力との相関性が高いようにみえる。人口に即してみる本稿のスタンスに則り、改めてわが国の人口規模と人口増加率を都道府県別にみると、人口規模が大きい都道府県ほど人口増加率が高く、逆に人口規模が小さいほど人口減少率が大きい傾向が看取される(図表5)。前述の都道府県別転入出者数や雇用動向を重ね合わせてみれば、東京圏や名古屋圏、大阪圏に代表される人口規模の大きい都道府県ほど労働需要が大きく人口吸引力が大きいため転入者を引き付けるのに対して、人口規模の小さい都道府県では労働需要が相対的に小さく人口吸引力が小さいため転出者数が増大していると捉えられよう。
しかし、こうした地域統合は、地方政府が国から権限の移譲を受け、自立を獲得していくうえで必要不可欠な要素であろうか。また、そもそも経済規模と地域活力との関係には相関性、さらに何らかの因果関係があるのか。仮に両者の関係が希薄で地域統合が必ずしも必須要件ではなく、さらに現行の都道府県制あるいはそれをベースとしたスキームで良いのであれば、市町村合併で看取されたような様々な紆余曲折を経る必要がなくなり、より早期に本格的な地方分権を実現することが展望可能になる。
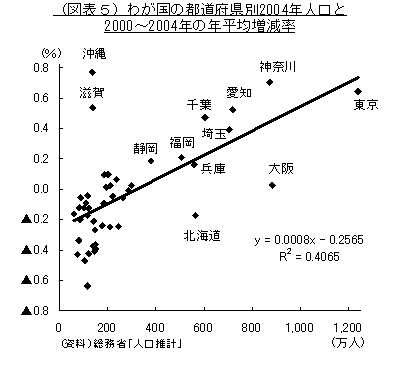
(ロ)そこで本稿では、こうした観点から、わが国よりも早くから地方経済の振興対策に取り組んできた諸外国のうち、州制度が採用されている米独仏3カ国について、近年の動向を人口や雇用動向を中心に取りまとめてみた。具体的には、まず州別に人口規模の分布をみたうえで、人口増加率のバラツキを確認し、人口規模と人口増加率の相関性についてチェックした。さらに、雇用増加率と人口増加率とを州別に対比してみた。これは、アメリカではメキシコ国境周辺で移民による人口増加がみられる一方、フランスではTGVや高速道路など交通網の整備・拡充に伴い南仏エリアで国内外から移住したり別荘を購入する動きが広がるなど、州別の人口増加率の格差がそれぞれの地域経済の活力を必ずしも反映した結果か否か不透明な部分があるためである。なお、検討する順序は、まずかつて代表的な中央集権国家とされ、82年の地方分権改革で州制度が導入されたフランスを取り上げ、次いで連邦制国家である米独のうち、相対的に州政府の権限が弱いドイツの実情を整理し、最後に州政府の権限が強いアメリカを概観した。
a.フランス
まず各州の人口規模を2003年末時点で対比してみると、最大がパリおよびパリ周辺の首都圏で構成されるイル・ド・フランス州で、1,126万人と他州に比べて際立って多い(図表6)。次いで、フランス第3の都市リヨンを中心とするローヌ・アルプ州が第2位で、589万人とイル・ド・フランス州のほぼ半分の人口規模である。第3位はローヌ・アルプ州の南に位置し、フランス第2の都市マルセイユを擁するプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州で467万人である。
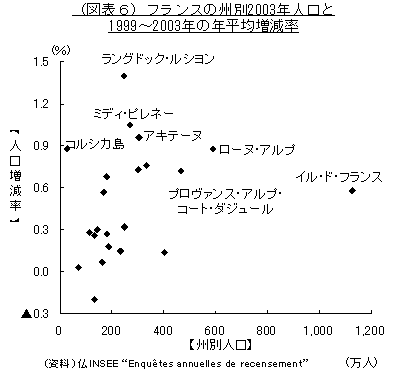
これら以外では、海外領土を除くと、最大がベルギー国境のノール・パ・ド・カレー州で403万人である。一方、最小はコルシカ島の27万人であり、次いでフランス中南部のリムーザン州が71万人であり、各州平均の人口規模は274万人である。ちなみに、わが国をみると、最大が東京都の1,238万人で、2位が大阪府の881万人、3位が神奈川県873万人であり、47都道府県の平均は272万人である。こうした点に着目すると、わが国の都道府県はフランス各州の人口規模とほぼ同様の規模と分布になっているといえる。
次に、99年から2003年までの年平均人口増加率をみると、最大がプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州の西隣に位置する南仏のラングドック・ルシヨン州で1.4%、2位がラングドック・ルシヨン州の西隣でスペイン国境に位置するミディ・ピレネー州で1.1%、3位はミディ・ピレネー州の西隣で大西洋に面したアキテーヌ州で1.0%、4位はプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州の北隣のローヌ・アルプ州で0.9%である。人口規模をみると、ラングドック・ルシヨン州は246万人、ミディ・ピレネー州が269万人、アキテーヌ州が305万人、ローヌ・アルプ州が589万人であり、ローヌ・アルプ州以外の州はフランスの平均的規模である。それらに対して、人口規模第1位のイル・ド・フランス州の人口増加率は0.6%にとどまる。
さらに、この人口増加率に99年から2003年までの年平均雇用者数増加率を重ね合わせてみると、総じて雇用増加率の高い州ほど人口増加率が大きく、近年のフランスにおける州別人口動態は各地域の経済活力の違いを反映した結果といえよう(図表7)。すなわち、27万人と突出して人口が少ないコルシカ島を除くと、雇用増加率が最も高い州は人口増加率が最大のラングドック・ルシヨン州で2.7%に上り、第2位は人口増加率で全仏中8位に位置する南仏のプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州で2.4%、3位は人口増加率第2位のミディ・ピレネー州で1.9%と、いずれもハイペースで雇用が増加している。逆に人口規模が最大のイル・ド・フランス州の雇用者数増加率は0.6%に過ぎず、全仏中最下位でイル・ド・フランス州の東隣であるシャンパーニュ・アルデンヌ州の0.4%に次いで下から2番めであり、首都圏および首都圏近郊の相対的な経済低迷が目立つ。
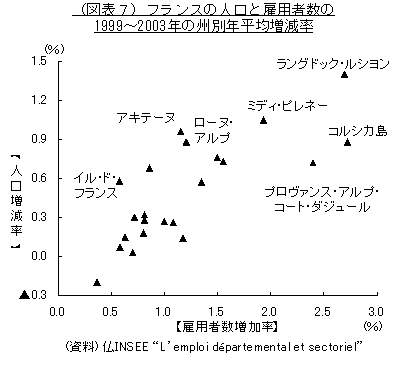
雇用や人口の増加率が高い主な州について、主な原動力を整理すると次の通りである。総じて南仏あるいは南仏隣接地域であり、交通網の整備が進むなか、居住環境の良さに着目した国内外からの移住や別荘購入の盛り上がりなどを背景に観光業や建設業が盛んであるうえ、近年、各地域それぞれ特色ある産業発展が看取される。
まず雇用増加率1位のラングドック・ルシヨン州では、欧州最古の大学医学部を誇るモンペリエ大学を中核として、バイオ医療分野を中心に研究機関や企業集積が進む一方、情報通信分野ではIBMやデル社、半導体メーカーが進出しているうえ、ミネラル・ウォーターをはじめ飲料食品産業が成長している。次いで雇用増加率2位のプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州では、まず、マルセイユ地域が、EU統合に伴って加速する地中海地域の物流拠点として成長している。加えて、ニース近郊のソフィア・アンティポリスで、欧州エリアの中核研究拠点という位置付けのもと、2003年末時点でフランス内外の1,276社が情報通信分野を中心に医療・バイオ、エネルギーなど幅広い分野にわたって進出しており、研究開発拠点としての産業集積が進展している。さらに雇用増加率3位のミディ・ピレネー州では、エアバス社の本社および中核工場が所在するトゥールーズを核として航空機産業を中心に機械工業が発達している。
一方、人口増加率第3位のアキテーヌ州では、隣州ミディ・ピレネー州の波及効果により航空宇宙産業の成長が展望される一方、1441年に起源をもつボルドー大学をはじめ高等教育機関が多く所在し学生数がヨーロッパ最大の7万人に及ぶなか、新規起業の動きが活発化している。さらに、人口増加率第4位のローヌ・アルプ州では、リヨンの病原体研究所を中核とするバイオ分野の研究開発が進む一方、グルノーブル周辺ではフランス産官学の協力、さらに外資も参入してナノテクをターゲットとするリサーチ・パークが形成され、そうしたなか、欧州委員会は2005年、ナノ2ライフ・プロジェクトを立ち上げ、グルノーブル・エリアをナノテクとバイオを融合させた欧州の研究開発拠点と位置付けた。さらに、拡大EUの中心という地理的利点を生かしてリヨンとグルノーブル間に所在するイルダボー・パークでは物流センターの建設が進んでいる。
こうした動きは、州別の転入出者数にも表れている。人口増減を出生や死亡による自然要因と転入出要因に分けてみると、人口や雇用が増加している地域では、おしなべて転出入要因が人口増加の主因となる一方、人口や雇用の伸びが低迷している地域では、逆に転出入要因がマイナスに作用している。例えば、99年から2003年までの年平均人口増加率に対する寄与度をみると、ラングドック・ルシヨン州では全体の伸び率1.4%に対して自然要因が0.1%、転出入要因が1.3%寄与し、ミディ・ピレネー州では全体の1.1%に対して自然要因が0.1%、転出入要因が1.0%寄与した。しかし、イル・ド・フランス州では、全体の伸び率0.6%に対して自然要因が0.9%寄与し、転出入要因は逆に▲0.3%のマイナスに作用する一方、シャンパーニュ・アルデンヌ州でも全体の▲0.2%のマイナスに対して自然要因は0.3%とプラスに寄与したものの、転出入要因が▲0.5%と大幅なマイナスに作用した。
こうした現象の原動力の一つが、パリあるいはパリ周辺から地方圏への企業や研究機関、大学の移転である。その背景には、TGVや高速道路など陸上交通網の拡充に加えて、ニースやソフィア・アンティポリスの近郊にはコート・ダジュール国際空港が、リヨンやグルノーブルにはサン・テグジュペリ空港があるなど空港施設の整備が進み、国内外の移動が容易である、あるいはEU統合に伴って南仏エリアの地理的有利性が強まったなど、様々な要因が指摘される。そうしたなか、各地方政府やサイエンス・パークの推進母体が総じて強調するポイントは投資コストの低廉さである。例えばソフィア・アンティポリスのオフィス賃貸料は首都圏に比べて大幅に低く、2005年第4四半期時点で1㎡当たり年間賃料は、ロンドンが1,251ユーロ、パリは690ユーロに上るのに対して、170ユーロにとどまる。加えて、気候が温暖で居住環境が良く、職住接近で良好なワーク・ライフ・バランスを享受でき、優秀な研究者や技術者など有為の人材を国際規模で集めやすいことも、ソフィア・アンティポリスをはじめ南仏エリアに国内外から多くの企業が進出した要因とされる。
これらを総合してみると、まずフランスでは、人口規模と人口増加の間に明確な相関関係は看取されない。さらに、わが国の都道府県とほぼ同様の人口規模を持つ州制度のもと、近年ではむしろ南仏エリアを中心に、投資コストの低廉さや地域独自の強みを前面に打ち出した地方圏で経済が活性化し、雇用や人口が増加している。
b.ドイツ
旧西独エリアと旧東独エリアで依然として無視できない経済格差があり、それらの単純な比較は適切性を欠くため、ドイツについては、旧西独エリアに焦点を当て州別格差についてみた(図表8)。まず各州の人口規模を2004年末時点で対比してみると、最大はデュッセルドルフを中心にルール工業地帯を擁するノルトライン・ヴェストファーレン州で1,808万人、第2位は南ドイツに位置しスイス、オーストリアに隣接するバイエルン州で1,244万人、第3位がバイエルン州の西隣に位置し、スイス、フランスと国境を接するバーデン・ヴュルテンブルク州で1,072万人である。4位は北西部に位置し、北は北海、西はオランダに接するニーダー・ザクセン州で800万人である。
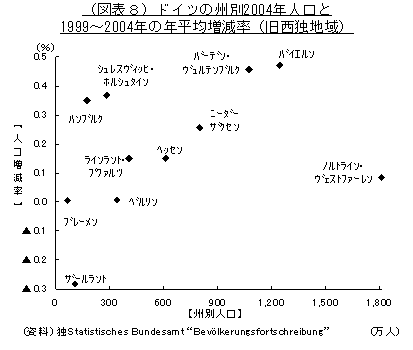
これら以外では、最大がノルトライン・ヴェストファーレン州とバーデン・ヴュルテンベルク州に挟まれたヘッセン州で610万人、最小はブレーメン都市州の66万人であり、その他は407万人のラインラント・プファルツ州から106万人のザールラント州まで総じて人口規模200万人から300万人台の州である。わが国と対比してみると、ノルトライン・ヴェストファーレン州に相当する都道府県はないものの、バイエルン州は人口1,238万人の東京都と肩を並べ、バーデン・ヴュルテンブルク州やニーダー・ザクセン州は人口881万人の大阪府や873万人の神奈川県にほぼ並ぶ。さらに、その他の州についても、人口最小のブレーメン州を含め、現在のわが国道府県の規模と大きな差異はない。
次に、99年から2004年までの年平均人口増加率をみると、最大がバイエルン州で0.47%、次いでバーデン・ヴュルテンブルク州が0.46%、第3位はシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州で0.37%である。逆に人口規模が最大のノルトライン・ヴェス茨城県トファーレン州は0.08%にとどまる。人口増加率が同州を下回る州は、a.旧東独時代の影響が残り、人口339万人で増加率0.01%のベルリン州、b.炭鉱と製鉄が依然主要産業であり、人口106万人で増加率▲0.28%のザールラント州、c.404k㎡とドイツ全州のなかで最も面積が小さく都市州の性格が強いものの、(北海に接し物流拠点として成長し、さらに積極的な産業振興に奏功したハンブルク都市州と異なり、)観光業を除くと相対的に有力産業が見当たらない、人口66万人で増加率0%のブレーメン州、の3州だけに過ぎない。逆に、ノルトライン・ヴェストファーレン州の人口増加率を上回る州はバイエルン州をはじめ7州に上っており、フランスと同様にドイツでも人口規模と人口増加率との間には明確な相関関係は看取されない。
さらに、この人口増加率に99年から2004年までの年平均雇用者数増加率を重ね合わせてみると、この点でもフランスと同様に総じて雇用増加率の高い州ほど人口増加率が大きく、近年のドイツにおける州別人口動態は各地域の経済活力の違いを反映した結果といえよう(図表9)。すなわち、雇用者数増加率が最大の州は人口第2位のバイエルン州で伸び率が0.14%、州都ミュンヘンを中心にBMWの輸送用機械製造業やアリアンツをはじめとする金融業が牽引役となっている。次が人口第3位のバーデン・ヴュルテンブルク州で伸び率は0.12%、州都シュトゥットガルトを中心にダイムラー・クライスラーやポルシェ、シーメンスなどの機械工業が拡がる一方、州北部のライン・ネッカー郡のヴァルドルフには企業向けERPパッケージ分野で世界屈指のSAP社の本社が置かれ、ソフトウェア分野でも躍進している。
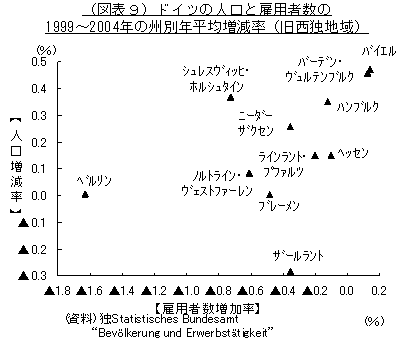
こうしたバイエルン州とバーデン・ヴュルテンブルク州に対して、それら以外の9州はいずれも雇用者数が減少している。マイナス幅が最大の州はベルリンで▲1.63%に達しており、依然として旧東独要因を払拭するに至っていない。マイナス幅第2位はバルト海に面した北部ドイツのシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州で、かつて軍港だったキールの物流業やリューベックの造船業以外、強力な牽引役が見当たらないなか、▲0.73%で雇用が減少している。マイナス幅第3位は人口規模が最大で、重化学工業主体のルール工業地帯を擁するノルトライン・ヴェストファーレン州が▲0.61%に落ち込んでおり、特殊要因が指摘できるベルリン州を除いてみると、シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州と並び、旧西独エリアのなかで、相対的に経済活力の低迷が著しい。
総じてみれば、フランスと同様に、ドイツでも雇用者数の増減と人口の増減に相関関係が看取されるうえ、人口規模の大きい地方よりも、むしろ人口規模が中堅から小さな地方で雇用や人口の増勢が大きい。なお、こうした見方に対しては、バイエルン州やバーデン・ヴュルテンブルク州は、人口が1,000万人を超えており、人口規模が中堅の地方とはいえないという指摘が想定されよう。
しかし、ドイツの場合、連邦全体でも各州別にみても、総じて中核都市に一極集中するよりも、中堅・中小規模の都市が分立する傾向が強く、フランスのような首都圏への一極集中問題は生じていない。ちなみに、州別の1k㎡当たり人口密度を州別にみると、フランスでは、首都圏のイル・ド・フランス州が940人であるのに対して、人口が増加している地方圏をみると、ラングドック・ルシヨン州90人、ミディ・ピレネー州60人、プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州が150人と隔絶したギャップがある。それに対して、ドイツでは、バイエルン州は176人でプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州とほぼ同水準である一方、バーデン・ヴュルテンブルク州は300人とやや多いものの、フランス首都圏に比べると大幅に少ない。
そうしたなか、2005年第4四半期時点におけるミュンヘンのオフィス1㎡当たり年間賃料は342ユーロで、フランスのソフィア・アンティポリスの170ユーロより高いものの、ロンドンの1,251ユーロやパリの690ユーロに比べれば格段に低い。バイエルン州やバーデン・ヴュルテンブルク州は、人口総数に着目する限り、欧州のみならず世界有数の都市圏と位置付けられるものの、分散化している分、ロンドンやパリで発生しているような人口集中に伴うコスト増問題は発生していない。一方、ノルトライン・ヴェストファーレン州の人口密度は1k㎡当たり530人で南独2州を上回っており、相対的にみれば、人口集中に伴うコスト増問題が発生している可能性は否定できないものの、パリに比べれば大きく下回っている。以上の諸点を総合すれば、同州やシュレースヴィヒ・ホルシュタイン州、あるいはベルリン州、ザールラント州と南独2州との経済活力の格差は、各国経済・産業が置かれた現下の事業環境に即したリーディング産業の有無、あるいはその牽引力の多寡が主因と総括されよう。
c.アメリカ
まず各州の人口規模を2005年時点で対比してみると、最大はカリフォルニア州で3,613万人、2位はテキサス州2,286万人、3位はニューヨーク州1,926万人である(図表10)。いずれも、わが国都道府県のなかで人口が最大の東京都の1,238万人を大きく上回る。そこで、もう少し下位のランキングまでみると、4位がフロリダ州で1,779万人、5位がイリノイ州で1,276万人、6位がペンシルベニア州で1,243万人である。いずれもアメリカを代表する有力州であり、この点に着目すれば、わが国でも現行の都道府県を統合して新たな道州制の導入が必要という見方も成り立とう。
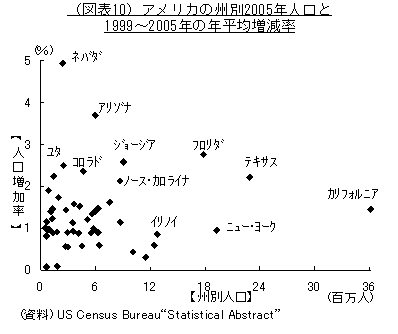
しかし、アメリカにも人口規模の小さい州は少なくない。例えば、わが国で人口が集中している都市圏として、首都圏の4都県および大阪府と愛知県の6都府県をみると、いずれも人口が600万人を超えるのに対して、それ以外の41道府県は600万人を下回る。そこで、便宜的に600万人を分岐点として区切ってみると、アメリカで600万人を上回る州は15州にとどまる一方、600万人を下回る州は32州に及ぶ。加えて、人口が最も少ないワイオミング州は51万人であり、わが国都道府県のなかで人口が最小の鳥取県の61万人をさらに10万人下回る。すなわち、国際的にみて独立色の色濃いアメリカ州制度を遂行する直接的主体である各州をみると、わが国地方圏の道府県とほぼ同様の人口規模で行っている州が全体の3分の2強を占めている。
こうした点に着目すれば、わが国が国と地方自治体の役割分担を抜本的に見直し、地方自治体の権限を飛躍的に強化するために、現行の都道府県を統合して新たな道州制の導入が必要不可欠であるとする主張が十分な説得力を具備しているとは言い切れない。さらに、フランスやドイツの状況を加味すれば、わが国都道府県の人口規模が過度に小さく、各国州政府が保有するような大きな権限を、わが国において国から都道府県に移譲することは難しいという主張は一層成り立つまい。
そうした指摘に対して、わが国の場合、地方圏の経済基盤は脆弱であり、経済活動の広域化に対応した広域行政を可能とするべく、現行の都道府県の統合が必要であるという反論が予想されよう。そこで、こうした言説の当否を検討するために、次に、アメリカについても、まず、99年から2005年までの年平均人口増勢の大きい順にみる。最大は、カリフォルニア州の東隣に位置し人口241万人のネバダ州で伸び率4.9%と全米のなかで際立って増加率が大きく、第2位が同じくカリフォルニア州の東隣、ネバダ州の南隣に位置しメキシコと国境を接する人口594万人のアリゾナ州で3.7%と、いずれもアメリカ西部の州である。次いで、第3位は人口1,779万人のフロリダ州で2.8%、第4位はフロリダ州の北隣に位置する人口907万人のジョージア州で2.6%と、アメリカ南東部の2州が続いている。さらに5位から7位は、人口907万人のユタ州が2.5%、247万人のコロラド州が2.4%、467万人のアイダホ州が2.2%と、ネバダ州以北のアメリカ西部各州が並んでおり、総じてアメリカ西部の人口規模が中堅以下の州が上位を占める。
一方、人口規模上位3州についてみると、2位のテキサス州は2.2%と全米平均増加率を上回るものの、最大のカリフォルニア州は1.4%であり、さらに3位のニューヨーク州は0.9%と伸び悩み傾向がみられる。その結果、全体としてみると、人口規模と人口増加率の間には明確な相関関係は看取されず、むしろ、州の人口規模が小さくなるにつれて人口増加率のギャップが拡大する傾向がみられる。例えば、2,000万人規模ではテキサス州やフロリダ州とニューヨーク州との格差は1%ポイント強にとどまるのに対して、100万~200万人規模になると、4.9%のネバダ州と0.1%と最低のウェスト・バージニア州とのギャップは5%ポイント弱まで拡がる。もっとも、伸び率の相対的に大きい州だけに着目すると、全米平均の人口増加率1.4%を上回る州は、人口が600万人を超す相対的に規模の大きい州で6州であるのに対して、600万人に満たない中堅規模以下の州では10州に上り、中堅規模以下の州が人口増加の中心となっている。
次に、99年から2005年までの年平均雇用者数増加率を重ねてみると、雇用と人口の増加には相関関係が看取され、例えば上位3位まで人口増加率の順位と同じである(図表11)。すなわち、1位がネバダ州で3.7%、2位はアリゾナ州で2.5%、3位はフロリダ州で2.3%である。4位はアイダホ州で2.2%、5位はワイオミング州で2.0%であり、人口増加率と同様に西部諸州が上位を占める。一方、人口規模が最大のカリフォルニア州は0.9%、第2位のテキサス州が1.0%と全米平均の雇用者数増加率0.6%を若干上回るものの、第3位のニューヨーク州は0.1%にとどまり、ほぼ横這いである。
全体としてみると、雇用の伸び悩みに直面している中堅規模以下の州が相当数に上る一方、雇用者数増加率が全米平均を上回る州を数えると、人口が600万人を超す相対的に規模の大きい州が5州である。それに対して、600万人に満たない中堅規模以下の州が21州に上っており、一部の州を除けば、このところのアメリカの雇用増加は人口規模が中堅以下の州によって牽引されている。
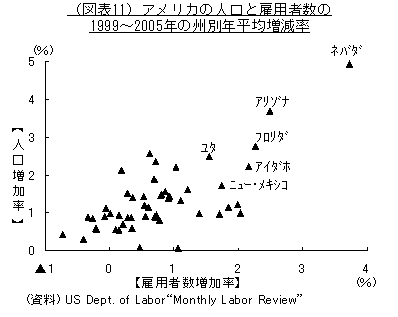
それでは、アメリカの場合、ハイペースでの人口や雇用の増加が中堅規模以下の州に多い要因は何か。まず全米のなかで際立って伸び率が大きいネバダ州についてみると、温暖な気候やカジノを中心とする娯楽施設の集積を背景に、観光業やサービス業が盛んなことに加え、近年、隣州カリフォルニア州を中心に州外からの企業移転が進展し人口が流入していることが指摘される。その根底には投資コストの相対的低さがある。例えば、生計費指数をみると、同州はカリフォルニア州に比べて2割強低い(図表12)。この点に着目し、同州政府は投資や雇用に対する優遇税制や整備された交通網などと併せ、電力料金や労働コストも含めた投資・事業コスト面の有利さを強力にアピールし、積極的に誘致活動を展開している。さらに、こうした取り組みはネバダ州のみならず、カリフォルニア州の周辺諸州で広く行われており、西部各州の人口増加はコスト格差を活用した企業誘致が原動力の一つとなっているといえよう。
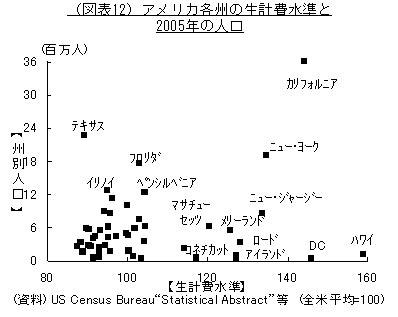
さらに、こうした視点からテキサス州やフロリダ州をみると、両州は、たんにテキサス州の石油業や電気製造業、フロリダ州の航空宇宙産業や半導体製造業などの産業集積が進んでいるだけでなく、ニューヨーク州やカリフォルニア州に比べて人口規模が大きい割にコスト競争力がある点に気が付く。こうした利点が、全米でも屈指のテキサス大学やフロリダ大学の人材供給力や研究開発力と共鳴しあい、カリフォルニア州のシリコンバレーになぞらえてテキサス州オースティンはシリコンヒルズ、フロリダ州マイアミがシリコンコーストとして著名になるなど、両州での新産業の台頭に寄与した。
こうしたアメリカ各州の動きにフランスやドイツの州別人口や雇用の動向を重ねてみれば、地方圏の経済基盤は脆弱という見方は正確さを欠く。少なくとも米独仏3カ国に即してみる限り、地方圏経済は、近年、フランスのイル・ド・フランス州、ドイツのヴェスト・ファーレン州、アメリカのニューヨーク州というかつての中核エリアに代わる経済成長のリーディング・エリアとして一段とその役割を増している。 - 今後の課題
(イ)世界的にオリジナリティーの高い日本的経営がバブル崩壊以降の深刻な経済停滞からわが国が脱却する拠り所となった経緯を踏まえ、そのアナロジーから国土開発においても、諸外国と同様である必要はなく、むしろ独自のスタイルを追求すべきという見方もありえよう。
しかし、少なくとも首都圏への一極集中型成長スタイルには制約が大きい。国際規模で企業間競争が激化するなか、地域経済の発展を実現するうえで、重層的な産業集積や強靭な研究開発基盤、有能かつ多様な人材プールといった諸条件に加えて、BRICsをはじめ先進各国以外の経済が近年急速に台頭するなか、投資・事業面でのコスト競争力強化の必要性が一段と重要になってきたからである。とりわけ、中核都市では人口集中や産業集積に伴う投資・事業コストが増大しやすい。現実に、ニューヨーク州、ヴェスト・ファーレン州、イル・ド・フランス州という米独仏3カ国におけるかつての中核エリアをはじめ、先進各国の中核都市圏では、すでに80年代以降、人口が次第に伸び悩み傾向に転じており、総じて成長力に昔日の面影はみられなくなっている。
わが国には日本的経営という強力な武器があるとはいえ、コスト競争力も含め総合力の強さを競う世界規模での企業間、地域間競争に一段と拍車がかかるなか、わが国ひとり集積のメリットのみ享受し、デメリットを回避することは難しい。一方、現行の経済・政治・社会スキームが温存される限り、わが国地方圏の経済停滞が一段と深刻の度を増していく懸念が大きく、都市圏の牽引力だけでわが国経済の成長を中期的に確保していけるか否かは極めて不透明と判断せざるを得ない。
このようにみると、地方経済の停滞打破と再生の実現は焦眉の急といえよう。無論、経済活性化は多種多様の要素から構成される総合的プロジェクトであり、主なポイントを挙げるだけでも、人材育成や研究開発力の強化、起業支援制度や投資・雇用促進策の拡充など、多岐にわたる。もっとも、わが国地方圏が直面する事態の緊急性に即してみれば、とりわけ次の三つの改革の断行が喫緊の課題である。
(ロ)第1は、現在の地方分権改革論議に沿っていえば、道州制を棚上げする一方、都道府県に国から大幅に権限と財源を移譲し、地方政府が独自に政策展開を行える仕組みへ改変することである。
まず、地方分権21世紀ビジョン懇談会の報告書、さらに本報告書が依拠すべきとする地方制度調査会の「道州制のあり方に関する答申」をみると、現行の都道府県は広域行政を行ううえで難点があり、財政基盤も十分でないから、国から包括的な権限と財源の移譲を行うには都道府県を地域別に統合した道州制が適切であり、10年後の実現を目処に検討すべきとされる。しかし、「道州制のあり方に関する答申」で具体的な統合プランとして3案が示されている通り、統合のスタート・ラインである区分自体未定であるうえ、国から移譲される権限や財源は何かから、州都をどこに置くか、統合後の新組織をどうするかまで、多様な問題が山積しており、今後10年間で実現できるか否か予断を許さない。
仮に10年間で道州制が発足したとしても、国立社会保障・人口問題研究所が2002年3月に公表した都道府県別将来推計人口に基づけば、地方圏の人口は2005年から15年の間に156万人減少する。加えて、想定を上回る転出増加による近年の人口下振れが今後も続くと地方圏の人口減少数は186万人に達する。さらに、道州制への移行が10年間先送りされ、権限と財源の抜本的移譲が本格化せず、地方独自の政策展開が難しいとすれば、今後少なくとも10年にわたり地方経済の低迷が深刻化し、人口流出傾向が一層加速する可能性も否定できない。そうなると、現時点で十分な財政基盤を備えていると看做せる道州圏が、今後、例えば10年後に変わらず財政基盤を維持できているかは不明であり、むしろ財政基盤が脆弱化する自治体が続出するリスクが大きい。
一方、わが国の都道府県は、人口規模でみる限り、ドイツのヴェスト・ファーレン州、アメリカのカリフォルニア州やニューヨーク州など数州を除くと、米独仏3カ国の州政府とほぼ同様であり、国から広範にわたる権限とそれに対応した財源の移譲を受ける主体として特段の問題はない。今後10年間を道州制の議論に費やし、地方圏への権限と財源の移譲を先送りして地方経済の疲弊を座視するより、一日も早く、地方政府が独自に政策展開を行えるよう本格的地方分権の断行を行うことこそ最優先課題である。
そうした国と地方の役割分担の抜本的見直しを行うに当たっては、プロセスをスピーディーに進めるために、フランスが82年に断行した地方制度改革を参考にすべきである。これは、フランスの改革には次のような事情と経緯があるからである。すなわち、ドイツやアメリカが建国以来連邦国家であるのに対して、フランスは単一国家であり、戦後長らく中央集権体制を堅持していた。しかし、パリ首都圏への一極集中問題と地方経済の低迷が次第に顕在化し、2度の石油危機によって一段と深刻化するなか、国から地方へ広範にわたる権限と財源を移譲する地方分権改革が82年に行われ、地方再生が目指されることになった。その意味で、南仏エリアを中心とするフランス地方圏の旺盛な経済成長は、EU統合や経済のグローバル化による効果に加えて、地方分権改革の成果との位置付けが可能である。さらに、2003年には憲法改正が行われ、国から地方への権限移譲は財源措置とセットで行われなくてはならない点が明記された。
(ハ)第2は地域再生の強力なスキームを整備、構築することである。
まず、地方圏の現状に即してみる限り、わが国の現行地域再生スキームが問題を孕んでいることは明らかであろう。しかし、広範にわたる権限や財源を国から都道府県に移譲すれば、それだけで地域再生が成功するとは限らない。地域再生プロジェクトは様々な主体が関与する総合プロジェクトであるだけに、プロジェクトに対する各主体の積極的参画を実現することなしに、推進力の強化は困難なためである。
もっとも、地域再生プロジェクトは多様性に富む取り組みであり、加えて地域それぞれの特殊性や市場ニーズの動向など様々な要素に左右されるため、プロジェクト一つひとつについて課題を抽出してみても、焦点が拡散しやすく、問題点を整理し切れない懸念が大きい。そこで以下では、地域再生で成果を挙げてきたイギリスのスキームの特徴をみることで、わが国が目指すべき地域再生の枠組みのポイントを整理してみた。
まず、91年に発足したシティ・チャレンジ補助金制度が指摘される。その主な特徴は次の3点である。すなわち、a.財政資金と民間資金を組み合わせたり、企業ノウハウなど民間活力を積極的に活用する一方、住民ニーズを取り入れ、推進スキームを柔軟なスタイルとした。b.再開発計画を策定し遂行する主体を地方自治体に限定せず、NPOなどの地域組織と地方自治体、民間企業など、プロジェクトに関与する者すべてに拡げ、パートナーシップの形成が義務付けられた。その結果、参加企業の積極的活動によってプロジェクトの実効性や推進力が強化される一方、NPOなどによって地域ニーズが吸い上げられ、地域問題の解決が図られた。c.条件が充足される限り、申し込まれたすべてのプロジェクトに補助金が交付されるバラマキ型スキームから、実効性が確保され大きなメリットが期待できるプロジェクトに対して重点的に予算を投入する競争型スキーム、いわゆるグラント型に補助金制度が改変された。その結果、地域の特殊性や強みを最大限活用することで事業性が高く、戦略的なプロジェクトが実施され、資金の効率的活用が進んだ。
次いで、94年に創設された単一振興予算制度、さらに2002年の単一予算制度によって、省庁毎に細分化されていた関連補助金が次第に統合され、資金使途が自由化された結果、弾力的な資金の活用が可能になった。この制度改定の根底には、地域経済再生事業を成功させるためには、都市の一区域について開発事業を行うだけでは不十分であり、地域全体にわたって、さらにインフラ整備や人材育成、保育・医療サービスの拡充も含め、長期的見地に立って総合的に地域再生事業に取り組んでいく必要がある、とのコンセンサスがあった。
このようにみると、地域再生プロジェクトを成功させる要諦として次の点が指摘できよう。すなわち、a.地方政府が主体となる一方、プロジェクトに参画すべき企業や研究機関、住民やNPO、さらに隣接する内外の自治体などの多様な主体が積極的に参画できる。b.対策を個別に行うのではなく、人材育成からインフラ整備、需要発掘までプロジェクトの一環として総合的に取り組む。c.競争原理を導入したり、インセンティブを付加することで、地域の特殊性や強みを最大限発揮させる。d.市場ニーズの動向や要素技術の変化に応じて機敏に戦略を修正したり、投資額を増減させる柔軟性を備える、の4点である。
(ニ)第3は地方政府のマネジメント力の飛躍的強化を図ることである。地域再生事業は国内のみならず、海外諸地域との厳しい競争を勝ち抜く高い戦略性を要求されるプロジェクトであり、単なる予算消化型の事業推進スタイルで成功は覚束ない。
こうした観点からみれば、今日、地方自治体の住民サービスにみられる業務スタイルで成果が上がる保証はない。むしろ、近年、アメリカの地方自治体で盛んに導入されているシティー・マネジャー制度の活用が有力であろう。これは、現在の制度では首長は選挙を通じて選任されているため、任期が設けられ、任期途中の解任が原則不能であるのに対して、シティー・マネジャーは、自治体運営の高い能力や技能を根拠に議会によって任命されるため、プロジェクト遂行の成否や巧拙、あるいは事情変化を理由として解任し、より適切な人材を登用することも容易にできるからである。
さらに、プロジェクト遂行に直接携わる公務員に対する業績評価の実施やプロジェクトの変更に伴う組織の柔軟な改変、配置転換など、公務員制度の見直しも重要なポイントである(藤井[2005b])。加えて、一定の財政制約のもとで新規事業を立ち上げる、あるいはプロジェクトの推進力強化のために投入する人員や資金を拡大させるためには、既存事業の見直しが避けられない。そのためには、すでに導入済みのPFIや指定管理者制度、さらに今後、本格的な導入が想定される市場化テストを含め、行政改革を一段と強力な遂行が不可欠である。しかし、わが国の場合、従来、組織の改廃やそれに伴う解雇、あるいは分限免職が現実に実施されるケースは稀であり、制度上、未整備なままに放置されている点が少なくない。
とりわけ、次の2点は早急な解決が必要である。すなわち、a.諸外国で広く認められている労働基本権、すなわち、団結権と団体交渉権、さらに団体行動権の労働三権を、わが国公務員にも認める。②職員の身分について官から民への円滑な移籍を促すために、EU指令に基づいて97年にイギリスで導入されたTUPE(Transfer ofUndertaking-Protection of Employment)制度を導入する。これによって、公的セクターが実施してきた業務を民間に開放する市場化テストを現実に実施することが可能になる。
(ホ)歳出歳入の一体改革を進め、公的セクターの財政破綻を回避するという視点からみれば、地方交付税の見直しと税源移譲、補助金改革からなる三位一体改革、さらにそれを核とする地方財政のリストラは最重要テーマの一つである。しかし。すでに厳しい状況に直面し、今後、一段と深刻化が懸念される地方経済が再生を遂げるためには、単に三位一体改革だけでは不十分であり、国から広範な権限と財源の移譲が不可欠である。
加えて、事態の緊要性に照らせば、1日も早い権限と財源移譲が必要である。そうした観点からみると、道州制、さらにこのところの地方分権の議論は、抜本的改革を10年後に先送りするものであるだけに、地方経済の疲弊を修復不能な窮状に陥るまで放置することになりかねず、分権改革によって却って改革の目的が達成できなくなる逆説的構造を持っているとさえいえよう。
米独のみならず、フランスでも82年の地方分権改革によって多様性と成長力に富む地域経済が近年実現されてきた。首都圏一極集中は政策の貧困に起因する事態であり、これを放置すれば、地域間格差の問題を拡大させる一方、少子高齢化のさらなる進行を加速させ、わが国経済が中期的停滞を余儀なくされるリスクが大きい。循環的景気回復に目を奪われることなく、新政権登場を間近に控え、中長期的視点からの骨太の改革が望まれる。

