Business & Economic Review 2006年07月号
【OPINION】
見直すべき給付削減型財政改革-わが国の社会政策支出は先進国中最小
2006年06月25日 藤井英彦
- 財政健全化に向けた取り組みが本格始動
(イ)財政健全化に向けた動きが本格化している。2010年代初頭において基礎的財政 収支を国・地方合算ベースで黒字化させる目標を達成するべく、政府は、2006年度、 まず年央をめどに改革の選択肢ならびに改革工程を明確にし、年度内に歳出・歳入一 体改革について結論を得るとするスケジュールを本年初、公表した。
これまでの議論を整理してみると、行政改革を一段と推進し歳出削減を図る点につ いて異論は少ない。議論の核心は、図式化すると、まず、歳出削減だけで財政権限を 目指すのか、それとも、深刻な歳入欠陥を是正するには歳出削減だけでは困難である ため、消費税率引き上げなど、歳入増加を組み合わせる必要があるのか、が入り口で ある。次いで、この点では総じて歳入増加を組み合わせる必要があるという見方が大 勢であり、焦点は、歳入増加を図るとしても、公的負担の増大をどこまで容認するか に絞られている。
例えば、2006年3月29日の経済諮問会議資料に即してみると、2011年度に基礎的財 政収支の均衡を実現させるためには、消費税率の引き上げだけで対応する場合、消費 税率を6%前後引き上げ、11%内外の水準にする必要がある一方、歳出削減だけで対 応する場合、すべての経費を一律18%削減しなくてはならない。経費一律18%削減の インパクトを社会保障分野について個別にみると、a.医療では患者の自己負担を倍増 させ、b.介護の自己負担は2.5倍に増加させて、c.年金の基礎年金支給開始年齢は65 歳から69歳に引き上げ、d.児童手当では支給対象を現行の小学校6年生以下から4年 生以下に引き下げることになるとされる。これは機械的な計算結果であり、政策的イ ンプリケーションは含意されないものの、経費18%削減のインパクトは相当大きいと いえよう。
(ロ)しかし、こうした財政健全化を巡るこのところの議論には問題が少なくない。 主なポイントをあげれば、まず議論のフレームワークが矮小化されていることである。 すなわち、負担と受益という観点からみれば高負担高福祉から低負担低福祉まで、さ らに公的セクターの位置付けや官民の役割という観点からすると大きな政府から小さ な政府まで、多様な組み合わせと選択肢があるなか、現下の議論では、負担と給付の 枠組みで整理すると、a.負担は増加するが給付は現状維持、b.負担は一部増加し給付 は一部削減、c.負担は現状維持として給付削減、のいずれを選択すべきかが争点にな るのにとどまる懸念が大きい。その場合、目指すべき負担と給付の組み合わせや公的 セクターの役割について議論が深化せず、抜本的改革が先送りされかねない。
次いで、歳出削減と給付カットが連動する関係として議論が展開されていることで ある。確かに政府支出の大半は、社会保障や文教分野に代表される通り、国民に対す る給付で占められる。しかし、サッチャー政権以来メージャー政権を経て今日のブレ ア政権に至る、エージェンシー化や民営化、PFIや市場化テストなど、20余年にわた るイギリスの様々な改革を代表例として、1990年代以降欧米各国で断行されてきた行 政改革は、総じてみれば、国民への給付をカットして歳出を削減するのではなく、国 民に対するサービスについては、質量両面から維持・向上および拡大を図りながら、 コスト削減を実現させていく取り組みであった。こうした観点からみると、歳出規模 と給付のボリュームを連動させ、給付カットと負担増の二者択一を迫る議論はやや短 絡的との謗りを免れない。
(ハ)それでは、財政健全化への取り組み、さらに歳出・歳入一体改革を巡る議論を どのように軌道修正すればよいか。本稿では、欧米先進各国との対比という視点から アプローチしてみた。 - 公的負担増加余地は限定的
(イ)現下の財政健全化の議論では、現行比大幅な給付カットが好ましくないとすれ ば、公的負担の増加は不可避とされる。それでは、そもそもわが国の負担と給付の規 模は、国際的にみて、どのような水準に位置するか。
こうした観点から、欧米先進各国と、国・地方を含めた政府全体について総収入と 総支出をGDP比で比べてみた(図表1)。なお、データは最新の2004年とし、対象国 はG7、およびスウェーデン、フィンランド、デンマークの北欧3カ国を加えた10カ 国とした。北欧各国を加えたのは、女性の社会進出や少子化問題への対応、さらに公 教育の充実など、今日多くの国々が直面する政策課題を適切に克服してきているから である。
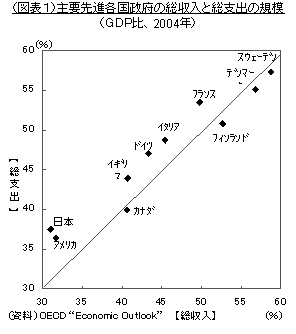
それによると、国によって若干のバラツキはみられるものの、総じて収入規模と支 出規模が見合っており、GDP比でみると、30%強から60%弱まで幅広い分布となって いる。そうしたなか、便宜的に収入規模を10%刻みでグループ分けをしてみると、 50%台には北欧3カ国とフランスの計4カ国が含まれ、40%台には英独伊加の4カ国 が入る。それに対して、30%台には日米2カ国がいずれも30%強と、他の8カ国から 大きく外れて低い水準に位置する。
まとめると、他の8カ国ではGDP比4割から6割弱の公的負担が課されており、そ れに比べて、わが国の負担水準は相対的に低いといえよう。この点に着目すると、わ が国の場合、公的負担を増加させる余地が相当の規模で依然残っているようにみえる。 加えて、総支出が総収入を上回る差額、すなわち、歳入不足規模は欧州主要各国が 3%台にとどまるのに対して、アメリカは4.7%、日本は6.5%であり、とりわけ日米 両国では支出に見合った負担の徴収が行われていないとみることも可能であろう。
(ロ)このように国によって公的負担の規模が大きく異なるうえ、政府支出に応じた 負担は必ずしも賦課されていない国がある。例えばわが国は、公的負担の規模は各国 中最小であるうえ、歳入不足規模は各国中最大である。この点に注目すれば、わが国 国民は他の国々を上回る経済的余裕を享受していて何等不思議ではない。
そこで1世帯当たりの年間消費支出を日米独3カ国で対比してみた(図表2)。な お、ここでは比較のベースを揃えつつ、広範な調査対象とするために対象世帯を、わ が国は夫婦のみまたは夫婦と未婚の子供から成る世帯とする一方、アメリカとドイツ は、夫婦のみまたは夫婦と子供から成る世帯とした。さらにドイツは旧東独を除いて 旧西独ベースとする一方、調査年次は2003年とした。比較の容易さという観点から、 米独とも円建てに換算し、市場為替レートと購買力平価の二つの計数を算出した。加 えて、わが国については、住居費に土地家屋借金返済を、教育費に仕送りをそれぞれ 加算する一方、宿泊・飲食費については詳細区分が不詳のため、わが国は外食費とし、 アメリカは外食と個人サービスを合算した金額とした。
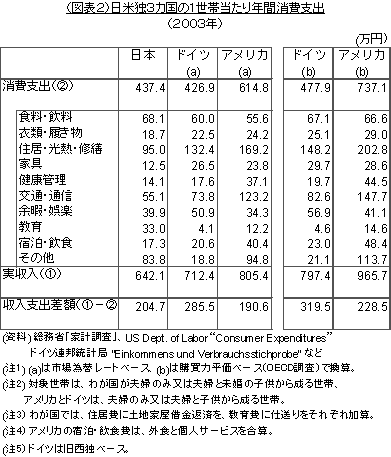
まず、わが国が米独を上回る支出項目は「食料・飲料」と「教育」の二つである。
それに対して、「住居・光熱・修繕」と「家具」、「交通・通信」の3項目は米独がわ が国を大幅に上回る。家具は居住関連と位置付けることができるため、住居費と併せ てみることとし、わが国が米独と異なるこれら4費目について、やや詳しくみると次 の通りである。なお、これら以外の費目についてみると、米独がわが国を上回る費目 では、健康管理費は、健康保険が公的制度として整備されている日独で少額であるの に対して、公的な保険制度のないアメリカで高く、制度の整備状況によって家計負担 が異なる点で、下記の教育費と相似した図式になっている。一方、「衣類・履き物」 や「宿泊・飲食」も米独がわが国を上回るものの、その格差は相対的に小さい。それ ら以外では「余暇・娯楽」はドイツが日米を上回って多く、「その他」では逆に日米 がドイツを上回る。わが国の「その他」には、a.使途不明のこづかい、b.季節の贈答 などの交際費、c.タバコや身の回り品などの諸雑費、の3費目が含まれ、諸雑費だけ であればドイツの「その他」とほぼ同水準である一方、こづかいは昼食などの飲食や 書籍、CDなどに支出されるケースが多いとすれば、外食費や余暇・娯楽費に計上さ れる筋合いとなり、ドイツとの格差が埋まることになる。また、中元や歳暮といった 習慣はわが国特有であり、米独との比較は難しい。さらに、国際比較の観点から補足 すれば、ドイツのアウトバーンやアメリカのハイウェイのように高速道路料金が無料 である国、あるいはガソリン税や車両保有に関わる税負担がわが国に比べて軽い国で は、その分、交通関連の消費支出が少額となる。加えて、地域のスポーツ・クラブが 定着し、あるいは各地に充実したオート・キャンプ場や宿泊施設が整備され、国立公 園の利用などと併せ、誰でも低料金または無料で利用できる国では、余暇・娯楽関連 の消費支出額がわが国より少なくてすむ。このように、消費支出は、習慣や風土、制 度など、様々な要素に左右される面が大きく、単純な比較は差し控えるべきである点 は改めて指摘するまでもない。
a.食料・飲料費
わが国の食料・飲料費の多さには、日本人が新鮮で良質の食材を選好する傾向が強 いことが作用している可能性も指摘されよう。しかし、総じてみれば国際的に国内価 格が割高であることが主因とみられる。購買力平価ベースで換算すると日米独3カ国 ともほぼ同様の消費金額となる。加えて、農林水産省の2005年7月発表の東京および 海外主要5都市における食料品の小売価格調査結果によると、東京を100とした場合、 ニューヨーク87、ロンドン78、パリ93、シンガポール58であり、129のジュネーブを 除く4都市がいずれも東京より割安である。
b.教育費
一方、教育費では、3カ国中わが国の高さが際立っており、わが国の33万円に対し て、アメリカは12万円で3分の1強、ドイツは4万円で8分の1弱に過ぎない。とり わけ、ドイツの消費額の小ささには、義務教育にとどまらず、大学など高等教育まで 国によって全面的に財政支援が行われているという制度上の要因が大きく寄与してい る。アメリカでは、ドイツと異なり、高等教育のなかで私立大学が有力な位置を占め ており、政府が全面的に教育に対して財政支援を行う枠組みとなっていないものの、 ドイツを上回る教育予算が支出されているうえ、民間サイドでも奨学金制度が充実し ており、家計負担の軽減が図られている。ちなみに、政府の教育支出をGDP比で対比 してみると、2002年時点でわが国の3.5%に対して、ドイツは4.4%、アメリカは5.3% である。
c.交通・通信費
交通・通信の年間消費支出では、わが国の55万円に対してドイツは74万円で1.3倍、 さらにアメリカは123万円で2.2倍である。交通・通信費の大半は自動車関連費用、と りわけ自動車購入費が中心を占める。そこで、人口1,000人当たりの新車販売台数を みると、ドイツでは乗用車が中心で商用車タイプの販売は相対的に低調なため、乗用 車ベースで比較すると、わが国の432台に対して、ドイツは546台で1.3倍であり、消 費支出額の格差と同様である。
一方、アメリカでは一般消費者でもピックアップ・トラックやミニバンなど商用車 タイプが選好されるため、乗用車と商用車合算ベースで比較すると、わが国の581台 に対して、アメリカは790台で1.4倍である。アメリカの交通・通信支出が自動車販売 台数の倍率を上回ってわが国より多い背景には、わが国の場合、都市圏では公共交通 機関が発達しており、1世帯当たりの自動車保有台数が2003年で1.1台と総じて一家 に一台であるのに対して、アメリカでは自動車中心の社会構造のもと、大きな経済格 差、すなわち、貧困層は総じて自動車を保有せず都市中心部に居住する一方、ミドル 層以上は郊外に居住し、一家に数台自動車を保有するという状況が指摘されよう。
d.住居・光熱・修繕費
(a)住居・光熱・修繕の年間支出は、わが国の95万円に対して、ドイツは132万円、 アメリカは169万円であり、他の支出項目に比べ、わが国と米独との格差が際立って 大きい。さらに、家具は、住居関連費用の一部と位置付けることが可能であり、これ を加えると、住居関連支出は、わが国の107万円に対して、ドイツは159万円、アメリ カは193万円に達しており、3カ国とも消費支出全体のなかで際立って大きなウエー トを占める。加えて、住居は生活の基盤であるものの、それに対する支出金額の多寡 は、生活の豊かさに直結するだけに、必需的費用よりも、むしろ個々人の選好によっ て左右される選択的費用という色彩が濃厚である。
上記の各費目を改めてみると、まず食料・飲食費は、嗜好性が含まれるものの、日 米独3カ国間の格差が相対的に小さいところに端的に表れている通り、必需的性格が 強い。一方、教育費は、発展途上国と対比すれば相対的に経済的余裕があるから支出 できるという見方もできるものの、自立した社会生活を送るために少なくとも初等・ 中等教育は不可欠である。交通・通信費にしても、一部には行楽や旅行目的だけで自 動車を保有する世帯も存在するものの、わが国の地方圏やアメリカの家庭の大半は生 活に不可欠だから一家に2台以上の自動車を保有するのであって、行楽や旅行は副次 的目的に過ぎない。
(b)このように住居関連費用は消費支出のなかで、その他の支出項目と性格がやや異 なる。そこで、住居費用の違いについてやや詳しくみると、次の通りである。
まず先進主要各国のうち、データが採れる国について1世帯当たり住宅面積および 一人当たり住宅面積を対比してみた(図表3)。対象国は日米独3カ国のほか、英仏 2カ国、デンマークとフィンランドの北欧2カ国である。調査年は国によって若干異 なり、2000年と01年、2002年である。これによると、まず1世帯当たり住宅面積では、 アメリカが162㎡と飛び抜けて広く、次いでデンマークが109㎡とやや大きいのに対し て、両国以外の国々は総じて90㎡前後となっている。すなわち、わが国は91㎡、独仏 90㎡、イギリス87㎡、フィンランド76㎡である。一方、一人当たり住宅面積でも、ア メリカが際立って広く62㎡、次いでデンマークが50㎡とやや大きいのに対して、両国 以外の国々は総じて40㎡前後で、ドイツ42㎡、フランス37㎡、イギリス37㎡、フィン ランド35㎡、日本34㎡である。これをみる限り、日米の住居費ギャップは説明が可能 であるものの、日独の格差に対する説明は難しい。
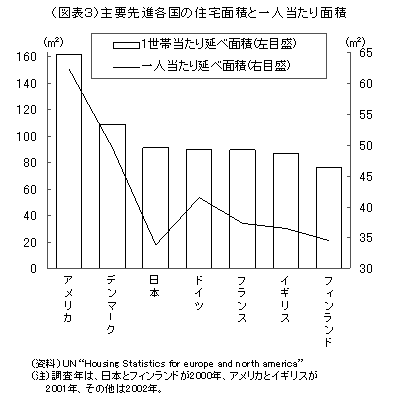
これに対して、近年のわが国住宅着工統計をみると、新築住宅の1戸当たり平均床 面積は、2000年の97.5㎡をピークに年を追って減少しており、2005年には85.4㎡とな っている。こうした年々の住宅投資が蓄積されて住宅ストックとなり、ストック全体 を平均して1世帯当たりや一人当たりの住宅面積が算出される。仮に、そのようにし て形成されてきた住宅ストックのもと、わが国の居住スタンダードとして90㎡規模の住宅面積が定着しているのであれば、近年の1戸当たり平均床面積の減少はどのよう にみればよいのか。この点に着目してみると、平均面積は90㎡、91㎡と日独で近似し ていても、それは全体の平均値に過ぎず、住宅ストックの分布が両国で異なる可能性 が想起される。
(c)そこで、住宅面積の広さを50㎡毎に分け日米独3カ国の世帯数割合と世帯人数の 分布をみた(図表4)。まず世帯数の分布をみると、住宅面積が際立って広いアメリ カでは、面積50㎡未満の住宅に居住する世帯は全体の3.6%に過ぎず、50㎡から99㎡ の世帯が19.1%、100㎡から149㎡の世帯が24.1%、150㎡以上の世帯が34.9%と、面積 が大きくなるほど多くの世帯が居住しており、面積100㎡以上の住宅に居住する世帯 がほぼ6割を占める。次いでドイツでは、50㎡未満の住宅に居住する世帯は全体の 11.2%、50㎡から99㎡の世帯が54.1%と過半を占め、100㎡から149㎡の世帯は25.7%と 4分の1であり、平均面積である90㎡前後の住宅に居住する世帯が大半を占める。
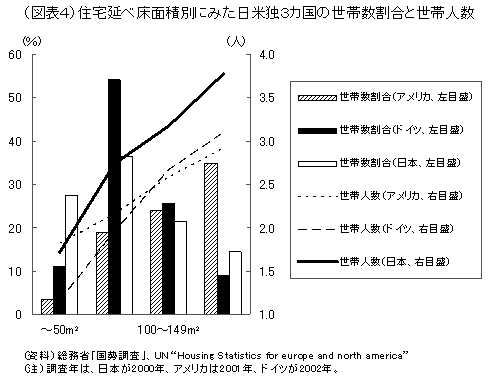
それに対して、わが国では、面積50㎡未満の住宅に居住する世帯が全体の27.5%と 米独を大幅に上回る一方、50㎡から99㎡の世帯は36.5%とドイツを2割弱下回る。し かし、100㎡から149㎡の世帯は21.4%で米独と同水準であるうえ、150㎡以上の世帯 は14.5%でアメリカには遠く及ばないものの、ドイツの9.1%を上回る。わが国は、50㎡未満の世帯数割合が3カ国中もっとも多い一方、150㎡以上の世帯数割合もドイツ を上回っており、米独に比べて、面積の広い住宅と狭い住宅が混在する点が特徴とい えよう。
(d)次に、住宅の広さ別に平均世帯人数をみる。3カ国とも住宅の面積が広いほど平 均世帯人数が多い傾向が看取される。そこで3カ国を対比してみると、わが国の平均 世帯人数は総じて米独を上回っている。
まずアメリカと比べてみると、住宅面積が広くなるほど格差が大きくなっている。 すなわち、50㎡未満の住宅ではアメリカの1.8人に対してわが国は1.7人であり、ほぼ 同水準であるものの、50㎡から99㎡の住宅ではアメリカの2.2人に対してわが国は2.7 人で0.5人多い。さらに、100㎡から149㎡の住宅ではアメリカの2.6人に対してわが国 は3.2人で0.6人多く、150㎡以上ではアメリカの2.9人に対してわが国は3.8人で0.9人多 くなっている。一方、ドイツと比べてみると、いずれの広さでも0.6人前後わが国が 上回っている。50㎡未満の住宅ではドイツは1.2人、小数点第2位で四捨五入すると わが国は0.6人多く、50㎡から99㎡の住宅ではドイツは2.0人でわが国は0.7人多い。100 ㎡から149㎡の住宅ではドイツは2.7人でわが国は0.5人多く、150㎡以上ではドイツは 3.1人でわが国は0.7人多い。
全体として平均世帯人数をみると、ドイツが2.2人、アメリカが2.6人、日本が2.7人 であるので、平均世帯人数二人および3人の基準で住宅面積をみると、わが国がもっ とも狭い。まずわが国の平均世帯人数は、住宅面積30㎡~39㎡の1.9人から40㎡~49 ㎡で2.2人と二人になり、90㎡~99㎡の2.9人から100㎡~109㎡で3.1人と3人になる。 それに対して、ドイツでは、住宅面積50㎡~74㎡の1.7人から75㎡~99㎡が2.3人と、 わが国であれば平均世帯人数が3人弱の広さで漸く二人台に乗り、100㎡~149㎡の 2.7人から150㎡以上で3.1人と3人台に乗る。アメリカも50㎡以外ではドイツとほぼ同 様である。このようにみると、わが国では米独に比べて狭い住宅に多くの家族が居住 する世帯が多いといえよう。
(e)もっとも、これだけでは平均住宅面積や一人当たり平均居住面積が日独でほぼ同 水準であることについての説明として説得力が弱い。そこで、世帯数割合でドイツを 上回る住宅面積150㎡以上の部分に着目すると、まず1戸当たり住宅面積が150㎡~ 199㎡と200㎡~249㎡、250㎡以上のいずれにおいても、最も多い世帯人数は二人、次 いで3人であり、広い住宅に少人数で暮らす世帯が相当数に上る。こうした実態に、 地域別に1戸当たり住宅面積を比べ、地方圏で広く、都市圏で狭いという事実を重ね 合わせてみると、日独で平均住宅面積や一人当たり平均居住面積がほぼ同水準である のは、わが国の場合、ドイツと異なり、地方圏で居住面積の広い住宅ストックがあり、 加えて、そうした住宅では少人数で暮らす世帯が相当数を占めるため、都市圏での住 宅の狭さや一人当たり居住面積の狭さが相殺されるという事情が作用していると判断 される。ちなみに、総務省の2003年住宅土地調査に依拠し専用住宅について都道府県 別に1戸当たり平均住宅面積をみると、上位3県は、1位が富山県の151.9㎡、2位 は福井県で143.6㎡、3位が山形県の136.8㎡である一方、下位は、1位が東京都で62.5 ㎡、2位は大阪府の73.1㎡、3位が神奈川県で74.6㎡となっている。
さらに、地方圏の居住者の年齢層は都市圏に比べて高いことや、地方圏の広い住宅 では、とりわけ居住人数が少ない世帯の場合、使わない部屋があるなど、利用度が総 じて低い一方、東京都のアンケート調査をはじめとして都市圏では住宅に関する不満 の筆頭に狭さがあげられている点を加味してみると、平均住宅面積や一人当たり平均 居住面積でみれば、わが国はドイツをはじめ西欧各国とほぼ肩を並べるまでに至って いるものの、その点だけでわが国の居住環境が西欧諸国並みまで向上したと言い切る ことはやや牽強付会に過ぎるといえよう。
(ハ)このようにみると、わが国は、公的負担の規模は先進各国中最小であり、歳入 不足規模は各国中最大であるものの、国民が他の国々を上回る経済的余裕を享受して いるとは必ずしも言い切れない。むしろ、必需的色彩が強い教育費や食料費支出が重 い一方、生活の豊かさを表す代表的支出であり、日米独3カ国とも消費金額が最大の 住居関連支出は、わが国が最小であるうえ、居住環境は3カ国中最低である点を踏ま えてみると、わが国国民の経済的余裕は他の先進各国より小さいという可能性が大き い。
さらに、実収入から消費支出を控除した収入支出差額をみると、わが国は、為替レ ートベースではドイツを下回り、購買力平価ベースでは米独を下回っている事実も、 そうした状況を示唆する事象の一つと位置付けることができよう(前掲図表2)。こ うした認識に立脚すれば、とりわけ個人セクターにおいて公的負担を現状比拡大させ る余地は限定的であり、大幅な負担の増加は深刻な生活水準の切り下げに繋がる懸念 が大きい。 - わが国の社会政策支出は先進国中最小
(イ)わが国の公的負担が先進各国中最小であり、歳入不足規模は各国中最大である という事実と、国民が享受する経済的余裕が他の国々を下回り、公的負担追加の余地 は限定的という認識には矛盾があるようにみえる。公的負担が小さいほど経済的余裕 が生まれる一方、公的負担が重いほど経済的余裕が失われると思われるからである。 この矛盾を解く鍵は何か。そうした観点から改めて日米独3カ国の消費支出を振り 返ってみると、教育費負担が格好の材料となろう。すなわち、制度が整備され政府が 強力に支援する体制が確立された米独に比べて、相対的に政府の支援体制が脆弱なわ が国では教育費負担が家計に重く賦課されている事態である。言い換えると、公的負 担が軽くても、その分、必需的支出が増えれば家計が享受する経済的余裕は増えない し、公的負担が重くても、その分、政府の国民に対する給付が増えて必需的支出が削 減されるなら家計が享受する経済的余裕は減らない。負担と給付が見合っている限り、 世帯毎にはバラツキが生まれるとしても、全体としてみれば、国民が享受する経済的 余裕に大きな変化は発生しない。
むしろ、所得分配やセーフティー・ネットの機能が強化され、国民が安心して生活 したり、新規事業の立ち上げにチャレンジする余裕が生まれる分、低負担低給付より 高負担高給付のスキームが望ましいという考え方も成り立とう。端的な事例が少子化 対策である。就業支援など積極的雇用政策を通じて若年層に対して雇用の確保やパー トナー探しを強力に支援したり、義務教育のみにとどまらず高等教育も含め、教育政 策の強化によって子育てに伴って家計が負担するコストやリスクの軽減に努めてきた フランス、北欧各国では近年合計特殊出生率が2弱の水準まで回復してきたのに対し て、子育ての責務は家庭にあり、政府が負うべきコストやリスクは限定的としてきた 南欧諸国では、一時に比べれば改善の兆しがみられるものの合計特殊出生率は依然と して1.3前後にとどまり、わが国では改善する兆しすらみられない。
(ロ)こうした視点をもとに、先進主要各国の社会政策関連支出および教育政策支出 を、最新データである2001年値についてGDP比で対比してみた(図表5)。これによ ると、医療・健康支出が6~7%で各国ほぼ同様である以外、いずれも大きな格差が みられる。まず老齢・障害・遺族年金では、欧州大陸各国のほぼ 14%前後に次いでイギリスが11.2%であるのに対して、わが国は9.1%、さらにアメリ カは7.3%にとどまる。次に、教育政策支出をみると、欧米各国が平均6%であるの に対してわが国は3.6%と半分強の水準に過ぎない。年金支出で最 低であったアメリカも5.6%と西欧各国並みに支出しており、わが国の教育支出規模 の小ささが際立つ。
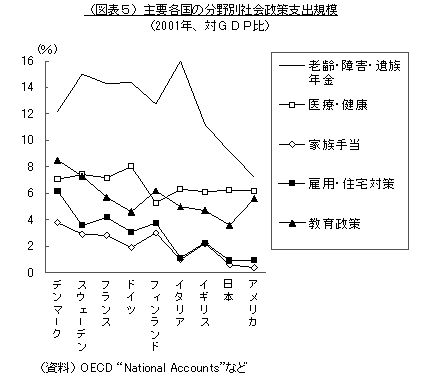
さらに雇用・住宅政策をみると、上記の通り、欧州大陸各国では、1年から数年に わたるインターン制度や就業支援など、積極的雇用政策が強力に展開されているなか、 総じて4%前後の支出が行われており、イギリスも2.3%支出しているのに対して、 日米両国は0.9%である。家族手当についても、手厚い給付を行う北欧各国やフラン スを中心に欧州大陸各国では総じて3%前後の支出が行われ、イギリスも2.2%支出 しているのに対して、わが国は0.6%、アメリカは0.4%である。
この結果、政府が国民に対して行う給付全体の規模に大きな格差が生まれている (図表6)。上記の社会政策関連支出と教育政策支出を合算してGDP比で対比し支出規 模の大きい順にグループに分けてみると、デンマーク、スウェーデンの北欧2カ国と フランスは35%前後、ドイツとフィンランド、イタリアの欧州各国は31%前後、次い でイギリスが26.5%と続く。わが国は20.5%で20.4%のアメリカと並んで最小グループ を形成しており、日米は先進各国中最も小さな政府となっている。
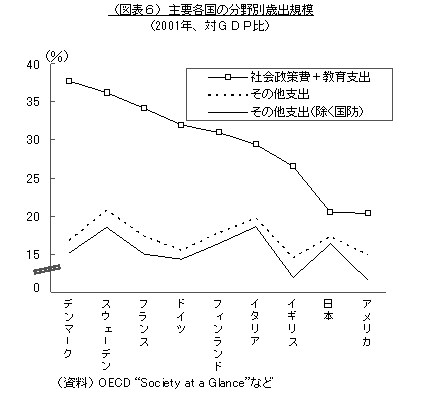
しかし、政府の支出はそれらだけではない。そこで、政府の総支出から社会政策関 連支出と教育支出を差し引いた残りをその他支出としてGDP比で改めて対比してみた。 これによると、社会政策関連支出や教育支出で諸国間にみられたような格差は看取さ れない。その他支出は総じて17~18%前後の規模である。もっとも、アメリカには各国を上回る国防支出がある。2001年にはイラク戦争が始まっていないものの、支出規 模はGDP比3.3%であった。
そのため、国防支出を除くベースでその他支出を再度対比してみると、アメリカは 11.6%で先進各国中最小である。小さい順にみると次いでイギリス11.9%、ドイツ 14.3%、フランス15.0%、デンマーク15.2%と続く。わが国は16.3%で16.4%のフィン ランドと同水準である。わが国を上回る国は18.5%のスウェーデンと18.6%のイタリ ア、2カ国しかない。このようにみると、アメリカは国民に対する給付および直接的 な給付以外のいずれの面でも小さな政府であり、政府支出全体としての位置付けと変 わらない。それに対してわが国は、国民に対する給付面では小さな政府であるものの、 国民への直接的な給付を除く部分では、むしろ相対的に大きな政府に位置しており、 政府支出全体として規模が先進各国中小さいという点に注目するだけでは実態から乖 離した認識を導く懸念があるといえよう。
(ハ)負担と給付が連動する限り、国民生活に大きな影響は及ぼさない。しかし、社 会全体で所得を分配しリスク分散を行うことで、国民サイドで安心が生まれ、起業や 新産業の創出、あるいは子育てなど、リスクに対して果敢にチャレンジする取り組み が拡がるのであれば、負担と給付の拡大は有益な政策になる。冷戦終結後、90年代入 り後の先進各国は、総じて国民に対する直接的な給付に繋がらない政府活動について 抜本的な見直しを断行し、それによって、負担と給付によるプラスのメカニズムを最 大限活用し、経済成長力の中期的な底上げを図ってきた。
こうした取り組みを、政府の支出を国民に対する給付とそれ以外に分け、90年から 2001年への変化からトレースしてみた。具体的には、社会政策関連支出と教育支出を 合算した金額を国民に対する給付とする一方、それを政府の総支出から除いた残余を その他支出とし、それぞれGDP比で変化をみた(図表7)。
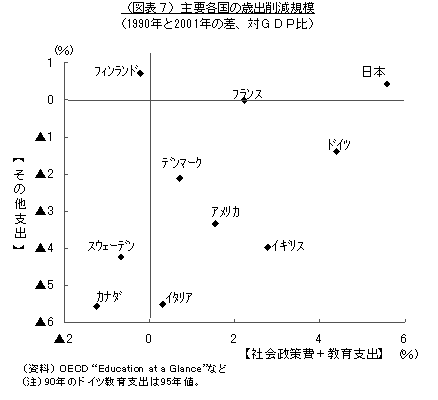
それによると、まず、その他支出は多くの国で削減されている。一方、国民への受 益支出は大半の国で増加しており、両者を重ね合わせてみると、その他支出を減らし ながら、国民への給付を増やした国が過半にのぼる。典型をあげれば、まずイギリス は給付支出を2.8%増やしながら、その他支出を4.0%減らし、政府支出全体では1.2% 削減した。また、アメリカは給付支出を1.5%増やしながら、その他支出を3.3%減ら し、政府支出全体では1.8%削減している。そうしたなか、わが国は国民に対する給 付支出を5.6%増加させたうえ、その他支出も0.4%増加したため、政府の総支出が 6.0%増加し、深刻な歳入欠陥を招来した。加えて、各国がその他支出の削減に取り 組むなか、わが国はその他支出の削減に着手しなかった結果、国民への直接的な給付 を除く部分で先進各国中大きな政府に位置することになった。
(ニ)それでは、わが国が国民に対する給付以外の分野で歳出を削減する場合、具体 的にどのような分野で、どれほどの規模の削減が展望できるか。上記の通り、国際比 較可能な社会政策関連・教育支出の最新データは2001年であるものの、わが国の場合、 その後、小泉改革が推進されており、2001年のデータでは現状から大きく乖離する懸 念が大きい。そこで、社会政策関連・教育支出のデータと極力相似しつつ、より最近 まで国際比較が可能なデータとして目的別政府支出に着目してみた。これは、政府支 出を10分野に分類した統計である。G7各国のうち目的別政府支出の採れないカナダ を除いた6カ国を対象に、目的別支出のうち、a.年金や生活保護あるいは失業手当な どを対象とする社会保護、b.医療や介護を含む保健、c.教育、d.住宅・地域アメニテ ィ、の4系列を合算し、社会政策関連・教育支出と2001年値を対比してみると、わが 国を除く5カ国のいずれもほぼ同値である。GDP比で両系列の差をみると、イタリア は同値、ドイツは0.4%、英仏両国は0.5%であり、最大のアメリカでも1.0%にとどま る。この系列を使うことで、アメリカは2004年、英仏独伊の4カ国は2003年と、より 新しいデータを使うことができるうえ、その他支出について、より細かい分析が可能 になる。
もっとも、各国の場合、政府総支出と目的別政府支出がほぼ同値であるため系列を 変更しても大きな問題は生じないのに対して、わが国では、例えば2001年次について みると、政府総支出の191兆円に対して、目的別政府支出は合計171兆円であり、両者 には20兆円もギャップがあるため、補正が必要になる。そこで、目的別政府支出から 固定資本減耗や財産所得の支払、土地の純購入、商品・非商品販売を加減して調整を 行い、2004年度値を試算した。ちなみに、2001年度値は191兆円となり、暦年と年度 の違いはあるものの、政府総支出の金額と符合する。なお、わが国は財産所得支払、 すなわち、利払費が別掲されている一方、各国の一般公共サービスには利払費が含ま れるとみられるため、利払費を控除してベースを揃えたほか、経常支出については、 a.社会政策・教育支出、b.防衛費、c.その他支出、の3者に大別する一方、経常支出 以外では、a.総固定資本形成、b.土地の購入、c.財産取得支払、の3者に分け、合計 6グループに分類してGDP比で対比してみた(図表8)。ただし、わが国の計数は試 算値のため、項目別にみると歪みが各国より大きく、比較可能な2001年値をみると、 社会保護と保健、教育、住宅・地域アメニティの合計値が社会政策関連・教育支出を 2.2%上回っている。そのため、試算結果に一定の限界がある点は付言するまでもな いが、その分、その他の経常支出が実態を下回り、この部分を含めると、削減余地が 試算結果を上回る可能性がある。
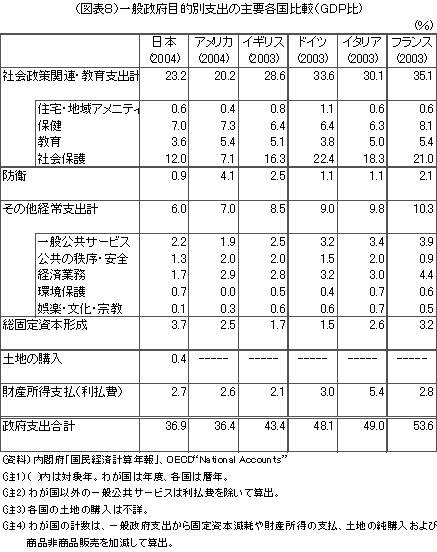
それらのうち、まず、社会政策関連・教育支出は国民に対する直接的な給付分野と して、また防衛は国家存立の基幹分野として、本稿での削減可否の検討対象から外す ことにする。次いで、その他の経常支出についても、a.スポーツや学芸振興に向けた 娯楽・文化・宗教、b.廃棄物処理や生態系保全のための環境保護、c.農林業などへの 産業振興政策やエネルギー政策などの経済業務、の3分野に対する支出規模は、唯一、 統計上ゼロとなっているアメリカの環境保護支出を除くと、主要先進各国をすべて下 回っており、削減余地は小さい。それに対して、警察や消防、裁判所および刑務所な どを対象とする公共の秩序・安全分野の支出は1.3%であり、米英独伊4カ国を下回 るものの、フランスの0.9%より大きい。すでにわが国でも始まっている駐車違反の 取り締まりや刑務所の民間委託など、アウトソーシングに向けた取り組みを一層強化する一方、ADR(Alternative Dispute Resolution)、いわゆる裁判外紛争解決手続の 幅広い活用などによってコスト圧縮を期待することができる。さらに、こうした具体 的な政策分野に含まれない一般公共サービス、具体的には、行政・立法機能や外交な どに対する支出についてみると、わが国は2.2%で、英仏独伊の4カ国よりも小さい ものの、アメリカの1.9%よりも大きい。わが国でも90年代には、長らく1.8~1.9%で 推移してきた実績に加え、アメリカの計数にはCIA(中央情報局)をはじめ、わが国 にない機関のための支出が含まれており、その分、嵩上げされている点を踏まえてみ れば、アメリカがとりわけ90年代を通じて取り組んできた公的業務スリム化への取り 組みを改めて参照する意義は大きい。
次いで、総固定資本形成、いわゆる公共事業についてみると、削減されてきたもの の、わが国の事業規模は3.7%であり、依然諸外国を上回る。PFIやPPPsといった新 たな手法を導入して公共事業の削減に成功したイギリスでは2003年の総固定資本形成 がGDP比1.7%であり、わが国より2%小さい。さらに、土地の購入のための支出規 模は、公共事業の削減が進むなか、趨勢的に小さくなってきているものの、依然とし て0.4%に上る。公共事業でPFIやPPPsといった新たな取り組みが広がっていけば、 購入でなく、経済的価値に見合った利用料金とのスキームが定着する筋合いであるう え、いずれの国でも歳入欠陥を打開する有力な方策の一つが資産売却である点を加味 してみれば、土地の購入支出の削減は焦眉の急といえよう。
こうしたコスト削減が期待できる分野すべてを合算してみると、GDP比で3.1%と なり、2005年度名目GDPを掛け合わせると削減余地は総額15.6兆円規模に達する。公 共工事の削減幅をイギリスを基準にGDP比2%ポイントとせず、イギリスを除く米仏 独伊4カ国平均とわが国との格差である1%削減としても、削減余地は10.6兆円に上 る。それに対して、冒頭で取り上げた全歳出18%削減、すなわち、公的負担の増加を 行わない場合、2011年度にプライマリー・バランスを達成するために、すべての歳出 項目で削減が必要とされた18%の規模は2006年度名目GDPベースで表わすと実額11.4 兆円であるため、仮にそうした歳出削減が実現されると、国民への給付削減を行う必 要性は大きく減退することになる。
(ホ)このようにみると、財政健全化に向けてわが国が第1に着手すべきは、国民に 対する給付の削減ではなく、その他支出について抜本的削減を断行することである。 そのためには、a.まず、市場化テストやPFI、エージェンシー化や民営化など、多様 な行政改革ツールを活用し、b.次いでNPOや個人、企業など、非政府部門が公的業務 の担い手として、政府の受け皿となる制度を整備・拡充し、c.さらに、 分限免職制度の本格的活用や労働三権の付与、諸外国を上回る俸給水準の是正など、 公務員の雇用・賃金制度の見直しを進め、d.地方レベルでは、業務 のスリム化と効率化に向けて三位一体改革のさらなる推進やシテ ィ・マネジャーやコントラクト・シティー制度を導入するなど、 様々な取り組みを強力に進めていく必要がある。
第2は、国民に対する給付の議論を本格化させることである。すなわち、第1の改 革によって、わが国特有の大きな政府路線から決別し、政府が行う負担と給付が連動 する点について国民の信認を確保したうえで、わが国が目指すべき負担と給付の規模 とスキームに関して国民的コンセンサスの形成を図る必要がある。財政再建を巡る現 下の議論では、給付の減少を最小限に食い止めながら、負担の増大を極力回避するた めには、どのような方策が必要かという局所的な論争に終始しかねない。それでは、 少子化問題や成長力回復課題など、わが国経済が直面する中長期的課題に対する備え が一段と手薄になり、先行き不安が増幅される懸念が大きい。
政府支出を全体として捉え、わが国は小さな政府と位置付ける議論や認識が今日で も依然支配的である。しかし、政府支出を国民に対する直接的給付とそれ以外に分け てみるだけで、全く異なる様相が顕在化し、わが国が小さな政府とは言い切れないと いう断面が浮かび上がる。大きな政府であればスリム化は不可避であるし、非効率で あれば合理化が焦眉の急となる。このところ、政府支出の削減に向け、国民に対する 給付カットの議論が先行しているものの、わが国の国民に対する給付規模はすでに先 進各国中最低水準である。それだけに、さらなる給付の削減はセーフティー・ネット を一段と脆弱にし、国民のリスク回避的行動を強化し、経済・社会の活力低下に帰結 するリスクは否定できない。人口減少時代が到来するなか、現状を直視した認識の共 有と改革ベクトルの修正は喫緊の課題となっている。

