Business & Economic Review 2005年11月号
【OPINION】
構造改革で国民負担の軽減を
2005年10月25日 藤井英彦
- はじめに
(イ)第44回衆議院総選挙で国民は構造改革のさらなる推進に絶大な支持を与えた。様々な改革メニューのなかで最大の課題は小さくて効率的な政府の実現にある。市場化テストや規制改革を断行し、公的セクターの非効率性や無駄を徹底して排除することで、戦後わが国の高度成長を支え、石油危機や円高不況からの立ち直りの原動力となった民間活力が再び盛り上がり、わが国経済の中期的成長力の確保に展望が開ける。加えて、財政再建に向けて国民負担の増加が不可欠としても、その規模を最小限度にとどめることで経済成長へのダメージを極小化することが可能になる。なお、そのためには市場化テストや規制改革が機能する公務員制度への転換が大前提であり、具体的には公務員の雇用保障と給与水準の見直しが鍵になろう。
もっとも、小さくて効率的な政府を目指すとしても、少なくとも現時点においてみる限り、わが国の場合、年金や医療など、社会保障サービスの削減まで踏み込んだ改革が容認されているとは言い切れない。むしろ、そうした改革は行き過ぎであり、セーフティーネットを確保し、さらに必要なサービスについては拡充を図る一方、それ以外の分野について効率化を最大限進めるべきという考え方がコンセンサスではないか。
(ロ)しかし、改革に当たり、そうしたグランド・デザインは果たして実現可能であろうか。仮に実現可能であるなら、現行の改革スタイル、すなわち、一つひとつの制度について、審議会や専門部会などでの議論や検討をもとにあるべき姿や望ましい方向性を見定め、サービス提供の内容や費用負担の在り方など、具体的な問題について詰めていく手法で特段の問題はなかろう。
逆に実現不能であるとすると問題は深刻である。その場合、すべての公的サービスについて逐次棚卸しを行って優先順位を付け、限られた予算やマンパワーの制約を睨みながら、実施するサービスと実施しないサービスに分けたり、実施するサービスについても個別にどの程度のサービス提供の水準にするかを決定する作業を行わざるを得ず、現行の改革スタイルだけでは問題が解決しない。いわば、予算制約のなかで選択と集中を公的サービスについても行っていく必要があり、今日、審議会などで実施されている個別問題ごとの検討や議論に加え、政府リソースの選択と集中を決定し、全体を調整する統合的機能が新たに必須となろう。
(ハ)以上の問題意識をもとに、本稿ではそうしたグランド・デザインが実現可能か否かに焦点を絞り、検討を行ってみた。具体的には、主要先進各国の近年の動向を整理することで、グランド・デザインの実現可能性をチェックしてみた。 - 主要各国の動向
(イ)まず、対象国はわが国と米英独仏の主要先進5カ国に、スウェーデンとフィンランドの北欧2カ国を加えた7カ国とした。相対的に小さな政府志向の強い米英、逆に政府機能をより重視する独仏、さらに社会保障分野をはじめ政府の積極的役割を特徴とするスウェーデンとフィンランド、3グループそれぞれ2カ国ずつとわが国とを対比した。
次に、対比する経済指標は失業率と国民負担率とした。経済状況を示唆する指標には失業率以外にも、経済成長率や税収など、様々な系列がある。しかし、近年、ジョブレス・リカバリー、すなわち雇用増加なき景気回復といった現象が各国で散見されるなか、単に景気の繁閑に応じた成長率や税収の変動に着目するだけでは経済状況を総体として捉えたことにならない。そのため、本稿では景気循環に感応的な成長率や税収ではなく、失業率を採ることにした。なお、各国政府公表の失業率ではなく、OECD(経済協力開発機構)が作成し公表している失業率を採った。各国発表の失業率と異なり、OECDの失業率は同一フォーミュラで計算されているため、相対比較しても歪みがより小さいと判断されるためである。
一方、政府の規模を示す指標として国民負担率、すなわち、一国全体の経済規模に対する租税や社会保障負担など国民負担のシェアを採用した。もっとも、わが国では、一国経済の規模を表す指標として国民所得が使われるケースが多い。これは、国民や企業が租税や社会保障負担をそれぞれの所得から支出する点に着目したためであろう。しかし、国際比較を行う場合、それでは不都合がある。国民所得は要素価格表示で生産・輸入品に課される税、すなわち、間接税が含まれないだけに、それを国民負担率の分母に使うと、分子の租税には間接税が含まれる結果、間接税のシェアの大きい国の負担率は間接税のシェアが小さな国よりも大きくなり、相対比較に支障を来たすためである。そこで、本稿では、一国経済全体を表す指標として名目GDPを採ることとした。
さらに、近年の推移をトレースするために2001年を始点とし2004年を終点として、2時点間の動きをグラフ化した。もっとも、国民負担率は統計の制約から、2000年と2001年の平均を始点とし、2002年と2003年を終点としたものの、スウェーデンとアメリカ以外の5カ国については2002年を終点とした。
(ロ)米英、独仏、北欧2カ国の順に整理すると、米英2カ国と、独仏および北欧2カ国の計4カ国との間に大きな格差が看取される。具体的には次の通りである。
a.米英
まず米英2カ国についてみると、国民負担率、失業率ともに低水準に位置する。イギリスでは、30%台半ばの国民負担率のもと、93年の10.0%をピークに10年余りにわたって失業率の趨勢的低下傾向が持続し、2004年半ば以降4.6%と4%台半ばまで低下しており、先進主要各国中、わが国と並んで最低水準となっている。
一方、アメリカでは、20%台後半の国民負担率のなか、失業率は相対的に低い水準で推移している。もっとも、ITバブル崩壊によって2000年の4.0%から2003年に6.0%へ上昇したものの、2004年に入って再び低下傾向に転じており、2005年6月には5.0%まで低下している。このため、グラフ上では失業率が上昇しているものの、これは構造的要因とみるよりも、むしろ景気変動に伴う動きと捉えられよう。なお、近年、アメリカでは国民負担率の低下幅が各国を上回って大きい。各国と同様に、この間、経済成長によって名目GDPが増加し、その分、国民負担率が低下したことに加えて、ブッシュ政権下、所得減税が行われた結果である。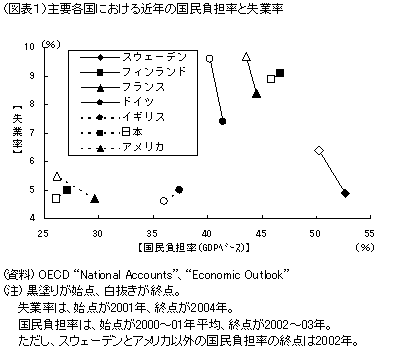
b.独仏
次に独仏をみると、国民負担率は40~45%で米英よりも高いものの北欧2カ国よ」り低く、両者の中間に位置するなか、失業率、とりわけ2004年の失業率は10%弱と米英のみならず、北欧2カ国をも上回って高い。そのため、独仏両国では雇用政策が最重要課題の一つとなっている。次の通り、両国政府は様々な対策を打ち出しているものの、2005年半ば時点でも依然として改善の兆しはみられない。
まずフランスでは、2004年に競争力強化重点地区(poles de competitivite)の創設が決定され、法人税免除の優遇措置や補助金の給付によってフランス企業の海外移転の抑制を目指すこととされた。さらに、2005年6月に発足したドビルパン内閣は、雇用創出を最優先課題と位置付け、従業員10人以下の中小・零細企業での雇用増加策と長期失業者への雇用促進策を2本柱とする雇用のための緊急計画を策定している。
次いでドイツでは、2001年に連邦法人税率が改定され、従来の配当利益30%、留保利益40%の税率が一律25%に引き下げられる一方、さらなる国民負担増大への歯止めを目指して年金の給付水準が現役世代可処分所得の70%から67%に引き下げられた。2002年末には雇用政策改革法が成立して、失業者の再教育や人材派遣など、再雇用促進策が始動しており、2005年1月には失業給付金の削減が実施されている。さらに2005年3月には、a.連邦法人税率の25%から19%への引き下げ、b.総投資額20億ユーロの交通インフラ整備事業、c.高齢長期失業者の就業支援に向けた2億5000万ユーロ規模の雇用促進事業など、雇用増加を主要目標とする景気対策が策定された。
c.欧2カ国
北欧2カ国についてみると、まずフィンランドでは、国民負担率は40%台後半で独仏を若干上回る。一方、失業率は9%台前半で独仏を若干下回るものの、総じてみれば独仏とほぼ同様の高水準に位置している。加えて、国民負担率、失業率ともに2001年と2004年で大きな変化が看取されない。
それに対して、スウェーデンでは、対象とした主要7カ国中最も国民負担率が高いなか、このところ経済に陰りが拡がっている。すなわち、失業率が、2001~2002年の4.9%と米英に比肩する低い水準から、2004年には6.4%に悪化した。さらに、次の要因を加味すると、実勢ベースでみたスウェーデンの失業率は独仏に比肩する高い水準に達している可能性が大きい。
まず、公的部門での雇用増加である。スウェーデンの雇用者数の2001年から2004年の推移を主要産業別にみると、製造業は70万人から64万人へ6万人減少するなか、行政・教育・医療など、公的サービス部門では151万人から156万人へ5万人増加した。5万人増を労働力人口に対する比率でみると1.1%に当たるため、仮に公的部門が雇用を吸収しなかった場合を想定すると、失業率は現状比1.1ポイント高くなり、6.4%から7.5%に達していたことになる。ちなみに、労働市場庁(AMS : Swedish National Labour Market Administration)では、2001~2004年の3年間に喪失した雇用は合計8万人、労働力人口対比1.8%にのぼると推計している。
加えて、若年者雇用促進政策による失業者の減少である。スウェーデンでは若年層を中心に長期失業者に対して、職業訓練や就職支援などの政策が雇用政策の一環として遂行されており、この制度の利用者は失業者から除外される。2005年6月末時点の対象者は労働力人口の2.5%に相当するため、この分を上記7.5%に上乗せすると、スウェーデンの実質的な失業率は10%前後の水準に達しているという見方が成り立つ。
こうしたなか、北欧2カ国でも、独仏同様、雇用対策が重要な政策課題となっている。まずフィンランドでは2005年1月に、a.法人税率を29%から26%に引き下げ、b.配当税率は29%から28%に引き下げ、c..株式譲渡益は非課税、の税制改革が行われた。企業の税負担を軽減して海外流出に歯止めを掛け、雇用環境の改善を図ることが目標である。
一方、スウェーデンでは、2004年度予算、2005年度予算での雇用施策の成果に着目し、2005年4月、a.長期失業者を雇い入れる使用者に賃金の85%相当の税優遇措置を付与、b.職業紹介サービスの拡充、c.高等職業訓練生の受け入れ枠拡大など、一段の雇用対策に重点を置いた補正予算が策定されている。
(ハ)しかしながら、独仏および北欧2カ国について少なくとも現時点までの推移をみる限り、依然として失業率は高止ったままであり、各国が打ち出してきた雇用創出に向けた積極策は奏功するに至っていない。その主因の一つとして海外への企業移転が指摘されることが多い。そこで、対外直接投資に着目し、近年の推移をみると次の通りである。
まず、フランスについてみると、ネット対外直接投資額は2002年の15億ユーロをボトムに再び増勢に転じている。2004年には189億ユーロに達し、GDPの1.1%を占めるまで増加した。
一方、ドイツでは、2003年に実質▲0.1%とマイナス成長に陥るなか、統計開始以来初めて対外直接投資が2003~2004年と2年連続して国内に還流し、対内直接投資が2004年に海外へ流出した。すなわち、深刻な国内経済低迷のもと、ドイツ企業は国内の資金繰り緩和のために海外事業から資金を国内に戻す一方、海外企業はドイツでの事業を縮小させ、資金をドイツ以外に振り向けたと捉えられよう。ところが2005年に入り、対内直接投資は依然低迷しているものの、対外直接投資は再び積極化している。ちなみにドイツ商工会議所連合会調べによると、製造業では、回答企業のうち2005年に対外投資を予定する企業が4割、さらにその4割は対外投資を拡大すると回答している。投資先としては中東欧や中国が中心であり、コスト削減と消費地立地が主な投資要因となっている。
さらにフィンランドでも、対外直接投資が、ドイツ同様、2003~2004年に2年連続して国内に還流した。これは、2001年のITバブル崩壊に伴うフィンランド経済の失速に加え、スウェーデンやフィンランドなど、スカンジナビア4カ国を営業基盤とする国際的金融機関、ノルディック・グループの事業再編が主因とされる。しかし、2005年に入ると対外直接投資が増加に転じており、企業の海外移転の動きが再び本格化している。
最後にスウェーデンについてみると、1990年代後半に対外直接投資が盛り上がった後、2001年にはGDP比2.9%と鈍化したものの、これをボトムに再び増勢に転じており、2005年には上期だけでほぼ昨年1年分に匹敵する規模の資本が流出している。下期も上期同様のペースが続いたとすると、年間ではGDP比8.1%の対外直接投資に上る計算になる。一方、スウェーデン国内への対内直接投資は、2001年以降、年を追って鈍化してきたうえ、2005年に入ると、これまでのところ若干ではあるものの、逆に海外資本がスウェーデン国内から流出する事態が発生している。この結果、ネットベースでも、2005年の直接投資は、対外直接投資の流出がほぼそのまま投影され、このところの資本の流出傾向が一段と加速している。
(ニ)従来、経済成長力と国民負担の多寡には弱い相関性が認められるのにとどまり、必ずしも連動しないという見方が支配的であった。典型的な事象が、高コスト体質からの脱却に向けた構造改革に迫られ、高い失業率に悩む独仏と、公的セクターの積極的な役割によって手厚い社会保障と良好な経済パフォーマンスの両立に成功したスカンジナビア諸国といった構図であろう。そうした事実や実績が、高い国民負担率が直ちに深刻な経済停滞に結び付くものではないという認識を拡げ、さらに、良好な経済パフォーマンスのために社会保障を切り捨てる政策運営は不適切であり、むしろその両立を目指すべきという主張を許してきた。
しかし、上記に整理した通り、2000年以降の動きに即してみる限り、こうした認識は修正を余儀なくされている。現状に即してみれば、国民負担率が4割を上回る国では高失業率など、深刻な経済停滞に直面する一方、国民負担率が4割を下回る国では低い失業率など、良好な経済パフォーマンスを享受しており、少なくとも国民負担の多寡からみる限り、実体経済の良否の分岐点は国民負担率4割周辺にあるといえよう。加えて、国民負担率4割は不変の分岐点ではない。経済のグローバル化に拍車が掛かるなか、内外資本を呼び込み、経済成長と雇用創出を実現するために、企業の税負担軽減など、魅力的な国内市場整備に向けた制度間競争が国際規模で一段と激化しているという状況下、近年、国民負担率4割が分岐点になっているのに過ぎず、各国の制度間競争がエスカレートすれば、分岐点が一層低くなる可能性は否定できない。無論、企業や内外資本が立地点として国や地域を選択する場合、労働力の質や技術水準、知的財産権保護やM&A関連の法制度、さらに市場規律や透明性など、様々な要素が勘案されるものの、租税コストなど、公的負担の重さが最重要ポイントの一つであることに間違いはない。
そうした観点から、企業の税負担という点に絞って、制度間競争の動向をみると、次の通りである。なお、対象は、国民負担率と失業率で取り上げた上記主要先進7カ国として、2000年とOECDの租税および社会保障負担関連統計の最新時点である2002年とを対比してみた。国民負担率は同様に対GDP比率とする一方、法人所得税負担についても対GDP比率とした。
これによると、法人税負担を最も大きく軽減させた国はフィンランドでGDP比1.7ポイント、次いでスウェーデンが同1.6ポイントであり、国民負担率が重く失業問題の深刻化に直面した北欧2カ国の積極的な姿勢が鮮明になっている。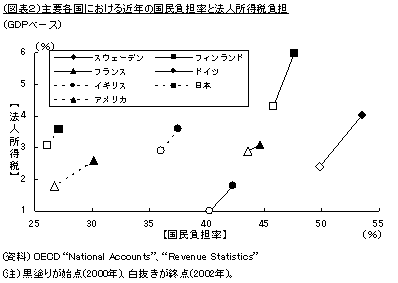
北欧2カ国を追う国はまず独米2カ国で同0.8ポイント、次いでイギリスが同0.7ポイントであり、失業問題が深刻なドイツのみならず、相対的に経済状況が良好な米英でも積極的に国内市場の整備を通じたさらなる競争力強化が図られている様子が窺われる。なお、わが国は0.5ポイントで、フランスの0.2ポイントに次いで、主要7カ国のなかで小さな軽減幅にとどまっている。さらに、2002年の負担水準を比較しても、ドイツの1.0%を筆頭にアメリカ1.8%、スウェーデン2.4%、英仏2.9%であるのに対して、わが国は3.1%であり、4.3%のフィンランドを除くと主要各国中最も負担が重い。 - わが国の課題
(イ)それでは、翻ってわが国の国民負担はどうか。まず近年の国民負担率はGDP比でみて20%台後半で推移するなか、失業率はこのところ4%台半ばまで低下しており、こうした点に着目する限り、現状、大きな問題はないようにもみえる。しかし、次の2点を加味してみると、わが国の行方を楽観視することは早計であろう。
第1は財政赤字である。赤字国債などで調達されている財政赤字分は本来、租税あるいは社会保険料など、国民が負担すべき筋合いにあり、潜在的国民負担とされる。上記、OECD統計から算出したわが国国民負担率の最新期が2002年で26.1%であることから、2002年の財政収支をみるとGDP比で7.9%の赤字となっている。その潜在的国民負担を加味すると、わが国国民負担率は34%に上昇する。
第2は少子高齢化の進展に伴う社会保障コストの増嵩である。2004年5月に公表された厚生労働省の「社会保障の給付と負担の見通し」によると、社会保障にかかる負担は2004年度の78兆円から2025年度には155兆円に達する。この見通しで前提条件とされた名目国民所得の伸び率をそのまま援用して名目GDPを算出すると、社会保障にかかる負担は、名目GDP比ベースで、2004年度の15.4%から2025年度には21.4%へ6.0ポイント増大する。もっとも、2005年7月29日に開催された第17回社会保障審議会医療保険部会提出の資料によると、医療と介護の連携強化や都道府県の役割強化など、医療費適正化に向けた中長期的取り組みによって2025年度時点で6.5兆円前後の給付費抑制が展望されている。これを上記155兆円から差し引くと、2025年度の社会保障にかかる負担は148.5兆円、GDP比20.5%となり、2004年度に比べて5.1ポイント増加する計算になる。これを財政赤字勘案後の34%に上乗せすると、2025年度のわが国国民負担率は39.1%に上昇し、ほぼ4割水準に達することになる。
第3は社会保障関連コストが想定を上回って増加する可能性である。例えば、上記の通り、2004年5月の厚生労働省「社会保障の給付と負担の見通し」によれば、社会保障にかかる負担は2025年度155兆円で名目GDP比21.4%である。それに対して、西欧主要先進各国の社会保障給付費は、98年時点ですでに2025年度のわが国を大きく上回っている。すなわち、GDP比でみて、イギリスは25.3%でわが国より3.9ポイント、ドイツは29.3%で同7.9ポイント、フランスは29.5%で同8.1ポイント、スウェーデンは34.1%で同12.7ポイント上回っている。さらに、老人人口比率、すなわち、総人口に占める65歳以上人口のシェアをみると、99年のイギリスが15.6%、2001年でフランス16.1%、ドイツ16.9%、スウェーデン17.2%であり、2025年のわが国28.7%を大きく下回る。その点を加味したうえで、わが国の場合、社会保障給付費と社会保障負担がほぼ同額である点を踏まえてみれば、2025年度時点のわが国社会保障負担がGDP比21.4%で収まるどころか、より早い時期において、さらに大きな規模に膨れ上がる懸念を否定できない。
(ロ)以上を要すれば、わが国が、深刻な経済停滞に陥る国民負担率4割の吃水線に早晩到達するリスクは大きい。加えて、国際規模での制度間競争が一層激化するなか、国民負担率4割の分岐点が今後一段と低くなる可能性も視野に入れておくべきであろう。
このようにみると、小さくて効率的な政府を目指す構造改革が必須であることに議論の余地はない。むしろ問題は、年金や医療など、社会保障サービスさえ、その要否や削減余地を議論せざるを得なくなった当今の情勢変化を明確に開示して国民の納得を得たうえで、すべての公的サービスを聖域なく俎上に上げて優先順位を付け、実施の要否と実施水準、あるいは制度変更を可及的速やかに決定し実施していく強力な推進力があるか否か、さらにそうした推進力を中期的に維持できるか否かにある。国民各層から絶大な支持を得た小泉政権のリーダーシップ発揮が切望される。

