Business & Economic Review 2005年08月号
【OPINION】
三位一体改革の推進力強化に向けて
2005年07月25日 藤井英彦
- はじめに
(イ)このところ三位一体改革に向けた論議が改めて盛り上がっている。もっとも、一段の検討や議論のために残された時間は少なく、最終決定に至るスケジュールは相当タイトな状況である。前年の夏に作業が始まるという例年の予算作成プロセスのもと、三位一体改革は2006年度が最終年とされており、遅くとも、今後数カ月の間に議論を決着させなくてはならないためである。例えば、焦点の一つとなっている義務教育の国庫負担金問題についてみると、中央教育審議会での中間報告が本年6月末を目処とされた。
(ロ)しかし、現下の議論をみる限り、三位一体改革の目的、とりわけ、a.権限と財源の移譲による地方の自立、b.国・地方を合わせた税財政改革を通じた効率的な政府の実現、という二つの主要目的が達成できるか否かは依然予断を許さない。地方分権の実現や公的セクターの効率化よりも、むしろ、4兆円規模の国庫補助負担金の削減と3兆円の税源移譲、さらに地方交付税の抑制など、地方の歳出カットに焦点が当てられているためである。そこで本稿では、現下の三位一体改革の問題点を指摘したうえで、三位一体改革の目的実現に不可欠なポイントを整理してみた。 - 三位一体改革の問題点
(1)税源偏在
(イ)三位一体改革を巡る現在の議論の問題点を、義務教育の国庫負担金論議を軸に整理すると、まず税源偏在問題が指摘されよう。すなわち、国庫負担金が廃止され国から税源が移譲されると、税源が豊富な都市部では従来同様、あるいは従来以上の歳入が確保されるものの、地方圏、とりわけ税源が必ずしも十分でない地域では、国庫負担金の廃止に見合う税収が確保できないという問題である。
そうしたなか、現下の三位一体改革が指向する地方交付税の抑制方針が全国一律に実施されると、地域によっては深刻な歳入不足問題を招来するリスクが大きい。加えて、義務教育は、警察や消防と並び基礎的な公的サービスの一つであるとする立場に立脚すれば、地域の歳入格差によってナショナル・ミニマムの教育サービスすら実現できない地域が発生する事態は容認されない。
(ロ)加えて、地域の歳入格差問題は、各地域の経済力に加え、留保財源率によっても増幅される。すなわち、まず東京をみると、都は財政力が強いため地方交付税を交付されない不交付団体であり、税源が移譲されると、移譲された金額がそのまま歳入調査部 ビジネス戦略研究センター 所長 藤井 英彦三位一体改革の推進力強化に向けて増加に直結する。それに対して、財政力が弱く地方交付税を交付されている交付団体の場合、地方税収のうち25%は自主財源として位置付けられているため、その部分については歳入増加となるものの、残り75%は基準財政収入額に算入される結果、税収が増えても、増収の75%分については、地方交付税が減額され、地方の歳入増加には繋がらない。地方交付税制度のもと、税源移譲に伴う税収増加のメリットは不交付団体と交付団体で異なることになり、税収増加に対するインセンティブ面でも両者に格差が発生する公算が大きい。
(2)歳出削減余地
(イ)さらに、諸外国と対比してみると、次の問題が指摘できる。
第1は歳出削減余地、すなわち、地方政府の効率化はどこまで可能かという問題である。今日、わが国でも、深刻な財政危機のもと、効率的な政府を実現し、歳出の削減を図るべきとの考え方から三位一体改革でも地方政府の効率化が主要テーマの一つと位置付けられている。政府部門においても生産性の向上は望ましいし、その結果、財政状況が好転したり、より良いサービスが低コストで提供される、あるいは税金など公的負担が軽減されれば、わが国経済・産業の国際競争力強化にも役立つ。
加えて、そもそも不適切な支出の見直しは不断に必要である。とりわけ、不明朗な会計処理や不正支出の問題がこのところ相次いで明るみに出るなか、違法・不当な財政支出は断固として排除されなくてはならないし、民間水準を上回る公務員給与の修正も重要課題である。
(ロ)それでは、歳出削減はどこまで可能か。こうした視点から、主要先進各国とわが国で地方政府の規模を対比してみた。もっとも、諸外国を視野に入れるとしても、提供されるサービス内容が国によって同一ではないだけに、単純な比較はできない。地方政府の所管事業をどこまで広げるか、提供するサービスの水準をどこまで充実させるかによって歳出規模が変わるうえ、提供される公的サービスの内容や水準は各国・各地域の風土や歴史、習俗によっても左右されるためである。
しかし、警察や消防、教育など、地方政府が提供している主要な行政サービスという側面からみれば、少なくとも先進各国についてみる限り、似通ったメニューとなっている。そうした地方政府の活動については様々な計測方法が想定可能であるものの、ここでは政府消費と資本形成に着目して、わが国を、米英独仏伊の主要5カ国とそのGDP比で相対比較してみた。なお、計数は最新値とし、わが国は2003年度、英独仏伊4カ国は2003年、アメリカは2002年値である。なお、主要7カ国からカナダを除外した理由は、データが依拠しているOECD統計でカナダは国と地方を合算した政府全体として数値のみ公表され、地方単独の計数が不明なためである。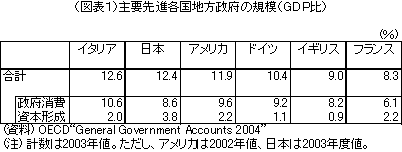
(ハ)まず政府消費と資本形成合算ベースでGDP 比が大きな国から並べると、わが国は12.4%と、1位イタリアの12.6%に肉薄して2位であり、11.9%の3位アメリカと合わせ、伊日米の3カ国が12%前後で上位グループを形成している。以下は、4位がドイツ10.4%、5位がイギリス9.0%、6位がフランス8.3%で、上位3カ国とギャップがある。わが国地方政府は最小国フランスを4.1ポイント上回り、それをわが国のGDPに換算すると20.6兆円に及ぶ。この点に着目すれば、わが国地方政府の歳出削減余地はきわめて大きいといえよう。
そこで次に、資本形成のGDP比をみると、1位は3.8%で日本、2位は2.2%で米仏2カ国、4位は2.0%でイタリア、5位は1.1%のドイツ、6位は0.9%のイギリスとなっている。もっとも、近年、わが国では国と地方とを問わず、公共事業の削減が推進されてきた。地方財政計画ベースで投資的経費をみると、2005年度は2003年度の15%減となっている。仮に、この比率で2005年度の地方政府の資本形成が減少しているとすると、わが国のGDP比は3.8%から0.6ポイント下がって3.2%となり、米仏伊3カ国との格差はほぼ1ポイントに縮小する。
(ニ)それに対して、政府消費のGDP比をみると、資本形成と様変わりのランキングとなっている。すなわち、1位は10.6%のイタリア、2位は9.6%のアメリカ、3位は9.2%のドイツであり、日本は8.6%で4位と下位グループに位置し、イタリアより2ポイント少なく、アメリカより1ポイント少ない。仮に2005年度の資本形成が上記試算の通りであるとすれば、固定資本と政府消費合算ベースでみたわが国地方政府の規模は11.8%となり、イタリアより約1ポイント少なく、アメリカと同レベルになる。
次いで、政府消費の5 位はイギリスの8.2 %であり、わが国とほぼ同水準である。しかし、6位のフランスは6.1%とわが国を2.7ポイント下回る。フランスと比べる限り、わが国地方政府の規模は大きいという判断も有り得よう。もっとも、その格差には日仏両国の制度の違いに起因する面が大きい。すなわち、わが国では、公立学校や都道府県警察の職員が地方公務員であるのに対して、フランスでは国家公務員である。そのため、この部分について政府消費の計上が国の勘定で行われ、それだけ地方の政府消費が少なく計上される。ちなみに、わが国の公立学校職員と都道府県警察職員を国家公務員と想定すると、地方の政府消費はGDP比で学校の1.3%、警察の0.6%で、合計1.9%減少する。なお、学校職員については、事務職員や兼務教員などを除外し、本務教員のみを対象とした。
さらに、公立学校を対象に教員一人当たりの児童・生徒数をみると、少人数教育が進展しているフランスに比べてわが国は小学校で1.6倍、中学校で1.1倍、高等学校で1.7倍多い。ちなみに、フランスの水準は他の先進主要各国のみならず、OECD加盟諸国の平均と同水準であり、国際的にみて、わが国の1学級当たり児童・生徒数は際立って多い。
そこで、地方政府の政府消費のベースを同様にするために、わが国の学校教員数がフランス並みに増加したケースを仮定すると、GDP比で学校分が1.3%から1.8%に増加し、警察分と合算すると全体で2.4%が、地方政府から国に振り替わることになる。翻って、地方政府の政府消費の日仏格差は、わが国の8.6%からフランスの6.1%を差し引いて2.5ポイントであり、この部分を勘案すると、日仏格差はほぼ解消される。こうした側面に着目すると、わが国は、先進各国のなかで、英仏2カ国と並ぶ最小グループに属しているという見方も成り立つ。
(ホ)以上の計算は、政府消費と資本形成のGDP 比の相対比較に過ぎず、提供された行政サービスに対してどれだけのコストが投入されたか、あるいは提供されたサービスに対する住民の満足度はどうかなど、生産性や質の視点が捨象されている。そのため、この計数だけで政府活動を総体として評価し国際比較を行うには不十分であることは間違いない。
もっとも、わが国地方政府の行政サービスには、諸外国と比べて待ち時間が短く事務ミスは数少ないなど、プラスの評価が行われるケースが少なくない。そうした点を加味してみる限り、わが国地方政府の行政サービスが生産性や質の面で諸外国に劣後しているとは必ずしも言い切れない。
この点を踏まえてみると、少なくとも地方政府のGDP比率に着目する限り、わが国の場合、まず資本形成については、今後、一層の抑制・削減に努める余地があるとみられる。柔軟な施設利用や多様なマーケティングなど、経営の自由度拡大を通じて事業化メリットを増大させ、民間の投資を呼び込むイギリスのPPPs(Public Private Partnerships)あるいはフランスのコンセシヨン(concession de service public :公役務の特許)制度をより積極的に採り入れることで現行のわが国PFI制度の一段の拡充を図ったり、不要不急のプロジェクトについて打ち切りも含めゼロベースで見直すことを通じて、公共事業に対する財政資金の支出を減らすことができるからである。
それに対して、政府消費についてみると、わが国地方政府の規模は相対的に小さく、業務・事業の廃止や抜本的な見直しを行わない限り、歳出削減を行う余地は限定的なものにとどまる公算が大きい。
(3)資金配分スキーム
(イ)第2 は資金配分のスキーム、すなわち、各自治体が財源を調達するルートをどのように構築するかという問題である。この点に関し、今日、わが国の三位一体改革論議では、国庫補助負担金を廃止し、基幹税を中心に税源移譲する一方、地方交付税については抑制の方向で見直すことが既定路線となっている。
しかし、諸外国をみると、地方政府の財源調達ルートは一様ではない。むしろ、国庫補助負担金や交付税制度など、わが国が見直そうとしているスキームを長年にわたり利用している国もある。それでは、資金配分のスキームが国によって異なる理由は何か。そうしたなか、わが国はどのようなスキームを選択すべきか。
資金配分のスキームの違いは、地方政府の中核財源が自主財源か、それとも国からの移転資金か、という問題と表裏一体であり、さらにその問題は国と地方の税収構造と密接不可分である。こうした点も踏まえ、カナダを除く主要先進5 カ国について資金配分の制度を税収構造と併せて整理してみた。なお、計数は日本も含めすべて2002年値である。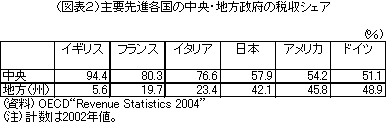
(ロ)総じてみると、特徴として次の3点が指摘できる。
a.国から地方への資金移転
まず、5カ国とも国から地方への資金配分が行われている。地方政府の自主財源だけでは不足するため、主としてナショナル・ミニマムを実現する観点から地方への資金移転が実施されている。もっとも、その形態は、アメリカでは個別項目毎の特定補助金が中心であるのに対して、イギリスでは一括交付金で行われる一方、フランスでは両方が混在するなど、形態は国によって様々である。
b.英仏伊では交付金が主要財源
次に、英仏伊では国の税収が総税収の大半を占めるなか、とりわけ、英伊2カ国では国からの交付金が地方歳入の根幹を形成している。なお、フランスでは、80年以降、地方分権の推進に伴って権限と財源両面で国から地方への移譲が進展した結果、交付金や補助金といった国からの移転資金と地方税が歳入の2本柱となっている。
こうした地方税のシェアが英伊2 カ国に比べて大きいという違いは、公立学校や都道府県警察の職員が国家公務員であるというフランスの特殊事情に起因する面が大きい。上記の通り、わが国に即してみると、この要因に伴う政府消費が最大GDP比2.4%に上り、わが国地方政府の政府消費の3分の1に相当する。この点を踏まえてみれば、その分、それらの職員が地方公務員である英伊に比べて、フランスでは国から地方への移転資金が少なくなり、歳入総額に占める地方税のウェイトが大きくなる筋合いにある。このため、その要因を割り引いてみれば、英仏伊3カ国は国からの移転資金が地方歳入の中心であると整理することが可能であろう。
c.米独では州政府の存在大
さらに、単一国家と連邦国家では事情が異なる。すなわち、英仏伊の単一国家では国が税収ならびに地方への資金移転で中心的役割を果たすのに対して、米独の連邦国家では、州政府が国家主権や統治権など幅広い権能を持ち、連邦政府に従属するよりも、むしろ拮抗あるいは凌駕する機関として並存する。その結果、税収面でも州政府の存在は大きく、地域自治体と合計すると地方政府と連邦政府の税収シェアは米独ともほぼ半々である。
しかし、資金配分については、米独で大きく異なる。アメリカでは州政府間で財政調整は行われず、財政支援は連邦政府から州政府および地域自治体に対して特定補助金を通じて行われるのにとどまる。それに対して、ドイツでは、州間財政調整が連邦政府を巻き込んで行われている。
(ハ)主要5カ国について国別に概要を整理すると、以下の通りである[財務省]。なお、以下では、国が徴収する税額が税収総額に占めるシェアの大きい国の順に資金配分の基本的スキームをみた。
a.イギリス
まず最大の国はイギリスであり、地方の5.6 %に対して、国は94.4%を占める。地方税は居住用資産を対象とする資産税、いわゆるカウンシル税のみであり、法人・個人所得税や事業用カウンシル税をはじめ、その他の税はすべて国が徴収する。そのうえで、ナショナル・ミニマムとして決定される地方政府の標準的な支出額のもと、各種補助金を含め交付金が国から地方政府に配分される。各地方政府は、標準的なサービス以外に、あるいは標準的サービスを上回る行政サービスを自主的に追加したり拡充することができる。もっとも、上乗せ部分の費用は全額各自治体が地方税、すなわちカウンシル税で負担しなくてはならないため、地方政府によってカウンシル税の税率が異なり、モラル・ハザードの発生回避が図られている。
b.フランス
次はフランスで、地方の19.7%に対して、国が80.3%を占める。地方税の大半は、住居税や建築不動産税など資産税で、イギリスと相似する。もっとも、配分については、イギリスの標準支出に相当する基準はなく、1980年以降、逐次行われてきた地方分権のなかで、国から地方へ移譲された一つひとつの権限毎に、当該業務に必要な財源が、税源移譲と各種交付金の二つのルートで地方に配賦されてきた。しかし、経済力にバラツキがあったり、交付金が新たな業務に必要な財源として必ずしも十分でなかった結果、地域間の財源格差が生じている。この問題を克服するために、自治体相互の財政調整が行われているものの、歳入格差は依然解消されていない。このため、地方税収によって歳入不足の補填が各地方政府毎に図られ、その結果、地域によって地方税率が異なる状況となっている。フランスでは、税源移譲や交付金、あるいは自治体間の財政調整制度によって、事実上ナショナル・ミニマムが確保される一方、地域間の歳入格差が地方歳出の歯止めなき膨張阻止に作用しているといえよう。
c.イタリア
英仏の次はイタリアで、地方の23.4%に対して、国は76.6%を占めており、地方と国のシェアはフランスとほぼ同様である。これは、フランスで80年に始まった地方分権の動きが、イタリアでも97年以降本格化し、国から地方への権限と税源の移譲が行われてきた結果である。もっとも、地方税だけでは財源不足であり、フランスと同様、国からの交付金が地方政府の主要財源となっている。さらに、南北問題に象徴される地域の経済格差問題を抱えるイタリアの場合、交付金制度の主要目的のひとつとして地域間の経済・社会的な格差縮小が掲げられ、各地域の財政調整を行う地方財政平衡化交付金が設けられている結果、地域間の財政力格差問題は顕在化していない。なお、 そうした措置が、地方政府の歳出削減がなかなか進展せず、政府支出が先進各国のなかでも高水準で高止まる一因となっている可能性は否定できない。
d.アメリカ
4番めはアメリカで、地方の45.8%に対して、国は54.2%と、英仏伊と大きく異なり、国と地方がほぼ半々の税収シェアとなっている。その結果、補助金を通じた連邦政府から地方政府への資金移転が行われているものの、地方政府の歳入の中心は地方税であり、自主財源を根幹とする財政運営となっている。加えて、財政調整という観点からみると、連邦政府から地方政府に、あるいは州政府から自治体に対して行われる資金移転制度のなかに、相対的に財政力の脆弱な州政府や自治体に優先的にファンドが配分される特定補助金があるのにとどまり、州政府相互間での財政調整制度も、州内で州政府から各自治体に対してイギリスのような標準支出に基づく交付金といった制度も設けられていない。地方税と特定補助金で地方財政が運営され、州間および地域間の財政力格差が是認されることで地方財政の肥大化が回避されているシステムはフランスに相似する。
e.ドイツ
5番めはドイツで、地方の48.9%に対して、国は51.1%と、拮抗した税収構造が特徴である。税収構造ではアメリカに近いものの、資金配分ではアメリカと異なり、徹底した財政調整が行われている。そのスキームの概要を整理すると、次の通りである。
(i)まず、所得税と法人税、売上税の3 税からなる共同税について、所得税と売上税の一部を市町村などに配分したうえで、連邦政府と州政府で分割する。
(ii)次いで、共同税の州政府分について、各州への分配を行うに当たり、所得税と法人税については原則として徴収地の州に配賦される。もっとも、事業地が2 州以上にまたがる企業の場合、法人税は従業員給与額の州別シェアに応じて、当該企業に勤務する従業員の所得税については州別人数に比例して按分される。
(iii)一方、売上税は、財政力の弱い州に優先的に配分される。
(ⅳ)さらに、それら共同税の受取額に、その他の州税などを加えた各州の総収入が、人口一人当たりベースでみて国全体の平均を下回る州は、上回る州から調整交付金を受け取る。
(ⅴ)こうした調整を経ても、依然格差がある場合、連邦政府から連邦補充交付金が州政府に配賦される。
(ⅵ)以上の財政調整とは別に、次の分野について特定補助金が連邦政府から州政府に交付される。すなわち、教育や学術振興など、連邦政府が州政府の事業に参与すべき共同事業、および地域間経済格差の縮小を目指す投資のための財政援助、アウトバーンの整備をはじめ州政府に対する連邦政府の委任事務などである。
(ニ)以上の動きを改めて概観すると、諸外国の取り組みは、a.資金配分のスタイルと、b.地域格差に対する許容度、の二つの異なるベクトルによって整理することができよう。すなわち、まず税収構造と資金配分の関係をみると、税収面で国のシェアが大きくなると、交付金制度が地方政府の歳入の根幹となる。逆に国のシェアが小さくなると、地方政府の役割が大きくなるなか、地域の独立性を重視するアメリカ型と財政調整を重視するドイツ型に大別される。
一方、地域格差が容認される、あるいは地域の独自性が追求されるアメリカやフランスでは地方税の位置付けとして歳入の根幹としての色彩がより濃厚である。それに対して、ナショナル・ミニマムをより重視するイギリスやドイツでは、教育や保安分野をはじめ行政サービスの質の維持に向けて交付金が配賦されている。
(ホ)翻ってわが国をみると、2002年時点で全税収に占める国のシェアは57.9%、地方が42.1%で、英仏伊よりも、米独に近い構造とっている。さらに、三位一体改革で3兆円の税源移譲が打ち出されており、これを加算すると、全税収に占める国のシェアが54.1%、地方が45.9%となり、アメリカとほぼ同水準になる。この点を起点にすると、三位一体改革では、国から地方への資金移転の問題よりも、むしろ地域間の財政調整システムをどうするか、とりわけ、アメリカ型とドイツ型のいずれを選択するかの問題が取り組むべき焦点になる。
仮にアメリカ型を選択する場合、わが国の場合、国から県への幅広く抜本的な権能の移譲によって連邦制に近い統治機構を改めて整備・構築する必要がある。本来、歳入システムと統治機構は表裏一体の関係だからである。なお、こうした議論に対しては、わが国の県は規模が小さく、アメリカの州政府機能を具備するのは困難との懸念を持つ向きもあろう。しかし、アメリカ各州の人口をみると、3,381万人のカリフォルニア州や2,085万人のテキサス州など、巨大な州がある一方、アメリカの多くの有力企業が本社を置くデラウェア州が78万人、ニューイングランド地方のバ-モント州が61万人、ワイオミング州が49 万人など、人口の少ない州も少なくない。
むしろ、問題は、少なくとも現時点において世界的にみても特異なアメリカの連邦制度をわが国が採り入れることの是非であろう。そうした観点から改めてみると、先進各国のなかでもアメリカと同様のシステムを採る例は稀有であり、上記の英仏伊独をはじめ、国の税収シェアの違いによって形態は異なるものの、総じて財政調整が行われている。これは、地域の独自性が行き過ぎると政治的・社会的混乱を招き、統一国家の基盤が毀損される懸念が大きいことに起因しよう。
(ヘ)このようにみると、わが国の場合、ドイツ型の財政調整スキームの整備がポイントと位置付けられよう。もっとも、ドイツの制度、すなわち、共同税制度をベースとする州政府間の水平的財政調整や連邦政府から州政府への交付税制度は、ドイツ固有の歴史的経緯に根差しており、わが国がドイツの諸制度をそのまま直輸入すべきか否かは一段の検討が必要である。むしろ、わが国に即してみれば、首都圏をはじめとする都市圏と地方圏との水平的財政調整が問題の中心である。
この問題に関連して、第2のベクトルが重要になる。すなわち、アメリカ型を採らないとしても、どこまで地域格差を容認するのか、あるいはナショナル・ミニマムの確保をどこまで重視するのかの問題である。地域格差を容認するのであれば、水平的あるいは垂直的財源調整に一定の歯止めを掛け、各地域の地方税を自主財源として活用する余地を大きくすべきであり、逆に地域格差を容認するよりもナショナル・ミニマムの実現を重視するのであれば、水平的財源調整を徹底し、さらに国から地方への垂直的財源調整にも踏み込む必要が出て来る。 - 今後の課題
(イ)それでは、三位一体改革の目的、とりわけ、a.権限と財源の移譲による地方の自立、b.国・地方を合わせた税財政改革を通じた効率的な政府の実現、という二つの主要目的を同時に達成し、改革の推進力を強化する方策は何か。そうした観点から改めて、今日の三位一体改革が目指すスキーム、すなわち、国庫補助負担金が廃止される一方、補助金の廃止額より少額の税源移譲が基幹税を中心に行われ、権限も国から地方移譲されるという枠組みに即してみると、次のような懸念がある。
まず、地方交付税の規模が抑制・削減される場合、国サイドで財政赤字が減少し、その意味で効率的な政府が実現される一方、都市圏を中心に税源が豊富で財源が確保される地域では国から移譲された権限が活用される結果、地方の自立が推進されるとしても、税源に乏しい地域では、資金制約のもと、移譲された権限の活用に限界が生じ、行政サービスの低下を招来する懸念が大きい。それに対して、この問題をカバーするために、地方交付税制度を通じて税源に乏しい地域に対する財源保障を行うとすると、行政サービスの低下は回避されるとしても、歳出抑制を通じた効率的な政府の実現に支障を来たす懸念が出てくる。
(ロ)そこで、a.地方の自立とb.効率的な政府の実現の二つの目標毎に、不可欠の重要な課題を整理すると、次の通りである。
まず、各地方政府がそれぞれ諸施策のスクラップ・アンド・ビルドを行いながら、地域事情に即した独自の政策を推進する、自立した地方行政を実現するには、a.財源の確保と、b.権限移譲、の二つが必須要件である。
a.財源の確保
どのような政策にせよ、円滑な実施に財源は不可欠である。もっとも、財源確保において、国あるいは地方政府が負うべき責任の大きさは分野によって異なる。警察や消防など、ナショナル・ミニマムの実現が強く要請される分野であるほど、国の負うべき責任は大きく、逆に、観光振興や公園整備など、地域の特性に根差したり住民の選好に依存する色彩が濃厚な分野であるほど、各地方政府が負うべき責任が大きくなろう。
そうした観点から諸外国をみると、まずナショナル・ミニマムが重視される分野として警察を例にみると、イギリスでは一括交付金とは別に特定補助金制度がある一方、フランスでは警察官を国家公務員とすることで国が直接関与している。一方、米独の連邦国家では、警察は州政府の所管のため、代わりに教育についてみると、制度上は州政府の所管と位置付けられているものの、連邦政府も積極的に関与している。すなわち、ドイツでは、連邦国家全体の発展に重要な分野について連邦政府の関与が共同事業として認められ特定交付金が州政府に配賦されるなど、教育・研究分野は共同事業の根幹を形成している。アメリカでは、連邦政府から地方政府に対する特定補助金制度において、教育は、メディケイドをはじめとする社会保障に次ぐ重要分野と位置付けられている。
それに対して、観光振興や公園整備など、ナショナル・ミニマムの要請が相対的に弱い分野についてみると、財源をはじめとして地方の主体的行動が前提となっている。例えば、イギリスではナショナル・ミニマムを上回る支出について、その財源を各地方政府がそれぞれカウンシル税によって確保する一方、仏独米伊4カ国では特定補助金で手当てされない限り、自主財源で賄われる。
このようにみると、わが国の三位一体改革でも、まずもって官民の役割、とりわけ、ナショナル・ミニマムの対象分野および、その水準をどうするかについて、次いで、公的セクターが担うべき分野のなかで国と地方がどのように役割を分担したり協力するかという、果たすべき役割や機能に関する2 段階の議論が欠かせない。加えて、この議論には、役割を果たすために必要な財源を確保するという観点から、前章で整理した、徴税の中心を国と地方のいずれにするかという税収構造の問題が重なる。国の税収シェアが大きい場合、英仏など、地方政府の主要財源は交付金や特定補助金となる一方、地方政府の税収シェアが国に拮抗するほど大きい場合、ドイツ型かアメリカ型かを選択する必要が出てくるためである。なお、この点に関連して、ナショナル・ミニマムの確保ではドイツの特定補助金制度が参考になり、地方の自主性尊重ではイギリスのカウンシル税が有力なツールとなり得る。
b.権限移譲
財源が確保されても、地方政府の裁量の範囲が限定的であれば、主体的な施策の推進は困難であり、地方主権の確立には、財源確保とともに、国から地方への権限移譲が必須要件である。
一つの典型例が、かつて代表的中央集権国家と称されたフランスの地方分権である。フランスでは、パリ周辺への一極集中と地方経済の停滞を打破し、経済再生を目指して80年以降、地方分権化が推進されてきたなか、2003年3 月の改正憲法において、権限移譲と財源措置がセットであることが明文で規定された。すなわち、国と地方政府との間で権限が移譲される場合、当該権限の行使のために充てられていた財源に相当する財源が地方政府に付与される一方、地方政府の歳出増となる権限の創出・拡大では、その遂行に必要な財源が法律によって措置されるとされた。
さらに、ナショナル・ミニマムに関する国の規制について、その位置付けをガイドラインとして見直し、サービス水準が基準を下回ることは禁止する一方、上回ることは容認するスタイルに変更すべきである。例えば、先進各国の教育サービスをみると、英米を嚆矢に、中央政府は、達成すべき学力水準など、目標としてのスタンダードを明示する一方、具体的な教育サービスの実施については、地域や学校の自主的運営にゆだね、標準的スタイルを上回ることを容認することで、様々な取り組みを促し、児童・生徒や地域に即した教育サービスの拡充を図る動きが拡がっている。こうした観点からわが国を振り返ってみると、学区制の廃止や学校選択の自由を打ち出した規制改革会議の議論を進め、特区事業のさらなる推進を図っていくことが望まれる。
(ハ)一方、効率的な政府は、財源を確保したり、権限を移譲するだけで実現することは難しい。一部には、効率的な政府をつくるために、官民の役割を見直し、公的セクターの果たすべき分野を縮減することで小さな政府を実現すれば、その分、歳出は減少し、効率的な政府を構築できるという見方もある。しかし、前章で概観した通り、先進各国のなかでわが国地方政府の規模は、政府消費でみる限り、仏英と並んで最小である。それだけに、わが国が効率化に向けて官民の役割を見直し、小さな政府を追求した場合、各国では公的サービスとして提供されている分野が抜け落ちるなど、サービスの低下に繋がるリスクが否定できず、役割の見直しが可能な分野があるとしても、その余地は必ずしも大きなものにならない公算が大きい。
このようにみると、わが国が公的セクターの一段の効率化を目指す場合、公的サービスが提供されるプロセスなど、抜本的な制度の見直しに踏み込む必要がある。とりわけ、現行制度の枠組みを見直し、公的サービスの提供主体を政府のみならず幅広い主体に拡大することによって、質や量、価格など、様々な面でサービス向上に向けた取り組みを促すことが焦点となろう。
(ニ)公的サービスとして国や地方政府が責任を負いつつ、具体的な推進プロセスを政府が民間にアウトソースし、効率的な運営を目指す手法として、公共事業の執行や公共施設の利用の分野では、わが国でも、PFI や指定管理者制度が定着し始めている。しかし、サービス提供の分野についてみると、わが国の場合、市場化テストの導入に向けた取り組みが進み始めているものの、独立行政法人制度をはじめ、現時点でみる限り、少なくとも効率的な政府実現に向けて本格的に幅広く活用されているとは言い切れない。
それに対して、各国には、公的サービスの実施を政府以外の機関が請け負う様々なスタイルがある。政府が提供サービスの水準を決めて民間にアウトソースする手法を整理すると、事業性がある分野ではPFIや市場化テストという仕組みが活用される一方、事業性が薄い分野ではNPOへの事業委託が行われるケースが多い。事業性がある分野では、民間の経営手法を活用することで採算が改善されるほど、財政資金の投入が少なくて済み、事業性が薄い分野では、NPOに対して収益事業や寄付金に対する優遇税制を認めることで、事業支援のために投入される財政支出の節約が可能になる。ちなみに、わが国で認定されたNPOが2005年4月時点で21,628件であるのに対して、NPO先進国のアメリカで活動するNPOは2001年時点で150万件に及ぶ。
さらに、外部へのアウトソーシングが困難な分野についても、民間活力を活用するスキームの利用が広がっている。端的な例がイギリスのエージェンシーである。これは、公的サービスの質向上と生産性向上を目指し、政府機能のなかでサービス提供業務を対象として、車両検査部門を皮切りに88年導入された制度である。今日、研究機関や登記所にとどまらず、税務業務や国防など、幅広い分野に広がっている。その結果、イギリス政府の職員数は、全体では本制度導入直前である88年4月の58 万人から2004年4月には52万人に減るなか、52万人のうち、省庁勤務の職員が14万人と4分の1にとどまる一方、エージェンシー職員が38万人と4分の3を占める。なお、エージェンシーには、公務員資格の職員と発足後入社した民間資格の職員が同居しているものの、いずれの職員とも成果主義に基づく業績評価によって処遇が決定される。
(ホ)翻ってみると、わが国では、公的サービスは政府セクターが実施するケースが大半であり、外部にアウトソースする動きは依然として低調である。この背景には、機能と主体両面で官民の役割分担を整理する2分論、すなわち、公的分野の業務は公的セクターが実施し、民間分野の業務は民間セクターが行うという考え方が根強く残存しているという事情が指摘されよう。
しかし、諸外国にみられる通り、公的分野や非営利分野であっても、外交や警察、国防など、純公共財以外の分野についてみれば、サービスの提供主体を政府セクターに限定するよりも、広く開放したほうがメリットは大きい。NPOや民間企業も含め、様々な主体がそれぞれの強みを生かした競争を繰り広げることで、ニーズにマッチしたサービスが、より効率的に提供されるためである。わが国でも、市場化テストやNPOに対する優遇税制、さらに、明確な業績改善目標のもと、達成度合いに応じて組織や個人の評価・処遇が決定されるエージェンー制度の本格的導入など、公的サービスへの参入主体拡大に向けた枠組みの整備・拡充を今後一段と強力に推進すべきである。
(ヘ)三位一体改革、すなわち、国から地方への権限と財源の移譲および地方交付税制度の見直しは中間目標であり、最終目標は地域経済の活性化と、それを通じたわが国経済全体の競争力強化にある。諸外国でも、近年、地方分権が積極的に推進されている背景には、市場間競争が国際規模で激化しBRICs 経済が急速に台頭するなか、とりわけ先進各国において、産業と雇用の創出に向けた地方経済の再生が喫緊の課題となっているという事情が指摘されよう。
しかし、地域経済の活性化は、市場原理にゆだねるだけでは成功し難い。政府機関だけでは事業・産業の創出が難しい一方、初期段階での投資リスクが大きいために民間企業だけでリスクを採ることが困難であることに加えて、技術や市場の変化に即応した柔軟性とともに、中長期的ビジョンの実現に向けて着実に取り組み、さらに重点分野には積極果敢にリスクをとってヒト・モノ・カネを戦略的に投入する総合的マネジメント力が要請されるためである。
そうしたなか、先進各国では、民間との緊密な協力関係のもと、地方政府が中心的役割を果たしながら、地域経済の活性化が推進されている。わが国でも地域間の経済格差問題が次第に顕在化するなか、経済活力の維持・強化を実現していくために地域経済の活性化は、今日、枢要な政策課題の一つとなっている。歳出削減のツールに矮小化されることなく、地域再生を実現する決め手として、三位一体改革の推進力強化は焦眉の急である。

