Business & Economic Review 2006年02月号
【PERSPECTIVES】
新年世界経済の展望-世界景気は緩やかな拡大局面へ
2006年01月25日 調査部 マクロ経済研究センター
要約
- 2005年の世界経済を回顧すると、年前半は世界的にやや停滞感の強い状況がみられたが、夏以降は 再び景気拡大傾向が強まり、総じて底堅い拡大基調が続いた。一方で、2003年以来アメリカはじめ世界経済を拡大させてきたメカニズムに綻びがみえ始めている。すなわち、a.アメリカ経常赤字の持続 的な拡大、b.原油をはじめとする商品価格の高騰、c.資産価格上昇の過熱、といった副作用が顕著になってきた。なかでも、a.原油高騰を受けたインフレ圧力の強まり、b.アメリカでの住宅市場過熱へ の対応が、当面の世界経済を占う重要なファクターとなっている。
- 以上の現状認識を踏まえ、2006年の世界経済を展望するに当たり、カギになるとみられる下記二つ のポイントについて検証した。
(イ)世界的なインフレ懸念
原油価格の高騰もあり、世界的にインフレ率は上昇傾向を辿っているが、価格上昇はエネルギー 関連に限定され、それを除いたコアベースでは、現状は欧米ともに低位安定が続いている。グローバル化の進展が、先進国での賃金および物価上昇抑制に作用していることが基本的背景。ただし、 アメリカならびにイギリスでは需給ギャップが縮小しており、なかでも景気好調が続くアメリカにおいては、今後賃金面からのインフレ圧力が強まる可柏ォがある。同国においては、実質政策金利 3%前後が、景気および物価に対し中立的な水準とみられ、この点から判断して、米FRBは政策金利を4%台後半まで漸進的に引き上げていくことにより、インフレ圧力の沈静化を図るとみられる。 ユーロ圏では、需給ギャップがなお残存しており、アメリカで適切な金融政策が行われれば、世界的なインフレ圧力が強まる可柏ォは小さいと判断される。
(ロ)アメリカ住宅バブル
2005年夏以降、中古住宅で在庫が急増するなど、バブルの色彩を強めてきた米住宅市場に沈静化 の兆しが出始めている。こうしたなか、米FRBの利上げ継続により、長期金利が一段と上昇すれば、住宅価格が急落するリスクがある。もっとも、米長期金利の低位安定はいわば国「的なものである。 すなわち、a.アジアなど新興市場国での海外貯蓄(経常黒字)の増加が米国債需要の増加につながっているほか、b.国内での投資機会の減少を反映して、アメリカ法人部門が資金余剰主体に転じて いる。こうした国「に大きな変化がない限り、米FRBが今後小幅の追加利上げを行ったとしても、米長期金利の上昇余地も限られるとみられる。したがって、米住宅市場においても、大幅な価格下 落は避けられ、ャtトランディングは助ェ達成可狽ニみられる。 - 以上の分析を踏まえたうえで、2006年の世界経済を展望すると、総じて緩やかながらも拡大傾向が 続く見通しである。
(イ)アメリカ…a.良好な所得・雇用環境、b.住宅価格上昇を受けた資産効果持続を背景に、当面、 個人消費を中心に堅調な景気拡大が続く見通しである。とりわけ、年前半は、ハリケーン 被害を受けた復興需要・財政支出拡大が景気押し上げに作用し、潜在成長を上回る高めの 成長が続くとみられる。もっとも、今後住宅価格の騰勢鈍化が卵zされるなか、資産効果 剥落・マイナス化した貯蓄率の是正が年央以降の景気抑制要因として作用してくるとみら れる。このため、年央以降は、個人消費を中心に潜在成長を小幅下回るペースにまでスロ ーダウンする見通し。
(ロ)欧州…ユーロ圏では、世界経済の持ち直しを背景に、緩やかながらも拡大傾向が続く見通し。 もっとも、EU拡大、労働市場改革の遅れなどを背景に、企業部門の好調が家計部門に容 易には波及しにくい告}に変化はみられず、内需は引き続き力強さを欠く状況が続く見通 し。イギリスでは、住宅価格騰勢鈍化を受けた資産効果剥落というマイナス要素が一巡す るなか、早晩持ち直しに転じる見通し。もっとも、家計部門の高水準の債務負担が重しと なり、景気回復ペースも緩やかにとどまる見通し。
(ハ)アジア…中国では、所得格差是正に向けた農村部への政策支援、貿易黒字縮小に向けた個人消 費喚起もあり、引き続き高成長が続く見通し。もっとも、安定成長に向けた投資抑制策も 継続され、成長率は2005年を小幅下回る+8.8%となる見通し。一方、中国を除く東アジア 諸国では、世界経済の拡大、IT関連需要の回復を背景に、当面景気拡大が続くと見られ、 総じて2005年を小幅上回る+4~6%程度の成長率を維持する見通し。
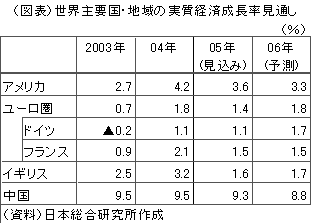
- 上記のシナリオに対するリスク要因としては、a.原油価格の高騰が持続するリスク、b.アメリカ住 宅価格が大幅に下落するリスク、c.米FRB議長交代に伴う金融市場のボラティリティー拡大、それを受け実体経済に悪影響が波及するリスク等があり、これらに対する注意が必要である。

